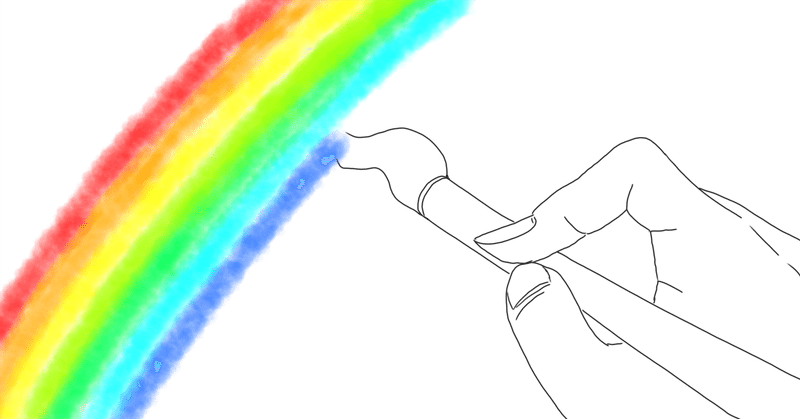
雨と晴れのあいだ
数時間前から激しく雨が降り、遠くに見える山々は灰色に霞み、町と町を流れる川の上に架かる赤い橋は車で渋滞して、タイヤから跳ねる水しぶきは勢いよく流れる川に落ちていった。縁石の内側を傘を差した人々がぶつからないように肩をすぼめ、ときおり傘を頭上高く掲げ、注意深く歩いていた。黄色いレインコートを着た子供は母親の手をつなぎ、水たまりに長靴ごとばしゃばしゃと入り、さも平気そうな表情で母親を見上げて、母親を困らせているのだった。電柱に止まっている一匹のカラスは寒そうに頭を体の中にうずめ、飛ぶことすらも諦めてじっと動かないでいる。すると、雨雲がゆっくりと東に向かって流れていき、雲の隙間からわずかに青い空が見えて、その中から太陽の光が差した。雨は霧雨に変わり辺りをやさしく包んでいた。
「あっ虹だぁ!お母さん見て見て、虹が見えるよ!」子供が指さした方向には大きな虹が高くアーチを描いていた。
「時間です。答案用紙を回収します。後ろの席から前の席へ答案用紙を回して下さい」と教授が言うと、教室はざわざわと話し声が響き出した。恵一は前の席の生徒に答案用紙を回した。恵一のテスト期間中最後のテストが終わり、このテストが終われば平常授業に変わることを喜び、恵一はぐっと背伸びをした。教室の外は、先ほどの豪雨から一転して、雲の合間から青空が広がり明るい光が教室に差し込んでいた。恵一はベランダで新鮮な空気を吸おうと外に出た。遠くに見える山の頂上付近は、太陽が照らし、山の稜線は鋭い刃物のように輝いていた。町の方角を見ると、川や家々が雨に洗われて、清々しく澄み渡っていた。ふと恵一が空を見上げると大きな虹が広がっていた。「おっ虹が出ているな」と恵一はつぶやいた。ベランダの入り口付近の段差に腰を掛けると鞄の中からデッサンの授業で使うノートと色鉛筆を取り出し、虹の色形、アーチのカーブの大小を詳細に紙の上に描いた。恵一が虹を描いている間中、周囲の生徒達は妙な視線を恵一の方へ送り、遠くの方では笑い声すらも聞こえてきたが、恵一は気にする様子もなく黙々と虹を描き続けた。描き終わると、恵一は次の授業に向かう生徒の人波を搔き分けて、大学創設者の銅像が立っている広場を抜け校門を出た。校門の前ではカップルが虹を背景に写真を撮っている。恵一はバイクに乗って自宅に向かって走り出した。
玄関を開けて中に入ると、土間に置かれた蚊取り線香の匂いがむっと鼻につき、奥の部屋のテレビからは野球の実況中継が聞こえてきた。
「さあ、ツーストライク、ワンアウト、走者は一二塁。バッター四番麻生。今日は内野安打一つです。ここは見せ場を作らなくてはなりません。投手投げた!あーつまりました。つまったー。ボールはサード。サード投げて、あーゲッツーです。ゲッツーに倒れましたー」
「はあ!」敏夫があぐらをかいた太ももを強く平手で叩いた。「あー!だめだ麻生は。全然振り遅れてるじゃないか!もうちょっと下に降りゃあな!もうちょっと下!」と敏夫は怒鳴った。敏夫はビールをぐっと呷り、畳の上に横になってチャンネルを回した。丸いちゃぶ台の上の新聞紙が扇風機の風に煽られてばたばたと揺れている。
「今帰ったけど」と恵一が居間のすりガラスをゆっくり開けて言った。
「おう!おかえり。今日はずいぶん早いな。勉強ちゃんとやってきたのか。勉強全然やらないんじゃ、学費やってる意味ないんだからな!」
「お母さーん、恵一帰って来たぞー!」と敏夫は言った。
「やってるって」と恵一は言った。
庭に勝手に生えてきたシソの葉を取りに行っていた節子が、勝手口を開けて入って来た。「はいはい、お帰り。お腹空いてるなら冷蔵庫に何か入ってるから食べなさい」「はい、お父さん枝豆」と節子は言った。
「さっき大学の食堂で食べたから大丈夫。そういえば父さん昼間虹が出てたんだけれど、あれって家のやつ?」と恵一は言った。
「ああ昼間のやつな。あれは家のじゃない。中村さんちの虹だろ。うちのは今日赤いのが足りなくてな。今日はやめといたんだ」と敏夫は言った。
「中村さんちも虹屋やってるの初めて聞いたよ」と恵一は言った。
「そりゃそうだろ虹屋やってるなんてそうそう言わないからな。でも中村さんも大変だ。今年子供が二人大学行くんだから。虹屋やってて大丈夫なんかね。いっそ会社にまた戻った方が良くないか。サラリーマンから虹屋になろうなんて今時変わった奴もいるもんだ。給料も良くないのにな」と敏夫は言った。
節子は台所に立って長ネギを細かく刻んでいる。
「うちは昔から付き合いのあるお客さんがついてるけれど、一からお客さんつけるなんて大変よ。今は何とかやってるけれど、あんたが生まれた時なんか大変だったんだから。お父さん、ちょっと何人かお客さん紹介してあげたら、中村さんに」と節子が言った。「それは中村さんのプライドが許さんだろうよ」と敏夫は言った。
恵一が古びた冷蔵庫から麦茶と冷えたメロン一切れを取り出して、居間を後にし二階への階段を上ろうとすると居間から声が聞こえた。
「おーい恵一!待て待て。お前今度の土曜開けとけよ。店手伝って欲しいんだ」敏夫が一階から言った。
「時間があったら手伝うよ」と恵一は言って部屋の扉を閉めた。
土曜の朝、恵一の目覚ましが六時にちょうどに鳴った。恵一がぼんやりとした視界の中窓の方を見ると、外は雨が降っていて、雨は家の屋根瓦を伝って雨樋へと流れていった。恵一が裸足のまま一階に降りると敏夫が電話口で誰かと話していた。「今日は八時に上がるってぇ?ちょっと話が違うじゃないかよ。俺んとこは七時半だって聞いてるんだからさあ。どうなってるんだねえ。まったくあいつらが来てからろくなことになんねえや。そういや新ちゃんとこ虹の赤いの余ってねえか。今日は俺んとこで出そうと思ってんのよ。ああ、そうそう、わりいな。そんじゃ」敏夫は少し白くなった頭を搔きながら電話を切った。寝室から節子の鼾が聞こえてくる。
「おう、恵一起きてたんか。ちょっとひとっ走り新ちゃんのところ走って、虹の赤いの貰ってきてくれんかな。それと行くついでにいつもの肉まん屋行ってあいつに渡してくれな」と敏夫が言った。
「しょうがないなあ。ちゃんと給料くれるんだろうなあ。こんな雨降りに出歩くなんてたまらんよ」
「お前、雨がなきゃあ商売なんねえんだぞ」
恵一が玄関を開けると、飛び石の上に雨が跳ね、百日紅の新梢がだらりと恵一の顔の辺りまで垂れていた。恵一は排水桝に流れ込む雨水を横目に見ながら、新ちゃんの家まで歩いて行った。
恵一の曽祖父は明治に染物屋として数十人の職人を雇い、財を成したと聞いている。酒好きの曽祖父は遊楽で遊んだ夜、川に落ちて死んだ。多大な借金の末に残った財産はこの家だけだった。当時は立派な商家だったが、今は屋根瓦のいぶし銀は剥がれ、屋根はいくらか傾き、漆喰壁は黄ばんでいた。母屋の飛び石を挟んで反対側には蔵があり、堅牢な窓にはいかにも重そうな観音扉が取り付けられていて、蔵の中には昔、古い仏像が置かれていた気がするのだが、恵一は子供の頃入ったきりで今はどんな顔をしているのか忘れてしまった。昔はよく地元の小学校の先生が生徒を引き連れて見学に来たものだったが、しだいに来なくなった。三人で暮らすには広すぎる母屋の半分を工場に改築し仕事場にしていた。
敏夫は長年の労苦で皺が出来た太い指で煙草挟み、工場の窓から顔を出して雨が落ちてくる暗い空を見上げた。煙草の煙はゆらゆらと工場の中へと流れていった。居間と工場を結ぶ廊下に足音が響き、恵一が薄暗い工場の中へ入って来た。「ずいぶんゆっくりじゃねえかよ。ちゃんと肉まん忘れなかっただろうなあ」と敏夫は言った。
「ずいぶん喜んでたよ。新さんも単純だよなあ、あれで済むなら安いね。この赤いので間違いないよね」と恵一は言って、折り畳み傘くらいの赤い筒を鞄から取り出した。
「そうそう、それで間違いない」と敏夫は言った。
「今何時だ恵一」敏夫が言った。
「今は七時半」恵一が言った。
「そろそろ仕込みをはじめんといかんな」と敏夫は言って、油汚れで染みの付いた作業着を着た。
敏夫が機械の操作盤の前に立ち、電源を入れるとボタンは赤く点燈し、機械のエンジンが回る音が工場内に響いた。天井にはゆうに直径10メートルはあろうの大きな穴が開いていて、その穴からステンレス製の巨大ダクトが、地面に向かって垂れ下がっている。敏夫はダクトの口を天井に設置してあるスライド式リフトを操作し工場の中心まで伸ばした。ダクトの口から生ぬるい外気がびゅうびゅうと部屋の中に入って来た。恵一はダクトの中を覗いてみたが、中は真っ暗で何も見えなかった。
「おいちょっと恵一!向こうの壁に立てかけてある木の四角い箱こっちへ持ってきてくれー」と敏夫は言った。恵一は壁際の箱をなんとか運搬機の荷台に乗せて運転席に座った。
「これどうするんだ父さん」恵一が言った。
「赤い電源スイッチあるだろ。それで電源入れて、右足にあるアクセルとブレーキで進む。要するにバイクと一緒」と敏夫が言った。
「このあたりでいいかな」と運搬機を止めて恵一が言った。「いやこっちのダクトの口の下まで持ってきてくれ」運搬機は音を立てて、工場の中心まで移動していく。
「ストップストップー」敏夫が言った。
「それをこの荷台に乗せ替えるから箱のそっち側持ってくれ」
「手をつぶさないようにしろよ。いくぞせーの」
箱はどしんとダクトの下の台に収まった。箱の一辺は5メートルほどあり、底は抜け、箱の上面は透明のガラス製の板がはめ込んであり、七つそのガラスの板の上に木製の仕切りがあった。
「これが肝になるんだな。どうだ恵一、なかなか大変だろう。お前運動しないから顔が真っ青だぞ」敏夫が言った。
恵一は頭に巻いていたタオルで顔の汗を拭った。「いや汗びっしょりだな」と恵一は言った。
「あとは色の準備だ。新ちゃんの家から貰ってきた赤色の筒と、壁際のキャビネットに他の六色も入っているから、それも箱の上に置いておいてくれ。何かあれば外で煙草吸ってるから聞きに来い」と敏夫は言って外へ出て行った。
恵一は壁際の薄緑色の大きなキャビネットの中から、オレンジ、黄、緑、青、藍、紫、六色の筒を取り出し、箱の上に乗せた。オレンジの筒をよく見ると「Orange」と書かれ、裏側には「made in USA」と書かれていた。他にも、緑色の筒には「vert」、紫色の筒には「紫色」と、様々な国名の色の表記があった。夏の工場は暑い。恵一はまたタオルで顔の汗を拭い、携帯電話を取り出し見ると、時刻は七時五十分だった。
少しすると敏夫が喫煙から戻ってきた。「どうだ恵一、大体出来たか」「ああ、全部の色は一応ここに出して置いたけど」「サンキュサンキュ」敏夫は筒の蓋を開け、一色ずつ箱の仕切りの中に流し込んだ。七色の透明な液体が流れ箱の中に小さな虹を作った。「最後はどうなると思う?」「いや分らんね」「まあ見てればわかるって」窓の外はだんだんと雨脚が弱まり、明るくなってきた。木々の葉の上に光がぽつりぽつりと落ちだした。
「そろそろ八時だ」敏夫が言った。
工場の壁の下の方に外と繋がる猫が通るくらいの穴が開いていた。雨が上がるにつれて、その穴がかすかに光り始めた。すると光の輝きがだんだんと強くなり、穴から光の液体が流れて出してきた。工場は突然強い光に包まれて、恵一は手で目を覆った。その光の液体は穴から続く水路に流れ込み、恵一の足元にある茶色い鉄板の下の桝へと流れていった。溜まった光が桝の隙間から漏れている。「それじゃあこのくそおもてえ鉄板を最後にどけるぞ」ふたりは勢いよく鉄板を引きずった。桝から強烈な光が天井に向かって放射され、光は七色が入った箱を通過して、暗い大きな穴に吸い込まれていった。
恵一が走って外に出ると、母屋の屋根から特大の虹が空に向かって出ていた。
恵一が家の駐車場で黒い原付バイクに跨りエンジンをかけようとした時に、同じく駐車場で隣の軽トラックに乗っていた敏夫が、窓を開けて外に身を乗り出して、手をこまねいていた。
「恵一、今日は大学まで送ってやっからこっちに乗れ」と言った。
「今原付で行こうと思ってたんだけど」と恵一は言った。
「つべこべ言わず、いいから乗れ」敏夫は言った。
敏夫の一度言ったら聞かない性格を知っている恵一は、仕方なく軽トラに乗り込み助手席の扉をバタンと閉めた。朝から暑い日で、車内にいても日差しが強く、恵一の白い顔は赤くなった。橋の上を通過するときに恵一が下を覗くと昨日の雨で川の奔流は速く、白い泡が下流に向かって流れていった。
「ちょっと回り道していくが時間あるな」と敏夫が言った。
「まあ大丈夫だけど」と恵一が言った。
「すぐ着くからよ」と敏夫は言うと、ハンドルを切って普段大学へは真っすぐに行く交差点を右折した。
軽トラがそのまま走って行くと、道路は次第に広がって、トラックと多く行違うようになった。ホームセンターや、陸上自衛隊基地を通り過ぎ、ひと気のない道を走っていった。道の左側に、フェンスに囲まれた大きな工場が見え、敏夫は工場とは道を挟んで向かい側の路肩に車をとめた。敏夫は工場の方を指さし言った。
「あそこに工場が見えるだろ、あの会社が虹システムだ。最近この町に進出してきたんだ」
敷地内には大きな倉庫が立っていて、作業員がシャッターの前にとまっている大型トラックの中から段ボールを中に搬入していた。
「あいつらには頭を悩ませていてな。地元のルールなんてお構いなしで、虹を出したいときに出すんだからな。町内会の一か月に四回っていうルールなんてえ無視さ。たまに、虹が二重に見える時ないか」と敏夫は言った。
「ああ、あるね」恵一が言った。
「あれなんてあいつらの仕業さ。俺たちと同時に出しやがるんだ、普通はこの前みたいに電話で今日はどうしますか、って感じで確認するもんだぜ」
「それじゃああの虹の一つはここから出てたんだ」
「ああ、まあでもあいつらの虹には俺たちの技術は真似できんよ。お前あいつらの虹ちゃんと見たことあるか、今度よく見てみろ。あいつらの虹は黄色と紫が欠けてるんだぜ。要するに俺たちに言わせりゃあ廉価版ってえところだな!」
「しかし最近そんなことなんぞ気にする人なんてめっきり減っちまったんだからなあ、俺たちの稼ぎもめっぽう減った。ああ、もうこんな時間か。それじゃあそろそろ行くか。大学の授業に遅れちまうからな」と敏夫は言って、軽トラのエンジンをかけた。
午前中の授業を終えた恵一は、ふみと昼ご飯を食べる約束をしていたので広場へ向かった。大学の銅像が立っている広場には、多くの学生達が青々とした芝生の上で、思い思いに過ごしていた。ふみが座っている広場の一角には噴水があり、恵一が見えるとふみは手を振った。「恵一、メールの返信ちょうだいよ。返って来ないから、友達と食べに行こうかと思った」とふみが言った。
ふみは、芝生の上にジーンズの長い足を伸ばして座り、眉間にわざとらしいしわを作って、笑顔を見せた。
恵一は「ごめん走ってきたからメールにぜんぜん気付かなかった」と言った。
「ふみ、小林って知ってるっけ?いつも俺と一緒にいる奴なんだけど、あいつ、英文のあの噂の美人の履修科目どこからか仕入れて来て、同じ授業取るらしいぞ」と恵一は言った。
「えーちょっと気持ち悪っ。ストーカーじゃんそれ」とふみは言った。
「この前なんて教室から教室まで後ろついて行ってたからな。かなりやばいよ。でもあいつ普通に頭いいんだよな。いつもテストでAは必ず取ってるもんな」
「へえすごい。じゃあもちろんもう就職も決まってるんでしょ」
「先週決まったんだって。大企業らしいぞ。広告業界って言ってたな」
「じゃあ私鞍替えしちゃおうかしら。なんて嘘だからね」
「はは、笑えないね」
「私も出来れば東京出たいんだけど、地元は落ち着くし悩ましいね。恵一はこれからどうするつもり?」
「まだまだ若いし、東京で新しい世界を見たいと思ってるんだ。自分の可能性の再発見だね」
「そんなキャラだった?それじゃあ二人で頑張ろうよ」
「そうだね。一緒に頑張ろう」
「手始めにこれ食堂で買ってきたよ。恵一のいつも食べている焼きそばパンと、フレンチトースト。このフレンチトースト絶対美味しいから食べてみて」
「いつも悪いね、さすがふみっていつも気が利くよな」
「またまた、こういう時だけなんだからそういう事言うの」
恵一は家の手伝いがない日は、一人暮らしをしているふみのアパートに行って酒を飲み、音楽を聴き、セックスをして過ごした。自由気ままな大学生活の幸せな堕落に二人は自覚なく流されていった。その日二人は授業が終わると恵一がバイクをとめた駐車場で人目を忍び別れのキスをして、ふみはバイトへ、恵一は家へと帰った。
日がゆっくりと山の稜線の先に落ちて辺りは暗くなってきた。自宅に向かっている恵一のバイクがまっすぐな道を走っていると、道路に並んだ外灯がいっせいについた。仕事を終えた人々の乗る車が慌ただしく通りを行き交い、恵一のバイクのヘッドライトが前を走る車のナンバープレートに反射して白く光っている。交差点で信号待ちをしていると、鬱蒼とした木々が生い茂る公園に、ゲームをしている男の子が一人ぽつんと取り残されている姿が目に留まった。急に不安に取りつかれた恵一は、公園の隣にバイクを止めた。
「ねえ君今一人かい。ゲーム面白い?」と恵一は尋ねた。
「面白いよ。これスーパーマリオって言うゲーム。お兄さんやったことある」と青いベースボールキャップを被った男の子は言った。
「そうだな。ずいぶん昔にやったことあるかもしれない。面白いよね。ところで君のお母さんはどこいっちゃたの」と恵一は言った。
「お母さんはお父さんと一緒に家にいるよ」五歳くらいの男の子はベンチに足をぶらぶらさせながら言った。
「じゃあなんで君は家にお父さんとお母さんと一緒にいないんだい」と恵一は言った。
「お母さんに公園にいるように言われたんだ」
「お父さんとお母さんは家で何してるの」
「二人は家でゲームしてるの」
その時どこからか女が現れた。
「俊介、ほらさっさと行くわよ」と女が言った。
黒い服を着た四十歳くらいの女の顔は痩せこけ、ほとんど艶のない髪を後ろで一つ結びにしていた。
「あなたどちら様?うちの子に近づかないでくれます」と言って母親はこちらを睨んだ。
「お母さんが呼んでるよ」と恵一は言ったが、男の子は黙ったままだった。ベースボールキャップを被った男の子は、帽子の下からちらりとこちらに意味ありげな視線を送ったかと思うと、母親の方へ歩いて行った。二人は公園を出て恵一の家の方へ歩いて行った。
その日の夜、恵一はテーブルに白い布を被せてその上に一階から持ってきた静物たち(リンゴ、パイナップル、白いウサギの置物、鉛筆)を運び布のかかった木箱に載せた。恵一はいっとき美大を目指していた時があって、予備校に通い詰めたのだが、まわりの人間との圧倒的な技術の差を見せつけられて、自分には美術の才能はないと思った。しかし、教師の説得もあって予備校は卒業したものの、結局普通の大学を受験した。今こうしてリンゴの濃淡を苦も無く描けるようになっているのは当時の苦労のお陰である。ウサギの目の黒い瞳を描こうと、3Bの鉛筆を持ってはみたものの、公園での出来事が頭から離れずに、なかなか進まない。ウサギがこちらを見返しているように見える。
「あの子供の視線はなんだったんだろう。あのままあの女に子供を連れて行かせて大丈夫だったのだろうか。もしあの女が犯罪者だったとしたら今頃あの子はなんらかの事件に巻き込まれているはずだ。そうなったら俺も同罪だ」恵一は自分を責めた。
寝る間際になっても布団の中で30分ごとに目が覚めた。
一段と暑い夏の日、節子は台所に立ち素麵の水を切っているところに、誰かが家のチャイムを鳴らしたので、急ぎ足で玄関へ行った。「あら新ちゃんじゃない。どうしたの急に。今日はお休み」
「いや、最近晴れてばっかりだから、ちょっとこの辺散歩してて、敏夫さんの調子はどうかなって思ってね」と新一郎は言った。
「そうだったのね。敏夫はいつもの通り、まっ昼間からビールですって。ほんと困っちゃうわよねえ」
「奥で呑んでるからいらっしゃいな。まだ新聞屋さんからのビール券たくさんあるわよ」と節子が言った。
「悪いね、じゃあちょっとお言葉に甘えて」
敏夫は居間で野球中継を見ていたが、応援しているチームがボロ勝ちだったので、たいして面白くもなく、ただ黙ってビールを吞んでいた。突然居間の扉が引かれた。
「おー、新ちゃんじゃないのよ。どうしたってこんな時間に訪ねて来たんだって。まあ座って座って。今一人で寂しく飲んでたんだよ。節子ビール、ビール持ってきて」と敏夫が言った。
「やあ悪いね。こんな時間に突然お邪魔しちゃって。連絡しとけばよかったなあ」新一郎は敏夫の向かいの座布団に座った。
「恵ちゃんはどうだい最近」と新一郎が言った。
「いや恵一はぷらぷら遊んでるよ。この前虹出させてやったんだが、めんたま丸くしていやがったよ。あれは新ちゃんに見せたかったなあ」
「そうか。あの恵ちゃんが虹をねえ。恵ちゃんが子供の時、昔あの虹はどこからくるの?なんて言って、あんときは可愛かったなあ」
「まさか自分の家から出てると思わんだろうね」敏夫は新一郎のグラスにビールを注いだ。「おっと、これくらいでこれくらいで」新一郎はグラスに手をやった。
「最近商売の方はどうかね、こっちはまったく上がったりだよ。あいつら卸の方にも手回してるみたいで、こっちは何色も欠品してるよ」新一郎は言った。
「そうかい。やってくれるねえ。そろそろ痛い目をみせねえと分かんねえようだなあ」敏夫は言った。
「どうやら虹システムの方はAIとかいうコンピューターが俺達の仕事をやってるみたいだよ。そうなりゃ俺達も失業だねえ」
「AIっちゃあ、なんかテレビで言ってたな」敏夫が言った。
「暗い話になっちまったな。ちょっと様子見に来ただけだから、そろそろ帰るよ、急に来ちゃって悪かったな」と新一郎は言った。
「なあにお前さんならいつでもよ」
「新ちゃん帰るの、ほらこれ持って行って。家でとれた小松菜。こんなに家で食べられないから」と節子が言った。
「節子さん悪いね。あとで家内に連絡させるよ」
新一郎は帰り支度をして玄関を潜ろうとすると、ちょうど門の前に仕立てのいいスーツを着た65歳くらいのきれいな白髪の男が立っていた。
「すみませんこちらは田中さんのお宅でしょうか」と男は言った。
男は玄関の前で百日紅を見上げていた。
新一郎とすれ違いざまに男は軽く会釈をした。新一郎も軽く会釈をしていって出て行った。
「すみませんがどちらさまで」と新一郎を見送った節子が言った。
「ああ、すみません申し遅れました。私、虹システムズで専務をしております。小澤と申します。」と男は言った。男はスーツの背広の内ポケットからハンカチを取り出し、額の汗を拭った。「いや、それにしても暑い」
ミンミン蝉が庭の木蓮の辺りから他の蝉に負けじと我先に鳴いていた。
節子は小澤の磨き上げられた黒い革靴と、贅沢な生地で作られたスーツに目を見張った。
「ああ、あの虹システムの…」節子は言った。
「今日は差し当たってお願いに参りました。ご主人様いらっしゃいますでしょうか」小澤は言った。
「ええ、呼んでまいりますので少しお待ちくださいね。お父さんーー」
「ここにいるよ」敏夫が言った。敏夫は玄関の入り口に立っていた。
「どうぞあがってください。きたねえ家ですがね。さあさあ」
小澤は敏夫に向かって軽く一礼した。「ご主人様ですか。どうもはじめまして、私……」
「さあ先に入って入って」敏夫は右手で家に招き入れる仕草をした。
男は居間に入ると自分を小澤と名乗り居間の敏夫の向かいに座った。
節子はお茶を小澤に出した。「すみません奥さん、いただきます」
「田中さんの家の百日紅は実にきれいですなあ。植木屋に頼んでるんですか。それともご自分で。いやそれにしても見事だ。うちはこんなに咲きません。きっと日当たりがいいんでしょうなあ」小澤が言った。
「うちのは植木屋に頼んでますよ。植木屋が言うには切り方が大切だって言うんですがねえ。わたしには全然隣の木と違わねえと思うんだが、プロには分かるんだろうよ」
「切り方ですか。ほうなるほど。うちの植木屋にもちょっとこずいてやらんといけませんねえ。庭全体きれいで羨ましい」
「家内も色々やってくれるもんだからねえ。ところで今日はどういったご用件で」敏夫が言った。
「おっとうっかり要件を言わずに帰るところでした。年にはかなわんですなあ。この前なんか家内の言う事がへんてこに聞こえましてね。心配になって病院にいきましたら、ただの疲れからくる耳の不調だなんて。嫌ですねえまったく。しかし、わたしもこんなこと言わずに帰れたら楽なんですがねえ」
「それでねえ、用件なんですが、田中さん、事業から手を引いてほしいんですよ」小澤が言った。
「事業から手を引くだあ、あんたなあに言っとるんだねえ」敏夫はテレビを消した。
「動揺するのは分かります、分かります。落ち着いてください。でもね、それが皆さんにとって、町内会の皆さんですが、最善の選択肢じゃないかと我々は考えているのですよ」
「誰もそんな話に賛成する奴なんておらん」敏夫が言った。
「まあまあ聞いてください。もちろんタダでとは言いません。売却金といたしましては、大体これくらいを見積もっているんですがね」小澤は鞄の中から紙を一枚取り出しテーブルの上にのせた。「どうですか悪くない金額でしょう。田中さん息子さんいらっしゃるんでしたかな。まだまだ学費のローンなんかかかるんじゃありませんか」蝉の声がいちだんと高く庭に鳴り響いた。
「あんた馬鹿にしてんのか!」
「おとうさん!何そんな大声出して」節子が走って居間へ来た。
「何か無礼でもありまして」節子が言った。
「いやいや意見の相違といいますかね。よくある事なんですよ。我々も長く事業を行っていますから、そのようなお気持ちは非常にご理解してるつもりなんですがね」
「あんたらのせいでこちらとは迷惑しとるんだ!勝手に卸に手を回すはで商売にならんのだがな!嫌がらせはそろそろ終いにしてくれんかなあ!」
「はあ、嫌がらせですか。あまり心辺りがありませんがね」
「とぼけるんじゃないよ、とぼけるんじゃ」
「お父さん!」
小澤は立ち上がりゆっくり玄関へ向かった。
「あらおかえりですか」
「ええ、また寄らせていただくかもしれません。今日はお茶ご馳走様でした」と小澤は言って、玄関を閉め、百日紅の花の周りをぐるぐる回る黒い蜂を見上げた。
Tシャツで町を歩くには肌寒い季節になった。恵一がふみとの約束に遅れる理由は様々あるが、よくある理由は目覚ましのアラームをかけ忘れ、起きたあとの朝のやわらかい日差しの中で、また心地いい眠りに引き込まれていくことだった。恵一がバイクのカギを回す時に、ふみは古着屋の一階にあるカフェで秋の日差しの中コーヒーを飲んでいた。恵一がカフェに入ったときに、ふみは二杯目のコーヒーに角砂糖を入れているところだったが、彼女の呑気な性格が幸いして恵一はいつも非難を免れるのだった。ふみの母性がぎすぎすした雰囲気を丸めてしまった。
ふたりは古着屋の中に入りクローゼットに服がパンパンにかかったハンガーの中から秋に着るための洋服を必死になって引っ張り出していた。「ふみこんなのはどう、ストーンウォッシュのリーバイス」恵一が言った。
「うーん、さっき見たコーデュロイのブーツカットの方がかわいいかも、でも一応両方試着してみるね」ふみが言って、試着室に入りリーバイスを履いて出てきた。
「おー、なかなかいいじゃん。フラッシュダンスって感じ。それにオーバーサイズの白いスウェット合わせてみたら」恵一は言った。
ふみはその場で一回転した。「フラッシュダンスー?それだったらやめとこうかな」今度は茶色いコーデュロイのパンツを履いて試着室から出てきた。
「うん、まあ、どこでも買える感じかなあ。あえて言うならバックトゥザフューチャーパート3のマーティーって感じだね」恵一が言った。
「フラッシュダンスかマーティーかあ。どうしようかなあ」
ふみは古着が並んだ通路を手でハンガーに触れながら歩いた。店内は古着の匂いをごまかすためのお香の香りが充満し、レジの方を見ると積みあがった服と服の間から店長のドレッド頭が見えた。
「恵一の服ちょっと見たら店でよっか」ふみが言った。
最終的に恵一は、大脱走のマックイーンが着ているような茶色い革の上着を、ふみは黒い鞄を買った。
「このあとアイスクリーム食べに行こうよ。話題のお店がこの近くに出来たんだって」とふみが言った。
「もう大人なんだからアイスなんて恥ずかしいよ。俺この水で十分」
「水なんてつまらないじゃん!」ふみは恵一の来ている上着の袖を引っ張っぱって行った。
「恵一携帯鳴ってない」とすぐにふみが言った。
「母親からだ。こんな時間に珍しいな」恵一が電話に出ると母親が電話ごしに言った。
「恵一、お父さん倒れたから、すぐに病院に来て。病院の場所は分かるわね。できるだけ急いで」
「いったいなにがあった?」
「昼間なかなか工場から帰って来ないから、見に行ったら。お父さん倒れてたの。今救急車の中だから切るわね」
電話はぷつり切れた。
「ふみ悪いんだけど。父親が倒れちゃたみたいなんだ。すぐに病院に行かないといけないから、悪いけど今日は帰るよ。この埋め合わせは絶対するから」恵一が言った。
「お父さん大丈夫なの?気にしないで。早く帰ろ」
二人が電車に乗ろうと駅のホームで待っていると、黒い雲がどこからか現れて雨を降らした。しかし、それは長くは続かず雲は移動して太陽が現れた。太陽の光を受けてビルの後ろから二色欠けた虹が見えたが、太陽はまたすぐに姿を隠し、虹はほんのわずかの時間で消え、黒い雲がまた空を覆った。
病室のカーテンが生ぬるい風に吹かれて波打ち、部屋は消毒液の匂いが充満していた。敏夫は酸素チューブに繋がれベッドの上に横たわり、顔には苦悶の表情をうかべて、何か独り言をつぶやいていた。恵一が扉を開けると医師がちらりと目をやった。「息子さんですか、どうぞ」若い医者が席を勧めた。恵一は節子の隣に座った。母親は敏夫の方を見つめていた。
「お父さんですが、おそらく過労のため気絶したのでしょう。もしかしたら脱水症状を起こしている可能性もあります。今は点滴で栄養を取っていますから、すぐに帰れると思います。しかし無理は禁物ですよ。しばらく仕事も休んだ方が良いでしょうね。お酒は飲まれます?」若い医者は言った。
「ええ、かなり」恵一が言った。
「そうですか。酒は万病の元と言いますからね。本当に気をつけてくださいね。酒がもとで棺桶に入った人なんてはかり知れませんからね。特にあなたみたいな若い方ほどアル中になりやすいんですからね。アル中ってご存じですか」と若い医者は言った。
「もちろん」
「あれはみっともないですね。私がアル中になったらきっと田舎の方へ引っ越すでしょうね。恥ずかしくて町にはいられません。彼らの末路は刑務所か河川敷の橋の下と相場は決まっているんですからね」
「はい」
「とにかく酒は飲まない。飲むなら毎日適量。いいですね。テレビCMを見るとおいしそうだから、ついつい若い人ほど飲んでしまいますがね。そろそろ日本も規制しなきゃな」
医師は敏夫の方を見た。
「彼もある意味、犠牲者ですよ。それを正常にするのが我々医者の役目ってわけですね。結局プラスマイナスゼロですよ。なんのためにやってるのやら」若い医者はすっと立ち上がった。
「それじゃあ私はこれで。あとは目が覚めたら帰れますから。詳しいことは看護師に聞いてください」と医者は言って病室を出て行った。
敏夫が目を覚ましたときには、恵一と節子はうつらうつらとしていたが、敏夫がコップの水を啜る音で目が覚めた。
「お父さん起きたかい、そろそろ帰る時間だよ」と恵一が言った。
「心配したんだから。あなた仕事のやり過ぎよ」節子が言った。
「心配かけたな。もう大丈夫。俺は一家の大黒柱だからな。いつまでも寝てるわけにはいかねえぜ」と敏夫は言った。
病室を出た敏夫は、右肩と左肩を妻と息子に支えられ、病院の裏の通用口から外に出ると、三人の顔をなでる秋の風がひんやりと冷たかった。
それから一週間後の夕方、恵一が画材を買いに川沿いの文具屋まで歩いて行こうと玄関を開けると、町の集会所の方から夕焼け小焼けが放送で流れてくるのが聞こえ、犬が曲に合わせて吠えていた。恵一がしばらくいつもの道を歩いて行くと、右手の古アパートの前にパトカーが一台止まっていて、パトカーの回転するランプが周囲の家を赤く染め、アパートの住人が何事かと窓から身を乗り出していた。警察官が一階の開けっ放しになっている部屋の前に立ち、恵一が近づくと、なにやら中の住人と会話しているのが聞こえた。ふと、アパートの階段を見ると大学の帰り道、夜の公園にいた男の子が座っていた。
「やあまた会ったね」と恵一は言った。男の子は何も言わない。
「この前会ったよね」と再び言ってはみたものの、男の子は黙り続けている。
「お父さんが誰とも話すなって」と男の子は小声で言った。
「警察の人がうちに入ってきた」と男の子は言った。恵一が昼間の光でよく見ると子供の顔は頬がこけ、目の隈は濃く、表情は乏しく、腕やふくらはぎには生々しい青あざがいくつかあった。
すると、開けっ放しの扉からうるさい女の声が聞こえてきた。
「やってないっていってるじゃないですか。そんなこと言うなら証拠見せてよ」
「奥さん証拠はあるんですからね。いいかげん中にいれないなら、令状とって強制捜査ですよ。そんなめんどくさいこと嫌でしょう。とりあえず腕見せてくれますか」今度は警察官の声だ。
「やっぱり跡ありますね、いちおう署に来てもらって検査しますからね、旦那さんも一緒に来てください」
「俺もかよ、やってねえっていってるじゃねえかよ!」男が叫んでいる。
「先ほどもいったとおり証拠はでてますからね。さあいきましょうか」
パトカーからもう一人の警察官が出てきて応援に駆け付け、二人でいっせいに夫婦をパトカーの中に押し込んだ。恵一が見ると夫婦はパトカーの中で大人しく前方を見つめていた。野次馬は先ほどよりもさらに身を乗り出した。
「すみません、階段にこの夫婦の子供が取り残されているんですがどうしたらいいですか」恵一は警察官に駆け寄って言った。
「それは残念ながらあなたの関与するところではありませんよ。今福祉事務所の人間が向かってますのでそちらに任せてください」警察官は言った。
警察官はパトカーに乗り込み、サイレンを鳴らし騒々しくアパートを去って行った。
恵一があっけにとられていると、すぐに福祉事務所の人間がやって来た。「失礼ですがあなたはこのお子さんとどんなご関係にありますか」と福祉事務所の女が言った。「ぼくは何の関係もありません。ただここを通りがかっただけで」恵一が言った。
「通りがかっただけですか」女は繰り返した。
「そんなに怪しまなくても。近くに住んでいるんです。パトカーが止まっているから近くまで来たらあの子がいたから気になって」恵一が言った。
「とにかく第三者なのですね。分かりました。この子はいったんこちらで預かります。心配でしょうがプライバシーの観点からどこにいるかは教えられません」と女は言った。
女はいらいらした様子で男の子の手を取ると、福祉車両へ連れていき、ドアを閉めた。子供がガラス越しに手を振り続けているにもかかわらず、車は先ほどのパトカーと同じくどこかへと走り去っていった。
朝日がカーテンの向こう側から部屋をぼうっと白く光らせてる。恵一が目覚めると、庭の鳥がけたたましく鳴いていた。敏夫が過労で倒れてからというもの工場は静かになり、虹出しは恵一の仕事になった。
敏夫が数か月使っていなかった機械や、道具は埃が溜まり、カビくさい工場の床に、窓から入ってきた落ち葉が風に吹かれて隅の方へ舞って行った。恵一が箒で床を掃くと何かがガサガサ動き、完全に昇りきった太陽の光が工場に差し込んだ。
恵一は巨大なダクトを天井からクレーンで引き下げ、箱の中に七色の色を用意した。虹を出す予定時刻は3時だったが、青空が広がり雨が降る気配もないので、仕方がなく、恵一は部屋からデッサンノートの入った黒い鞄を持ち出して公園へ向かった。
公園の三本のケヤキの大樹は、太陽を受けて黄色に輝き、その下でサッカーボールを追いかける八人の少年達が砂埃を上げていた。椎の木陰になったベンチに座った恵一は、デッサン道具を取り出して、ケヤキの細かい葉の形状や、子供の走り回る姿を瞬間的に紙に写した。恵一の鉛筆は素早く動き、日光の下の物の形を正確に描いた。ホームレス姿の男が、荷台に乗せたがらくたをリヤカーで引きながら現れ、公園のごみ箱の中に上半身を入れて何か取り出していた。そのとき、公園の前の空き地に古アパートで見た福祉車両が止まった。中からベースボールキャップをかぶった男の子が降りて公園に向かって歩いてきた。少年は恵一にすぐ気づくと手を降った。
「おにいさんいつもこの公園にいるね」男の子が言った。
「今日は絵を描きに来たんだ」と恵一は言った。
「どれどれ見せて」少年はベンチの隣に座り恵一の描いた絵を覗き込んだ。「へえーすごいすごい」と男の子は目を輝かせた。
「ありがとう」
「ぼくもこれやりたいな」と言って、男の子はサッカーで遊ぶ少年の素描を指さした。「君も混ざってくればいいじゃん。ちょうど一人足りないみたいだし」恵一は少年たちの方を見た。男の子は恥ずかしそうに首を横に振った。
「そういえばお父さんとお母さんは帰ってきたの」恵一が言った。
「お父さんとお母さんはまだ帰ってこないよ」男の子はこの前とくらべて表情が明るい。
「そうか。君も大変だな。まだあの家に住むの?ひとりじゃ暮らせないだろ」恵一が言った。
「今日引っ越しするんだ。べつのところで暮らすんだ。友達もたくさんできるんだって。あの女の人が言ってた。3時ごろに出かけるの」
福祉バスの中から女がじっとこちらの様子をうかがっている。
「そうか、さみしくなるけど頑張ってな。そうか3時ならちょうどいいや。もうすぐ雨が降ってきて、3時には雨があがるはずなんだ。そのあとに虹が出るからよく見ておいてくれよ」恵一が言った。
「虹?虹がでるなんてどうしてわかるの?」
「お兄さんは分かるんだ。きっと出るから信じて待っていて。お別れの虹だよ」
「わかった」男の子は言った。男の子は少ししょげているように見えた。
「ここだけの話なんだけど、君が見てる虹は僕たちが出してるんだ」
男の子はきょとんとした表情になった。
「虹は七色あるだろ。あの七色は世界中の国から出来てるんだ。アメリカやカナダやフランスや中国やインドネシア、たくさんの国からね。インドネシアって分かるかな。まあいいや。とにかく君が虹を見たときに世界中と君はつながっているってことなんだ。そう考えるとどこへ行っても寂しくないだろ」恵一が言った。
男の子は不思議そうなをした。
「だからどこへいっても僕らは一緒にいるってことなんだよ」
男の子はうなずいて帽子をかぶりなおした。そのあと「おにいさんさようなら」と言った。恵一も手を振った。男の子はバスに向かって歩いて行った。
バスが走り出す時も窓ガラス越しに男の子はこちらに手を振り続けていた。
恵一が家まで歩いていると、空が急に暗くなり、黒い雲が西の方角から流れてきた。はじめは額に軽く触れる程度の雨だったが、すぐに強く降り出し、気づくと恵一の上着は色が変わるほどに濡れていた。恵一は走って家にたどり着くとすぐに虹を出す準備に取り掛かった。
大きな木箱が恵一の乗ったリフトに運ばれてダクトの下に固定された。恵一はリフトを降り、虹の入った筒を取り出して、一色ずつ木箱に流し込んだ。木箱の中はキラキラと七色に輝いている。すると屋根の雨音がしだいに静かになってきた。恵一は窓辺に行って空を見上げると、雨雲の隙間から太陽の光が差し出した。壁下の小さな穴の方を見ると光が徐々に強く輝き出し、光の液体がどろりと工場へ流れ込んできて、大きな桝の中に溜まった。恵一が重い鉄板をどけると、強い光が空に昇った。
福祉事業所の女が不動産業者と退居の手続きを進めているあいだ、男の子が古アパートの廊下で雨を眺めていると、遠くの山の頂上あたりの雲がちぎれて青い空が広がってきた。すると急に強い太陽の光がアパートを差して、かれの部屋の靴箱やカーテンレースを黄金色に輝かせた。男の子がふと空を見上げると大きな虹がアパートの上に出ていた。
男の子は虹の終わり見ようとアパートの外に飛び出すと、虹は山の麓の所に消えているようだった。
「やっぱりほんとだったんだ!」男の子はまだ小雨が降るなかを公園の方へ走って行った。
敏夫と節子は居間でせんべいを食べていた。さっきからの雨がいつ止むか今か今かと待ち望んでいた。すると庭の池の波紋がしだいに小さくなってきた。「さあでるぞでるぞ。恵一の仕事とやらをみせてもらおうじゃねえか」
「まあまあそんなに熱くならずに。またすぐ仕事したくなるんでしょうから」
敏夫と節子は縁側から庭に出た。飛び石に足を滑らさないように気をつけながら、空を見ると、工場から巨大な虹が山の方角に向かって出ていた。
「最初にしちゃあなかなかやるじゃねえかよ。うんきれい、きれい」
「恵一の初仕事ね」
ふたりは居間に戻り、テレビをつけて、またせんべいを齧り出した。
恵一は窓から大きな虹が出ていいるのを確認すると、ふみに電話した。
「今虹が出てるの見れる?」恵一が言った。
「あーちょっと待ってね。わー出てる、きれーい」ふみが言った。
「あれ俺の初仕事なんだ。なかなかきれいだろ。腕を磨いてもっときれいな虹を出してやろうと思うんだ」
「初仕事?虹を出すってなんのこと?」
「ああそうか。まだ説明してなかったんだった、また今度説明するよ」
恵一は東京に就職する約束をすっかり忘れて、「しまった」と思った。
虹は再び町にアーチをかけて、人々は同じ虹を見つめ、喜び、泣き、笑い、またいつか会えると希望を持って、消えゆくときをただ待っているのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
