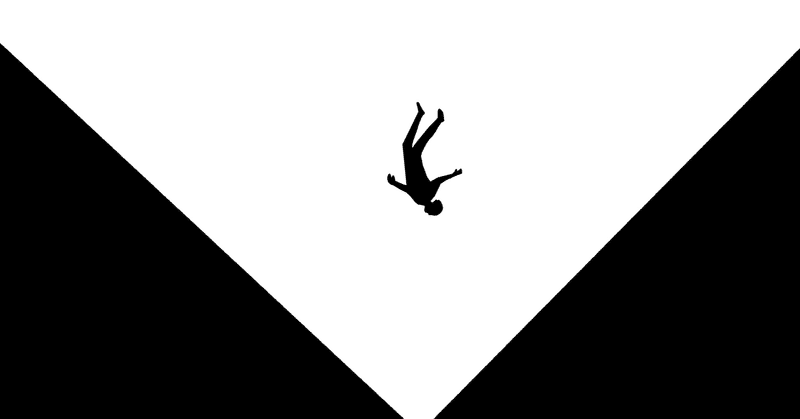
中国の若者達は将来の不安から貯蓄に励んでいる/中国も日本も実は同じ傾向になりつつある?
意外と堅実?中国若者のマネー事情
https://news.yahoo.co.jp/articles/a0456568b78b794fbce847c2d053fe62a9569e5f?page=1
中国の消費の主体が既にZ世代に移り変わりつつある現在、逆に彼らの借金額の大きさが指摘されたりと、なかなか刺激的な内容が色々なメディアで記事にされているが、この記事によると都市によってそのデータは違うものになるという。
中国中央銀行が発行する「中国统计年鉴(中国統計年鑑) 2021」(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm)によると、2020年12月の家庭での貯蓄額は93兆元。それが2021年6月には100兆元に増加しています。国内経済の成長を祝うという論調で報道されました。中国では16歳以上ならば一般的な銀行口座を開設できます。16歳以上の人口は約11億5000万人なので、100兆元を単純にこの人数で割ると8万7000元(約160万円)となります。
ただ、この数字だと貯蓄をしていない人も多く含む数字となってしまうので、これはまず正しくない。
北京市の貯蓄額は約4兆元で、1800万人(16歳以上人口)で割ると一人当たり約24万元。全国平均の3倍近い金額です。筆者が住む広州市は一人当たり13万元。北京とはだいぶ差がありますが、それでも全国平均よりは多いです。
これも北京でというデータであるのと、北京でも「退休幹部・軍人」が100万人いて(上海は3万人程)、彼らの「年金」は10,000〜30,000元/月というデータがあるし、金持ちの貯蓄額はこれより更に遥かに上をいく数字となるので、あくまで参考程度となる。
中国における貯蓄の大きな特徴は、収入に対する貯蓄の比率(貯蓄率)です。経済データをを提供しているCEIC Data(https://www.ceicdata.com/ja)によると、2010年の貯蓄率は51%、2020年にはやや下がって45%です。それでも日本は20~30%、米国は5%程度と見られているので、中国は貯蓄率が圧倒的に高いと言えます。
私が大学生の時、丁度世界各国の貯蓄率を比較研究していたのだが、当時のアメリカの貯蓄率はマイナスであった。つまり、借金してでも消費活動を行うというデータだったのに、今では少しは貯蓄をするようになったという点に驚いている。
ちなみに、日本の貯蓄率についてよい記事があったので、下記にあげておく。
貯蓄率減少は本当なのか否か、家計の貯蓄率を複数視点で確認する(2021年公開版)
https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20210418-00231918
これを見て見るといわゆるZ世代の人達の黒字率は30〜32.5%とあり、貯蓄は出来る状態にはあるが、この黒字額のどれだけが貯蓄に回っているのかは正直分からない。
Fidelity Investment Groupとアリババの金融関連会社アントグループが発表した「中国养老前景调查报告(中国の年金見通しに関する調査報告)」(http://www.fidelity.com.cn/zh-cn/market-insights/china-retirement-readiness-survey-2020/)によると、35歳以下の若手層は収入の25%を毎月貯蓄しています。これは2020年の20%から増加しており、2018年の調査開始以来の高い数値です。この貯蓄傾向の背後には、老後に対する不安の高まりがあるかもしれません。2035年以降、中国の年金にあたる、「养老金基金」が赤字になるという予測が出ています(「中国养老金精算报告2019-2050」、http://www.cisscass.org/yanjiucginfo.aspx? ids=26&fl=1)。また、前述の「中国养老前景调查报告」によると、若手層が定年に備えて目標とする貯蓄額は155万元。35歳以上が目標としている139万元を上回っています。つまり、年金があてにならない状況が明らかになってきたことで、貯蓄を増やしてそれに備えようという意識が芽生えてきていると言えそうです。
一時の好調な経済に比べると現状政府が認める程景気は失速段階に来ている中、若い人達を中心に将来に備えて貯蓄を行うというデータが浮かび上がっているのである。そういう意味では中国も日本も同じような状況になりつつあるのかもしれない。
今日はここまで。じゃあの。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
