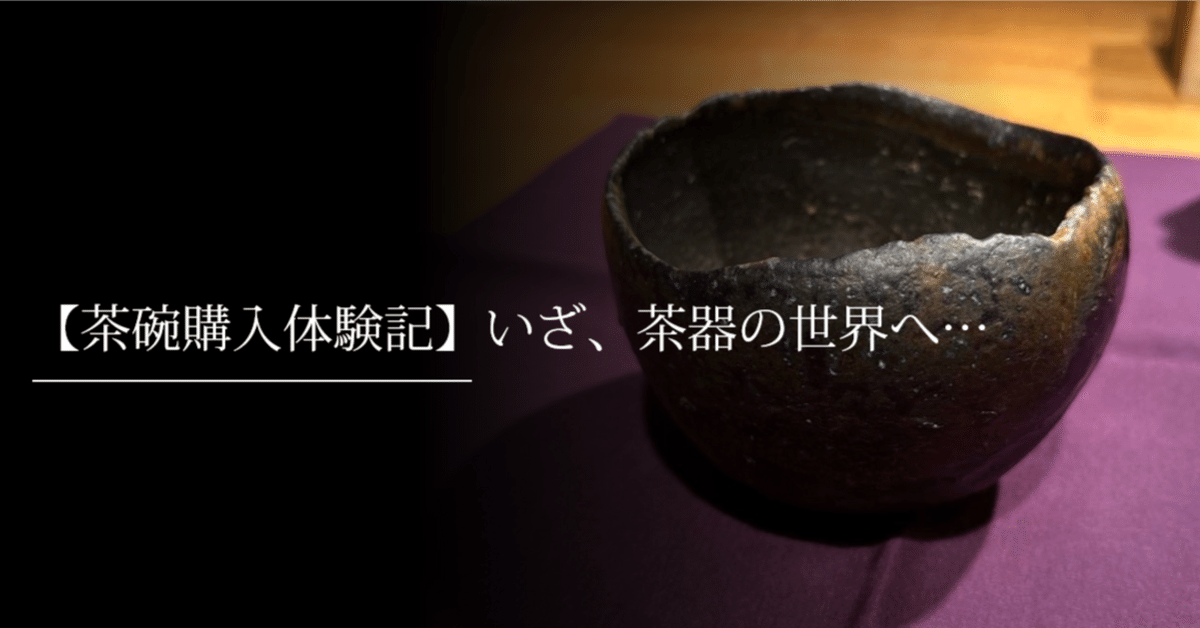
【茶碗購入体験記】いざ、茶器の世界へ…
先日東京国立博物館で「本阿弥光悦の大宇宙」展を見に行った際にぼんやりとしていた自分の中の理想の茶碗像という物が明確になった。
形で言えば乙御前、色は紙屋。
360度全方位から見える展示であれだけ魅了された作は今までなかった。
勿論本物が手に入れば言う事は無いが手に入るわけはない。
そんな感動以降、ネットで本阿弥光悦の乙御前や紙屋を写した作が多数ある事を知った。
しかしどれも色の深みが足りないように感じたり、形が整い過ぎてイマイチつまらない。(あくまで画像上で見ただけの判断でしかないが。)
これが光悦ゆえの凄さなのだろうか…。
欲しい物のイメージがボヤっとしていた状態でかれこれ1年以上茶碗を探している気もするが、イメージが固まってもなかなか「コレ」という物が無いものだなと感じる。
因みに茶器は現代作に絞って探している。
古い物で気に入ったものは得てして50万円以上するし、知識不足ゆえ真贋が分からない。使うにも勇気がいるのでなかなか手を出しにくいというのが本音である。
一方現代作は誰が作っているかはっきり分かる安心感と気持ち的に使いやすい感じがある。
知識が付けば刀同様に古作ならではの堪らない味がきっとあるのだろう。
しかしまず最初の茶碗は現代作で慣れる所から始めてみたい。
刀でいう所の現代刀や新々刀からスタートする感じに近いだろうか。
そして昨日、ネットで探していたところ画像越しではあるものの光悦の作を見た時と近い心に何か訴えて来る、心を震わせてくれるような茶碗を見つけた気がした。
色や形が俄然好みであった。
早速問い合わせてみるとまだ在庫があるとの事で急遽来店する事に。
いいなと思った物をクリックすると既に売約済の表記となっている事も多いので、在庫があるというのは何とも嬉しい。
縁は時に獲りに行くものである。(と少し恰好良い事を言ってみる。)
・いざ茶器専門店へ初入店、そして対面
初めての茶器の専門店。
非常に緊張する…かと思いきや意外に刀屋さんと比較すると緊張しない。
ドアもなくオープンなお店だったから入り易かったというのはあるかもしれない。

地味に良く行く刀剣店の霜剣堂さんから徒歩10分くらいの位置にあった。
これも何かの縁だろうか…

早速問い合わせていた茶碗を出して頂ける。

お、お、お、お、お、


お、、おおおおお・・・・!

こ、こ、こ、これであるっっっっ!!!ヒョオウッッ!!!
程良いザラザラ感、見る角度によっては艶のある場所があり、時に釉が強調された荒々しい面もあれば、少し青みがかって地色に星のようなキラキラとした部分の見える箇所もある。
ずっしりしているが、手持ちは良い。
形も味わいある「歪み」を持っている気がする。
手びねり(粘土を手でこねるようにして)で作られた作品との事で、どうやら本阿弥光悦も手びねりで製作しているらしい。
形などが乙御前に少し似ているのもそうした所があるのかもしれない。
以下の部分は釜の中で火が直接当たった部分で、

青く星の様に見える以下の部分は火が直接当たっていない部分だそうで。
変化が実に面白い。

光悦の紙屋と色味はだいぶ違うが、これはこれで感動させられた。
・様々な茶碗を拝見
他にもいくつか見せて頂けた。
まずは丸みのある織部。

見る角度を変えると表情がガラッと変わるのも面白い。
この織部は丸みがあり全体的に艶やかで手への納まりが非常に良かった。
茶碗にしては少し小ぶりな感じだろうか。
この緑色がことに美しく、最後まで悩まされた。

以下も釉が非常に良い風合いで垂れているように感じる。
黒っぽい色味に白い釉が垂れ、オレンジの様に見えているような茶碗である。光にかざすとキラキラと光るのも非常に美しい。

飲み口の厚さや形も全て異なるが、こちらは比較的分厚い印象を受けた。

皆どういう基準で茶碗を選んでいるのか聞いてみた所、使う人と鑑賞(展示)する人で分かれるらしい。
なんと、刀と同じではないか。
使う人は手持ち感など手への納まりも重要な要素として見るらしいが、鑑賞する人は形にある角度での見え方にこだわるとの事。
私はどちらかと言えば後者になりそうな気もするが、使ってみたい気持ちもあるので前者寄りでもあるだろうか。
以下はまた少し大径の茶碗。
表面がザラザラし、中は艶のある飴色をしている。
尚この黒色、先の緑色の織部と同じ釉を使用しているらしい。
どうやら火の強さや土に含まれる鉄分の量などで緑にも黒にもなるとの事。
まさに自然の神秘を垣間見た気がする。


以下はまた一風変わったもので、非常に薄造りで木の肌のような質感をしている。


中はブロンズ色とでもいうべきか、ゴツゴツキラキラしており、一種の宝石を見ているような感覚になる。

そして今流行りの曜変天目。
説明不要の美しさを兼ね備えている。


・ついに購入
色々見せて頂くなかで緑の織部茶碗が候補に急浮上してきたものの、形が整い過ぎていた事もありもう少し変化が欲しく、やはり最初に見て心震わされた以下の茶碗に決めた。
渋い色なのもまた良い。

お店の方に本阿弥光悦の乙御前と紙屋に惚れ、この茶碗にも同様に何か不思議と惹かれるという話をしたところ、「本阿弥光悦の手びねりによる緩やかでありながらも細部まで行き届いた造形には感嘆させられます。こちらの茶碗も手びねりで制作されており、絶妙な形と口や高台のつくりに隠崎隆一先生の美意識が込められています。正面の釉の流れは勢いがあり、窯の中の炎を写し取ったかのような景色となっていて、黒の中から覗く青色も美しく、岩の中に眠る鉱石を想起させます。大胆さの中に込められた無数のこだわりや美意識に本阿弥光悦と通ずる部分を感じられたのかもしれませんね。」とのこと。
なるほど…そのような所に光悦との共通性が。
無意識に共通項を頭で認識するのが人間なのかもしれません。しかし美しいという表現を別の言葉で具体的に説明できるのは知識あってこそで格好良いですね。徐々に知識を付けていきたいと私も思いました。
という事で1年以上にわたる茶碗探しの旅も終わりを迎え、ようやくスタートラインに立てました。
これから茶碗箱師、もしくは器箱師としての新たな人生がスタートするかもしれませんし、しないかもしれません。
茶碗は後日郵送してもらうことにしたので受け取りが楽しみです!
この茶碗の作者である隠崎隆一さんの事などについては私もまだ調べきれておらず良く分からないので、また届いてから別のブログで書こうと思います。
今回も読んで下さりありがとうございました!
面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。
記事更新の励みになります。
それでは皆様良き刀ライフを!
続き↓

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
