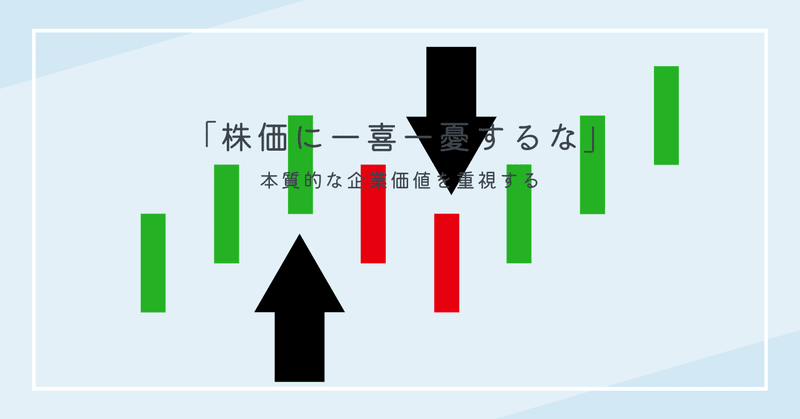
株式の非公開化について思うこと
おはようございます!
バタバタしており久しぶりのニュースから考えよう投稿。
今日は株式の非公開化について。
先日東芝は臨時株主総会を開き、同社株式の非公開化に向けた議案が承認された。1949年から続く株式上場は12月20日に廃止となる。
あまり経済ニュースが報道されない日本国内のテレビニュースにおいても報道されるくらい大きな節目となるニュースであった。
先日シダックスやベネッセのMBOの件を記事にまとめたが、株式上場に思惑があるように非公開化には様々な思惑がある。
企業が上場する理由
多くの企業がIPOを目指し準備を進めている。かくいう私もIPO準備企業のコンサルをしたり、時折役員をしたりしている。
なぜ企業が上場を目指すのか?
資金調達
上場時の株式発行により資金調達ができます。この資金需要が一番の理由である会社が多いのではないか。また、上場後の方がデッドでの調達もしやすくなることが多いだろう。
与信確保
新規の取引先と取引を開始する際にも与信を確保しやすい。そもそも上場していて世間に知れ渡っている会社である方が取引自体開始しやすい場合が多い。
人材確保
これも切実。特に新卒採用には上場企業であることが重要になるように思う。力試し的にベンチャーに入ってのし上がる人もいるだろうが、多くの場合はまず大企業で経験を積むことを選ぶ人が多いイメージだ。これは実際に上場後の方が人が確保しやすくなったという企業の話をよく聞く。
あとは、経営者個人的には自身の箔がついたり、持ち株が上場することで資産性がupするといったこともあるだろう。与信確保や人材確保は必ずしも上場しなければなしえないことではないかもしれないが、信頼を勝ち得たり、ブランディングをしたりというある程度時間が必要な工程を上場することで割愛することができる(かもしれない)。そして、普通に企業運営をしているだけでは、こんなに一気に資金調達ができることもない。
上場は”タイパ”がいいのだ。
企業が非上場化する理由
時間効率を最大化することができた上場ではあるが、果たして上場し続ける意味はどの程度あるのだろうか?上場するということはかなり維持コストがかかる。四半期の決算を開示し、監査法人の監査を受ける必要がある。株主総会の開催もリアル開催の場合はかなり工数がかかるし、J-SOXだって必要以上に負担になる会社もあるだろう。
四半期の決算を開示することで短期的な利益目標の達成へのプレッシャーを感じることになり、思い切った戦略転換に踏み切れないこともある。株主との対話も重要になり、アクティビストに株主還元を求められ、十分な戦略投資が行われないこともあるだろう。
そんな時にふと思う。このまま上場し続ける意味はあるのだろうか?もう十分に知名度も上がっり、取引先の信頼も勝ち得ているのであれば、上場を維持するメリットよりも上場によって身動きが取れなくなって企業価値を棄損し続けるデメリットの方が大きいのではないか?
非上場化するためには?
非上場化するということは誰かが上場会社の株式を買わなければならない。多くの場合は多額の資金が必要となるので、ファンド等が出資者になることが多い。
ファンドが不当に安い価格で買い取らないように第三者委員会を設置したり、従業員取引先に十分な説明を尽くさないといけない。上場する時よりも各所に配慮が必要になり、それを怠ることで訴訟リスクも抱えることになる。不謹慎かもしれないが結婚は勢いでできるが離婚は財産分与や親権問題等で大変になるのと似ているのではないかとふと思ったりもした。
無事所定の手続きを経て非上場化した後、株主となったファンドのExitのために徹底した体質改善が求められるだろう。どうにもならない状態で非上場化をすると利益のある所だけ残して解体されて資金化される可能性も当然ありうる。
誰と組むか、いつ非上場化するかはとても重要だ。
まとめ
企業は企業価値を最大化するべく行動するべきという考え方が私の根底にはある。それは上場企業でも非上場企業でも同じで、上場はあくまでも企業価値を早期に高めるための一手段でしかないと思う。
上場すると株価がつくので一喜一憂してしまう経営者の方もいるかもしれないが、本質的な企業価値の向上を目指して、色々な選択肢を持って企業のかじ取りを行っていっていただきたい。
上場企業が必ずしも正ではなく、非上場化した後継続的に安定成長を続けている企業も日本には数多く存在する。上場ゴールではなく、自社にとって最適な資本構成を検討していってほしい。
と、いちIPOコンサルとしては思うところでした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
