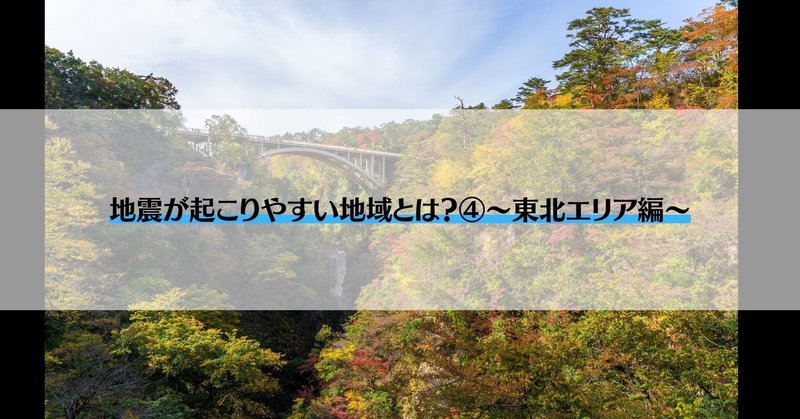
地震が起こりやすい地域とは?④~東北エリア編~
東北エリアで地震が起こりやすいエリアは?
東北は昔から巨大地震の発生が多く、地震による津波の被害も多く受けています。震源が三陸沖に集中しており、過去に発生した大規模地震の震源は宮城県沖に集中しています。
また、内陸では人口集積地を活断層が縦走しているため、海溝型地震や直下型地震の発生が懸念されています。
もともと全体的に地震の発生が多いエリアですが、気象庁が集計したデータを見るとその地震の多さがよくわかります。
・2010年6月10日~2020年6月9日の震度1~震度7までの地震の数
全国の中でも東北エリア(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県)は地震の発生回数が多く、10年間で23,352回となっています。また、都道府県ごとに見ると福島が全国1位で7,457回、さらに3位に宮城5,693回、4位に岩手5,041回と続きます。
東北エリアで過去に起こった大きな地震
【日本海中部地震】
1983年に秋田県能代市西方を震源地として発生したM7.7の地震です。当時日本海側で発生した最大級の地震であり、この本震は2回の揺れで構成されていて約20秒の間隔を空けて揺れが発生しました。建物の全壊数は944棟、死者・行方不明数は104名で、そのうち100人が津波による犠牲者でした。津波による被害が大きく、秋田県、青森県、山形県の日本海側で10 mを超える津波を観測しました。
【岩手・宮城内陸地震】
2008年、岩手県南部で発生したM7.2 の内陸型地震です。岩手県奥州市と宮城県栗原市で最大震度6強を観測し、この二つの市を中心に被害が発生しました。建物の全壊数は30棟、死者・行方不明数は23名でした。同程度の地震と比較すると建物の被害が少なく、土砂災害が目立ったのがこの地震の特徴です。
【東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)】
2011年3月11日に発生したM9.0の日本の観測史上最大の地震であり、世界的に見ても4番目に規模の大きな地震です。岩手県沖から茨城県沖を震源域として宮城県栗原市で最大震度7を観測し、東日本を中心に強い揺れに見舞われました。建物の全壊数は121,783棟、死者・行方不明数は18,427名でした。津波による被害が甚大で、津波が到達した最高地点は40.4mと人が住んでいる地域では国内最高を記録し、広域に浸水被害を発生させました。また、福島第一原子力発電所の事故を引き起こすなど、戦後最悪の自然災害といわれています。
東北エリアで今後想定される地震は?
2011年に東日本大震災という巨大地震が発生したため大きな地震は起きにくいと考えがちですが、もともと地震が起きやすい地域のため依然として注意が必要です。
2019年2月に政府の地震調査委員会が公表した予測では、宮城県沖と青森県東方沖から岩手県沖北部の2ヵ所で、M7~7.5程度の地震が30年以内に起こる確率を90%としています。
また、福島県沖のM7程度の地震の発生確率は50%、岩手県沖南部のM7前半程度の発生確率は30%程度となっています。
このように東日本大震災級の超巨大地震が起こる確率はほとんどありませんが、比較的大きな地震が起こる確率は非常に高くなっています。万が一の時に備え、早めに地震に備えた対策を行いましょう。
東北エリアの一戸建ては火災保険・地震保険で備えよう
東北エリアは他の地域に比べ地震の発生回数が多く、特に太平洋側ではM7以上の地震が起こる確率が非常に高くなっています。また、過去の地震による被害を見てもわかるように、津波による被害が大きくなる可能性が高いことがわかります。
東日本大震災の影響もあり、宮城県は地震保険の加入率・付帯率共に全国トップとなっていますが、今一度、保険の契約内容などを確認しておきましょう。
また、過去に地震による影響で自宅にダメージがある場合でも、保険が使えるケースもありますので加入している方は確認してみましょう。
参考:相談を受け付けているサイトの例
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
