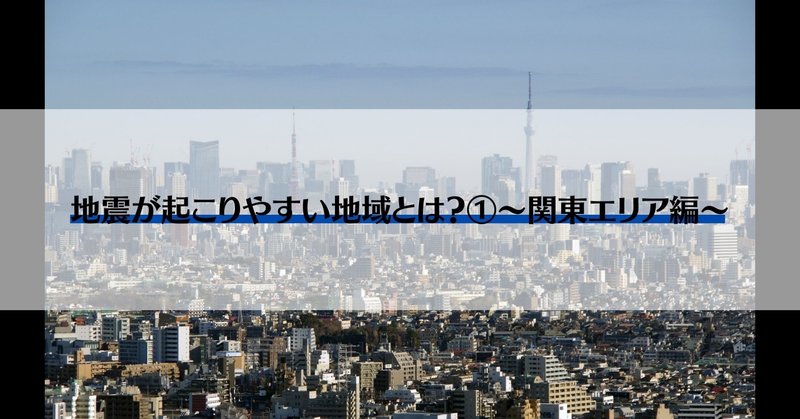
地震が起こりやすい地域とは?①~関東エリア編~
関東で地震が起こりやすいエリアは?
関東エリアは地震が起こりやすいエリアの一つで、その理由は北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートが複雑な構図でぶつかっている場所にあるからです。
2018年、千葉県東方沖でM6.0(最大震度5弱)の地震が発生し、その後も千葉県東方沖や茨城県などでM4~5クラスの地震が多発しています。
中でも茨城県は地震活動が活発で、過去97年間(1922年1月~2019年7月)の震度5弱以上の地震の回数は48回です。
これは全国3位で、1位の東京は小笠原諸島などの島で発生した地震も含まれるため、実質2位となります。
茨城県南部には筑波山があり、過去にもM6程度の揺れが頻繁していることから、「地震の巣」とも言われています。
2011年の東日本大震災以降には地震活動がさらに活発化し、茨城県南部にとどまらず、北部も地震が多く発生するようになりました。
関東で過去に起こった大きな地震
関東地方では、過去にも大きな地震が発生しています。
以下の2つは、歴史に残る大地震として知られています。
【安政江戸地震】
1855(安政2)年に発生した江戸(東京)を襲った地震です。地震のマグニチュード(M)や震源の場所などは正確にわかっていませんが、M7.1~M7.2クラスで、震源地は隅田川の河口付近とされています。
幕府の公式調査によると家屋倒壊は14,346棟、死者数はデータを元に推測すると1万人以上であったと考えられています。
被害のほとんどは直径20Kmほどの狭い範囲に集中している一方、震度4以上の領域は東北地方南部から東海地方まで及びました。
【関東地震(大正関東地震)】
1923年、相模トラフのプレート境界に沿って発生した地震です。正午前後(11:58~12:03)に3つの地震が相次いで発生したことがわかっています。
また、この地震によって引き起こされた災害を「関東大震災」といいます。建物の全壊数は20,179棟、死者・行方不明数は105,385人でした。
・1回目は小田原周辺を震源とする相模トラフでのM7.9
・2回目は東京湾北部を震源とするM7.2
・3回目は山梨県と神奈川県の県境付近を震源域とするM7.3
以上の3つの地震を関東地震と呼びます。
埼玉県、茨城県、東京都、千葉県、神奈川県、千葉県の一部、山梨県の一部、静岡県の一部で震度7相当の非常に激しい揺れがあったとみられています。
一般的に火災による被害の印象が強いですが、揺れによる家屋倒壊は約11万棟あったとされています。地震による被害は小田原付近が最も大きかったと言われていますが、津波、火災、地すべり、崖崩れなど地震に伴う災害が広範囲で起こり、過去最大の被害を出しました。
関東で今後想定される地震は?
関東地震のように相模トラフ沿いで発生する地震は周期的に起こるため警戒は必要ですが、発生の可能性が上がるのは100年ほど先だと言われています。
この地域で最も注意が必要なのが首都直下型地震です。M7クラスの地震が発生する可能性は今後30年間で70%と言われています。
東京が震源地と思われる方が多いですが、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨木、山梨と関東全域が震源となる可能性があります。
東京都(24区)を震源とした場合、想定される被害は家屋の倒壊・焼失が最大約61万棟、死者数は2万3,000人、経済被害は95兆円に達すると言われています。
また、東京都内はビルが密集している地域が多く、このような場所では”火災旋風”という炎の竜巻が起こりやすくなります。関東大震災ではこの火災旋風により、多くの方が命を落としました。
このように経済の中心であり、人口が集中している首都圏を震源地として巨大地震が起きた場合、甚大な被害を受けることは容易に想像できます。
過去の地震の時のような被害を出さないよう、地震に備えてまずは自分で出来ることから始めましょう。
関東の一戸建ては火災保険・地震保険で備えよう
関東は東日本大震災以降、千葉県東方沖や茨城県北部・南部で地震が頻発しています。また、首都直下型地震が30年以内に高い確率で起こるとされています。
万が一の場合に備え、火災保険・地震保険に加入するようにしましょう。既に加入している人は契約内容を確認することも大切です。
また、過去に自宅が地震によりダメージを受けた場合は、保険で対応できることもありますので確認してみましょう。
参考:こんなこともいけるの?という作業の例
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
