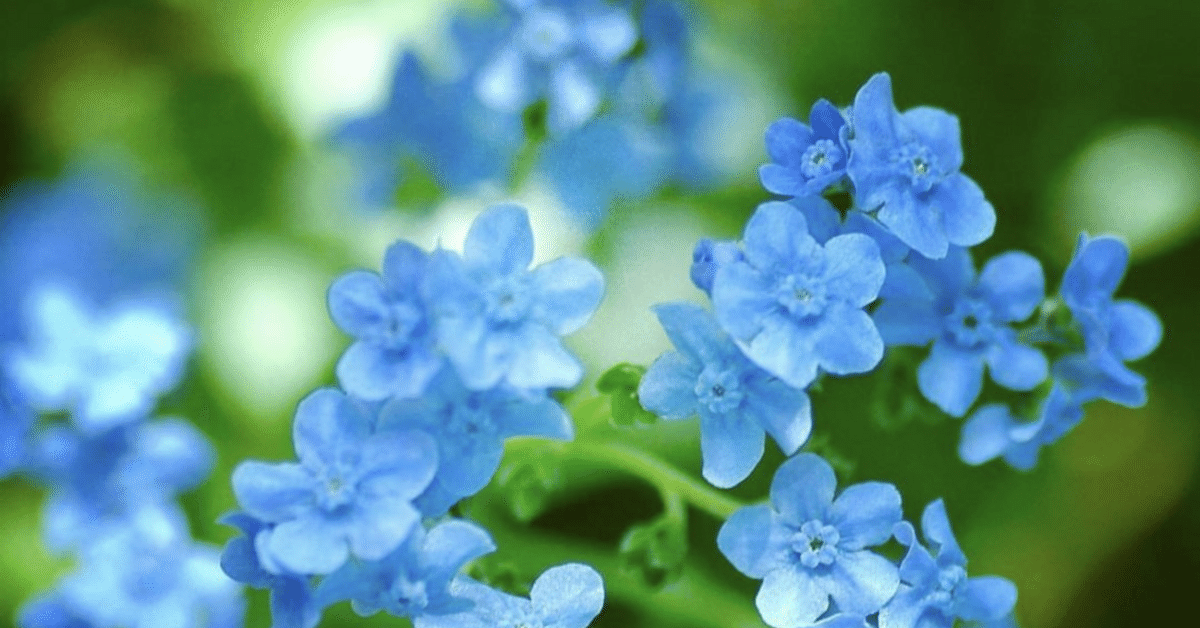
そこのあなた、ちょっと里見弴について知りたくないですか?(志賀直哉編3)
前回簡単に「ご紹介します」と書きましたが、実は話はそう単純ではなかったりします。
なんと、里見が書き志賀が怒る、というパターンは3回繰り返されました。大正元年から5年までの5年間に3回です。
これだけで、もう君らどうしちゃったの、と言いたくなりますが、本人たちは真剣です。
里見は、自分たちの関係を見直そうとして作品に書きました。
その際、志賀をなじる書き方はするまいと気を付けたようですが、志賀の怒りは防げなかったのです。
くわしくは「志賀直哉×里見弴×暗夜行路」で触れていますので、そちらをご覧ください。
ここでは、いったい何が起きたのか、なぜ志賀は怒ったのかをざっと見ていきましょう。
「恋愛関係」と言われる理由もこのへんにありますから、一つ一つご紹介します。
第1ラウンド…「腐合ひと蝉脱」(明治45年/大正元年)
最初からドキッとするタイトルです。
里見25歳の夏の終わりに書かれた作品で、おそらく未完。現存していません。読んだのは里見と志賀だけだと思われます。
内容は、里見とある女性の関係について明らかにし、今まで志賀にウソをついていたと告白するものだったようです。詳細は里見の「善心悪心」、志賀の「暗夜行路草稿」「暗夜行路」で読むことができます。
読んだ志賀は、その後の経緯もあって立腹。
里見から1か月ほど距離を置きます。
ただ里見のほうは、志賀との関係が変化するならいいことだと考え、さほど気にしなかったようです。
志賀はことの顛末を短編に書きました。この短編は「暗夜行路草稿」に取り込まれて、のちに「暗夜行路」の冒頭を飾ることになりました。
そう、「暗夜行路」冒頭に出てくる友人阪口のモデルは、里見弴なのです。
断っておきますと、のちに志賀は、「阪口は里見ではない」と書いています。
これについては「志賀直哉×里見弴×暗夜行路」で検討していますので、ここでは深く立ち入りません。
しばらく絶交した事実だけをおさえておきましょう。
この作品を読み、その後の里見の行動を見た志賀は、里見が自分から離れたがっていると感じたようです。里見の手を放そうとしない自分を、里見は煙たく思っている、とそれが志賀のイライラに火をつけることになります。
この時は1か月ほどでまた元の付き合いに戻りますが、これによって、のちの絶縁の種はまかれたと言えるかもしれません。
第2ラウンド…「君と私と」(大正2年)
翌年、里見はさらに自分を掘り下げようと、「君と私と」を執筆。
これが前回ご紹介した文庫本「君と私」の表題作です。
この作品は、白樺に小分けにして連載されました。
里見は第1回で「少年時代に志賀を好きだった」と書いており、そのことでも有名です。
これが原因で志賀が怒ったという風説も生まれましたが、実は志賀はその回について「面白く読んだ」としており、決してネガティブな反応ではありません。
爆発したのは連載第3回目でした。
抗議文「モデルの不服」を白樺に掲載する事態となります。
なぜ志賀が怒ったかですが、どうも第三回目の内容は「腐合ひと蝉脱」をベースにしていたようです。
「モデルの不服」は、物わかりのよい先輩が、未熟な後輩をたしなめながら厳しく文学的指導をする、というような体裁で書かれていて、志賀の余裕さえ感じさせるものです。まるで感情的になっていないように見えます。
ところが、志賀はその前に未発表の抗議文「『君と私と』の私に」を書いています。こちらを読むと、志賀の態度がまったく違うのです。
こちらは、里見に切り捨てられようとしているという認識が見られ、裏切られたという怒りが全編に満ち、この怒りは自分のわがままだと書いています。
2つの文章を読み比べると、志賀は巧妙に「志賀のわがまま」に見える部分を削除し、里見の考えが間違っているかのように書き直していることがわかります。
もちろん文学作品には客観性が必要です。しかし志賀のこの書き直しはそのためだけなのでしょうか。
けっこう個人的なプライドとか、里見を翻意させたいとか、そういう個人的事情によって書き直したようにも見えるのです。
「モデルの不服」「『君と私と』の私に」は、志賀全集に収録されていますので、よろしければぜひ読み比べてごらんになってください。
さて、最初のうち里見は頑として志賀の怒りをはねつけていたようなのですが、電話や訪問によって志賀の怒りをぶつけられるうちに精神的にすり減ってしまったのか、降参してしまいます。
当時の志賀宛の手紙が残っており、読むと精神的に疲弊しきっていたことが伝わってきます。志賀に謝罪し、自分を責め、しかしなお遠回しに絶縁への望みを訴えています。
志賀はそうなると罪悪感があったのでしょうか、謝りながらも、二人で乗り越えようという趣旨の返事を送っています。
志賀をかばうわけではないのですが、ここでの志賀の発言を見ていると思わず感心することがあります。
彼はどうも、里見の苦しみの原因が、志賀だけではなく里見を取り巻く環境全体から来るものだということを、この時点でずばりと見抜いているらしいのです。
実際、視点を変えると、里見の苦しみは大人になるための成長痛とも言えます。
一人前の大人になりたい、作家として自立したいと思えばこそ、里見は周囲との軋轢を感じているわけです。
里見の痛みを支えようという気持ちが志賀にあったのも、事実ではあるのでしょう。
根本的な部分を見抜く目は、さすが志賀直哉らしい鋭さだと言えます。
とは言え、志賀が離れてやれば問題がひとつ解決し、里見の成長痛がもっと楽になったのも事実だと思われますので、どっちが正しいと一概には言えないのですが……。
志賀のその申し出で、この対立はいったん収束します。
なお、喧嘩の1か月後に二人で出かけた際、志賀直哉が電車にはねられるという、かの有名な事故が起きていることを付け加えておきます。
ふたりの争いの結果、連載は一時中断。
やがて里見は連載を再開しますが、印刷所で原稿が行方不明になってしまいます。原稿は今でも不明のまま、犯人もわからず、「君と私と」は永遠に未刊に終わりました。
第3ラウンド…「善心悪心」(大正5年)
二人のつきあいはその後も続きました。
以前ご紹介した「世界一」もこの時期の出来事です。
松江にしばらく二人で滞在した大正3年、事件が起きます。
この松江行きでは、里見は「絶対に同じ下宿はいやだ」と主張しつつ同行したり、毎日一緒に宍道湖の無人島にわたって相撲したり芝居を見にいくなどするという、なかなか矛盾した行動をとっており、二人の関係がまだまだ一筋縄ではいかないことを感じさせるのですが、ある夜のことです。
いつものように、志賀が無理やりに里見を自分の下宿へ連れて行こうとすると、里見は全力であらがって、ついに志賀の手を振り払ったのです。
これらの経緯は、「或る年の初夏に」という里見の短編で読むことができます。
このできごとは一つの区切りになります。
二人はそれぞれの人生を生きるための準備を始めます。
志賀はそのころ住んでいた京都に戻ると、白樺の親友の一人である武者小路実篤に連絡を取ります。以前、武者小路の従姉妹との縁談があったのを志賀は断っていたのですが、その縁談がまだ有効かを尋ね、3か月後には彼女と結婚しました。
里見も、大阪で下宿していた家の娘と結婚します。彼女が芸妓をしていたことから有島家は大反対で、結婚話がまとまるまでに時間がかかりました。
長兄武郎は協力してくれましたが、次兄生馬は反対派だったようです。
この間、里見は文壇に認められ、みるみる人気作家への道を駆け上っています。一方の志賀はスランプ状態で、思い切って休筆しているところでした。
手紙で励まし合っているうちはよかったのですが、実際に会えるようになるとトラブルが起こります。
いよいよ絶縁へのカウントダウンが始まります。
大正5年。
志賀は、第一子の出産を控えた妻とともに、千葉県の我孫子に住んでいました。
一方の里見は大阪を引き払い、住み慣れた東京で新婚の家をかまえたばかり。このころ、どういういきさつかはわかりませんが、里見が志賀の近所へ引っ越す話が持ち上がります。志賀は土地を買うなどの世話をしています。
しかし、仕事が忙しかったこともあり、里見は転居のための志賀との打ち合わせを何度もすっぽかすのです。しまいに立腹した志賀は、手紙で激しく里見の態度をなじりました。
これに関しては、いくら今より時間にルーズな時代だったとはいえ、志賀の怒りもむべなるかなというところです。
里見は謝罪の手紙を送った……ように見えました。
が、この手紙、途中からどんどん里見が激していきます。
いつも色々心配してくれてありがとう、でもきみの好意に応えるだけの好意が自分にないのが心苦しい、そもそも我孫子への転居は不安があった、引っ越しても君とは没交渉でいきたい。反論無用。
そういった手紙を、一気呵成というような勢いで志賀にたたきつけたのです。
里見の我孫子転居は取りやめになります。
里見の逆ギレと言ってもいいところですが、しかし長年の思いをついに口にした……ともいえるでしょう。
これは個人的な推測ですが、里見としては、我孫子で近所(志賀の買った里見の土地は、志賀家から100メートルくらいしか離れていません)に住めば、せっかく適正な距離を作れてきたのにまた元の木阿弥になってしまうのではないか、という不安があったのかもしれません。
その感情が一気に出てきた……というのは考えすぎでしょうか。
志賀は反論できず、1か月が経過します。
そこで里見の「善心悪心」が雑誌に掲載されました。
明治45年の里見の動向を私小説に仕立てた作品で、よく初期の代表作としても挙げられます。何とかして自分らしさをつかもうという青年の試行錯誤が描かれています。
この作品には、「腐合ひと蝉脱」を書いたこと、志賀の怒りを招いたことなども書かれていました。
列車の中で一読後、志賀は窓から雑誌を投げ捨てました。さらに「汝けがらわしき者よ」と大書したハガキを里見にたたきつけます。それだけでは足らず、それまで里見が贈ったものをすべてたたきこわして捨てる始末。夫人もさぞかし驚いたことでしょう。
ただ梅のかたちのお皿と、「神父セルギュース」という本だけは、ちょっと考えてからとっておいたそうです。
差出人のないハガキでしたが、誰が書いたものか、里見にはすぐにわかりました。しかし、志賀がなにに怒っているかはわからなかったようです。
心当たりと言えば1か月前の自分の手紙だけでしたから、その返答だと考えた里見もカッとします。
こうして本格的な絶縁状態が始まったのです。
絶縁は約7年続きました。
これが文壇史で有名な、二人の絶縁事件です。
志賀は「善心悪心」の何にそんなに怒ったのでしょうか。
これに関しては、志賀は具体的な個所を明らかにしていないので、はっきりはわかりません。隠したかった病気について書かれたからだとか、志賀を殺して自由になりたいと書かれていたのでそこが不快だったのだとか、いろいろな説があります。
個人としては、最後の場面が問題だったのではないかと思っています。志賀は、上り調子の里見と、スランプ状態で逼塞している志賀の現在の状態を対比され、当てつけられたように感じたのではないだろうか、と。
なんにせよ、少なくとも里見は悪意で書いたわけではなかったのでしょう。もしもそうならば、ハガキを受け取ったときに志賀の怒りの原因は「善心悪心」だとすぐにわかったはずです。
さて、5年にわたる争いを見てきました。
それほどの期間、二人は仲直りしたり喧嘩したりを繰り返してきたわけです。正直言って、なぜとっとと絶縁しなかったのかと不思議になるような話です。
ここに、ふたりにとって切るに切れない何かがあったのでしょう。
「何か」とはなんでしょうか?
おそらくそれがあったので、これほどの喧嘩をしておきながら復縁もできたのだと思います。
では、次回、復縁の経緯を見てみましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
