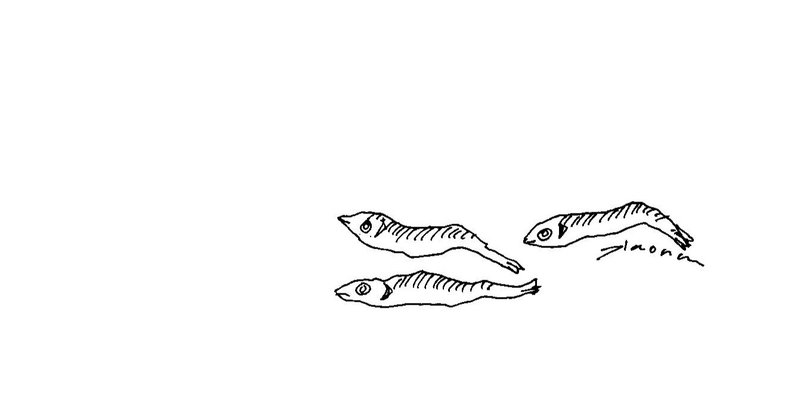
だしの呪縛から解き放たれよう
料理に使う「だし」を、すごく難しく考えている人が多いようです。
だしってどうやってとればいいんですか?と身構えて尋ねてくる人に「顆粒だしでもいいと思いますよ」と答えると、ほっとした表情になります。だしは敷居の高いものだと思われているのかもしれません。その一方で、だしは何でもいいですよと言うと不満そうな人もいます。だしに、こだわりたいのです。一筋縄ではいきません。
だしは漢字で「出汁」と書きます。食品を煮出したり漬けたりして、うまみや風味を出した汁、という意味です。
和風のだしは「出汁(だし)」、中華だしは「湯(たん)」、洋風だしは「ブイヨン・スープストック」などと呼び分けますが、私は全部ひっくるめて「だし」と言ってしまっています。どんな料理でも「だしは重要」とされて、基本中の基本とされています。
そんなわけで私も長年、だしがないと料理が成り立たないと思っていたのですが、あるとき、野菜をさっと炒めて、そこに水と塩を加えて煮出しただけの「だしなしスープ」がとてもおいしかった体験をして、だしから自由になりました。
だしなしスープといっても、わざわざ専用でとっただしがないというだけの話で、具から出たうまみがだしとなり、ちゃんと味は成立しているということです。
スープばかり作っていると、鶏ガラのブイヨンがあるのと同じように、ブロッコリーだし、小松菜だし、白菜だし、ベーコンだし、とうふのだし、りんごのだし、漬物のだし、鯵の開きを食べた後に残った骨のだし……とにかくありとあらゆるものから、だしが出ていることを感じます。
それらは、本格的にとった昆布かつおだしや鶏ガラのブイヨンに比べると、うまみも風味も淡いものです。でも、だしだけを飲むわけではなく、他のだしや具材と一緒に食べるのであれば、特にそれが家で食べるものなら、十分なだしといえます。
とはいえ、昆布やかつお、肉などで本格的にとっただしが加わるとぐっとおいしくなる料理もたくさんありますし、だしを使わないというわけではありません。
日本はだしについては本当にさまざまな選択肢があって、それが迷いのもとになっています。家庭で一番活躍するのは「顆粒だし」や「だしパック」ではないでしょうか。どんなスーパーでも売っているブランドの製品は本当によくできています。顆粒だしはとても強いうまみなので、使う量を加減したいところです。ほんのひとつまみでも劇的に味が変わります。コンソメや、中華だしも同様です。
いや、やっぱりだしも手作りにこだわりたい、という人もいるでしょう。それについては長くなるので、別のnoteで紹介します。
料理を始めたばかりの人にまず覚えてほしいのは、これでなくてはいけないというだしはないということと、だしがなくてもおいしくできる料理はたくさんあるということです。プロを目指す人をのぞけば、本格的なだしについて考えるのはもっと料理に慣れた後でもいいと思っています。
【だしを使わないねぎスープ】
材料:長ねぎ 1本 鶏モモ肉80~100g ごま油大さじ1 塩小さじ1/2
1 長ねぎは斜め薄切りにする。鶏モモ肉は小さめに切る。
2 鍋にごま油を引き、長ねぎを焦がさないようにじっくり炒める。
途中から鶏、塩も加えて一緒に炒める。
3 水500mLを加えて煮立て、ふたをずらしてかけ、弱火で5分ほど煮込む。好みで黒胡椒をふる。
読んでくださってありがとうございました。日本をスープの国にする野望を持っています。サポートがたまったらあたらしい鍋を買ってレポートしますね。
