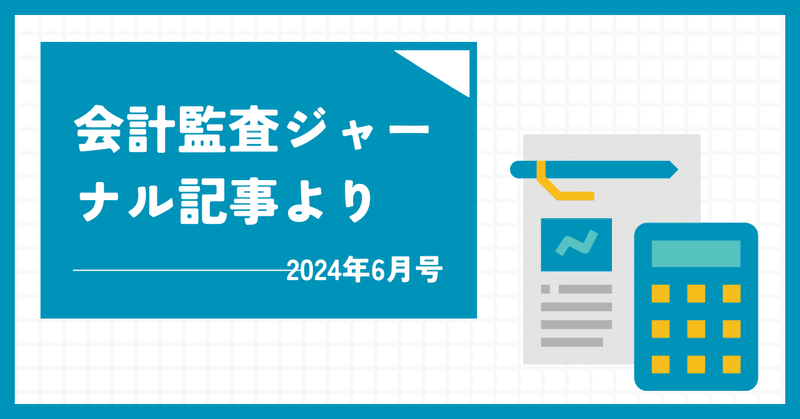
「有事における社外役員の対応」~会計監査ジャーナル2024年6月号より~
日本公認会計士協会の機関紙、「会計監査ジャーナル」が自宅に届いていました。多忙な時は表紙だけ見て封を切らずスルーする月もあったのですが、今回は「有事における社外役員の対応」というキャッチーなタイトルで、「ビジネス法務の部屋」で有名な山口弁護士の対談記事があり、思わず封を切って一気に読みました。
個人的にとても学びが多かったので、自分への備忘も兼ねて内容をシェアしたく思います。要約でニュアンス含むので、正確な文章を確認されたい方は会計士のみなさんはジャーナルの本文をご確認いただき、他の皆さんは下記よりお求めいただければと思います。

https://www.fujisan.co.jp/product/1287/new/?backnumber_media=print
山口先生のブログ「ビジネス法務の部屋」でも取り上げられていました。
企業買収があると社外役員のリスクは高まる
今回とりあげられた「有事」の一つは、会社が買収提案を受けるケース。体感、任期中に1回あるかないか、ない人も多い、というイベントです。
株価算定や統合比率等が出てきた場合、会計士的にはついつい、自分が買収する側や監査する側の感覚で中立公平に、まるで他人事のような客観性をもって意見を言ってしまうということもありがちかもしれません。
しかし、社外役員として特別委員会の委員に就任しているケースでは「少数株主の利益」を守る姿勢で対処しないと善管注意義務違反となるというご指摘がありました。
会計士の場合、会計はわかっている前提ですから(当たり前か)、会社提案が少数株主の利益に反すると判断された場合、はっきりとロジカルに反対意見を述べなければならず、役割と責任がより重要となってくる、と。
不祥事をおこす組織の特徴
別の「有事」としては不正や不祥事についてでした。
この対談は、3人で行われており、山口弁護士の他は会計士2人、会計士協会の会長をされていた手塚さんと、副会長をされていた北山さんという豪華対談でした。お話によると、不祥事をおこす組織の特徴として下記のような項目が挙げられており、身につまされるような気持がいたしました。
・同質性で閉鎖的な組織文化により現実を直視せず、内輪の論理で問題を過小評価する
・情報共有と説明責任が欠如しており、重要問題が明らかにされないことから組織全体として健全な危機感を持つことができない
・外部の知見を活用せず独善に陥る
・経営のKPI、ダッシュボードが提示されるだけの管理基盤が整備されていない
取締役会で対峙しているこちらも同様で、潜在的な不祥事があったとして、第三者委員会でもなければ、これが不正です、どうぞ見てください、という形ではでてこない。淡々と進んでいく日々の中で、あれ?おかしい?、違和感を感じた時に、いかに端緒をつかんで裏をとり、「これはダメです」と、能動的に声を上げるのか、その難しさについて語られました。
情報収集をどのように行うか
対談では、不祥事が起こる前から、経営判断の傾向、経営陣の人柄、CEOと他の役員との関係、議題の説明の仕方など、会社の組織文化を日常から理解しておくことが重要との指摘がなされていました。
また、不祥事があった場合、初期段階では詳細がわからなかったり金額規模が推計できないこともありますが、だからといって、手をこまねいて時間を浪費するわけにもいかない。その際にはやはり、会計監査人との連携が必要であり、前広に相談できる関係性の構築が重要である、と。
会社の会計監査人と、会計士の社外役員との関係性についてですが、経験上、社内の役員会計士の場合と異なり、監査報酬の値下げ交渉をしたり、これ見つかったらまずいといった関係性にはなく、同じ目的意識をもって連携することで有用に機能するなと実感していたところでした。
女性だからか、特に知ったかぶりをしたり牽制しようという意識もなく、(先方がどう思っているかはともかく、こちらとしては)協力体制でなかよくやっているつもりです。このあたりは、会社の規模感にもよりますが、例えば年配の重鎮感のある男性会計士とはまた違ったカジュアルさが良い方向に影響していそうに思っています。
話は戻って情報収集方法について、
会計監査人以外から、また、取締役会の場以外の方法としては、事務局を通じて詳しい方を紹介してもらったり、一緒に食事に行く、雑談ルームで話す等のアイデアもあるなど、「オフレコ」の情報交換の重要性について触れられていました。
いわゆる「たばこ部屋」コミュニケーションだったり、もはや都市伝説かもしれませんが、男性の場合狙ってトイレでとなり合わせになって仲良くなったり?なんてあるのでしょうか。
女性役員の場合、トイレで隣・・・は相手が女性でないならもちろん無理ですし、夜の会食もさすがに一人で男性役職者を食事に誘うというのもなかなかやりにくいですから、複数の女性役員がいるというのはその意味でも有効なのかもしれません。夜のオフ会となるとつい、働き方改革が・・・なんて思ってしまいますが、役員なので関係なし。必要なら夜中でも対応しなければなりませんね。目的は必要な情報を収集することで、方法論も含め、工夫が求められるところです。
社外役員として公認会計士に期待されること
最後に、会計士の社外役員に期待すること、として、時々でよいので、会計士の視点で「問題の本質を突くような質問」を取締役会でしていただきたいというリクエストがありました。
本質を突く質問・・・・ハードル高いです。
良い会社にするために、議論を活性化するにはどのような問いかけ、質問をすべきなのか。常に問題意識をもって考えておく必要がありそうです。
また、監査をやってきた会計士は会社組織全体を見てきた経験もあり、監査意見というジャッジ経験もあるのだから社外役員には適しているはずですが、監査感覚でいると、提出された資料ベースで判断をしてしまいがちである、とのご指摘もありました。
たとえ監査役であっても、自らも経営を担うものとして、能動的にかかわっていく姿勢が必要とのご意見はあらためて自覚を促すものでありました。
まあ、そこまで気張らなくても、まずは専門家として会計監査人と会社の橋渡し、いわゆる通訳をするところからでも貢献できることはありそうです。
最後に北山さんより、社外役員の役割の重要性、期待の大きさに応えるため、自分たちが知識やスキル向上に努める必要性について思い知る機会となりました、とのまとめがありました。
あの北山久恵さん(有名人、検索すれば何かヒットする。以下サンプル)に「知識やスキル向上に努める必要性を思い知る」なんて言われてしまえば、こちらはさらに努めるしかないわけで、こちらもますます身の引き締まる思いがした対談記事でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
