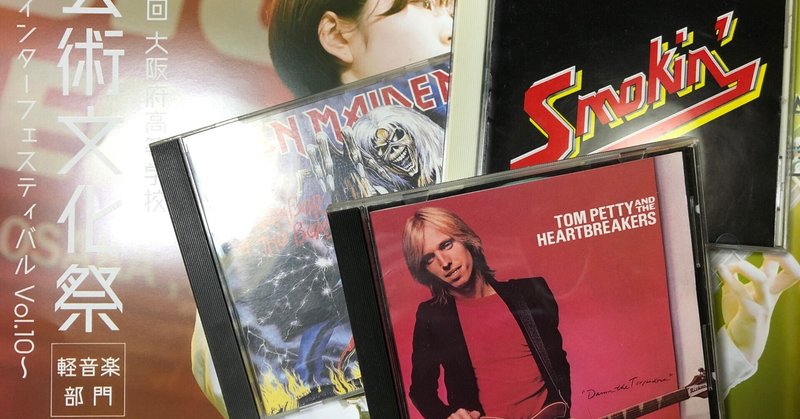
ファイターズ賛歌
新庄剛志は本当の意味でパリーグのイメージをプラスに変えた人である。阪神からFAでメジャーリーグ行って、数年後に日本に戻ってきたとき、誰もが「阪神に復帰するんだろうなあ。でも派手好きだからジャイアンツかも。」くらいに思っていた。ところが彼は「これからはセリーグでもメジャーリーグでもない。パリーグです!」と記者会見で宣言して、北海道への本拠地移転が決まっていた日本ハムへ入団したのである。
これはパリーグを愛する者にとっては驚愕の素晴らしい出来事だった。当時不人気パリーグの象徴のひとつでもあった東京ファイターズが札幌に移転することになったとき、おそらく札幌の人たちは、ファイターズのほとんどの選手のことを知らなかっただろう。「岩本がエースでサムライ小笠原が4番です」って言われても「誰それ?テレビで見たことないし。」てなもんだ。
それでも読売ジャイアンツとフランチャイズ球場が一緒という不幸な状況から脱出する方策として、札幌移転は賢明な選択だった思う。すでにホークスが福岡へ移転して成功しつつあった時期であり、それを研究しての戦略だったのだろう(不人気球団であるから、札幌移転自体が大きくは報じられなかった)。
そこへ新生ファイターズの目玉商品としてメジャー帰りの新庄が入団したわけである。最初は新庄剛志だけに注目が集まる中、その影響で徐々に小笠原、金子、岩本、田中賢介などの生え抜きの選手にも注目が集まるようになり、数年でファイターズは知名度の高いチームに変貌するのであった。
来年、日本ハムは球団から搾取することしか考えない札幌ドーム(という名前の役所)を捨てて、北広島へ移転することになっている。球団自前のスタジアムだからいろいろなボールパーク企画が実現可能だ。
このタイミングで新庄のカリスマ性を再び切り札として使うというのは、実に思い切った戦略だとは思うが、おそらく数年先には「新庄監督のおかげで今のファイターズ人気がある」っていうくらいその貢献度が評価されるんじゃないか。
監督としての新庄の言動を批判する評論家もいるけど、「プロ野球はエンターテインメント」という強い信念を持ってやっていることなんだからパリーグ全体としては彼には感謝しないといけない。「優勝は目指さない」というセリフが批判を浴びたけれど、「まずは注目されないとダメ。注目されることによってチームは強くなっていく。」という意味だと理解する。
昭和のパリーグはメディアからは無視され続けた。阪急がどれだけ強くてもテレビ新聞では扱ってもらえない(当時はネットは存在しないので、テレビラジオ、新聞がすべて)。ましてや弱小南海や日本ハムなんてのは「そんなチームあるんですか」というレベルの認識で、プロ野球イコールセントラルリーグというのが一般大衆の常識であった。読売とその対抗馬としての阪神だけがメディアには異様に大きく取り上げられて、それを偏向してると感じる人は少数だった。毎年のドラフト会議のたびに目玉選手が「パリーグは拒否します」なんていうのは当たり前だったもんな。
強いチームを作ってもニュースにしてもらえない。プロ野球は人気商売なんだからメディアの露出を増やさないと、と努力した監督は折に触れて存在した。思い出すのはオリオンズ時代のロッテ金田監督。この人はサービス精神満点の監督。福岡の太平洋クラブライオンズとは意図的に対立をあおって、「遺恨試合」なんてのを演出した。仰木監督もメディア露出を常に考えていた人で、イチローを売り出したのはこの人の功績も大きい。楽天監督時代の野村監督もそうだった。田中投手への気の利いた辛口コメントをマスコミは連日こぞって取り上げたものだ。
新庄監督にはこういった先人と同じテイストを感じる。自分が派手な言動をとることによって、その流れでチームの選手にも注目がいくようになり、ひいてはパリーグ全体の繁栄につながる、と。
たとえばプロレスの興行においては、ひとつひとつの試合の勝ち負け結果はそれほど需要ではない。エンターテインメントなんだから、シングルであれタッグであれ、それぞれの選手が鍛えた身体能力をアピールして見ごたえのある技の応酬があれば、充実した内容の試合にお客さんは満足する(タイトルマッチの場合は若干違うかもしれないが)。「いやプロ野球はとにかく勝たないとダメなんだ」という人もいるが、客観的に見て今のファイターズの戦力は他球団に2枚も3枚も劣る。弱い戦力なんぞは承知の上で、それでもあの手この手の作戦、奇策を講じて、何とか強いチームに立ち向かっていきますから、その懸命な姿を応援してください、ということなんだろう。
だから、今シーズンについては、むっつり顔の藤本監督率いるソフトバンクが日本ハム戦は横綱相撲で圧倒するべきなのである。ソフトバンクと互角に戦えるようになるまであと数年はかかるだろうが、その過程はパリーグファンにとっては、所沢ライオンズや福岡ホークスが新興勢力としてのし上がっていった時のようなワクワク感が味わえるはずなのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
