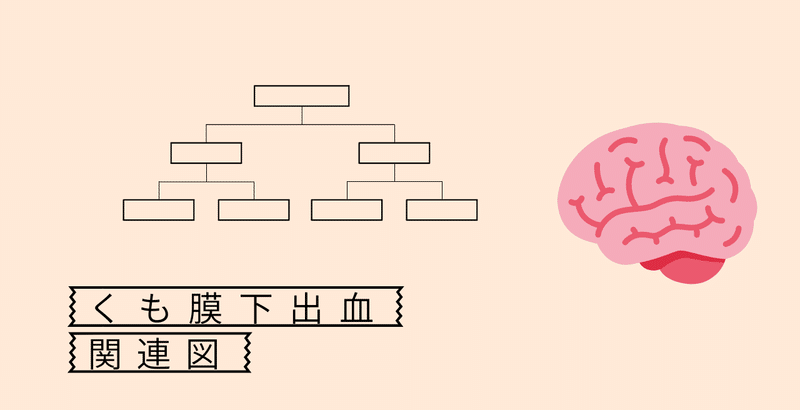
くも膜下出血【関連図】
脳表面(脳の周り)は、軟膜、くも膜、硬膜の三層の膜で覆われています。
くも膜下出血は、くも膜と軟膜の間のくも膜下腔に存在する血管の破裂などで起こる疾患です。
40歳以上では、5万人あたりに20人の人が発症します。
脳血管疾患に占めるくも膜下出血の割合は、10%程度です。
同じ脳血管疾患でも脳梗塞や脳出血と比べて、くも膜下出血出血の割合は多くないため、関連図もあまり出回っておりません。
しかし、くも膜下出血は脳梗塞や脳出血に比べて注意が必要なことが多かったり、特徴が異なります。
この病態関連図では、くも膜下出血の成り立ちから、病態全体を把握することができ、受け持ち患者の状態をより深く理解できるように作成しています。
全体の関連がわかれば、アセスメントはやりやすくなり、関連図も個別性のある情報を追加することで作成できます。
実習を少し楽に進め、睡眠時間を確保するお手伝いができます。
くも膜下出血と脳梗塞・脳出血との大きな違い
くも膜下出血は、くも膜下腔内の出血です。
脳梗塞や脳出血のような脳への直接的なダメージではありません。
くも膜下腔に血液が流れ込むと、血液の成分により
・脳血管の攣縮
・髄液の吸収障害
などがおきます。
脳血管の攣縮
脳血管の攣縮は、くも膜下腔に入った血液の成分の一部が血管に作用し、血管を攣縮(収縮させて細くする)させます。
血管の攣縮により、脳血流が途絶え、脳梗塞を併発するリスクがあります。
発症から14日間が好発期間とされ、この間は徹底した血圧管理と脳圧管理がされます。
髄液の吸収障害
髄液の吸収障害が起きると、髄液増えていき、水頭症を引き起こします。
水頭症は、脳室の拡大を起こし、前頭葉に影響がでると歩行障害、見当識障害、尿失禁の三徴と呼ばれる神経症状が出現します。
脳室のさらなる拡大は、頭蓋内圧亢進にもつながり、脳ヘルニアを起こすリスクもあります。
関連図を書いてもらう方法もあります
実習の忙しい中、関連図を書くのは辛いですよね。
たくさんある情報を整理して、疾患別関連図を参考にしながら、看護問題を導き出して…
何時間もかかって完成させたら、そのあとさらに日々の記録を終わらせていく…
何時間あっても足りないし、睡眠時間ばかりがなくなっていく毎日ですね。
体調を崩したら実習に行けず再実習か、悪ければ留年です。
そんなリスクを抱えるくらいなら関連図を書いてもらって移すだけにしませんか?
こちらのサービスを利用すれば、関連図を代りに書いてもらえます。
一度相談してみましょう。
くも膜下出血の関連図
上記に加え、詳しい症状などをまとめた関連図を作成しておりますので、ご確認ください。
【ご購入後、関連図が表示されます】
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
