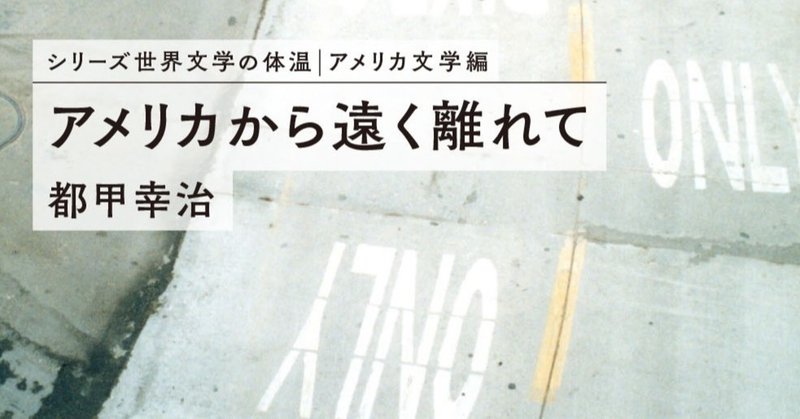
第6回 自分探しの終わり(都甲幸治)
二度目の大学院は最初のものとはまったく違った。なぜか。原因は、僕の変化にある。一度目のときはとにかく、自分探しの真っ最中だった。自分に何ができるか、何に興味があるかもわからず彷徨っていた。しかも対人関係もヘタで、すぐに人とぶつかっていた。
けれども二度目は、そんなことをしている暇はなかった。このままでは生きられない、だから一日も早く、どこかの大学で英語の先生にならなければならない、とまで思いつめていたのだ。とにかくこれが最後のチャンスだ、ということは身に染みて分かっていた。
だが僕の思い詰めた気持ちとは裏腹に、先生たちはやわらかくて温かだった。今思えば、ワケありの学生だ、ということはみんな最初からわかっていたわけで、ずいぶん気を遣ってもらっていたのかもしれない。
矢口祐人先生は僕のたった三歳ほど上で、もう准教授だった。ああ。でも同世代なせいか気が合って、アメリカ研究や文化研究の最新の感じを親切に教えてもらった。現代小説やフランス流の文学理論しか知らなかった自分にとって、こうしたアプローチは目から鱗だった。
矢口先生はお父さんがイギリス詩の研究者で、それもあって日本の大学の英文科に入ったが馴染めず、アメリカで大学に行き直した。大学院を出たあといったん商社に入ったんだけど、なんだかヤラかしちゃって、結局大学の先生になると決めたらしい。
へー。端から見ると成功ばかりの人生のようだけど、しっかり挫折もあるんだね。自分ばっかりダメ人間に思えていた当時の僕にとって、こうした先生の苦労話は新鮮だった。そして大学院生の気持ちに寄り添いながら、丁寧に何度も論文を見てくれる矢口先生の姿勢に惚れた。
その矢口先生と研究室が同部屋だったのがシーラ・ホーンズ先生だ。彼女は文化地理学の専門だった。文化地理学っていうのは、文学などを空間の視点から読み解くものらしい。イギリス人のホーンズ先生はある日、F・スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』を読んでいて疑問を持ったそうだ。
ギャツビーは隣人のニックにある頼み事をする。君の家で、デイジーというニックの従姉にあたる女性とお茶の会をさせてくれないか。この奇妙な願いにニックがオーケーすると、ギャツビーの庭師が彼の庭から隣家の庭まで、全部続けて芝刈りをしてしまう。
このくだりを読んでホーンズ先生は思ったそうだ。どうしてアメリカでは、隣の家との間に垣根も塀もないわけ? そして、もとイギリスの植民地であるアメリカは、自分が知っているのとはものすごく違う世界だと悟ったそうだ。
彼女はアメリカに渡り、ボストン大学で学位を取った。そのころたまたまお兄さんが日本に住んでいて、日本ではスキーができる山がたくさんあると聞いて遊びに来たらしい。
そのまま日本が気に入って英会話学校の先生になり、実力がありすぎて大学の先生になり、で結局、東大の先生になったそうだ。そのあまりにも計画性のない人生航路にシビれた。そこまで深く考えずに世界に出て行くイギリス人ってすごい。
ホーンズ先生の名物は午後のティーの時間だった。ちゃんとお茶っ葉が中で踊るように、かなり大きなポットにお湯を注いでじっくりと蒸らす。当時の東京では納得できる味のスコーンが手に入らない、と言って、自分でも焼いていた。
というわけで、ホーンズ先生の授業では、イギリス風の美意識や生活の仕方を叩き込まれた。授業内容はアメリカ研究のはずだったけど、いまだに覚えているのはそうした、彼女の柔らかさや、人の話を聞く態度や、ちょっと皮肉な冗談ばかりだ。
たとえば、アメリカでは人生の頂点は十代だとか言うけど、イギリスではどうですか、と聞いたら、頂点なんかないわ、イギリス人はずっと低空飛行だから、と返してくれる。いつも品のいい『モンティ・パイソン』みたいで、あのジョークのセンスは僕も確実に影響を受けたと思う。
文学の先生は、柴田元幸先生ともう一人、國重純二先生がいた。國重先生はお茶目な人で、女子学生が父親を批判するようなことを言っていると、「なんだ、誰に育ててもらったと思ってるんだ!」なんて怒り出す。なのに次の日になると、昼休みに学科の部屋でその学生と仲良くお昼ご飯を食べている。
要するに学科のお父さんという感じで、だから授業中にもうっかりいろいろ言ってしまう。十九世紀アメリカ文学の専門なのだが、ヘンリー・ジェイムズとも仲のよかったイーディス・ウォートンの『無垢の時代』を一学期かけて読む、という授業で、「なんだこの本、詰まんないなあ」なんて言い出してしまった。まだ学期は半分も残っているのに。
でも学会に行くととたんに偉い人になる。なにしろ、アメリカ文学会会長、かつ英文学会会長なのだ。あるとき学会のパーティが始まるまで廊下で國重先生と話していて、会場に一緒に入っていったら、大きな部屋にいる数百人がパッと二つに割れて、一斉にお辞儀をしてきたことがあった。いや、僕じゃなくて國重先生にね。
でもまるで自分が海の真ん中を歩くモーゼになったみたいで、ちょっと気分がよかった。今後も僕が國重先生ほど偉くなる可能性はないから、こんなの後にも先にも一度きりだ。そのときは、先生の普段のゆるーい感じと、公的な場で急に偉くなるところが僕の中でどうにも一つにならなかった。
でも今になると、だからこそ國重先生がみんなに慕われていたのだとわかる。要するに、誰に対しても優しさや温かさを配っていて、その少しずつが積み重なって、あそこまでの絶大な信頼感になっていたんだろう。
先生自身はだいぶ苦労をなさった方らしい。満州で生まれ、終戦後に四国に戻ってきた。とは言ってもやはりよそ者で、かなり日本に違和感があったそうだ。そうしたところから先生はアメリカ文学を志したのだろうか。結局聞きそびれてしまった。
価値観も経歴も、なんなら国籍もバラバラで、それでも僕の存在を受け止めてくれる先生方に囲まれて、僕の凝り固まった心もだんだんとほぐれていった。前は文学しか眼中にない、という感じだったけど、歴史学も社会学も大事なんだな、世界には日本とアメリカだけではなくて、もっといろんな国があるんだな、と思えるようになった。
そうそう。竹村和子先生の話もしておかなければ。お茶の水女子大学の先生なのに、一学期だけ駒場に非常勤に来ていらしたことがあった。来ていた、とは言ってもなかなか教室に来ない。忙しくて来ないというのもあるけど、なにしろ方向音痴過ぎて、なかなか教室にたどり着けないのだ。
竹村先生は車の運転が好きで、ちょっと大きめのセダンでキャンパスまでやってくる。で紛らわしいことに、駒場キャンパスの近くには先端科学技術研究センターもあり、建物の雰囲気が似ていて、しかも似た感じの時計台まである。
こうなったらもう無理だ。竹村先生はもちろん、隣の研究所に行ってしまう。そして教室を探すが、当然ながらみつからない。ようやく違う場所だと気づいて駒場に着いた頃には授業時間が終わっている。
駒場キャンパスに着いても気が抜けない。時計台の横の、決して駐車してはいけない場所に駐車して、そのまま最初の曲がり角で、教室がある右とは反対に曲がる。そしてキャンパスの端まで歩いて、そのまま遭難してしまう。
そのときは結局、坐禅堂の近くで親切な学生に発見され、なんとか教室までたどり着けた。もちろん大幅な遅刻である。しかもなぜ遅刻したかの説明の時間があるから、またもや授業開始が遅くなる。
正直言って、正門から教室まで、せいぜい五十メートルぐらいしかない。そこをどうして毎回迷えるのかは謎だった。でも竹村先生はチャーミングな人で、だからなんとなく許せてしまう。
いやいや、チャーミングどころか、文学理論では当時、日本でもトップクラスの存在だったのではないか。どうしてあの難解なジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル』をすらすら訳せる天才が、教室まで来られないのか。まあ、人間ってそういうものなのかもしれないね。
授業はそのころ先生が訳していたバトラーの『触発する言葉』を英語でまる一冊読み切る、という内容だった。もちろん高名な先生だから、最初はたくさん学生が来ていた。でも作品が難しいし、授業が今日、本当にあるかどうかは運次第だしで、人数はどんどん減っていった。
けれどもそれが良かったんだと思う。おかげで筋金入りの人ばかり残ったのだから。その授業で、今ジェンダー研究で有名な清水晶子さんとも知り合えた。早稲田で同僚になった日本研究の由尾瞳さんなんかもいたなあ。
いや、筋金入りだからじゃなかったのかな。一学期が終わる頃には、全員が竹村先生の人柄を愛していたのだから。バトラーの難解な文章を一文ずつ読みながらみんなで訳していく。それに先生が解説もつけてくれる。
先生が途中でわからなくなると、「あれ、家で読んだときはわかったのに。今はわからない。頭が悪くなったのかも。どうしたのかしら」なんて言って悩んでいる。みんなも一緒に悩む。
そうするうちに、不思議な現象が起こった。先生が理解すると、その理解がなんとなくこっちの頭の中にも入ってくるのだ。そして徐々にバトラーが何をやっているのかが摑めてくる。
こういうのを、脳のミラーリングと言うのだろうか。要するに、理解や気づきは伝染するのだ。だから同じ空間にいて、同じ時間を過ごすことが決定的に大事なんだろう。これは今流行のe-ラーニングなんかには欠けている視点じゃないか。
たった一学期の授業だったけど、文学理論を読むコツ、みたいなものが摑めた気がする。今早稲田でアメリカ文学に加えて文学理論を教えていられるのも、竹村先生のおかげという気がしてならない。
竹村先生はその後、すさまじい勢いで仕事を続けて、たぶんそれがもとで体を壊して、そのまま亡くなってしまった。まだ五十代だったんじゃないかな。もっとゆっくり生きてくれれば良かったのに。
あるとき竹村先生に、「都甲さんみたいな子供を産みたかった」と言われたことがある。竹村先生が当時、僕に何を見ていたのかわからないけど、その言葉に、僕はその後の人生をずっと支えてもらってきた気がする。
あとでアメリカに留学していたとき、ジュディス・バトラーが自分の通っている大学に講演に来たことがある。あんなに本は難しいのに、話自体はわかりやすい文章で、しかもユーモアに満ちていた。なんだ、普通にしゃべれるんじゃないか。
終わったあと、ちょっと言葉を交わすことができた。竹村先生の話を出したら、まだお目にかかったことはないけど、丁寧な手紙をもらった、と答えてくれた。なんだか僕の中で、違う場所と時間が直につながった気がして嬉しかった。
さて、大学院に入ってからも学生の傍ら、翻訳は続けていた。中川千帆さんと共訳でジョン・アーヴィングの『未亡人の一年』を訳したのも懐かしい。奇妙なことに、翻訳一本でやっていたときにはさっぱり仕事がなかったのに、学生に戻った途端、仕事が来るようになった。あんまり思い詰めるのも良くないのかもしれないね。
無事に二度目の修士論文も終わって、いよいよ留学準備をすることになった。TOEFLやGREの準備をし、提出用の英語論文も書いて、全米十カ所以上の大学に願書を送った。なんだか全部受かるような気がして、新宿のFedExの事務所に何度も通った。
結果から言えば、今まで経験したことがないほどたくさん落ちた。受験ってこんなに落ちるんだ。三十歳過ぎてこんな経験をするなんて思いもよらなかった。人生ってわからないものだ。
結局合格したのは、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、クレアモント大学、そして南カリフォルニア大学の三つだけだ。なぜか全部カリフォルニア州だった。仕方がない。その中で一番奨学金を多くくれて、なおかつ興味に沿った勉強ができる南カリフォルニア大学に決めた。
一つ問題があった。南カリフォルニア大学のあるロサンゼルスには、バス以外、ほとんど公共交通機関がない。ということは、車で登校しなければならない。そして僕には免許がないのだ。
文学者に免許なんて必要ない、というそれまでの確信を捨てて、僕は近所の自動車教習所に通い始めた。二十歳ぐらいの大学生と一緒に、毎日授業を受けたり教習を受けたりするのは楽しかった。でも実際に留学したらどうなるんだろう。僕は不安でいっぱいだった。
プロフィール

都甲幸治(とこう・こうじ)
1969年、福岡県に生まれる。現在、早稲田大学文学学術院教授、翻訳家。専攻はアメリカ文学・文化。主な著書に、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社、2009年)、『21世紀の世界文学30冊を読む』(新潮社、2012年)、『狂喜の読み屋』(共和国、2014年)、『読んで、訳して、語り合う。――都甲幸治対談集』(立東舎、2015年)など、主な訳書に、ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(共訳、新潮社、2011年)、同『こうしてお前は彼女にフラれる』(共訳、新潮社、2013年)、ドン・デリーロ『天使エスメラルダ』(共訳、新潮社、2013年)、同『ポイント・オメガ』(水声社、2018年)などがある。
「アメリカから遠く離れて」過去の記事
第1回 聖書と論語
第2回 サリンジャーの臙脂色の表紙
第3回 すね毛と蚊
第4回 相性がいちばん
第5回 コーヒー買ってきて
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
