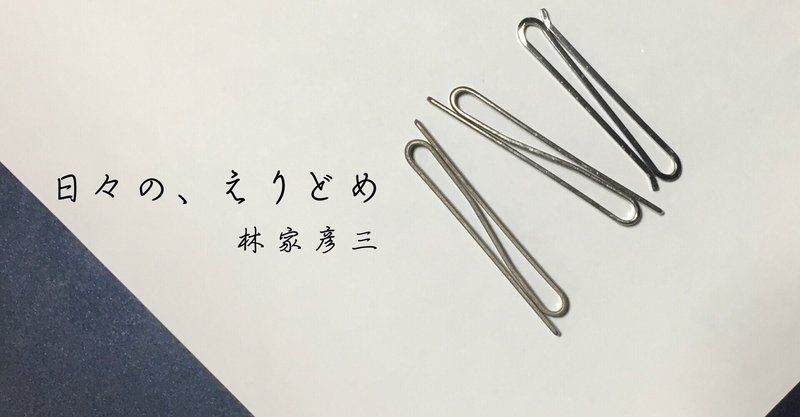
【日々の、えりどめ】第9回 駄菓子屋(一)
最寄り駅の近くの路地に、一軒の駄菓子屋がある。ここはいまではもう珍しいいわゆる昔ながらの駄菓子屋で、少し田舎に行けばこのような商店もまだ残っているのだろうと思うが、ここは一応都内ということになっているのでその筋ではわりと有名のようで、たまに都心からも趣味人がちらほらとやってくるようであった。
この駄菓子屋は「古風」というよりも「古体」と表現したくらいで、いわゆるよくあるような昔風の真似事では決してないように見えた。雑然と整然という二つの言葉が同義語であると感じるような風景なのである。
まずは神社の裏っ手にあるというその立地が、いかにもお誂えである。赤い天幕の庇があって、ガラス戸はもちろん開けている。煤けたコンクリートの地面はそのままで、中央左手には大人には低すぎる、しかし子供にとってはちょううどその目線に当たるであろう高さの陳列棚があって、棚といってもそれはただの木製の台なのだが、そのうえには小箱に入った一文菓子たちが隙間なく置かれている。色味のない紙に青みがかったインクで値段が押されていて、その紙がそれぞれの小箱に綺麗に付属されている。その価格の印の数字が画一的なので、色彩は氾濫していようともどこか涼やかなのである。左手の壁一面にはボトル入りの駄菓子がそのまま並べられていたり、場所を取るような棒状のゼリー類があったりする(しかもその幾つかは、冷凍庫でしっかり凍らせてある)。奥の棚はいわゆるベイゴマをはじめとした玩具類である。おみくじもあるし、紙飛行機もある。ボール類もある。一番上の棚には、いつのものかとも知れない経年劣化した箱入りのプラモデルが幾重にも積まれている。向かって右側にはコカ・コーラ社の小型冷蔵庫が設置されていて、せいぜい三種類ほどの瓶ジュースが売られている。もちろん例のロゴ入りの真っ赤な瓶ケースも欠かせない。それは冷蔵庫に寄り添うような形で無造作に置かれている。全体は埃っぽく、そして土臭い。しかしもちろん嫌にはならない。むしろ快適なのである。
こういう風景は懐かしいものであるが、その影にほの暗さが潜んでいるような気がする。ちょうどお祭りの屋台の過ぎ去ったあとには、秋風にも似た虚しさが残るように。――そう感じるのは、わたしだけであろうか。というのも、わたしにはマッチを擦らずとも時折どうしても燻り出してしまう、一枚の思い出の絵があるのである。
幼少の頃、わたしの生まれ育った田舎町には、町内に二、三軒ほど駄菓子屋があった。その内の一軒は小学校の目の前にあって、好立地も手伝って、子供たちからも大変な人気であった。
とういうのも、その駄菓子屋ではお菓子だけではなく、学習帳や鉛筆などの文具類も、一揃い置いてあったのである。もちろん、クレヨンや絵の具も。あるいは体育で使うようなゼッケンやビニール縄飛び、学校生活で使うような雑巾なども売られていて、いわばその駄菓子屋は小学校の道具箱役を担っていたのである。当時の子供たちは、コンパスと分度器は大抵ここで買っていたと思う(しかもこの駄菓子屋で買える文具は、子供が見てもひと昔前のものであった。コンパスはその当時一般的であった青色に塗色されてあるものではなく、安っぽいシルバーの細身で、大きなネジで鉛筆を固定するタイプのものであった。分度器も、いまは温暖化の影響なのかどこかに消えてしまった、柔軟性のない半透明ケースに入れられた「地球ペンギン印」のものであったと記憶している)。
【プロフィール】
林家彦三(はやしや・ひこざ)
平成2年7月7日。福島県生まれ。
早稲田大学ドイツ文学科卒業。
二ツ目の若手噺家。本名は齋藤圭介。
在学中に同人誌『新奇蹟』を創刊。
「案山子」で、第一回文芸思潮新人賞佳作。
若手の落語家として日々を送りながら、文芸表現の活動も続けている。
主な著作
『猫橋』(ぶなのもり)2021年
『言葉の砌』(虹色社)2021年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
