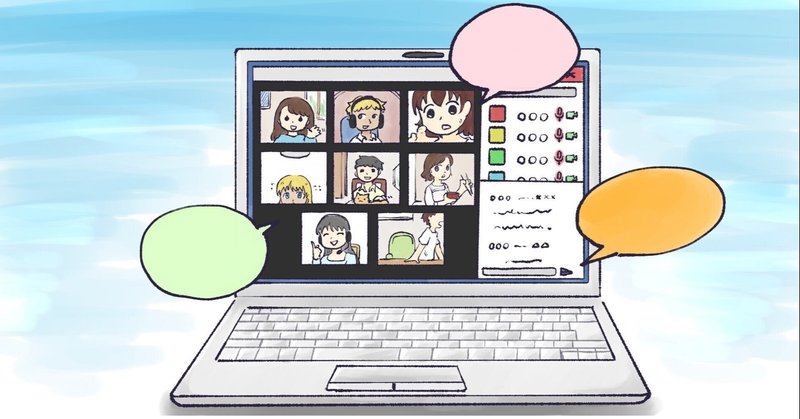
原価企画コミュニティとカルテル抑止
原価企画歴12年の私が見つけたやりたい事「原価企画コミュニティ」
これについて企業内起業ワークショップや子連れMBA内で壁打ちしたり、実際に発表会の時に審査員からも「カルテルに繋がらないか」という懸念点を複数人から戴いたのだが、その時私は、「他にも異業種コミュニティは存在するし、何か方策はあるだろう」くらいに考えていた。しかし、そんな甘いものでは無いという事が後々分かってきた。
一番早いのは指摘した本人に意見を聞く事
まず最初にやった事は、所属しているコミュニティのfacebookページに、原価企画コミュニティの企画書を添付した上で、以下のように投稿。「皆さんの中で異業種コミュニティに運営/参加されている方いらっしゃいましたら、機密漏えいにかんする規約を参考にさせて戴きたいのでお返事ください」
すると複数人が自分が実際所属しているコミュニティの規約のページやリンク先を送ってくれた。それを見る限り、「個人情報に関する取扱い」「反社会勢力に所属していない誓約書」等、実際コミュニティを作る際に規約に入れなければならない事項の参考にはなったが、カルテル抑止的な「このコミュニティで得た情報を使って違法行為を行わない事」というような文言は無かった。
また、海外子会社との業務提携に関わった事のある方から、裁判沙汰に巻き込まれない為の方法として、「一切責任を負いません」的な文言を規約に入れておく事を勧められた。これも確かにそうだ。
企業間でデータをクラウド上でシェアするサービスを使っている人からは、サービス利用に関しての規約があるのだが、規約自体が社外秘の為公開出来ないので申し訳ない。と連絡がきた。異業種コミュニティ以外にも、会社間のデータやり取りなどのルールも参考になるという事が分かった。
色んな人に協力戴いたが、カルテル抑止に関連する情報にたどり着けない。カルテルを気にする必要がどこまであるのかも懐疑的になっていたが、複数人に指摘された事を考えると、軽く考えてはいけないとは思いつつも具体的に何をすればいいのか全く分からず動きが止まってしまっていた。
そんな中、企業内起業ワークショップChallenge事務局の一人から、最終ピッチ審査員を務めた人物に直接聞いてみる事をお勧めされた。
その方は最終ピッチの時に、「今後も相談受付ます」と仰っていた。彼の煌びやかな肩書、そして事務局の方が「お忙しい所本当に有難う御座います!」「特別ゲストです!」とこの審査員の方が来て下さった事に心底感謝している様子を見て、「雲の上の御方だ」と感じていた。まさかそんな雲上人に直接連絡を?!しかし暫く考えてみて、「いや、連絡すべきだ」と考えは変わった。なぜなら、このコミュニティに参加している人は、チャレンジする事に対する「遠慮」や「気おくれ」が無いのだ。「相談して下さい」と言っている人には本当に相談すべきなのだ。審査員の方達も、今の立ち位置にたどり着く前は、臆する事なく誰かに相談し、試行錯誤して来たに違いない!
気合を入れて審査員の方のFacebookメッセンジャーを通じてメッセージを送ってみた。「最終ピッチの時にカルテルに関する指摘を戴きました。様々なコミュニティや会社の規約を探っていますが、難航しております。何か良い方法ないでしょうか?」
するとすぐに「今週日曜だったら時間取れるんでお話ししましょう」と返事が来た!さらに、「これは新たに設計する必要があると思います」
新たに設計・・・?!既存の仕組みを教えてもらおうと思っていたのでかなり面喰った。打ち合わせ当日は朝から緊張し、ネットで独占禁止法について調べたり、今までアドバイス下さった方の情報をまとめたり・・・とソワソワし、ついにzoomで顔を合わせた。
知らなかったカルテルの世界
今回相談に乗って下さった方は、現在の新規事業に携わる前はとある会社で自動車業界向けの営業をしていた。営業部ではカルテル行為を防止する部内教育が徹底しており、例えば競合他社のセールスマンから連絡があった、街で声をかけられただけでも、すぐに部内で報告するルールになっているとの事。また、展示会など他のセールスマンに会いそうな場所や、社外活動については全て部内で申請して許可を貰わないといけない。なぜならカルテルというのは「カルテルを持ちかけた人」だけではなく、「持ちかけられた人」も違法行為の対象となるので、社員の行動は会社として把握し、何かあったら責任を取れる状態にしなければならないからだ。もし原価企画コミュニティが、どれだけ規約でルール化していたとしても、悪意のある人がチャット等で価格や数量などの機密情報を漏らした場合、コミュニティ内全員が違法行為として制裁を受ける可能性もある、一歩間違えば危険な事になりかねない。もし自分だったら怖くてこのコミュニティには入れないし、入る為には会社に申請しなければならないが、今のままでは許可が降りないだろう。と言われた。
社内の価格情報を担う原価企画という立場でありながら、社外の人と関わる事のない管理部門に属している私は、カルテルについて全く疎かったのでこの話を聞いて驚きと同時に、原価企画コミュニティの実現の難しさに呆然。
しかしすぐに新たな提案も戴いた。「同業種から1名づつしか参加できない仕組みを作ればいいのでは?」例えば、自動車業界からは1名、食品業界から1名、医薬品業界から1名など・・・。すぐにアイデアが出てくるところが流石だ。
相談会を終えて、原価企画コミュニティの進め方についてこのように考えた。
①まずは社内で始める。(小さくスタート、これも数人から勧められていた)
②カルテルを防止しながら社外の人と繋がる方法を模索
仲間を集めよ 一人では答えは出ない
そんな中、もう一人の審査員の方とも連絡が取れ、打ち合わせさせてもらった。その方ももちろん凄い方。審査員2名と個別にお話しさせてもらえるとは本当に有り難い事だ!
「カルテルを抑止しながらコミュニティを作りたいんだが、やり方が分からない」という相談をしたところ、
「とりあえず仲間を募ってみたらどう?流行りのクラブハウスでもなんでもいいから、一緒に原価企画を語りましょうと言って」と提案を受けた。
今考えたらそんな簡単な事なぜすぐやらなかったのか?と思うのだが、カルテルの一件で、コミュニティを安心安全な場にしなければ・・・と妙にハードルを上げ過ぎてしまっていたように思う。
1人で考えると陥りやすい穴だ。まずは軽く座談会形式で始め、その中から賛同してくれる仲間を募って、ゆっくりコミュニティを作り上げていけばいいのだ。
という訳で、「原価企画を語る会」から始める事となった。
第一回目はどうなるか・・・仲間は見つかるか・・・ 不安はあるが突き進むしかない!!
全く知らない人を集めて会を開くにあたり、しょっぱなから勉強になる事ばかりなので、そちらについても今後書いていこうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
