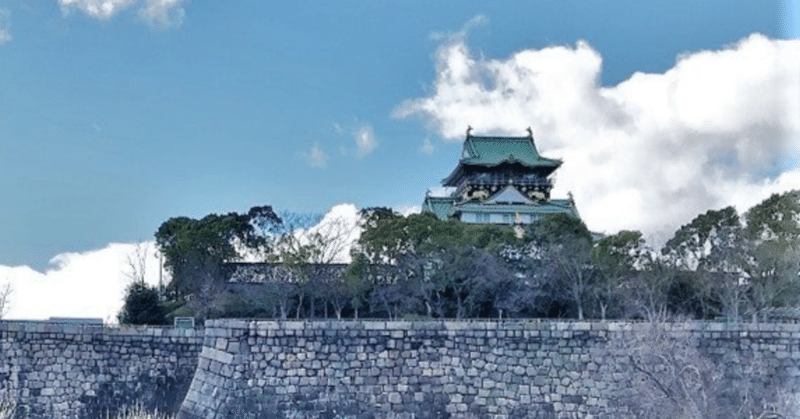
守山事件の顛末と花井主水の一件(4)所伝③元和年録(その1)
「元和年録」は、将軍秀忠の御前で行われた花井主水と安西右馬允の対決について詳しい。しかし、他に見えない記事のある事、詳細が述べられているからといって、それがその正しさまでをも保証するものではない事には留意すべきだろう。この御前公事は六月の十日と十二日に分けて行われたので、ここでもそのように分けて扱う事にする。
〇元和年録の場合(以下、年録と略す)
「年録」(※1)においては六月の十日に御前での対決があったと云い、花井は忠輝の母方の爪のはしをもけかす家老分であるのに対し、安西(※2)は軽輩であったが忠輝に気に入られ、この頃には目付役にて三百石ほどの身上であったと云う(151/513)。
公事は安西が訴え出た事によるもので、そもそもの事件は「上総殿、御陣へ御立之道、森山ニ而将軍様へ御目見得の為に御出被成...将軍様小十人衆長坂六兵衛、富士太兵衛、伊丹弥蔵此三人と上総殿衆致喧嘩(※3)、右之三人を討果し申候、其相手之本人は石谷縫殿助預り候鳥見之衆一人、富永大学預申候歩行之衆一人、山田将監組之者一人、以上三人也。其外其場へ馳付申候者数多有之..」と云うものであった(151/513)。
この三人は、閏六月迄色々と詮索している間に欠落ちしてしまい、安西が上様から忠輝家中に付属させられた衆でもない新参者であった事に加え、横目という役目柄彼を嫌う者が多かった事から、これを闇討ちして森山一件の喧嘩相手として成敗した事にしようと討手に指示が出されたと聞き(※4)、安西は越後を脱して江戸へ訴え出たと云う(151/513)。
安西によれば、問題となっている大坂陣での越後勢の遅滞と働きが十分でなかった事は、上総殿の曲事ではなく、奉行衆の曲事、とくに花井の勝手が原因であるとの事であった(※5)。(151/513)
曰く、大坂陣の折、五月五日に伊達勢との距離が三里ほど離れてしまい、先手の花井に距離を詰めるように指示が出たが、花井がぐずぐずして五里ほども離れてしまった。又、伊達勢から敵勢が出て来てるのでこれと戦うべしと連絡してきた際に、花井は忠輝はおやすみになっているので御目覚めになってから申し上げるとして時間が経ってしまい、合戦に遅れてしまった(※6)。上総殿が急ぐようにと指示を出した処、花井が前年の大坂陣での事についての江戸での風聞を悔しく思っていて、脇道を駆け抜けて他勢の先に出ようとしたため、大軍で脇道が渋滞してしまい、着いた時には戦はあらかた終わってしまっていた。とは言え、残敵もまだあるので是非に一戦をという声もあったので伊達政宗に相談した(※7)ところ、伊達勢は朝から晩までずっと戦っていたので夜も合戦というのは難しいとの事であった。そこで自分達だけでも水野勢など大和口の諸勢と語らって攻め掛かれば、敵勢は引き気味なので勝てるだろうという話になり、その事を花井に持ち掛けてみたが、政宗が同意していないのに合戦するのはいかがなものかと忠輝には言上してはくれなかった。七日の出勢前、花井が上総殿に牢人を抱えて欲しいとやってきて、今はなんともなりがたく無用との事であるのに、再三この事をいうので時間を取られてしまい、落城後の到着となってしまった(※8)。(151-152/153)
他にも様々な悪事があり、その事を知っている我々が花井にとって迷惑な者である事から、森山の件での喧嘩相手に仕立てて討手を差し向け闇に葬ろうと企んだ(「喧嘩之相手と名付候て、我等ニ討手を向、理不尽ニ闇討可仕とたくみ申候由」)のだと云う。(152-153)
以上が、「年録」の述べる六月十日に行われたという御前公事のあらましである。
前回見た「絶録」においては、花井が安西を問い糺せば守山での一件は解決するとしてこの公事の話に触れられていたが、「年録」においては、公事は安西が訴え出た事によるもので、逃げた下手人の代わりに家中の目付役で新参者であった安西を、下手人にしたてて殺害せんとはかったことから訴え出た(「安西方よりかけ申し」151/513)のだったとして、公事にいたる経緯と、その発端としての守山事件の事が述べられている。
十日の御前公事では、大坂での五月五日、六日、七日の事(※9)が扱われたが、五日というのは「東大寺雑事記(『大日本史料』12-18、pp.594
)」によると、忠輝、政宗その他廿五名の将らが四万程の軍勢を率いて当都を出陣した日の事であり、「言緒卿記」(12-18、pp.620)によれば伊達勢には六日、後藤又兵衛を討ち取るなどの武功があった。「年録」には、この六日の事について、出遅れた忠輝の家中の者たちが語らって一合戦をと期待したものの、家老の花井が「政宗の合点なき戦は如何」と取り合わなかったとの話が見えるが、伊達側の史料にも、忠輝から遣わされた花井の「御手前人数可致疲労間、我等人数一戦可仕(12-18、pp.653)」との申し入れに対して、「軍は今日にかぎらず、今日は相止らるへき(12-18、pp.653)」と政宗が止めたという話が伝わっている事から、忠輝側と伊達勢との間で一合戦をめぐるやりとりがあり、花井は政宗に止められていた事がうかがえる。
しかし、七日については、忠輝に属して従軍した者たちの所伝をみる限り、年録の云うところとは、だいぶ話が異なっているようである。
例えば、忠輝の旗本にいた長谷川権之助(※10)は、この日、忠輝に近侍していたが、忠輝の旗本が左右に分かれて崩れてしまい、敵がいないか確認するため五十間(90m)ほど先まで馬を出したが、そこでかつての家老であった皆川山城守(※11)と邂逅しており、皆川から味方が崩れているが敵はいないと聞いて、その旨を忠輝に伝えに戻っている。また、忠輝の旗が立っていなかった為、長谷川が代わって旗持ちに立ったといい、この混乱で旗奉行の三名ばかりか、持筒頭と足軽頭の姿も旗本には見えなくなっていたらしい。この他、松平庄右衛門(※12)組に属した西山昌綱(※13)の所伝にも、西山もこの日、忠輝の旗本にいて「味方敗北すといへとも昌綱其場をしりぞかず」といい、忠輝の陣が崩れるという事態のあった事はうかがえるが、長谷川の云うところと合わせて考えると、忠輝の旗本が崩れたのは直接敵と戦っての事ではなく、まわりの混乱を受けての事のようである。
忠輝の旗本がこの後、陣を立て直して戦ったのかどうか、また先手と旗本との連携がどのようであったのかについては不明だが、松下左門(※14)組に属した堀新右衛門(※15)は、七日、天王寺で合戦と聞いて旗本から先手へと移って戦った事をその経歴で述べている。それによれば、新右衛門は天王寺で首級を一つ挙げた後、それを山田隼人に預け、また、大坂城二の丸の大手門で一人を生け捕りにして、これもまた山田隼人に預けたと云い、その兄弟らも詳細は不明ながら、天王寺と二の丸大手門でそれぞれに高名を遂げた事が「堀系図」(『大日本史』12-19、124-125/591)の略譜に記されている。この他にも、その立ち回りは不明ながら、忠輝に属して戦った服部半蔵(※16)は七日の天王寺の戦いで討死にした事が伝えられており、これらを見ても、忠輝に特段の功のなかった事は、到底、年録の云うような花井に無用の事で煩わされた事によるものではなかった事が明らかである。
してみると、年録に見える安西の言動というのは、「手ニ御逢不被成候事...花井の私故也、更に上総殿之御曲事にあらす(151/513)」とあるように、花井一人に責任を押し被せて、何の功もなかった忠輝を庇ったという話なのだろう。
次回は、十二日の公事についてである。
※1 年録について
『日本史大辞典』第二巻、1993、pp.1302に解説がある。1615-1623の幕府に関する編纂物であり、この時期を扱う実紀においても参照物として用いられている文献である。編者、成立時期ともに不詳であるが、すくなくとも寛永年間(1789-1801)よりは以前に属すると云う。
※2 安西右馬允について
〇安西正重「寛政重修諸家譜」〔138〕巻582、67-68/132
兵部、文右衛門、安西右馬允。はしめ松平上総介忠輝朝臣につかへ、元和二年七月二十七日めされて御家人に列し、越後國頸城郡のうちにして采地賜はり大番となる。これさきに大坂の役に忠輝朝臣の従者御家人を殺害せしを糺さるるにをよひ、正重曾て家老花井主水某等の所為たる事をしるかゆへ、主水等はかりて正重を殺害して其口を消、罪をこれにあたへむと企つ。其罪状を挙て老職のかたかたに訴へやかて人衆を正重か宅に向はしめこれを捕むとす。ここにをいて正重ひそかにのかれて江戸へ来り奉行所に封書を捧けて主水等の陰悪の始末を陳へ、且、忠輝朝臣大坂の役におこたらせたまふの事もまた主水等のなせるところにて、主人のひか事にはあらさるよしを訴へ申せしかは、則主水某をめしくたされ、台徳院殿の御前にをいて対決せらるるの処、主水辞屈して其罪に伏す、正重はもとより身のあやまちなきのみならす、主人の罪を申宥めむとす志のほと奇特なりとて御家人にはめされしなり。寛永二年十二月一日、新墾の地をあはせてすへて八百五十石の御朱印をたまふ。十四年大坂城の守衛にありて死す、年五十五、法名道悟。妻は北條家の臣、三富甚左衛門某か女。
〇「信濃史料」補遺編下-3、3コマ〔古文書〕〇東京都 内閣文庫所蔵
安西文衛門正重拝領、同徳太郎正倫書上
知行目録
一弐百石 越後頸城郡苅田村之内
一弐拾七石壱斗 信州木内南長池村
一七拾三石 同北長池村
高合三百石者、
右令扶助〇、全可領知者也、仍如件、
慶長拾六年
八月廿八日
安西文衛門とのへ
※3 喧嘩相手の上総殿の衆
年録はこの騒動を「喧嘩」と見ている。恐らく、忠輝側で死んだ人数と、下手人として差し出すことが予定されている人数で帳尻が合わさっている事によるのだろう。
〇長坂信時「寛政重修諸家譜」〔51〕巻221(115/137)
六兵衛。母は上におなし。台徳院殿につかへたてまつり小十人をつとむ。元和元年大坂御陣に供奉す。ときに信時近江国守山の駅にして上総介忠輝朝臣の前を乗打せしとてその無礼をとかめられてかの朝臣のためにうたる。のちこの事兄信次東照宮に愁訴まうすのところ、かの家臣等十人を誅せらるるの上は、恨申ましきむね仰をかうふる。
大日本史料は「素打」と書いているが、「寛政重修諸家譜」による限りでは「乗打」である。
〇富士信友「寛政重修諸家譜」〔90〕巻379(18/132)
與四右衛門。母は某氏。台徳院殿につかへたてまつり御小姓をつとめ采地四百石を知行す。元和元年大坂御陣のとき近江国守山の驛にをいて長坂六兵衛信時、伊丹弥蔵勝久とおなしく上総介忠輝朝臣の前を乗りうちせしかは其無礼を咎められ彼家臣等に討る。
年十七。年録では太兵衛となっているが、家譜には与四右衛門とある。
〇伊丹勝久「寛政重修諸家譜」〔65〕巻276(12/104)
彌蔵。母は上におなし。台徳院殿につかへたてまつり小十人をつとむ。元和元年大坂御陣に供奉するのところ近江国守山驛にをいて長坂六兵衛信時、富士與四右衛門も信友とおなしく馬上にして上総介忠輝朝臣の前を過りしかは其の無礼を咎められかの朝臣乃為に害せらる。
※4 原文「何とそ越後ニ而闇打二いたし捨、森山にての喧𠵅の相手に候間、成敗仕候由可申と打手両人申付候間…」(151/513)
※5 原文「大坂表ニ而、上総介殿遅成被成、手ニ御逢不被成候事、奉行共曲事、就中花井主水の私故也、更ニ上総殿之御曲事にあらす」(151/513)
※6 伊達側の史料によると、この日、未明に攻撃を受けて日の出前から交戦状態に入っているが、忠輝の着陣は辰刻(7-9時)以降であったと云う(「伊達政宗記録事蹟考記」『大日本史料』12-19、pp.652)。
※7 伊達側の史料によると、花井が忠輝の使いとして政宗の陣を訪れ、伊達勢が疲れているのであれば我らが戦ってもいいと伝えたところ、戦は今日だけでないのでやめておくようにと釘を刺されている。(「伊達政宗記録事蹟考記」『大日本史料』12-19、pp.653)
※8 花井の一事で説明する事の難
この日、忠輝が花井に雑事でを煩わされたかどうかは不明だが、少なくとも従軍した者たちの所伝を見る限り、それだけでこの日の越後勢の動きを説明するには無理がある。
※9 伊達側から見たこの間の動きについて、史料上に見えるところを拾って見ると、以下のような流れになる。
4/27 大坂方が大和国郡山城を攻撃。(『大日本史料』12-18、目次)
4/28 未明に京都出陣、未刻に井出着陣。仙台より片倉、横田ら参着。
4/29 井出に留陣、少将殿へ書状、少将殿よりも御使両度参る。仙台より大町、福原ら参着。
4/30 寅刻に出陣、申刻に木津着陣。仙台より遠藤以下参着。
5/01 木津に留陣、少将殿へ使者。仙台より大町以下参着。
5/02 已刻に少将殿陣所へ見廻りとしてお出、未刻に御帰。仙台より新田以下参着。
5/03 午刻に木津を出陣、未刻に奈良着陣。仙台より瓦理以下参着。
5/04 奈良に留陣。越後少将よりご使者、端午の祝儀。仙台より磯田以下参着。
5/05 奈良を出陣。(『東大寺雑事記』2、『大日本史料』12-18、pp.594)
5/06 未明より道明寺合戦。辰刻に忠輝着陣。未刻以降に花井主水が使者として打診に。
5/07 辰刻に道明寺を出て、午刻には天王寺辺で合戦、未刻に大坂焔上。申刻、難波へ陣。
これらを見ると、政宗の陣には仙台からの人員が連日到着しており、伊達勢は忠輝と連絡を保ちつつ、配下の合流を待って進んでいるのが分かる。
五月五日に四万程の軍勢が南都をたったといい(「東大寺雑事記」2『大日本史料』12-18、pp.594)、五月六日の未明に敵方から銃撃を受け、夜明け前から交戦状態に入った事が述べられている(「伊達政宗記録事蹟考記」21、『大日本史料』12-18、pp.651)。
その後、辰刻に忠輝が着陣して参会した話が見え(★「只今おしつまり入り候間、少御目覚可能申上とて時刻移り候(152/513)」という話に一致)、午刻に政宗は、松平下総守(忠明)、本多美濃守(忠政)、水野日向守(勝成)らの陣をまわっているが、その際に三将から、伊達勢が戦うなら兵を出すと言われたものの、政宗は朝から戦ったので今日はもうこれ以上戦わない旨を伝えて自陣に戻った。
他方、越後勢は、ハツ時分(未刻)に松平筑後守と堀下総守が二十町計(2.2km)物見に出て、敵夜討についての心掛けの話をしており(「六日之夜、自然敵夜討ニ出可申哉と面々心掛申候」、「堀文書」『大日本史料』12-19、122/591)、政宗の方には、忠輝の使いとして花井主水がやってきて、伊達勢が疲労困憊であるなら我々が戦うとの話がなされるが、政宗はこれを戦は今日だけではないのでやめておくように「今日に限るへからす、今日は相止らるへき由ご返答」と釘を刺している(★「御敵もいまた数多見得申候間是非御かかり被成一合戦被遊可然と申上候間、政宗に御相談被成候へは(152/513)」云々という話に一致)。
七日、五ツ時(辰刻)に伊達勢は道明寺を出て、四ツ時(刻)に茶磨山より五町計(500m)前で秀忠と会っており、本多佐渡守から秀忠に茶磨山には家康、岡山に秀忠が落ち寄せるとの方針が示された(「伊達政宗記録事蹟考記」21『大日本史料』12-19、117/591)。その後、伊達勢は九ツ時(午刻)に茶磨山の近辺で戦って首級1000を挙げ、七ツ時(未刻)に大坂の城が焔上して、八ツ時(申)に政宗は難波に陣取った(「伊達政宗記録事蹟考記」22『大日本史料』12-19、117/591)と云い、六日の後藤又兵衛討ち取りに続いて伊達勢にはこの日も功のあったがうかがえる。
以上が公事で取り上げられた五日、六日、七日の動きを伊達勢から見た流れである。
してみると、「年録」における安西というのは、花井の私にした曲事故と無功の忠輝を庇っているが、こうした流れを見る限り、政宗は無理をせず、また忠輝にも無理をさせずに軍を進めており、単に徳川との重要な帯紐である忠輝を危険に晒すよりは、無事に温存しておきたかったのだろう。しかし、活躍の場を得られず家康に失望された忠輝は、思うようにならなかった不満から政宗をなじり、その思惑を勘繰ってあらぬ難癖を政宗に加える事になったのではなかろうか。
※10 長谷川権左衛門について
長谷川権左衛門の名前は、忠輝が朝熊に配流された際の随行者の中にも見えている(『大日本史料』12-25、「東武実録」148/513、「元寛日記」161/513)。「柳営婦女伝系」には、井伊家の家士に長谷川八郎右衛門なる者がいて、この者は於八の従弟にあたり、於八の父の敵を鉄砲で撃ち殺した事から忠輝に召し出されたと云う話や、忠輝家臣の木全刑部なる者は長谷川氏の親類らしく、茶阿局の子である喜八郎と又八郎はその養子となって、忠輝に小姓として仕えたと云う話(『柳営婦女伝叢』52/280)が見えており、権左衛門とこれら長谷川の関係は定かでないが、忠輝の家中には母堂の縁に連なる者が多く見え、忠輝の側近くに仕えた権左衛門もまたそうした一人だろうか。
※11 皆川勢の動向
皆川広照は慶長十四(1609)に公事に敗れて改易となったが、大坂夏陣には井伊掃部頭の手に属して従軍しており、「(隆傭は)七日味方少しやふるるといえともその場を退かず(〇皆川隆傭「寛政重修諸家譜」〔201〕巻862、121/148)と云う。
※12 松平庄右衛門組
松平清直「寛政重修諸家譜」〔9〕巻40。長澤松平氏、出羽守、庄右衛門。慶長十四年(1609)に改易となるも、「ゆるされてもとのごとく忠輝朝臣に勤仕す」(同、148/513)。宮川にて五千石と云う(「續武家閑談」『大日本史料』12-25、172/513)。
※13 西山昌綱「寛政重修諸家譜」〔186〕巻794、119-120/137。
※14 松下左門組
松下左門は、「柳営婦女伝系」に花井主水の弟としてその名前が見える(『柳営婦女伝叢』52-54/280)他、「堀文書」に「拙者儀者、少将殿旗本に罷在候、組頭松下左門にて御座候」(『大日本史料』12-19、122/591)、「大泉叢誌」所収の長谷川権左衛門書付に「土井遠江殿(利隆)にて松下左門」(『大日本史料』12-19)などとある。
※15 堀勢の動向
堀親重は堀秀政の末弟であり、内膳、勘兵衛ら他の兄弟とともに忠輝のもとで夏陣を戦った(「堀系図」『大日本史料』12-19、124/591)。三四郎、新右衛門(〇堀親重「寛政重修諸家譜」〔180〕巻764、160/199)。
※16 服部正就「寛政重修諸家譜」〔264〕巻1168。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
