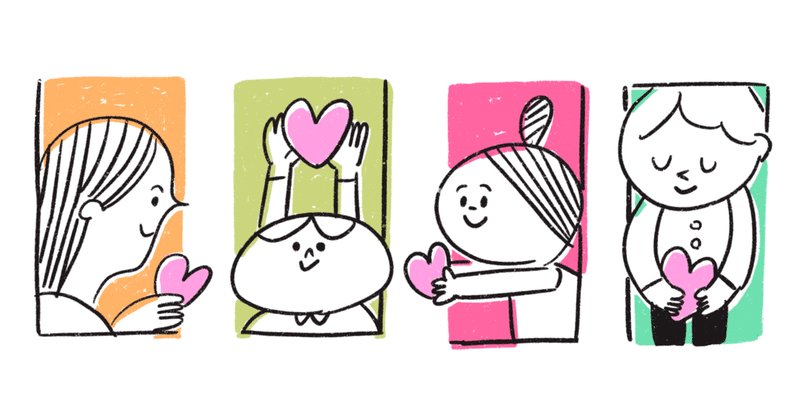
感動のエクストラクトを純化せよ
ひところ修行僧のように美術展巡りをしていた時期があったが、今はなんでも観ておかなくっちゃという強迫観念のような焦りが薄らいでいる。
年齢とともに体力が低下しているというのもあるだろうけれど、「好き」の推進力に任せたきり、いったい何を求めてそんなにがむしゃらになっているの?と立ち止まることができたのだ。
もっと言えば、感動を求めて動くことで見落としてきてしまったものがじつはその体験の要だったとハタと気づいたのだ。
今は、これと思った美術展を、あるいは一点の作品を納得のゆくまで理解したいという気持ちが強くて、どれだけ自分の中で広がりを持てたか、というところに焦点を当てて鑑賞していきたいと思っている。
人生は短い。すべてを知ろうとするなんてしょせん無理な話。だからそこはやっぱり、とことん好きなことに注力すべきなんだと。世の中そんなムードなので、自分も感化されているのかもしれないけれど、それよりもっと切実に「人生の残り時間」を意識できる時期にさしかかっているということの方が強い。人生100年時代といわれたところで、質量ともに充実した実質的な稼働時間というのは案外短いものである。そのはかなさにはぜひとも注意しておきたい。
確かに、いいものをたくさん見るというのは審美眼を養う一つの方法ではある。しかし、次から次へと目新しい感動を求めて動き回ったところで当の本人がその体験をいかに次へと繋げるかというもう一つの眼を持っていないと総体としての経験が言葉もなく漂うばかり。その虚しさに気づいた頃から徐々に美術の見方も変化してきたのだと思う。無駄な経験など何一つないのだ、という実感も持ちながら、その言葉のトリックには注意しておこう、と考えるようになった。
目指すべきは、多種多様な感動を結晶化してその純度を高めダイアモンドのように磨き上げていくプロセスにこそある。散発的で雑食性の体験は、そのままではただの感動付きの楽しい思い出になってしまう。
感動のエクストラクトの純化は何を惹きおこすかと言えば、それはセレンディピティだと思う。セレンディピティとは偶然の産物、あるいは幸運を偶然手に入れる力といった意味であるが、この偶然は体験の意味内容を純化したストックがあればこそ起こりうるものだという気がしている。そうでなければ、その偶然を発見することができないからだ。漫然とした朧げな感動の記憶の束では、セレンディピティだと気づけないかもしれない。
しかし、これは体験の生産性や合理性を高めることではなく、むしろ対極にあるはずで、1の感動に対して10や100の検証といったぐあいの寝かせ時間が必要だ。美術を研究するというのも、そんなものだという気がする。私が研究したい欲に駆られるのは、きっとそれを求めての行為なのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
