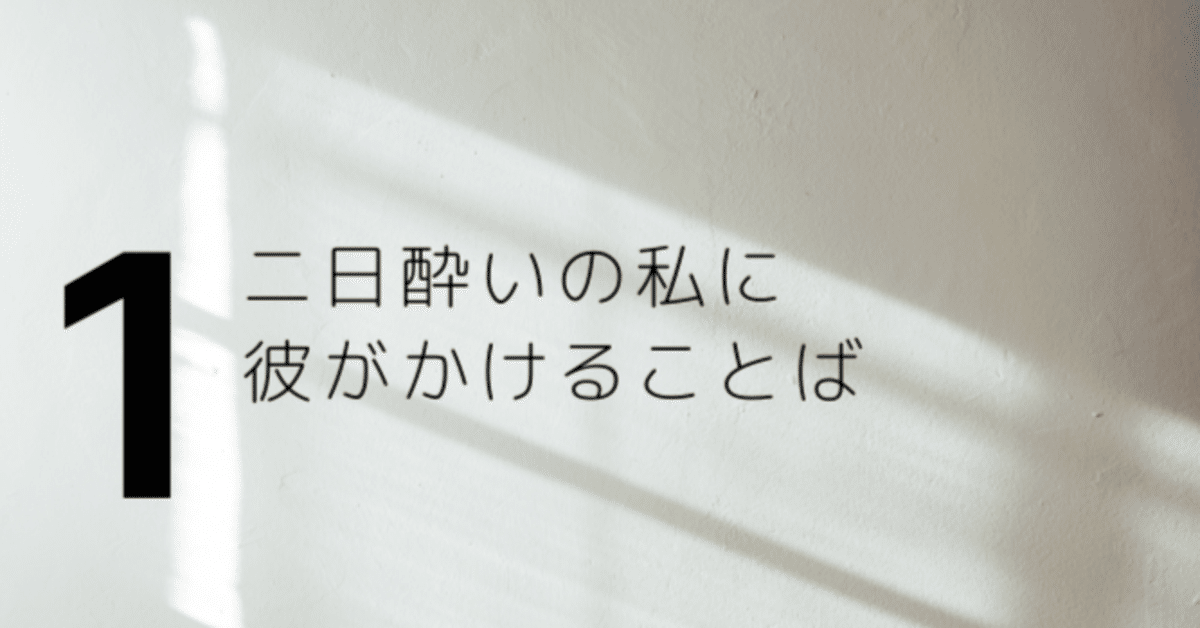
二日酔いの私にかけることば1
雨の音がする。控えめな日差しがカーテンに遮られている。
もう一度目を閉じたいけれども、乾いた喉を潤したくて起き上がる。
「もう起きたんか」
リビングにいた恋人が、マグカップを手にこちらへ目を向ける。
小さい声でおはようと答えて、私もマグカップを手に取った。視線はそらしたまま。
昨日私は大事な仕事があって飲みすぎてしまった。
帰ってくるなり気持ち悪いといってトイレへ直行した。
ただいまの代わりに甘えた声で恋人の名前を呼んで、抱きつくような可愛い酔い方じゃなかった。
こんなに酔うことはあっても恋人に見せたのは初めてだった。
昨日はただ必死に気持ち悪さを解消したことしか覚えていなくて、恋人がかけてくれた言葉とか、その時の表情も、全く記憶にない。
だから、怒らせたか、呆れさせたか、どう思われたか、わかっていない。
ソファでココアを飲みながら、スマホを見る彼。言葉は発しない。
休みがかぶることは珍しく、休日に彼がどんな朝を過ごすのかよくわかっていない。
だからその態度が、不機嫌なのか、いつもどおりなのか、私には判断がつかなかった。
「お前さん、体調はどうなんじゃ」
スマホに目を向けたまま、彼が問う。
「あ、昨日は迷惑かけちゃったけど、今朝はまあまあ。大丈夫」
「まだ寝とったほうがいいんじゃなか」
低い声に怖がりながらも、繰り返し大丈夫だと返事をする。
そうはいいつつも、食欲はない。
白湯を注いで、少しずつ飲む。身体があたたまるのがわかる。
ちょいちょい、と彼が手招きをするので、黙ったまま彼の横へと腰掛けた。
「なんじゃ、あまり喋らんの。昨日のこと、気にしてるんか」
私の表情から察したのか、彼から鋭い指摘が入る。
「昨日は大事な仕事だと思って気合が入りすぎて…。あんな姿を見られ、
呆れられたのではないかと、目覚めて一番、心配になりました…」
つらつらと心情を吐露する私を、彼は静かに頷きながらみている。
「しかしこの歳になって、お酒の量をセーブできないのはいかがなものかと…」
次々に出てくる言い訳が積み重なっても、彼はそのまま聞いている。
「…だから、ごめんなさい。」
私の長い話が終わったところでようやく、彼は冷めたココアを飲み干した。
「お前さんが、必要と思って飲んだ酒ならよか。ちゃんと帰ってきたのもよか。
だけどな、俺が迎えに行けるときはちゃんと連絡せんといけんよ」
そうしたらもう少し早く休めたじゃろうに、と言いながら、私の頭をぐしゃっと撫でる。
「どんな姿でも呆れたりはせんけど、もっと頼ってくれたほうが俺としては安心するんじゃけどな」
読めない彼がこんな風に考えてくれているだなんて思っていなかった。
せっかくの嬉しいを言葉を、二日酔いの冴えない頭で聞くことを少し残念がる。
すると彼は、「弱ったお前さんにだから言える言葉じゃ」と、私の心を読んだような事を言う。
まだまだこれから、心配かける。助けてもらう。
この人のそばにいて、私も同じように支えでありたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
