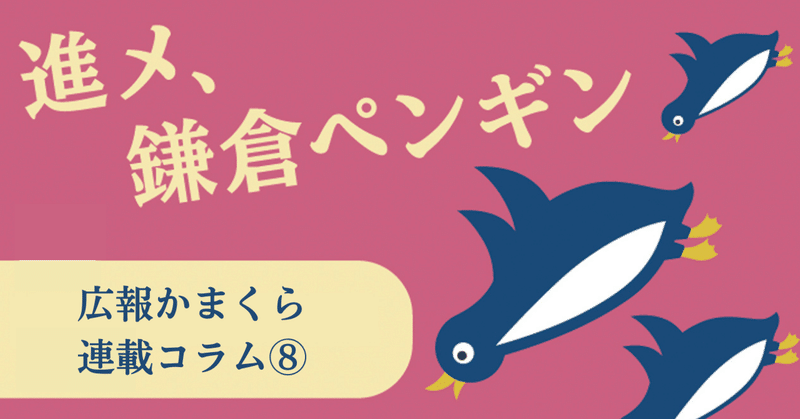
子どもの視点に立った教育を
教育長の岩岡です。
昨年7月から始まったこのコラムでは、市教育委員会や市立小・中学校が実施している様々な取り組みや込められた思いを紹介してきました。これらの取り組みには共通するポイントがあります。
それは「子どもたちの視点に立つ」ということです。これには2つの意味があり、私は着任以来、判断の際には必ず心に問い掛けています。
1つ目は「子どもたちの現在の視点に立つ」ということです。これは、子どもたちの現在の心情や特性に寄り添って、子どもたちの成長や行動変容を促す最適な方略を選択することを意味します。
この視点に立った取り組みとしては、GIGAスクール構想に基づき1人1台配布したタブレット端末やAIドリルなどのデジタル教材を活用した個別最適な学びの実践、また、子どもたち一人一人が自分のユニークな特性と自分らしい学び方に気づき、自立していくのを支援する「かまくらULTLAプログラム」などが挙げられます。

2つ目は「子どもたちの未来の視点に立つ」ということです。これは、子どもたちが将来飛び込んでいく社会を予測し、そこで求められる力を逆算して現在の教育を組み立てることを意味します。
この行政・学校といったサプライサイドの視点ではなく、子どもというデマンドサイドの視点に立って教育を組み立てるという基本的な考え方は、何も鎌倉市教育委員会が独自で思いついたものではありません。
例えば、令和3年度から小・中学校において全面実施となった新しい学習指導要領も、「主体的・対話的で深い学びの実現」に向けた授業改善を中核的な概念の一つに据えていますが、「〜〜力の育成」「〜〜な教育の実現」といった教授者側が主語となった概念ではないことにお気づきと思います。学校現場では、「どういう発問をするか」「どういう教材を提示するか」を目標に授業改善するのではなく、学習者である子どもたちが「どう学ぶか」をゴールにしながら(=子どもたちの視点に立って)授業改善を行っていくことが求められています。
また、OECD(経済協力開発機構)が2030年の学校での学びのあり方を示した「Learning Compass 2030」においても、Student Agency(生徒エージェンシー)が中核的な考え方として示されています。エージェンシーというと聞きなれない言葉かもしれませんが、責任をもって自分自身で考え行動していくことを指す言葉です。学びをコンパスに例えたことについて、OECDはこのように記載しています。「ラーコング・コンパスという比喩は、生徒が教師の決まりきった指導や指示をそのまま受け入れるのではなく、未知なる環境の中を自力で歩みを進め、意味のある、また責任意識を伴う方法 で、進むべき方向を見出す必要性を強調する目的で採用されました。」(仮訳)

様々な技術が発展し社会のありようが急激に変化する時代が到来する中、人と違った特性や興味をもっていること自体が価値の源泉であって、一人一人の多様な幸せ(well-being)を実現できる世の中を目指そう、というのは時代の潮流とも言えます。だからこそ、「子どもの視点に立つ」という考え方はとても重要であって、鎌倉市だけが目指す特異な方針ではなく、教育界全体で大事にするべき考え方なのではないでしょうか。
時代の変化を前向きに捉え、Society5.0と呼ばれる社会をペンギンのようにしなやかに泳ぐ子どもたちを育むため、子どもと同じ目線に立ち、新年度も様々な取り組みに挑んでまいります。
(広報かまくら 令和4年4月1日号 掲載文に加筆)
