
ベトナム オフショア開発のメリット・デメリット 〜これからのグローバル開発時代に向けて〜
「オフショア開発は聞いたことあるし、理解はしているが、最近オフショア開発はベトナムがいいと聞く。何がいいのだろう?」
という方々に向けてこの記事を書いています。
私は2020年8月時点でベトナムに約8年間住んでおり、オフショア開発に関しても8年間、開発者として、ブリッジとして、PMとして、経営者として、顧客として、様々な立場で、様々な案件に関わってきました。
その経験をこの記事にまとめてみました。
この記事の前提
始めに言っておきたいのが、私自身「オフショア開発」という言葉は好きではありません。
「オフショア開発」は基本的に、仕様が決まっている(ときにはレガシーな)ソフトウェアのメンテナンス、機能追加やテストを、物価が安い海外の地域の企業へアウトソーシングを指し、発注する側には開発費用削減という大きな効果があるものです。
実際、これまでのベトナムのソフトウェア産業は典型的なオフショア開発でした。
そして、「仕様が決まっている仕事する経験ばかりを積んでいる」ということがベトナム人エンジニアの仕事への作業的な姿勢を促進し、新しい技術を実践する機会を少なくしていた側面が少なからずあると私は考えています。
時代は変わり、ベトナムの物価は上昇し、いわゆる「オフショア開発」としての価格的なメリットが小さくなっている一方、ベトナム人エンジニアは力をつけ、経験豊富なエンジニアが増えてきています。
2030年にはワーストケースでIT人材が約80万人不足すると言われている日本にとって、ベトナムは強力な開発リソースとして期待する「グローバル開発」へとシフトしています。
しかし、本記事では、一般的に認知されている「オフショア開発」という言葉を使うことにします。
「ソフトウェア開発を海外に外注する」という広義の意味で「オフショア開発」という言葉をとらえていただければと思います。
オフショア開発のメリット
オフショア開発プロジェクトをやることによる直接的なメリットは下記のようになります。
・開発費用を抑えられる
・日本と比較して開発リソースを調達しやすい
・「ラボ型開発」を利用すれば、採用費用のかからない採用の代替手段になる
また、オフショア開発を継続的に利用することで、下記のような効果も期待できます。
・外国人と一緒に働くという経験を積むことができる
・(通訳を介さずに業務をすれば)英語を使う機会を作ることができる
・リモート勤務に慣れることができる
・リモート勤務に慣れ、日本国内でリモート勤務を前提とした採用も視野にいれることができる
・将来的に現地法人設立も視野にいれるのであれば、社員に海外出張、海外駐在の機会を作ることができる
・現地法人を起点に、日本で展開しているサービスを現地マーケットでも展開できる
ベトナムのオフショア開発のメリット
では次に、ベトナムでオフショア開発をすることのメリットを挙げていきたいと思います。
理系人材が豊富
国際数学オリンピックにおいて、ベトナムはメダル数上位ランキングの常連で、日本よりメダルを取っている年もあります。2019年はベトナムは7位(日本は13位)です。
国際情報オリンピックにおいても、今までのメダルの総数でソートするとベトナムは7位(日本は33位)です。
なぜこんなに理系に強いのか因果関係はよくわかりませんが、高等教育によるものが大きいと思われます。
またもう一つの事実として、大学生1学年あたり、ベトナムはIT系学部専攻の学生を日本の5倍以上排出しており、人数比にすると7倍以上になります(*1)。それほど、IT人材の教育に力を入れているということです。
*1 大学生数の参考
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/06/27/1387312_03.pdf
https://www.qtsc.com.vn/uploads/files/2019/03/19/Nghe-CNTT-Official-Small.pdf
非常に真面目で勤勉な国民性
一般的にベトナム人は非常に勤勉で真面目な性格が強いと言われています。
これは定性的な話なので、事実を元に検証することは出来ませんが、私の周りには会社が終わったあとに夜間学校に通ったり、大学のうちからインターンで実地経験を積んだりしている人はたくさんいます。
また、日本料理屋さんのスタッフが、日本人のお客さんに日本語を教えてもらったりするなんていう光景もよくみます。私の個人的な感覚としても、ベトナム人は非常に向学心が強いように思います。
時間距離も物理的距離も近い
ハノイやホーチミンは日本各都市の空港へ直行便が出ており、ハノイー羽田で約5時間程度です。福岡だと4時間以内に着くこともあります。この程度の移動であれば映画や本を2,3本見ていれば着くので全く苦になりません。
また、時差もたった2時間(日本から見て−2時間)しかありませんので、業務上の支障もほとんどありません。
同じアジアなので当然といえば当然ですが、時間的/物理的距離の近さは非常に魅力的で、日本ーベトナム間でリモートで仕事をするといったことも簡単に出来ます。
日本語人材を積極的に育てている
ハノイ工科大学のIT系専攻の学生に日本語教育を提供するHEDSPIプロジェクトや、日本語を第一外国語として選択可能な学校、ブリッジSEを1万人育てる計画をだしているFTPソフトウェア等、ベトナムは日本語人材の教育を積極的に進めています。ベトナムにとっても日本は重要なパートナーということです。
実際、日本語能力試験で業務上支障のないレベルのN2、N1を持っている人材を見つけることは難しくありません。
ただし、ポジショントークにならないようにもう一つの事実を伝えておくと、十分な日本語能力とソフトウェア開発周りの知識の両方を持った人材を探すのは比較的難しいです。
平和で住みやすいので駐在に向いている
スリやひったくりの類の犯罪は当然あります。また、交通事情もカオスなので交通事故のリスクもあると言えばあります。
ただし、東南アジアの中でも非常に治安はよく、凶悪事件に巻き込まれる可能性は非常に低いです。会社としても、出張や駐在の許可をだしやすい国の一つだと言えます。
どことなく日本と雰囲気が似ている
これは非常に主観的で、私の個人的な意見に過ぎませんが、アジア大陸に位置する国の中でも、非常に「日本の懐かしさ」のようなものを感じる国だと思います。実際、ベトナムへの視察を今まで何回も受け入れてきましたが、多くの参加者の方が「懐かしい」とおっしゃいます。
根拠はやはり人と食にあると思います。
ベトナム人は非常に家族を大切にします。ご近所付き合いも活発です。また、ベトナムでは飲みニケーションも可能です。要は、飲み食いしながらワイワイやるのが大好きな人が多いです。
主食は米ですし、野菜や魚を好んでべます。ベトナム料理は日本人の口に合いやすいです。というか、美味しいごはんがたくさんあります。
街並みは日本と全然違いますし、電車が走っていない、コンビニがまだまだ少ない、自動販売機がほとんどないなど、インフラ面は日本と違う部分はたくさんあります。
それでもほとんど違和感なく生活できるのは、人とのつながりを大切にする考え方が日本人と似通っている点、ご飯が日本人の口に合うという点は非常に大きいと私は考えています。
ただ、最近では日本の社会では人とのつながりが希薄になっているように感じます。ベトナム人から見た日本の一つの残念なイメージは「電車で老人や妊婦の方に席を譲らない」です。日本人がお互いに助け合い、人と人とのつながりを大事にしていたのは一昔前の話になってしまったのでしょう。だからベトナムで「懐かしい」と感じるのかもしれません。

ベトナムにはどことなく懐かしい景色が広がります。
ベトナムのオフショア開発のデメリット
良いことばかり書いてきましたが、当然オフショアはそこまで簡単ではありません。以下に、気をつけるべき点を挙げてみたいと思います。
物価上昇が激しい
一時期に比べるとだいぶ落ち着いてきましたが、ベトナムの物価上昇率は高いです。物価が上昇しているということは、最低賃金や平均給与もどんどんあがっているということです。
もし開発コストを抑える目的でベトナムオフショアを考えられているのであれば、この点も加味して判断する必要があります。通訳の費用も考慮すると、現時点ですでに日本のニアショアより若干安いくらいの価格帯です。
エンジニアが全体的に若く経験に乏しい
ベトナムの人口ピラミッドはまだまだ一番若い世代が一番膨らんでおり、平均年齢もやっと30歳を越えたくらいです。
特にIT業界は、産業自体が若いので、エンジニアも総じて若いです。
つまり、十分な経験を積んだエンジニアの数が少ないです。
且つ、ベトナムのエンジニアの大半は「オフショア開発」をずっとやってきており、たとえ経験年数が長くても、エンジニアとしてあまり濃い経験を積んでいなかったりするのが実情です。
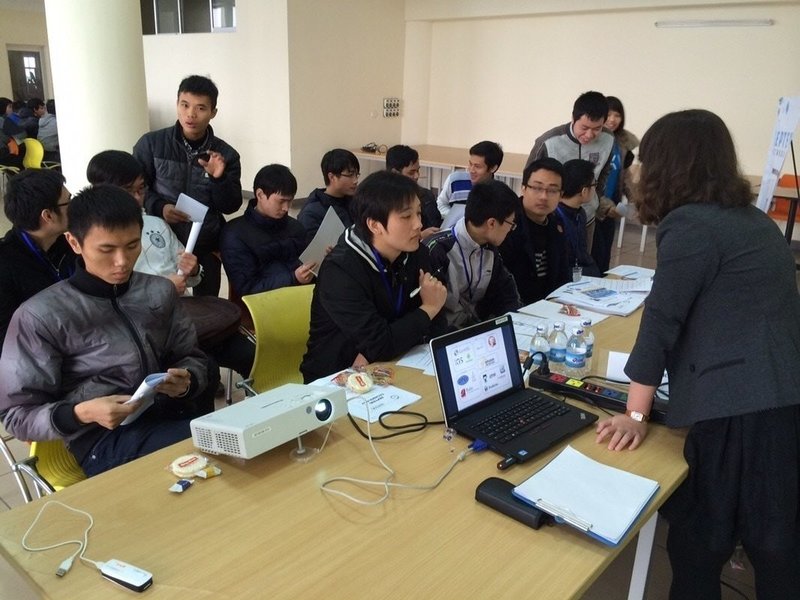
ベトナムのエンジニアは全体的に若いです。写真はハノイ国家大学の学生達。
いきなり「日本品質」を求めるのは難しい
どんなに品質を担保する体制を組んでも、日本人が求める日本クオリティをいきなり出すのはかなり難しいです。
これはまた別の機会でも書こうと思いますが、原因は主に2つだと考えています。
①日本がどのレベルで品質を求めているかの合意形成が取れていない
②日本が求める品質レベルで仕事した経験がほとんど無い
したがって、仕事を出す日本側もある程度「育てる」という姿勢が求めらますし、いきなり難しいプロジェクトで開始するのではなく、プロトタイプを作ってみるなど徐々にチームを大きくしていくなどの対策が必要になってきます。
社会インフラはまだまだこれから
電車が走っていない、舗装されていない道路が多い、下水道整備が不十分等あげればキリがありませんし、こういう点にストレスを感じて駐在出来ない日本人もいるのではないかと思います。
しかし、業務上一番影響が大きいのは「インターネットが遅い」ことです。
オフショア開発をやる場合は週1回くらいのペースでやることになりますが、途中で切れてしまったり、音声が途切れがちだったりなどの不具合は覚悟しておく必要があります。
また、年中行事のようにAAG海底ケーブルが頻繁に切断します。その事故が起きるともう、ベトナム国内から海外サーバへの接続は絶望的になり、ほとんど仕事にならないくらいにインターネットの速度が低下します。
最後に
冒頭に述べさせていただいたように、近年日本のIT人材不足が深刻化し、オフショア開発はIT人材不足問題の解決方法の一つして注目されてきています。
本記事が少しでも役に立てば幸いです。
この記事は私が経営する株式会社スクーティーのコーポレートブログの下記記事を焼き直したものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
