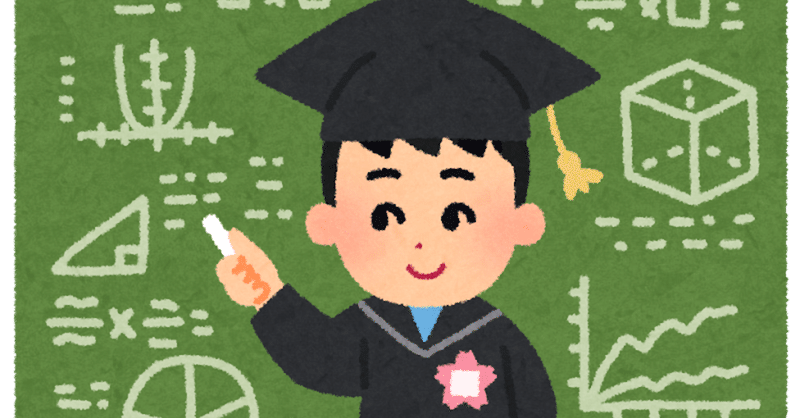
【53日目】 才能と競争
こんにちは。本日は、52日目です。
今日は、土曜日なので、のんびりとnoteを書いています^^
人は面白い生き物で、時間があるといつもとは違ったことをしたくなったり、色々なことに思いを巡らせてみたりします。それがふとしたところで、大きな価値人なっていたりもするので、結果、人生に無駄な時間なんてないのかもしれません。
さて、「才能と競争」というテーマですが、オリンピックが近づく中、社会を生きていく上で、切り離せないキーワードであるなと感じました。「才能と競争」という2つの言葉は、人に”希望”も”絶望”も抱かせろパワーのある言葉だと感じます。要するに、”取扱注意”ということですね^^
今回は、この2つの言葉をテーマに私なりに「才能と競争」について考えをnoteに書き記していきたいと思います^^
○目次
①才能と競争について
②この2つをどう考えるか?
③まとめ
①才能と競争について
才能とは、「元々生まれ持った性質」のこと。
競争とは、「勝者と敗者が生まれる競い合い」のこと。
という解釈が自分の中にあります。そして、”競争”が自体が顕著に現れる昨今(特にインターネットが発達してきた21世紀初頭)において、それと同時に、”才能”についても多くの議論が活発化しているように感じます。
「学校という均一化された教育環境」「資本主義社会という競争社会」「大卒や資格に対する特別感」それらは、全て他者と差別化を図るため、政府が用意した競争の縮図であると感じます。
私は、競争を否定しているかというと、そうではありません。現に、社会主義の衰退は、国民から競争を奪うことによって起きたことは事実です。ただ、リテラシー無くして”競争”に飛び込むことの、無謀さを今の歳になって改めて感じます。
だからこそ、”才能”や”競争”という言葉については正しく知り、それと向き合う必要があると考えます。
②この2つをどう考えるか?
では、どのように正しくしればいいのか?そもそも、正しい方法なんてあるのか?ということについてですが、私は以下のように考えます。
・競争とは何のためにあるのか?
・才能という言葉は、なぜ出現したのか?
上記2つについて、考えることがその答えです。
まず、競争とは何のためにあるのか?
これは、「より良く進化し続けるため」であると言えます。そもそも、競争とは、自分の実力を他者と比較し、勝負することによってそれを確かめるものであると言えます。
すなわち、勝負に負けるという結果は、自分の現時点でのレベルを知る上で必要不可欠であり、「負けた」という結果によって自己喪失感に陥る、自信をなくすということは、”一時の感情”であってもそれにより、自信を失ったり、人生に失望する必要は全くないと感じます。
次に、才能という言葉は、なぜ出現したのか?
才能という言葉は、競争の結果の間違った解釈として生まれた、と私は考えています。例えば、「勝負に負けた」という結果の解釈として、「結局は、才能だ」「育ちが違う」「習った先生が良いのだ」としてしてしまうのは、才能に対する誤った解釈をしてしまっていると言えます。
間違った解釈は、偏見を生み、その人の考え方を固定してしまうのです。
上記のように、「才能と競争」は、その捉え方によって、個人の人生を大きく変えてしまう考えであると感じます。改めて、それについて考えてみるのも必要なのではないでしょうか?
③まとめ
・才能と競争について、正しく考えることで、その後の人生に大きな影響を与える
・競争の間違った捉え方が、才能についての考え方を歪める
本日は以上です。
内容が人によって様々な解釈がある内容なので、様々な意見があるテーマだと思います。ただ、やはり社会の前提となっている、「競争」や「才能」について考えることは、大切だと感じます。
ここまでご覧頂いた方は、ありがとうございました。
それではまた。
2021.7.17
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
