
(読書感想)「エデュケーション 大学は私の人生を変えた」(ネタバレあり)
タラ・ウェストーバー著
読み進めるのが辛くなる本。でも読んで良かった。事故や虐待などの怪我が多くて、痛々し過ぎるこの本は、著者自身の幼少から大学で博士号を取るまでの体験記。
1986年、米国アイダホ州生まれ。両親が病院、公立学校、連邦政府を頼らないサバイバリストだったため、自宅で助産師の手を借りて生まれた。9歳まで出生届が提出されていなかった。学校にも行かず、医療機関も受診せずに育った。10代半ばに、大学に進学した兄の影響を受け、大学に通うことを決意。独学で大学資格試験に合格する。2004年、ブリガム・ヤング大学に入学。2008年に同大卒業(文学士)。その後ゲイツ・ケンブリッジ奨学金を授与され、ケンブリッジ大学トリニティカレッジにて哲学で修士号を取得。ハーバード大学に客員研究員として在籍ののち、ケンブリッジに戻り、2014年、歴史学で博士号を取得。2020年よりハーバード大学公共政策大学院 上級研究員。
彼女の出身地は、モルモン教信仰が厚い地域だけど、このお父さん、異常。後に大学の授業で心理学をかじったときに、彼はbipolarと確信。(教授はschizophreniaぽいっと言ったけど)異常な程の自身への自信はもう幻想でしかない。家族が瀕死状態でも病院に行かせない。大事故を経験しておきながら、また同じ状況を自ら作り、結局また大事故。彼曰く、全ては、神が天使が守ってくださるから大丈夫なのだそう。
兄の一人もまた強烈で、父親と同じで支配欲が強く、でも父親と違うのは暴力を振るうこと。そして、何よりも最悪なのが、父親と母親の対応。
ともかく、強烈な家庭環境で育ったこの著者。どうやって、長い長い真っ暗なトンネルを歩いて、そしてそこから抜け出せたか、それが書かれたのがこの本。
ここからネタバレなので、これから本を読まれる方は閉じることをお勧めします。
この本、この日本語のタイトルだったら絶対手に取らなかったな。「大学は私の人生を変えた」ってポイントがズレてる気がする。大学が変えたんじゃない、一番最後に書いてあるけど、強烈な抑圧された生活の中で自分の中に疑問が生まれたこと、そこから全く違う世界に出たことで、自分という人間を認識したのだと思う。
疑問を持つことは人間の最大の武器の一つだと思う。支配的な親やカルトの恐ろしいところは、疑問を持たせないこと。父親の言う通りに動いて、父親の求める人間になっていた著者が、その自分は本当の自分なのか?と疑問を持ち、その仮面を被った自分から離れる決心し、本当の自分を模索した大学時代。何度も父親の世界に引き戻されそうになりながら、疑問を持つことを諦めなかったこと。彼女は知的にも頭がいいのだろうけど、精神的にも強いなと思った。
人間が成長できる場所は何も大学だけではない。新しい場所、新しい人、新しい知識、それに触れることは大事なんだなと思った。
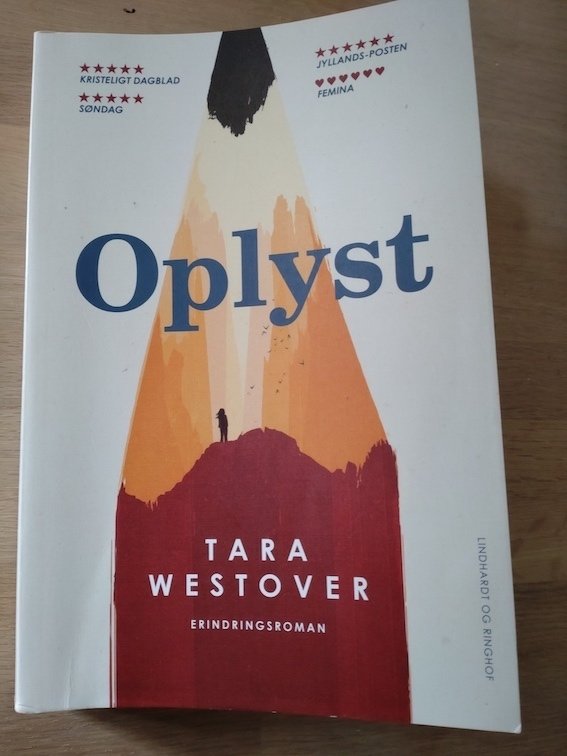
と思う。
ふと、思い出したのが、以前ニュースで見た話。
デンマークに住む79歳の女性が、37歳の娘とともに社会から脱退したと勝手に宣言し、年金受取、病院受診、電気、暖房などを拒否し、庭での菜園や鶏飼育などで自給生活をしている。ただ、家を所有しているので固定資産税を支払わなければいけないのが問題。以前は、役所が彼女支払われるはずの年金から勝手に差し引いていたが、これが違法とわかり、彼女が年金を受け取り、その中から資産税を支払うように説得を試みているとのこと。このまま拒み続ければ、家は強制オークションにかけられるそう。(専門家は他の方法もあるはずと指摘しているが、それは本題とズレるので割愛)
彼女の信条は個人の自由なのでいいとも悪いとも思わないが、気になるのは彼女の娘。まだ37歳。自分は娘という相棒がいるので、病気の今も世話をしてもらえるし、話し相手になるし、何より自分の信条でやってるのであと残り僅かの人生までやり抜けるだろう。でも、残される娘はどうなるのだろう。娘さんは中一の時にいじめで学校を辞めて以来社会に出ていない。娘さん自身も母との隔離生活に満足しているよう。でも、一人になった時に続けられるだろうか?彼女は年金もないので、どうやって資産税を払うのか?公的扶助を拒否することを教え込まれていれば、家を没収され道に放り出された時、本当に危ない。その点を質問された時、このお母さんは自分は変えられない、間違いだと思ったことは受け入れらない、と言っていた。
参考記事:「https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-og-sjael/med-guds-hjaelp-vil-79-aarige-annie-melde-sig-ud-af-samfundet-men-mod-systemet-kaemper」(デンマーク語)
このお母さんと前出の本の父親、通じるものがあるように見える。娘の将来より自分の信念を貫くお母さん。自分の子どもが目の前で死にかけてるのに自分の信条を貫く父親。でも信念を曲げてでも守るべきものがあるのではないのかな。それが親である責任ではないのかな。
親であるということは、かけがえの無い贈り物と同時に、大きな課題をもらうようなものでもある気がする。
今回この本を読んで、自分の子ども達に、疑問を持つこと、好奇心を持つことを折に触れて伝えていくことを忘れないようにしようと改めて思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
