
点描画家hiromiの大阪個展で感じたこと
正直、今回の大阪個展には関わりたくない思いでいた。
点描画家hiromiの過去を扱うのはあまりにも苦しい。
逃げ出したかった。
全部放り出してしまいたかった。
それでも、彼女の過去と最後まで向き合ってよかったと心から思えるのは、
彼女が創り出す空間が、ぼくが求めていたものだったと氣がついたからに他ならない。

点描画家hiromiのお手伝いは、彼女が点描画家hiromiと名乗る前からさせてもらっている。
渋谷個展が開催された年、2021年の4月。
彼女の「作品集を作りたい」という一言から、それは始まった。
まだ「しんこきゅう展」という個展を考えてもいないころ、彼女はぼくに声をかけてくれた。
これまで描いてきた絵をまとめて、一つの作品集にしたい。
けれど、作り方がわからない。
彼女がそういうものだから、
兼ねてより漫画制作に取り組んでいて、原稿のデータ化を経験しているぼくは、軽い氣持ちで了承した。
このお手伝いがまさか、彼女の、今ほど大規模な画家活動に繋がるなるなんて、このときは微塵も感じていなかった。
彼女はぼくによく話をしてしてくれる。
おそらく、他人には言えないであろう悩みも、「かいちさんだから」と、当時からよく話してくれていた。
これまでも何度か、人から相談ごとを受けることはあった。「話しやすい」とよく言われる。
だから、彼女もそうなのだと、このときはまだ軽い氣持ちで、彼女の心が少しでも楽になるならと、彼女の話を聴いていた。
大阪個展の開催費用を集めるためのクラウドファンディング本文には、点描画家hiromiが経験した、幼い頃の苦しい家庭環境の話が綴られている。
ぼくはこの話を事前に聴いていた。
最初の「しんこきゅう展」、渋谷個展が終わったあたりから、部分的にではあるが、彼女はぼくに口を開いてくれていた。
そのときも、彼女が苦しそうに話していたことは感じていた。
決して多くは語らず、言葉に詰まることも、涙ぐむこともあった。
思い出すだけでも辛いのだろう。
彼女のそんな様子を、何度も目にしてはいたのだが、ぼくは阿呆な人間だ。
この話のことで、ぼくは彼女をさらに苦しめてしまうことになる。

渋谷個展のときから、クラウドファンディングページの編集はぼくの役割だ。
彼女曰く、ぼくは文章を書くのが上手らしい。
ぼくの撮る写真も、彼女は点描画家hiromiを名乗る前から氣に入ってくれている。
本文作成、写真撮影、トップページや各リターンに使用するサムネイルの作成等々、
クラウドファンディングも全面的にぼくがサポートする形となった。
点描画家hiromi は人を頼るのが上手である。
彼女は文章で伝えるのが上手ではない。
しかし、対面で話す力は人一倍強い。
なので、点描画家hiromiのクラウドファンディングページを作るときは、ぼくが彼女から話を聴き、彼女の言葉を極力崩さず文にまとめている。
大阪個展のクラウドファンディングページも、そうやって一緒に作っていた。
そのときは電話での打ち合わせ。
当初の予定では、大阪個展のクラウドファンディングの内容は、あっさりとさせる予定だった。
現ページに記載されているような、彼女の幼少期の家庭環境は触れず、
“生まれ育った大阪で、思い入れのあるla galerieで、母に個展を見てもらいたい”と、
それだけを伝えて資金調達をしようとしていた。
彼女の過去の断片はこれまで聴いてきたが、
やはり、過去を全て晒すのは、彼女にはできなかったらしい。
それはそうだ。
ぼくに少し口を開くだけでも苦しいのに、不特定多数の方に公表するのはさぞ勇氣が要ることだろう。
だから、渋谷個展のクラウドファンディングよりもむしろ小規模に、こじんまりとやるつもりと、彼女は話していた。
でもぼくは、そのことについて納得がいかなかった。
当たり障りない内容で資金調達をするのであれば、クラウドファンディングをする意味がない。
やりたいことのために“想い”を伝えるのがクラウドファンディングだ。
想いが人に届き、お金が動く、それがクラウドファンディングだと思っていた。
だから、「なぜそれをやりたいのか」をきちんと伝えなければ、うまく資金は集まらないと、ぼくは確信していた。
ぼくは彼女にその旨を伝え、大阪個展にまつわる彼女の過去の全貌を聞き出そうとした。
どんな言葉を投げかけたか、今となっては覚えていないが、
全てを曝け出すことを怖がっている彼女に対して、
「ぼくがまとめるから、全部を聴かせてほしい」
ということを伝えた。
なんとしても語って欲しかったから、
「過去の話が本になったら読んでみたい」
というような言葉も口にした。
自分なりに氣持ちを伝え続けたが、気づけば、電話越しの声は詰まっていた。
鼻を啜る音が聞こえたあと、ガラガラの涙声で、彼女はぼくにこういった。
「どうしてそんなに簡単に言えるの?」
やってしまった。
心が痛む。
泣き止まない彼女の声を聴きながら、ぼくは自分を責めた。
思い出すだけでも辛い記憶。
口にするのはさぞ辛い。
そんなことはわかっていたのに、
ぼくが無神経で、愚かだった。
彼女の繊細な心についた傷跡に、無神経に触れてしまったことをひどく後悔した。
彼女がそれほどまでに苦しむくらいなら、予定通りあっさりとした内容でページを作ってしまおう。
そう思ったのだが、
後日、彼女の意見が改まった。
お互い言いたいことをぶつけ合ったからか、ぼくが色々考えたように、彼女も色々考えてくれたのだろう。
「やっぱり、大阪個展を語るには、過去を全て話さなきゃいけないと思う」
そう、ぼくに伝えてくれた。
どうやら覚悟を決めてくれたようだ。
斯くして、点描画家hiromiの幼少期の家庭環境の全貌を、ぼくは聴くことになるのだが、
このことが、今度はぼくをひどく苦しめることになった。

ぼくの父も氣性が荒いところがあった。
物心ついた頃から父が亡くなるまで、父にはいい印象を抱いたことがない。
ぼくが8歳のころ、病院のベッドで息絶える父を見て、微塵の悲しさも感じなかった程度には、ぼくは父のことが好きだった。
決して悪いような人ではなかったと思う。父親らしいことをしてもらった記憶は確かにある。
けれど、印象が転じなかったのは、ぼくにとって、父の存在がそれだけ負担になっていたからだろう。
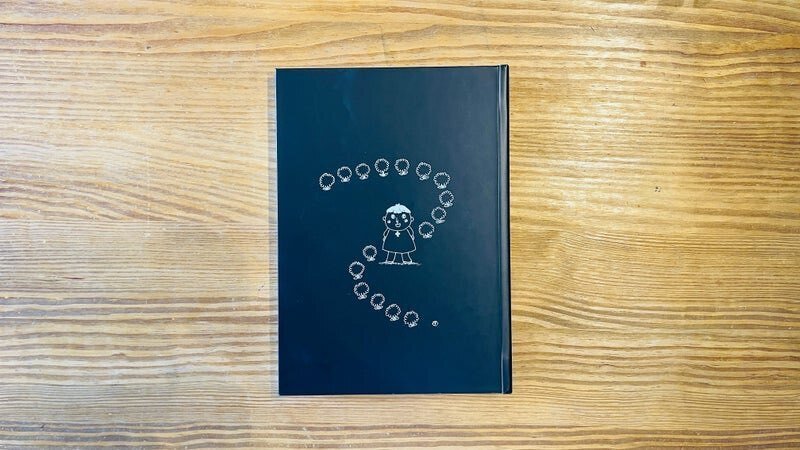
父にはよく拳骨(げんこつ)をされた。
物心ついたときから、何かにつけてよく。
まぁ、原因のほとんどはぼくにあると思うのだが。
例えば、鏡を割ってしまったとき、薪ストーブに触って火傷をしたとき、水道の蛇口が取れてしまったとき、
父はものすごい形相で、中指が突き出た拳をぼくの頭に振り落とす。
痛い。
齢4〜7のぼくにとっては耐え難い痛さだった。
涙など堪えられるはずもない。
父は加減を知らない人だった。
ほんの些細な失態で何度も痛い思いをした。
事実確認をされずに拳骨をされたことも何度もある。
父の拳骨はいつも、ぼくの話を聴いてくれない。
次第にぼくは、何をするのも怖くなっていった。
今でもぼくは、目の前の人が手を上に振りかざすと、肩を窄めて目を閉じる。
真っ暗な蔵に閉じ込められたことも何度かある。
父は泣きじゃくるぼくを抱き抱え、家の裏にある蔵へ。
微かな光も入らない、土ぼこりと蜘蛛の巣に塗れた木造の蔵。
扉は重く、鍵をかけずとも、幼な子の力ではビクともしない。
父はぼくをその蔵に閉じ込めると、2時間は開けてくれなかった。
蔵の重たい扉の前で、泣き叫びながら助けをこう記憶が残っている。
蔵に保存されていた梅漬けの瓶とはずいぶん仲良くなった。
とても冷たい、陶器の瓶。
梅の香りは、今もぼくに暗闇を連想させる。
しつけと言えばしつけだが、ちょっと度がすぎていたようにも思う。
他の家庭の父親を知らないから、なんとも言えないのだが。
父はよく怒鳴った。
ぼくにじゃなく、家族に。
夜の茶の間にはよく、父の怒鳴り声が響いていた。
ぼくの幼少期は、父、母、祖父、祖母との5人暮らし。
夜ご飯を食べたあとの団欒、家族同士のちょっとした言い合いが、氣がつけば大喧嘩。そんな光景を何度目の当たりにしただろうか。
喧嘩の原因は、幼いぼくにはわからなかったが、とにかくうるさかったことだけは覚えている。
立ったまま、他の家族を怒鳴り散らす父と、
泣きながら座り込む母、
泣きながら父を説得する祖母に、
父にムキになって怒鳴る祖父。
そんな光景が、ぼくの記憶には眠っている。
父の怒鳴り声と、母の泣き声、
祖母の叫び声と、祖父の怒り声、
父が歩くときの地鳴りの音、
引き戸のガラスが揺れる音、
台所の皿が割れる音、
引き戸のガラスが割れる音、
扉が激しく閉まる音、
自分の部屋がなかったぼくは、他に行き場もなく、居間の隅でその様子をじっと見ていた。
「またはじまった」
「いつおわる?」
「うるさい」
「うるさい…」
母、祖父、祖母がどんな様子だろうと、家がどんな状態だろうと、父は自分の氣がおさまるまでは、決して怒鳴ることをやめなかった。
喧嘩の原因はなんだったのか、家族の会話の内容は覚えていない。
ただ、騒がしい日常が、ぼくの記憶には残っている。
父は、ぼくが8歳の頃に病気で死んだ。
授業中、父が危篤との連絡を受け、親戚の車で病院へ向かった。
ベッドの上の父の、弱々しい手を握ったのを覚えている。
少しの悲しさも感じなかったのを覚えている。
最期を見取ったとき、安堵の氣持ちが込み上げてきたのを、はっきりと覚えている。
父が嫌いだったわけじゃない。
父はぼくに愛を注いでくれなかったわけじゃなかった。
男二人で出かけたことも何度かある。
ぼくを楽しませようとしてくれた父の姿も、記憶に残っている。
ただ、ぼくは父のことを微塵も好きではなかった。
それほど、父に苦痛を感じていたのだろう。
母も祖母も祖父も大好きだった。
でも、父にだけは、好きという感情を抱けなかった。
大人になってから氣づいたのだが、ぼくはゲームセンターが大嫌いで、本屋と図書館が大好きだ。

大阪個展のクラウドファンディングページの編集は、ぼくにとっても地獄だった。
点描画家hiromiの過去は、ぼくの記憶を容赦なく掘り返してきた。
彼女の壮絶な過去の話を、受け止め、噛み砕き、伝わりやすいよう記事にまとめる。
聴くだけでも心が軋むほど苦しいのに、加えて、幼少期のぼくの記憶も反応してしまう。
彼女の話に、ぼくの過去がリンクする。
怒鳴る父、母の泣き顔、皿やガラスが割れる音。
吐き出す彼女がいちばん辛いのは重々承知。
だが、聴く方も大概だ。
彼女の苦痛に比べたら、ぼくが味わった苦痛なんてちっぽけなものだろう。
それでも、同じ人間。
ChatGPTのような文章生成AIではない。
話を聴くたび、文字に起こすたび、どうしても心がざわつく。
苦しかった。
とても苦しかった。
早く終えてしまいたかったが、本文の編集は1日では終わらない。
彼女の話を文におこし、齟齬がないか確認する。
話を深ぼった方がいい箇所、情報が不足に感じる箇所があれば、また追加で細かい話を聴く。
彼女が編集した文を、ぼくがまた編集する。
そんなやりとりが2ヶ月も続いた。
話を聴くたび、文字にするたび、やりとりを交わすたび、ぼくの心は疲弊していった。
氣がつけば、毎週の打ち合わせがすっかり億劫になっていた。

できることなら手を離したい。
点描画家hiromiのサポートから身を引きたい。
そう思っていた。
それほどまでに、彼女の過去はぼくを追い詰めていた。
彼女はぼくと似ているところが多い。
彼女が感じること、思うこと、苦しみ、痛み、
話を聴くたびに、他の人よりも強く共感できる。
だからぼくも、彼女の前ではつい口を開いてしまう。
感じたこと、思ったこと、苦しかったこと、痛かったこと、
父のことも、誰かに話したのは彼女が初めてだった。
ぼくは彼女に近づきすぎたのかもしれない。
近すぎるから、彼女の苦しみも、人一倍強く感じてしまう。
彼女に関わらなければ、耳を傾けなれば、歩み寄らなければ、こんなにも苦しむことはなかった。
彼女と出逢わなければ、こんなにも感情を揺さぶられることはなく、ぼくは今頃、自分の作品づくりに集中していた。
そんなことを考えながら、クラウドファンディングの本文が完成する頃には、
ぼくは、もう点描画家hiromiには関わりたくないと思っていた。

クラウドファンディングページの制作が終わったあとも、彼女のお手伝いは続くはずだった。
次は、個展に向けての準備を…、
けれどぼくは、お手伝いから手を離した。
自分の時間が欲しいことを言い訳に。
辛かった。
これ以上、心をざわつかせたくなかった。
彼女と連絡を取ることも、次第に億劫になっていった。
このまま彼女のサポートを降りようか…。
そんなことを考えてしまうほど、彼女との距離間に悩んでいた。
前年の渋谷個展が終わった後。
『しんこきゅう展 in zakura』に感極まったぼくは、彼女に「次の個展も全力で支える」と約束していた。
にも関わらず、ぼくはその約束を、破ろうとしていた。
月日は、大阪個展に向かって進んでいく。
ぼくは彼女を、無意識のうちに遠ざけていた。
彼女がどんなふうに個展の準備を進めているのかも、個展に向けてどう動いているのかも、
連絡は度々来ていたのに、一切頭に入っていなかった。
個展まであと1ヶ月と迫った9月。
氣がつけば、彼女の周りにはたくさんの応援者さんがいた。
渋谷個展のときより遥かに多い数の、ものすごい熱量で応援してくれる人たち…。
本当に知らぬ間に、彼女はぼくの見知らぬたくさんの人に囲まれていた。
彼女はたくさん動いていたのだ。
この数ヶ月、幾つもの人の集まる場に、足を運んでいたのだ。
赴いた場所、出逢った人、
彼女からの連絡を遡ると、確かに連絡は来ていたのに、ぼくはそんなこと、知る由もなかった。
たくさんの人に応援される彼女を見て思った。
もう、ぼくは必要ない。
熱烈に応援してくれる人が、今はたくさんいる。
指示をしなくても動いてくれるような人たちがたくさん。
よかったじゃないか。
これでぼくも、心置きなく離れられる。
きっと、ぼくより上手に彼女をサポートできる人はいる。
彼女の想いを記事にまとめて、諸々の画像データも作って、写真も撮って、
あれだけの応援者さんがいればきっと、ぼくの代わりは誰かしらに務まるだろう。
なんてことを、本氣で思っていた。
ぼくは本当に、彼女のサポートを降りようとしていた。
渋谷個展、4日目。
ぼくはわけもわからず号泣した。
お客さんが抜けて、いっとき静かになったタイミング。
ずっと堪えていたものが溢れてきた。
渋谷個展は、スタッフとして全日お手伝いをしていた。
意図したわけではなかったが、成り行きで、7日間ある個展を、7日間お手伝いすることに。
あのときは、点描画家hiromiの「しんこきゅう展」を、誰よりも近くで感じていたと思う。
個展1日目から、ぼくの心はなにかをひたすらに感じていた。
その“なにか”は、自分でもよくわからなかったが、
今まで感じたことの無い、正体不明の感情を、ひたすらに感じていた。
壁に飾られた作品を見て、配置された装飾や小物を見て、空間の静けさに耳を澄ませて、
お客さんのあたたかさに触れて、彼女のあたたかさに触れて、あたたかい言葉が飛び交う空間を感じて、
ぼくの心に、なにかが溜まっていった。
溜まっていったなにかが、4日目に溢れてしまった。
なぜ涙が出るのか、自分でもわからなかった。
堪えられなかった。堪えたくもなかった。
ぼくはひたすらに、心の内に溜まった“なにか”を、止めどなく流し続けた。

10月のアタマ、
大阪個展に向けてカメラを買った。
Canonの EOS RPという機種。
大阪個展の期間中、ぼくは彼女にカメラマンを努めるようお願いされていた。
渋谷個展のとき同様、個展の様子を収めた写真集を作りたいのだと。
出逢った頃から、彼女はぼくの撮る写真を氣に入ってくれている。
写真の勉強をしたことも、努力をしたこともない、iPhoneで撮るぼくの写真を、なぜか氣に入ってくれていた。
前年の渋谷個展でも、ぼくが好き勝手に撮った写真を使って、写真集を作ってくれた。
大阪個展では、iPhoneではなく、ちゃんとしたカメラで撮ってほしいとのことだったのだが、
ぼくはずっと、カメラを買うのを拒んでいた。
ここでカメラを買ってしまったら、ぼくは正式に、彼女のカメラマンになってしまう氣がしていた。
この先もずっと、彼女の活動から離れられない氣がしていた。
その打ち合わせは、増上寺近くのBARで。
ぼくは、撮影は前回の個展同様、iPhoneで十分だと主張する。
ちゃんとしたカメラの方が、画質がいいことは分かりきっているはずなのに…。
最近のiPhoneは画質も上がっているし、などと、それっぽい言い回しで、カメラの購入を回避しようとしていた。
そんな、フワついたぼくの主張を、彼女は真っ直ぐに断ってくる。
「大阪個展の写真集は、画質のいい写真で作りたい」
「紙に印刷しても綺麗な写りになるように」
何度やんわり断っても、「でも、」、「でも、」と真っ直ぐに。
おそらく彼女も、ぼくの熱量が以前と違うことに氣づいていた。
氣づいていながらも、彼女はぼくから目を逸らしてくれない。
「約束してくれたから」
何かの折に、彼女はそう溢した。
渋谷個展のあとにぼくがした約束を、彼女は忘れていなかった。
敵わない。
彼女はいつだって真っ直ぐだ。
いつだって真っ直ぐな目で、ぼくのことを見つめてくる。
ぼくはそんなに、綺麗な人間じゃないのに。
ぼくはカメラを買った。
まだ、心の迷いが消えないまま、
ぼくは購入したカメラを片手に、大阪個展へ向かうための、迎えの車に乗り込んだ。
一体何時間カメラを回していただろうか。
個展前日の朝、
一定のリズムで揺れる車は、東名高速道路を走行しながら、大阪府にある個展会場へ向かっていた。
プロデューサー佐野翔平が運転するハイエースの助手席には点描画家hiromi。
二人は他愛もない話を繰り返す。
ぼくは後部座席で、ひたすらに映像を撮っていた。
スマホのカメラに時折映り込む太陽が眩しい。
今回ぼくは、個展の写真集制作と一緒に、映像制作も任されていた。
どの場面を撮ろうか、ある程度は固まっていた。
頭の中にある映像作品を再現するために、車内での画が必要だった。
だからと言って、10秒程度の素材のために、カメラを数時間も回す必要は全くない。
助手席にいる彼女に、話しかける言葉が見つからないだけだった。

会場となる古民家のレンタルスペース「la galerie(ラ・がルリ)」へは、予定より少し遅れて到着した。
会場には既に、搬入をお手伝いするスタッフが待っていた。
搬入スタッフは全員で3名。いずれも彼女とは面識があったようだが、やっぱりぼくには誰一人わからない。
スタッフたちと挨拶を交わす彼女は、いつものように朗らかな空気感を放ちつつも、どこかピリついていた。
表情が少し硬い。
念願の大阪個展だ。緊迫するのも無理はない。
けど、彼女らしくない。
車から「しんこきゅう展」の荷物を運び出す。
空っぽの la galerie(ラ・がルリ) に、着々としんこきゅう展が運ばれる。
設営の準備が整うと、彼女はすぐさま作業にとりかかった。
「飾り方はその紙に書いてあるから」と、誰に向けて言ったかわからない言葉をふわっと放つ。
やっぱりどこか、様子がおかしい。
積まれた荷の上には、A4サイズのメモ用紙。確かに、何をどこに飾るかは書いてある。
彼女はすでに、みんなに背を向け、長押の頭に釘を打ちつけ始めていた。
少し戸惑った様子のスタッフたち。
それとなく、各々作業に取り掛かろうとするも、何をどうしていいかわからない様子。
それはそうだ。彼らは設営のプロ集団ではないのだから。
胸が痛い。
「どうやって飾ればいい?」とぼくが聞くも、「その紙に書いてあるから」とまた放ち、黙々と作業をする。
ヒリヒリとした空気を感じる。
これ以上は踏み込めなかった。
彼女の様子がいつもと違うことは察しつつも、彼女との距離感に戸惑っていたぼくは、うまく接することができずにいた。
普段の様子とはまるで違う。
けれど、彼女は彼女で、いっぱいいっぱいなのだろう。
明日から始まるのは、念願の大阪個展だ。
たくさんの人から応援されて、新聞にも取り上げられて、期待がかかった、前回とは比にならない規模の個展だ。
それにしたって、開始の挨拶くらいはしたほうがいいんじゃないか?
段取りを把握したほうが勧めやすいし、何より、スタッフさん同士の間にある緊張も、少しはほぐれるだろう。
ぼくが一旦この場を仕切ろうか。
いやでも、ここは彼女の場だ。
ぼくが出しゃばる場面じゃない。
こんなとき、スパッと物事を言える人でありたい…。
そんなことを思いながら、これ以上彼女に近づけないぼくは、スタッフお一人お一人に、それとなく話かけて回った。

順調に、「しんこきゅう展」の会場が作られていった。
スタッフさん同士もうまく役割を分担し、作業を進めている。
彼女にも余裕が出てきたのか、場内からは徐々に、朗らかな会話が飛び交うようになっていった。
よかった。
ぼくはホッとしながら、設営の手を離れてカメラを回す、シャッターを切る。
「しんこきゅう展」が段々とつくられていくと、思い出してきた。
懐かしい。
そういえば、去年もこんな感覚だった。
目に映るもの聴こえるもの、全てから彼女を感じる感覚。
渋谷個展のときに味わった、いや、それ以上の、とても繊細で、優しい感覚。
壁からプラグが見えるのが嫌だからと、被せるように飾ったお花のボンボン。
仲間たちのことを想って作ったという、アイコンがたくさんついたお祝いのリース。
作品はもちろん、用意したグッズや小物ももちろん、
今回もまた、作り上げた空間は点描画家hiromiそのものだった。
細部の細部の細部までのこだわり。
想いの込もった装飾。
外から溢れる光があたたかい。緑が揺れる音が心地いい。
古民家独特の古びた匂いが、肺の奥まで入ってくる。
設営が終わり、みんなが外で談笑している隙に、
ぼくは、静かな la galerie で、まだ始まる前のしんこきゅう展を、ひとり感じていた。

そうだった。

ぼくはこれに魅了されたのだ。






前年の11月、渋谷個展で感じていた。
この落ち着いた空間に、優しい空間に、
たくさん傷ついてきたであろう、心あたたかい人たちが集まって、誰も傷つくことのない言葉だけが飛び交って、
どうしようもなく込み上げてくるあの、
寂しくもあたたかい感情に、
どうしようもなく包み込まれたのだ。
渋谷個展のお手伝い4日目、突然涙が止まらなくなったのは、「しんこきゅう展」が、ぼくの探し求めていた場所だったからだと氣づく。
ぼくは多分、無意識にずっと探していた。
ゲームは好きなのにゲームセンターが嫌いで、本を読まないのに本屋が好き。
そんなこと、今までの人生で、これっぽっちも氣にかけたことはなかったけど、ただの、ちょっとした好みの問題だと思っていたけど、
おそらくずっと、心の内側で探していた。
幼い頃、父が母を怒鳴りつける姿に胸を痛めたあの時から、きっと、ずっと、
波風が立たない、平穏な、
誰かを罵倒するようなうるさい人も、それによって傷つく人もいない、
ひたすらに心落ち着く、
そんな空間を。
「しんこきゅう展」は、幼い頃にぼくが求めた“やすらぎ”そのものだったのだ。
渋谷個展で、とめどない涙を流し続けていたのは、幼い頃のぼくだった。

やっぱりぼくは、点描画家hiromiが大好きだ。
彼女の思いやり溢れる心と、彼女の作り出すあたたかい世界が大好きだ。
離れようとしていたぼくが間違ってた。
辛いとか苦しいとか、そんなことは重要じゃなかった。
大切なのは、“彼女がぼくに何を与えてくれたか”だった。
彼女はぼくに、あたたかい感情をたくさんくれた。
心の内にいる自分に氣づかせてくれた。
こぼれないよう、必死に抱えていた孤独をほどいてくれた。
ちゃんと傷ついていいということを教えてくれた。
自分に素直でいいことに、氣づかせてくれた。
人生を変えてくれた。
辛いけど、辛いをまるごと包み込むほどの、幼少期から受けてきた傷をまるごと包み込むほどの、大きくあたたかいものを与えてくれた。
これだけのものを与えてくれる存在に、ぼくの短い生涯のうちで、他に出逢うことができるだろうか。
翌朝、ぼくの心は晴れやかだった。
あれだけ距離感に戸惑っていた自分が嘘のように、彼女に氣軽に挨拶を交わした。
もう大丈夫。
改めて「しんこきゅう展」が好きだと認識したぼくに、迷いはなかった。
初日から夢中でカメラを回した。シャッターを切った。
心動く瞬間を捕まえようと、慣れない手で追い求めた。
やっぱりそうだ。
渋谷個展のときと同じか、それ以上に、
ほんの些細なことで心が動く。
彼女の元に集まる人はいつだって優しい。
彼女の作り出す空間が彼女自身なら、そこに集まる人たちもまた彼女自身。
静寂な空間に訪れるあたたかい瞬間に、涙が溢れそうになる。
足の悪そうなお客様にすかさず椅子を持っていくスタッフに、
苦しかった過去を語るお客様に、
点描画家としての活動を始めた経緯を、涙ながらに話す彼女に。
外から差し込むあたたかい光、
木造の床が軋む音、
作品をじっくりと見つめるお客様の目、
品物を受け渡すスタッフの手、受け取るお客様の手、
場内で交わされるあたたかい言葉の数々、
ぼくは終始、涙を堪えていた。
だって、渋谷個展さながら、全てがあたたかいのだもの。
けれど、今回は泣くわけにはいかなかった。
ぼくの手にはカメラがある。映像を撮ってる。
個展の様子をまとめた動画を作ることを、彼女から任されている。
ぼくの泣き声が入って、せっかくの素敵な映像が使えなくなったら台無しだ。
そう思っていたのだけれど、
どうしても涙を堪えられない瞬間があった。
お客様のお誕生日をお祝いしたとき。
花束を持ってきてくださった女性は、その日がお誕生日だった。
女性がそのことを口にするや否や、彼女は「みんなでお祝いしましょう」と、会場にいる人に呼びかけた。
一切の迷いもなく、あたかもそうすることが、世間一般の常識であるかのように。
会場いる人たちも、彼女の提案を素直に飲み込んでくれる。
すぐさまその場にいる全員で、女性のためのバースデーソングの合唱が始まった。
こんなにあたたかい世界が、この世にあるのか。
そう思ってしまったら、ぼくはもうダメだった。
映像を撮っている最中なのに、思ってしまったがために、堪えていたものが溢れ出す。
なんでそう躊躇なく、他人の心に入っていける?
こっちはしきりに、相手との距離を氣にしているのに。
彼女はいつだってそうだ。
こっちの戸惑いなんか氣にもせず、素直に氣持ちを表してくる。
壁を作ってる自分が阿呆らしい。
ぼくが氣にしすぎてるだけなのか。
人間もっと、単純でいいのだろうか。
孤独と幼ななじみのぼくのような人間には、彼女は少し眩しすぎる。
お祝いが終わり、涙する女性のお客様に、そっとハグする彼女。
ぼくはカメラを回しながら、溢れる涙は仕方なしに、音を漏らすまいと必死だった。

3日間の個展が終わり、4日目の深夜に帰宅した。
真っ暗な部屋の明かりをつけ、荷物を軽く整理する。
氣づけてよかったと思う。
彼女が、自分に辛さを与えるだけの存在でないことに。
近づくと痛いぶん、とてもあたたかいことに。
自分を傷つける存在が、必ずしも危険なわけじゃない。
むしろ、そんな人が自分にとってかけがえのない存在、なんてこともある。
辛さのあまり目を背けた相手は、探し求めていたものを届けてくれた相手だった。
いちばん離れたいと思った人は、いちばん居たい場所をつくってくれる人だった。
氣づけて、本当によかった。
人間社会は騒がしい。
いつだって、誰かが誰かを傷つけてる。
どうしてこうも、人は騒がしいものか。
もっと平和でいられないものか。
なんて綺麗ごと、ぼくに言う資格はないのだけれど。
ぼくだって、誰かを傷つけてきたのだから。
それでもやっぱり、ほんの少し、わずかな時間でも、心穏やかに過ごしたい。
あの頃のぼくが、心の内側でそう言ってる。
もう、彼女から目を背けたりしない。
「しんこきゅう展」は、やっぱりぼくに必要だ。
幼い頃のぼくが癒される、唯一の場所。
ぼくだって、それなりに傷を受けてきた人間だもの。
求めたい場所くらいある。
どうなろうと、点描画家hiromiの活動を支えていこう。
翌朝、壁にかけられた「新緑と花たち」を、布団の上から見つめながら、
そう固く心に誓った。

最後まで読んでくださってありがとうございました。
この投稿は、ひろみさんにお願いされて書きました。
大阪個展を通して、いろいろ感じてはいましたが、こんな感情、無論どこにも出す予定はなく(笑)。
けど、お願いされたし、書くからには出し切りたいと思い、振り絞って書きました。
アホみたいに恥ずかしいです(笑)。
ぼくは自分のことをよく語りません。受けたこと、感じたことは、基本胸にしまったまま。
傷つけられても、反抗することもなく、かと言って、誰に愚痴を吐くわけでもなく。
ずっと、溜め込んで生きてきました。
時間が経てば忘れるだろう。
そう思っていたのですが、
今回、ひろみさんに触れて思ったのは、“受けた傷はしっかり残っている”ということでした。
忘れたつもりでも、忘れてない。
一度心についた傷は残っていて、どんなに時間が経っても消えないのだなと、
流した涙が教えてくれました。
大阪個展を終えてからまた、突然涙を流すことが増えました。
過去に通ずるものに触れたとき、記憶が突然湧き上がってきて、思わず…、なんてことが。
幼少の頃だけじゃない、その後もたくさん傷ついてきたことを自覚します。
そして、ぼくはそれをずっと我慢してきたことに氣づきます。
決して、平氣だったわけじゃないのだなと。
どうもぼくは、自分を大切にしない癖があって、周りを優先してしまいます。
誰かが傷つくことになるから、自分が受ければいいと思ってしまいます。
父に苦しめられる母の顔を見るのが、よっぽど辛かったのでしょう。
あの頃は、母が世界でいちばん好きだったので。
認めてあげてもいいのだと思いました。
傷ついてきたことを、しっかりと。
感情を抑えないことで、自分が求めているものに氣付くことができるから。
自分の氣持ちに素直になって、自分にとって心地のいい場所を、求めればいいのだなと思いました。
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。
石井嘉一郎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
