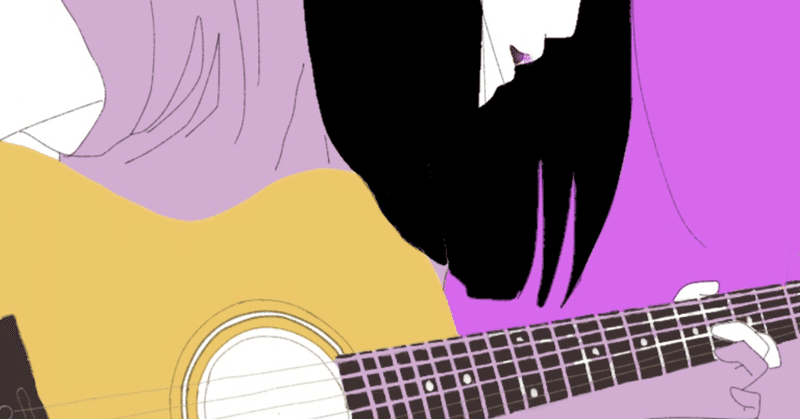
楽器が上手い!と言われるための方法・アコギ歌伴編
わたくし、楽器の指導と演奏を生業にしております。
主に鍵盤。次いでウクレレ、アコースティックギター。
依頼があればDJも。
演奏に類することはこんなところです。
不思議なことに、アコースティックギターをよく褒められます。
(笑)とか付けません。本当に褒められるから。
ギターの師である小林涼さん(近藤真彦・チューリップ・本田美奈子等々サポート)からも「カイくんはギターでも仕事できる」とお墨付きをいただいているものの、自身のギターの実力に関しては懐疑的でした。涼さんはなぜ俺のギターにOKを出しているのか・・・
鍵盤弾く現場に行って、ちらっとアコギ弾くと「なんでこんなに弾けるんですか?カイさん鍵盤の人ですよね?」みたいに言ってもらえたことが、一度や二度じゃないんです。嘘みたいにアコギうまいうまい言ってもらえる。嬉しいんですが、同時に、何がいいのかよくわかってなかったんで、自分で考えて分析することにしました。分析と言いながら単なるダメ出しになってます。気を悪くする人続出、嫌われること請け合いの「楽器が上手いと言われる方法・アコギ歌伴編」スタートです。
リズムがきちんと取れる

ミュージシャンとして基本中の基本で、こんなことを書くと「そんなの俺だって取れるわ」と言われそうですよね。
普段、生徒さんには「曲の中に2種類のリズムがある」とお伝えしています。
1つは曲全体の基幹となるリズム。4/4とか6/8とかそういうやつ。
もう1つはメロディとかフレーズの譜割。
この2つが密接に絡み合って曲に、歌になっています。
このどちらか、もしくは両方の理解が甘い人が多すぎる、と思っています。
4/4を8分音符に分解してみてください。4拍目の裏に当たる、8個目の8分音符、しっかり取れてない人が目立ちます。そこで突っ込んだりモタったりして、曲全体のリズムが揺れます。これを読んだあなたは「その揺れもグルーヴだよ、わかんねぇのか?お前機械か?」と笑うでしょうか。
揺れてる伴奏に歌がしっかり乗れますか?リズムが行ったり来たりする伴奏が、果たしてかっこいいですか?伴奏なんて、気にされないくらいでちょうどいいのに、「バックのギターが揺れてるよね」なんて指摘されるの、恥ずかしくないですか?歌伴の仕事をしてきた身としては恥ずかしいです。
もう一個。メロディの譜割が取れてないせいで、伴奏がめちゃくちゃになってる演奏をよく聞きます。8分弾きでも4分弾きでも、ガチャガチャしてるんですよ。メロディに合った伴奏を、なんていうと抽象的ですが、それをできてない人があまりにも多いです。正確なメロディを理解できなければいい伴奏はできません。「自分の歌が歌える伴奏ならいい」っていう方も多いでしょう。別にそう思う方はそれでいいです。目標がその程度の人にわかってもらおうとは思っていません。
あえてアレンジチックに、ゆったりした曲を細かい譜割で弾く(もしくはその逆)方もいらっしゃいますが、「基本ができた上」でやるなら別にいいと思います。正確でグルーヴィなら。
ちなみにリズムの取り方は、人によって癖があります。
大きく分けて「前目(ツッコむ)」「ど真ん中(ジャスト)」「後ろ目(モタる)」です。これらは癖なので悪いことではないんです。自分の癖を理解した上で、「前、真ん中、後ろ」をそれぞれ狙って弾けるようになればいいんです。バンド演奏だと「この曲はみんなツッコミ気味に演奏してね」とか指示が出たりします。また、ツッコミ気味の人とモタり気味の人の演奏が混ざって面白いグルーヴになることもあるので、先にも書いた通りクセ=悪いことではないです。ただ、弾き語り完結の人も自分の演奏タイプは理解しておくべきでしょう。後に書く「テンポを守る」ことにつながります。
弦のバランス
ギターなら6本、弦の太さは全部違います。
6本バランス良く音が鳴るのが理想です。大抵の方は、低い方が大きいか高い方が大きいかに偏っています。
エレキから入った方なんかは、上下3本ずつを分けて弾く癖がついてるから、6本バランスよく弾くことに苦心されている話をよく聞きます。って、こういうふうになんとかしようと思ってる方はいいのですが、やっぱりリズムと一緒で「これでいい」と考えてる方が多いのが実情です。
例えば5、6弦は太いですよね。ちょっと触れば音が出ます。
一方1、2弦は細く、しっかりピッキングしてあげないと音が鳴りません。
この構造を考えたピッキングができないと、低音弦ばかりがガキンと鳴ってしまいます。逆に高音弦に力が入りまくってキンキンな音になってしまう方もいます。
ピックで弾くならピックの先にしっかりと神経を持っていきましょう。
自己分析した結果を自画自賛しますが、僕は6弦と1弦で、ピックの当たる面積を変えています。というか、変わるようなピッキングをしています。僕ができるんだから、気を遣えば誰でもできることだと思いますので詳細は伏せます。ちなみに生徒さんにはちゃんとやり方を教えています。
ウクレレの指弾きも一緒です。
Low-Gにしてる方はギターと全く同じ原理が使えます。
High-Gの場合は・・・力を入れるポイントを少し変えている程度で、基本的には一緒です。4弦が低音ではありませんが、ギターと同じ原理でやっても大丈夫です。
綺麗な音を出そう
これまた大雑把な見出しですが、綺麗な音であることは大事です。
リスナーさんが気になるようなノイズの混じった演奏はよろしくない。
ここもまた「フレットノイズも味だ」とか「押さえた時のキュッて感じがギターじゃん」とかいう勢力に負けそうですが、あえて解説を進めます。
そんな音が気になるような伴奏はいい伴奏じゃないんです。
「フレットノイズしてたよね」「弦押さえる時キュッてしてたよね」などと指摘されるような伴奏は、歌の邪魔になっています。だってその部分の歌が聴かれてないんですよ。楽器が発生させてるノイズに耳を取られている時点で負けです。
フレットを押さえる原理を、こんなもん知らなくてもいいと思われるのを承知で書きます。
弦を指板にくっつけて演奏してると考える方が多いのですが、それはフレットレスの場合です。ギターやウクレレの大多数のようなフレットボードタイプの弦楽器は、フレットに弦を引っ掛けて音程を作り、それをピッキングして音が出ます。構造上弦をいくら力一杯押さえても指板には到達しません。到達してしまった場合はフレットの減りがすごいことになってるのですぐリペアに出して打ち直しましょう。
だからこそフレットの近く、真横くらいで押弦するんですね。
この原理を知ってると綺麗な音が狙って出せます。すぐに出なくても、ポイントを抑えて練習すれば出せるようになりますので、フレットの真横を意識して押さえてみてください。余計な力がかからないから、お客様が気になるようなフレットノイズもコード押さえる時のキュッキュッも減って、さらに歌が立ちます。
また、指板を押さえる指の位置・角度も徹底的に研究することもお勧めします。人によって手・指の形、大きさ、指の長さ、骨格、皮膚の厚さの分布など違いますので、自分なりの一番音が出る位置を知ることは大切です。講師としてはいくつか実例を提案することはできますが、最後は生徒さんの探究心に賭けています。確率の高いポイントをいくつか示すことはできても、最終的にどの位置・どの角度がいいのかは演奏する人のおてての構造で変わってきます。
レッスンでのエピソードを紹介します。
あるレッスンで、生徒さんとアコースティックギターを弾いていました。
僕は国産の、比較的お安いギターを使用しています。
生徒さんには、教室備え付けの高級輸入ギターをお渡ししてレッスンをしました。
生徒さんからレッスン中に「先生のギターはなんでいい音なんですか?ずるいです。私のと交換してください💢」と、怒りマークをつけるレベルでキレられてしまい、交換したんです。
数個のコードを弾いた10秒後、生徒さんから「私が間違ってました。腕の問題なんですね」とあっさり白旗が上げられました。
そのくらい「手と指」は重要なんです。
もちろん高級な楽器を買って「この楽器に見合う実力になろう」という目標を持って練習するのも一つのやり方です。しかしながら安価な楽器でも、自分の手と指で楽器を自由自在に操れるようになるまで練習することだって、悪いことじゃないと思います。
ダイナミクスを理解しよう

ダイナミクス。
なんだそれ。プリンミクス(古い)の仲間か?
違います。曲の中の音量差です。強い弱い、大きい小さい。
ダイナミクスをつける、と言います。
弾き語りの人に多いのが、頭から終わりまで全部同じ強さ。
速い曲なら歌も楽器も全部フォルテ。遅い曲なら全部ピアニシモ。
そういうこっちゃない。
すっごい基本的な、音楽の一般論をお伝えします。
「同じメロディが2回出てくる時、1回目より2回目を大きく演奏する」
です。あくまで一般論です。基本のキです。例外も山ほどあります。
例えば歌の1番と2番が全く同じメロディー構成の歌だとします。童謡とか唱歌がわかりやすいかな。こういう曲の場合、1番より2番を強く大きく歌う・弾くということです。
ポップスでも、Aメロが「8小節で同じメロディ、コード進行」を2回繰り返す場合、1回目より2回目を強く大きく行きましょう、ということですね。もちろん、全部がその限りではありませんが、一般論・基本としてはこういう考え方です。多分小学校の音楽の授業なんかでも触れる事柄です。
と、ここまで書いただけでも、1曲の中に音量差が発生することがわかると思います。これをもっと追求していくと、曲の中に山と谷ができていきます。で、この山と谷を繋げるために「だんだん強く」「だんだん弱く」という歌・演奏も必要になってきます。もちろん唐突に山や谷が現れるケースがあるのは音楽も人生も同じです。
弱く・小さく・優しくという表現をするために白玉系(全音符や2分音符)を使用したセクションを曲の中に作る人を散見しますが、その音符も「ガキーン!」と強く弾いていたらガチャガチャ弾いてるのと変わりません。伴奏だけ白玉、歌は強さがそのまんま、なんてのはダイナミクスを付けてるつもりかもしれませんが、全然付いてないです。
別に楽譜を読める必要はないです。
コピー・カバーしたい曲をよく聴いて、どんなふうになってるか確認して実行すればいいだけの簡単なお仕事です。ご自身のオリジナル曲なら、どこをどうしたいかよーく考える、参考にした曲や今まで自分が聴いてきた曲からアイデアをもらう、などなどできることはいっぱいあります。
こと歌伴においては、速く複雑なフレーズが弾けることより、強弱を押さえた正確な演奏ができることの方がずーっと大切です。テンションがバキバキに入ってリズムが複雑、フレーズはかっこいいけど荒くて強弱のないバッキングより、4分音符4つの、歌を邪魔しない、リズムが正確で音量が適切な伴奏の方が断然歌いやすいのは言うまでもありません。
テンポを守る努力を怠らない
はいこれ。リズムとも関係あるんですが、分けました。
いわゆる「走る」「もたる」です。
リズムが取れていない故に起きる現象でもありますが、ナチュラルにどんどん速くなっちゃう人、遅くなっちゃう人がいます。とはいえクリックでも鳴らしていない限り、本当に正確な演奏は無理です。すごくリズム感とタイム感が優れている指揮者でも曲中で揺れることはあります。これはもう仕方ないことです。それでも「味」「グルーヴ」と呼べる範囲を逸脱したテンポのズレ方をしていく人がよくいます。
いろんな人の歌や演奏を聴いてみましたが、伴奏が走っていってしまい、それについていくため歌もどんどん速くなっていく人、それについていけなくて伴奏と歌が離れていく人、なんていうパターンが見受けられます。
悪いこと言わないからメトロノームとかリズムマシンで練習しましょう。
打ち込みのできる人なら、ベースとドラムだけ作ってその上に乗っかれるように練習してみましょう。最近はiPhoneで安価なアプリもあります。無料のGarageBandを使えば簡単なバッキングなんてすぐ作れます。楽器は上手くなるしDTMへの理解も深まるし一石二鳥です。
リズムのセクションで書いた「4/4の4拍目のウラの8分音符」の話がありますが、4拍目に限らず裏拍がしっかり取れていれば、スタート時のテンポから大きく変わることはないと思います。「テンポを守れ」というのは絶対ズレるなってことではなくて「できる限りスタートのテンポから逸脱しないようにね」っていうことです。
とにかく歌を聴け。
歌を聴くこと。人様の伴奏をするときも、自身の弾き語りだろうと同じです。歌の伴奏なんです。歌が聴こえないことにはどうにもなりません。
自分の演奏で歌が聴こえないなんてことはあってはならないです。
先にも書きましたが歌のメロディーを理解していないと伴奏はできません。
譜割も強弱もそうです。また、どこでブレスをしているのか、伸ばす音はどれだけ伸ばしているのか、などなど、歌ってる人の身になって考えて弾くことが大切です。
歌モノをやる以上、歌が聴こえることを最優先しなければなりません。
歌い手の音量に合わせて演奏の音量を調整するとか、言われなくても対応しなけりゃならないんです。歌伴の仕事で「俺の音を聴け」とばかりに大音量で弾いていたら、当然次の仕事はありません。
弾き語りでもそうです。
歌が聴こえなかったら歌モノやる意義がないじゃないですか。
伴奏なら、歌い手の背中をよく見てあげてください。顔が見えなくても、ブレスする時の体の動き、ダイナミクスをコントロールしようとする様子など、絶対伝わってきます。顔が見える位置で演奏するなら、アイコンタクトも大切でしょう。
弾き語りなら、自身の歌をどのようにするか、事前に考えなくても対応できるならしっかり自分の中の「ボーカリスト」を見てあげてください。できないうちは、ある程度歌をどうするか、構成を考えてから入ってもいいのではないでしょうか。考えもなしにのっぺりした歌を歌うより、展開を考えて歌の中にドラマを作ってあげる方が経験値が上がると僕は踏んでいます。
演奏レベル向上も大切
と、いろいろ偉そうに並べ立てましたが、「誰でもできること」しか書いていないつもりです。
ちょー速いソロが弾ける!
複雑なリズムに対応できる!
アドリブが30分弾ける!
なんてのは、あって邪魔になりませんが、僕はどれひとつ持っていません。
それでも歌の伴奏で、ありがたいことにお金をいただいています。
クルーズ船のバンドに参加することもできました。企業イベントでさいたまスーパーアリーナの大きなステージに立つこともできました。著名な方と共演させていただくこともありました。大舞台で活躍する方のお手伝いをすることもできました。
僕にできることが、ここに書いた6項目です。
裏を返せば、これができるとある程度プロとしての演奏はできるということです。もちろん仕事のもらい方とか、人付き合いとかの上にプロ活動は成り立つので楽器がうまい・歌が上手いそれだけでプロになれるわけではありませんが、それでも仕事させてもらえるくらいの演奏力は担保されています。
弾き語りの人への苦言、みたいになりそうでまあ怖いっちゃ怖いんですが、あえて書きます。
「歌の伴奏だからこの程度でいい」なんて気持ちで楽器を弾いてたら上手くなりません。その楽器で、バンドのメンバーになれるようなレベルを目指してほしい。「俺はボーカリストだから楽器はこんなもんでいいや」ではなく、演奏レベルの向上を常に忘れないでもらえたら、きっと少しずつ見える世界が変わってきます。
終わり!
と、自分のできること、やっていることを言語化してみました。
そりゃーこんだけ言語化できれば講師もやれるか、となんとなく自分の実力に安心している節もあります。一方で、言語化しすぎてやいのやいの言われそうだなーなんて思ったりもしています。
以上、楽器が上手いと言われる方法・アコギ歌伴編をお送りしました。スキもコメントも、怖いからやめてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
