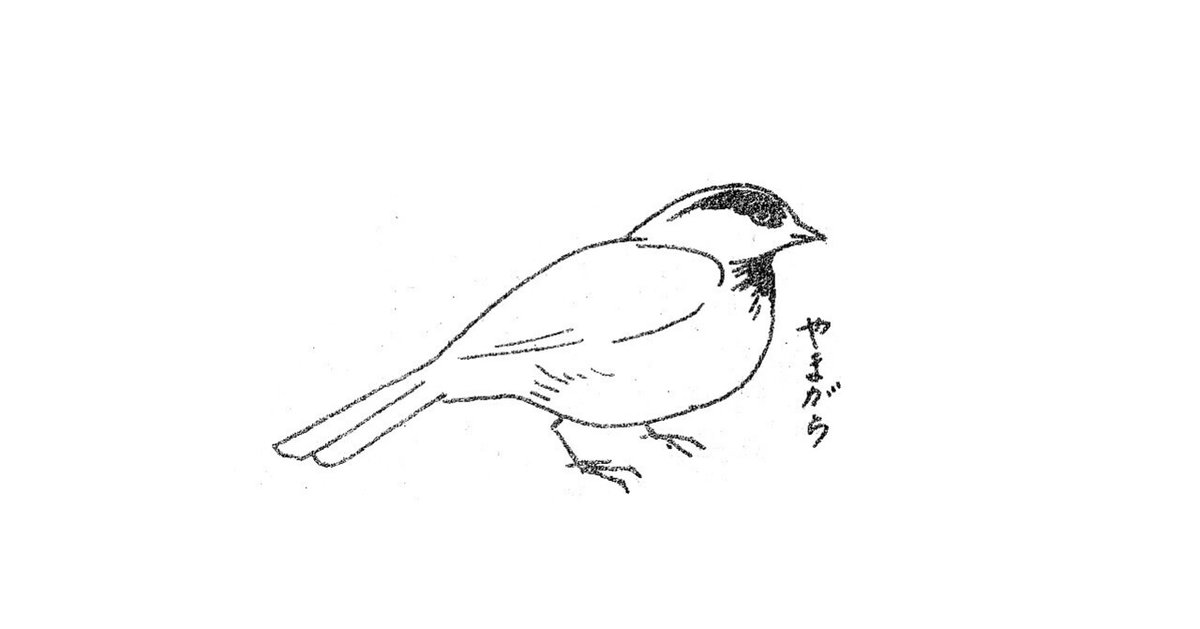
ヤマガ
「彼女はときどき、ヤマガの家に空き巣に入るようになるの」
最初は、友達の話でも始まったのかと思った。ベッドの上に、裸のシルエットが映し出されている。シルエットが語りに合わせて微かに息づいているところを見ると、どうやら彼女が語り手らしい。ベッドで物語られているのだとしたら、あるいは夢で見た話なのだろうか。それにしては妙だ。夢の中の見知らぬ人には、たいてい名前がない。自身の知り合いでもない男が、ヤマガなどという固有名詞を伴って出てくるのはどうかしている。
むかしむかしヤマガという男がおりました。語り手自身も知らない固有名詞が物語の中で語られるとき、聞き手は、物語がすでに語り手よりも前に存在したことを知り、伝聞されたものであることを知る。降霊術において、霊媒師が自身も知らない名前を口にするとき、聞き手は、その語りを霊媒師の作った絵空事ではなく、降りてきた霊による語りだと確信する。物語の中の固有名詞は、それが伝聞であることのしるしである。
いや、作者がいちから作った語りにも、作者が会ったことも話したこともない者の固有名詞は出てくるではないか。名前は創作に必須のものだろう。そう言われるかもしれないけれど、それは話が逆で、作者は、名前を埋め込むことによって、自身の語りに伝聞性を与え、伝聞を擬装するのだし、聞き手もまた、それがただの作者の作り話ではなく、伝えられた話としてきき、語りの世界に住まおうとするのだ。
奇妙なことだが、語り手である音自身も、あとからこの物語を伝え聞く。悠介の話によれば、音の物語は悠介とのセックスから「産まれた」。しかし翌朝になると、音の記憶はあいまいだった。それで、悠介が逆に、音に覚えている話を「語り直した」。音は、自身が口にしながら、語り直された物語を、脚本にした。
この映画が参照している短編の一つ、村上春樹の原作「シェエラザード」では、物語の主人公は十代の語り手、シェエラザード自身であり、相手は「彼」と呼ばれるだけで、名前がない。そしてシェエラザードの物語ははっきりしており、聞き手から語り手に改めて語り直されることはない。物語にヤマガという固有名詞が登場すること。語り手が語った話を、聞き手が改めて語り手に語り直してみせること。これらはいずれも原作にはない、映画独自の設定だ。ただ語るのではなく、語り直す。物語が伝聞され、語り直されたことを固有名詞によってしるしづける。それは、この映画にとって必要不可欠の変更だったのに違いない。
それにしてもなぜ、ヤマガ、なのか。窓の外には山並みが見える。印象的なやまかげだ。山が見えるので、ヤマガ、なのだろうか。あとで、語り手は東京の放送局に勤めているらしいことがわかるのだが、都心にはそんな風に山が近い場所はない。車が多摩ナンバーであることからすると、八王子に近いあたりなのだろうか。悠介は後のワークショップでも、わざわざ一時間離れた場所から通おうとしているから、東京でも、都心から一時間離れた西に暮らしているのかもしれない。
***
ヤマガ、という固有名詞は映画の冒頭でいきなり現れ、悠介はその名を、しるしづけるように繰り返す。
音: 彼女はときどき
悠介:うん?
音: ヤマガの家に空き巣に入るようになるの
悠介:ヤマガ…
ヤマガは。ヤマガが。ヤマガの。音は、ヤマガ、という固有名詞を何度も繰り返す。「ガ」という濁音が耳にさわる。観る者は、ヤマガということばの響きを音の声で覚えてしまう。のちに車の中で、高槻が物語の続きを語り出すとき、彼は平然と「ヤマガ」という固有名詞を用いるのだが、その名を声にするときの口調は、音そっくりだ。高槻は確かに音から、この物語を伝え聞いたのだ。
なぜ高槻は、音からヤマガの物語を聞くことができたのだろう。音には何人もの別の男がいた。もしかしたら、セックスのたびに、音は相手に物語を語っており、高槻にもそのようにして物語したのだろうか。しかし、そう考えるには不自然なところがある。少なくとも映画の冒頭のシーンでの音の語りには、たった今、物語が降りて来ているかのような生々しさがある。もし別の男とのセックスの後に、音に突然物語が降りて来るのだとしたら、それは悠介にした物語の再話などではなく、まったく別の物語だっただろう。そもそも、いくつかの夜にわたって語られる女子高生の物語は、別の男に寝物語で語るには長すぎる。
いつ、どこでなのかはわからないが、音は、すでに悠介によって語り直された物語を、セックスの後などではなく、覚めた状態で、高槻に語ったのではないか。物語は、音に降りてきて、音から悠介へと吹き込まれ、悠介から音へと語り直され、音から高槻へと語り直された。ヤマガという固有名詞は、その伝聞のしるしなのだ。
では高槻が音から、悠介の知っているこの物語をきき、さらには悠介の知らない続きまできくことができたのはなぜだろう。これはあくまで推測だが、高槻には、特定の相手の声を自分の声としてきく、ある種の力があり、相手はその力に感応するのではないか。ジャニスを相手に、お互いに違うことばを話しながら「相談に乗って」しまうのは、その力が発揮された証のように思える。
では高槻のその力はどこからくるのか。わたしは、彼が車の中でいきなり切り出す台詞が、一つのヒントではないかと思っている。
家福さん、ぼくはからっぽなんです。ぼくには何もないんです。テキストが何か問いかけても、そのことを、ぼくは音さんの声に感じていた気がします。
* 「降霊」というキーワードは、岡室美奈子さんの未発表原稿「ドライブ・マイ・カー」論(→発表されました 2022.2.13追記)から着想を得たものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
