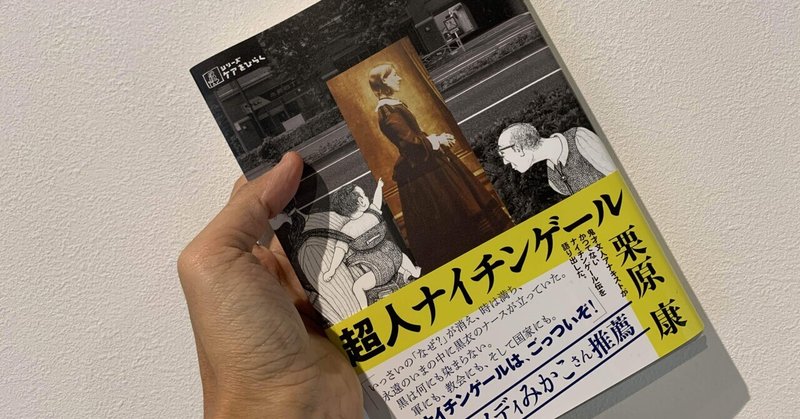
栗原康『超人ナイチンゲール』を読んで
アナキストブームの立役者のうちの1人、栗原康によるナイチンゲール伝。
栗原康といえば、伊藤野枝や大杉栄といったぶっ飛んだ人物をぶっ飛んだ文体で語り尽くすスタイルで知られている。だが、個人的にナイチンゲールにそこまで「ぶっとび感」があるとは思っていなかったので、意外性を感じて読んでみた。
読後感はといえば、悪くないものの、煮え切らないものだった。
イギリス上流階級の良妻賢母の枠に押し込められることに抵抗したナイチンゲールが、家族の束縛を逃れて看護師になり、クリミア戦争で多大な功績を残し、公衆衛生の発展に大いに貢献したというエピソードは楽しく読ませてもらったし、ナイチンゲールが貯蔵庫に強奪に行くシーンは是非とも映画化してほしいと感じるくらいの手に汗握る展開だった。
だが、一冊を通して、栗原康が自身が理想とする「ぶっとんだ人物」の枠にナイチンゲールをはめ込もうとしている印象を抱かずにいるのは難しかった。
僕はアナキズムの思想は好きなのだけれど、栗原アナキズムにまるっきり賛同しているわけではない。
栗原は「自他の区別が消える」「能動でも受動でもない」といった言葉をアナキズム的な言葉として多用し、その結果としてナイチンゲールは無私のケアに尽くしたという論調で語る。
僕は、ケアを小難しい東洋哲学で解説するのはインテリの悪い癖であると思っている。ケアとは「私が世話したいと思ったから世話する」というだけの話であって、わざわざ小難しい話を持ち出す必要はない。
まるで山奥で何年も修行しなければ、本当の意味でのケアはできない(自他の区別が消えていないなら、それは本当のケアではない)と言われているようだ。
試しに通りすがりのおばさんに荘子の話でもしてみるといい。「あ、よくわからへんけど、偉い学者さんはすごいわ〜」と反応されるのがオチだろう。実際はそのおばさんこそが、イキイキしながら子どもたちの世話を焼いている現代のナイチンゲールだというのに。
だから僕は「貢献欲」という言葉を使用すべきであると主張している。食欲に突き動かされて飯を食っていると感じているように、人は貢献欲に突き動かされて病人の世話をする。崇高な理念ではなく、当たり前にある欲望として理解することがアナキズムの第一歩だろう。
それに、自他の区別が消えるように感じる瞬間は、誰しも一度や二度は経験したことはあるだろうが、それでも自我が完全に消え去るようなことはない。あくまで僕たちは自我に軸足を置いて生きているはずだ。
もちろん自己なるものは本来の意味では幻想に過ぎないことは明らかである。しかし、僕たちは自己が存在し、自己の選択により運命が変えられると感じながら生きている(なにをしても無駄だと感じているなら、なぜ彼はトイレに行ったり、歯を磨いたりするのだろうか?)。「自己」というモデルは明らかに日常経験と合致していて、それを使い続ける方がどう考えても合理的だ。もし自己を捨て去った方がいいのなら、常にアヘンでも吸いながら生きている方がいいし、そもそも死ぬ以外ない、ということになってしまう。
脱線したが、元に戻ろう。
栗原は栗原アナキズムの思想で膨大な紙幅を割いた挙句、予め用意された脚本に合わせてナイチンゲールをダンスさせていたが、ナイチンゲールは、単に貢献したいという欲望に従って貢献しただけのように見える。別に自他の区別が消える悟りの瞬間や、大いなる正午を経験したわけでもあるまい。いや、そうなのかもしれないが、そうであるという描写は栗原の願望に過ぎない(「貢献欲」も僕の願望ではないか?とツッコミを入れたくなるかもしれないが、それは的外れである。なぜなら「貢献欲」とは食欲と同様に単なるトートロジー的にマッピングする単語だからだ。「人は貢献欲に従って貢献する。貢献しているなら貢献欲があるはずだ」となり、確実に真なわけだ)。
また、栗原アナキズムの自然観と、それにすっぽりおさまるようにナイチンゲールにコルセットを嵌め込むようなやり方も、正直なところみていて痛々しかった。
栗原は文明、農業、人為、国家=悪であり、自然、無為=正義といったあからさまな党派主義を隠そうとしない。
この手の二分論は、グレーバー&ウェングロウ『万物の黎明』で既に乗り越えられている。アナーキーな組織のまま大都市を築いたり、逆に自然児たちが絶大な権力構造を生み出したり、人類史は政治形態のカーニバルパレードだったのだ。
つまり「なにが自然か?」を問うことに意味があるとは思えない。「なにが自分たちにとって好都合か?」を問うことが、アナーキーな社会には欠かせないはずだ(正直なところ、都市は自然でなく、読書が自然というカテゴライズは、読書好きの栗原の贔屓目以外の何物でもないように感じる。)。
支配と権力を否定するアナキストすら、国家や経済といった大義名分の代わりに「自他合一」とか「自然」といった大義名分に固執していて、結局はミイラ取りがミイラになっている。そして「〇〇は自然だからOK」「〇〇は自然じゃないからダメ」みたいな評価の体系が用意され、それにがんじがらめにされていく。
僕は徹底的に感情を大義名分として重視すべきであると主張する。なにが自然とか、なにが正義とか、そういう論点はまるっきり無視して、「やりたい」「嫌」といった感情だけを重視するのだ。
結論、ナイチンゲールの伝記としてはあまり情報量は多くなく、栗原のイデオロギーが強かった。また別の伝記でも探そうと思う。
アナキズムはやっぱり党派主義になるから微妙だ。やはりアンチワーク哲学こそ至高。時代はアンチワーク哲学さ。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
