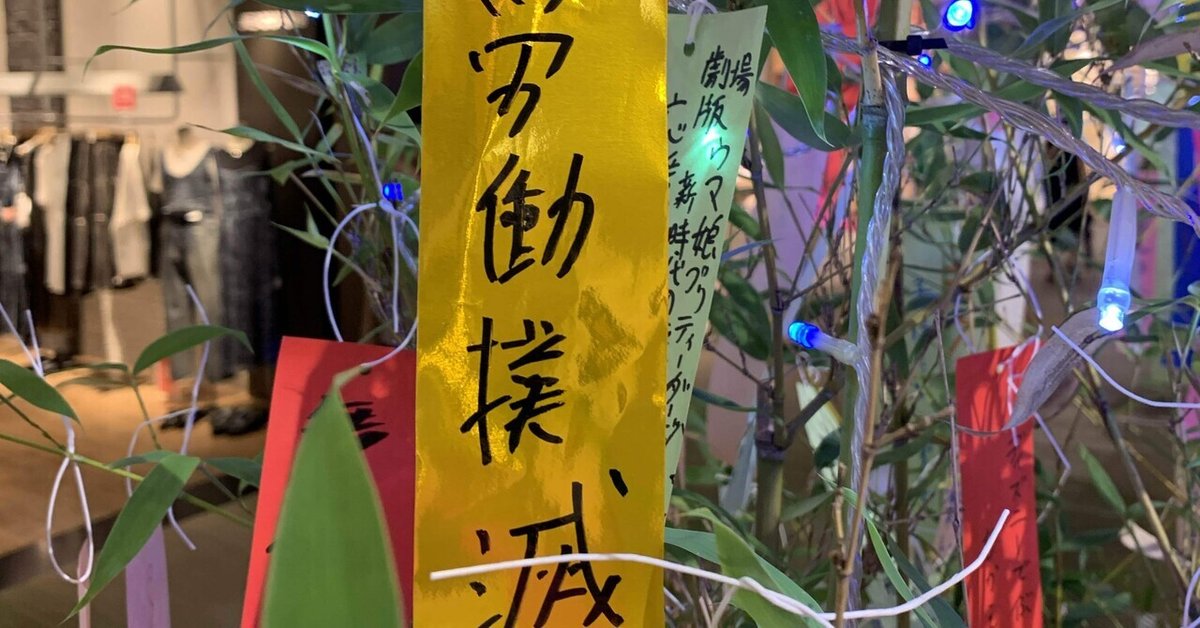
雑記オブ雑記【雑記】
■命令とお願い
お願いと強制の境界線に悩み続ける人生である。人は金と暴力に強制されているというのが、アンチワーク哲学の主張だが、金と暴力がなくなったからといって、強制がまったくなくなるわけではない。なんの利害関係もない友達同士。今となってはほぼ関わりのない先輩。別に養ってもらってるわけでもない親戚。それですら「なんか、断りにくいなぁ」という現象は必ず生じる。
確かにそれは致命的で、常態化した強制にはなりづらい。でも、小さな強制として、人の心にのしかかる。
これまでの人生で、人を都合よく使おうとしたことが何度かある。それが労働なら、相手は「くそ、こいつなんやねん」と思いつつも渋々従わってくれる。僕も「労働だから仕方ないよね」と強制することを正当化する。それが労働でならいなら、断られたり、断られなかったりする。
これが労働の魅力の一つである。相手がちょっとやそっと嫌がっていようが、それを度外視して、なにかをスムーズにやり遂げることができる。労働がなくなったときのコミュニケーションがどうなるのか、正直わからない。
とは言え、それは僕たちが感情のやり取りにあまりにも不慣れになってしまった結果であると思う。「嫌」というひとことを言う側も言われる側も恐れすぎているのかもしれない。「気軽に断ってくるやつは、気軽に誘える」と、よく言われる。労働がなくなれば、もっと「嫌」という感情が、当たり前のものとしてありふれていくのだと思う。
■酔っ払いとアート
道を歩いていると、四人ほどの人だかりがあった。七〇歳くらいのおじいちゃんが倒れていた。酔っ払ってこけて、寝そべっていたらしい。雨が降っていたので、サラリーマンらしいおっちゃんが、屋根のあるところへ移動させようとしていて、僕も肩を貸した。
「歩ける? 救急車呼ぼか?」と周りの人々が声をかけるも、おじいちゃんは「いまから散髪行かなあかんねん」の一点張り。散髪屋の場所は隣の駅で、いつも電車に乗っていくとのこと。自宅は近所だけど独り身らしい。
救急車を呼ぶほどではないらしく、ふらつきながらも立ち上がることができた。とはいえ、とても一人で散髪屋に辿り着けそうもない。僕は印刷会社に打ち合わせに行く途中で、散髪屋の方向と同じだったので、僕が近くまで付き添うことにした。
おじいちゃんの身体は日常生活に支障をきたしているようで、年末から施設に入る予定らしい。余計なお世話なんだが、さぞ退屈な暮らしを送っているのではないかと邪推して、普段なにをしているのか聞いてみた。すると、絵を描くのが趣味とのことだった。
本人曰く、人に見せれば「自分にも描いて」とかなんとか言われて大変らしいとのことで、人にはあまり見せず、あげることもしないらしい。だから自分の部屋で絵を描いては、自分の部屋に飾っているとのこと。
彼が幸せなのかはよくわからない。でも、なんやかんや楽しそうだ。パスカルは、人間は部屋の中でじっとしてることができないと言ったわけで、なにかやるべきことがあること自体、人間にとっての救いになり、生き甲斐になる。
息子に絵を教えてくれないか、聞いてみた。どうやらなんかそれは違うっぽい。やることがあればいいってもんでもないらしい。
酔いが覚めるまで駅で休憩していくとのことで、僕はおじいちゃんにペットボトルの水を渡してから別れて、電車に乗った。印刷会社の人には遅れると連絡したけれど、間に合ってしまった。一番気まずいパターンである。
それにしても、道ゆく人たちもなんやかんやと助けてくれた。きっとあれこれ用事もあったはずだろうに。これが貢献欲ってやつである。
■自分とかあるのか、ないのか
たぶん、厳密に言えばない。すべては空であり、すべては縁起であり、カントの言う物自体は存在せず、すべては人間が引いた境界線にすぎない。それでもなお人間は、そこに境界線を引き、なんらかの規則性を見出し、意味付けるという行為を行ない、対象を存在と呼ぶ。そして、存在を存在たらしめる存在としての人間を、ハイデガーは現存在と呼んだ。
そういう意味では、人間は存在しているし、自分はある。あらゆるものが存在しないがゆえに、あらゆるものを存在させることができる。自分という、歴史を持ち、性格と呼ばれるパターンを形づくる一人の人間を、僕たちはずっと存在させている。それは自由に変形させることができるし、「そんなもの無意味だ」と切り捨てることはできる。それでも、切り捨てたくないものはあるし、どうしても譲れない部分もある。それこそが自己である。僕にとって父親という属性は恣意的なフィクションにすぎない。それでも僕は父親を名乗り、父親という役割を生きることにコミットする。そして、そのことに価値があると思っている。
この決意こそが、人間が現存在である所以なのだろう。「それは空だよ」という教えは役割に苦しんでいる人の重荷を下ろすのには役立つと思う。でも、それは次の重荷を背負うための準備にすぎない。人は重荷を背負って生きていくことを欲するのだろうなぁ。
■感情に線を引きたくない
「我こそが女の理解者なり」と言いたいのは山々なのだが、どうもそういうわけにはいかない。男と男ですらわからないのだ。女はもっとわからない。そしてこれはあらゆる属性にも当てはまる。健常者と障害者。日本人と外国人。年寄りと若者。金持ちと貧乏人。既婚と未婚。うんぬん。
僕にできることは、あらゆる感情を受け止める姿勢を示すことしかない。同意できるかも、理解できるかもわからない。でも、誰かがなんらかの感情を抱いているなら、それは事実として受け止める。そして、できることがあれば対処し、できることがなければ対処しない。それしかないのである。
人がなにを感じようが、その感情は事実である。苦しんでいるなら、苦しんでいる。僕がLGBTなどの線引きに否定的なのはこれが理由である。線を引くことは、感情を承認(あるいは否認)しようとする営みである。たとえば同じだけの苦しみが存在したとして、一人が被差別部落出身なら救済されるべきで、そうでなくまだ定義づけられていない苦しみなら救済されない。そうした事態にうんざりしているのである。そこに苦しみがあるなら、手を差し伸べればいいのだ。
そうしないのは「なんでもかんでも救えない」とか「苦しんでいないのに、苦しんでいるフリをする人が出てくる」といった考えが根拠にある。アンチワーク哲学的には馬鹿馬鹿しい考えである。苦しんでいるふりをしなければならないのは、評価のシステムが存在するからであって、評価を抜きにして思うままに感情を発露できる社会には、苦しんでいるふりは必要ないのだ。そして、人は困っている人を助けることを欲する。苦しみがあるなら、助け合える。そういう生き物である。
■読んだ本

トースターというシンプルな機械をつくるために、素材を地面から掘り起こしたり、精製したり、型抜きしたりするプロセスが書かれた本。規模の経済のありがたみを実感するにはいい本だった。鉄や銅、プラスチック一つとっても、膨大な手間が加えられているわけだ。労働が撲滅された世界で、同じことができるだろうか。なんとも言えないが、できなくはないと思うんだよなぁ。

頭の上に何十キロの物を軽々と乗せて、数キロの道を歩く、頭上運搬という技術についての本。頭に載せるのは「体重が増えるだけ」という感覚らしい。なるほど。
モータリゼーションとともにほぼ失われたらしいが、いまだに年寄りの記憶には残っているらしく、やろうと思えば誰でもできるらしい。こんど米袋でも載せてやってみよう。
身の回りにあれば「あ、できるんだ」となるわけで、それは当たり前のスキルになる。ないからできないわけで、あればできるようだ。
でも、どこの地域でも男はあまりやらなかったらしい。なぜだろうか。女のやることみたいな感覚があったのか、力強く運ぶ姿を見せたいのか、なんせマッチョイズムを感じる。どれだけ暑くても革靴を履く、みたいなことなのだろうか(いや、違うか)。
この本に度々登場するのは、身体性と動作に美しさが宿るという考え方である。それはその通りだと思う。アイドルがダンスするのは、洗練された身体性を表現するためだし、突っ立って顔を見つめるだけでは即座に飽きるのである。
僕たちの生活からは身体性はどんどん失われていく。本来なら身体を動かすことは喜びであって、それを繰り返すことが身体性の向上であり、運動であった。生きることに身体性が必要なくなることは、果たして進歩と呼んでいいのかわからない。生活の中にある身体性の発露を苦行であるとして切り捨てるのは、労働化効果(強制により、本来苦痛ではなかった行為を苦痛だと思い込む効果)が作用したものだと思われる。労働が悪いよ、労働が。
その副産物として、運動=スポーツという考え方が誕生した。余暇、楽しみ、ゲームとしてのスポーツと、それ以外の苦役とに、運動が分離させられた。しかし、勝利至上主義的な価値観に嫌気がさして運動嫌いになった人は多い(僕もその一人だ)。結果、一握りのスポーツ好き以外、だらしない身体をぶらさげて生きていくことになった。もちろん、僕もその一人である。
僕は三十歳を超えてから、身体を動かすことが嫌いではないことに気づいた。これは明らかに学校教育が悪い。いまからでも身体を使って生きていきたいものである。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
