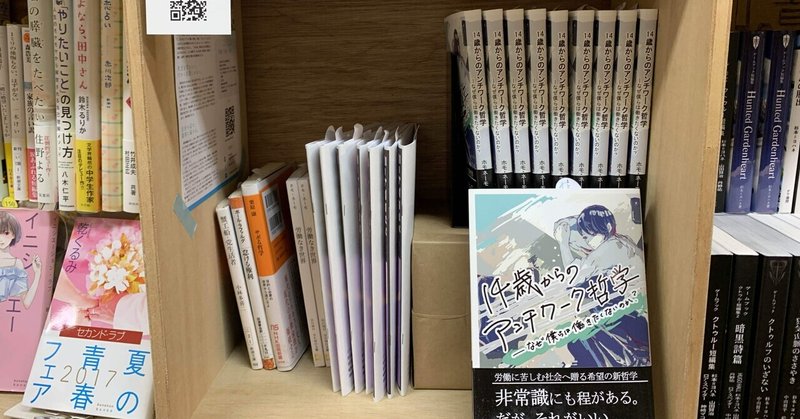
書肆七味での一日店長体験(前編)【出版社を作ろう】
昨日から僕は阿倍野にある棚貸し書店「書肆七味」の棚を借りることになっていた。棚会員は月に一回だけ店長をできるらしく、僕は搬入がてら一日店長をやることにした。とはいっても、さほど大仰なものではなく、カウンターに座ってお会計をして、たまに来る買取の受付をするくらいであるが、気分はすっかり店長である。前日の夜は「俺がこの店を盛りあげてやるんだ・・・」と、浮足立ったそわそわ感と共に眠りについた。
翌朝、僕のそわそわ感は、室内まで響く豪雨の音と、各路線の運転見合わせのニュースに迎え入れられる。幸いにして枚方から阿倍野までの電車は動いているようだったが、和歌山あたりがやられているらしい。阿倍野~天王寺周辺は、和歌山や南大阪からの通勤客も多いだろうことを考えると、客足の損失は大きいだろう。
そして、本をパンパンに詰め込んだバッグは、防水仕様っぽいテカテカ感を放っているが、どうにも心もとない。僕はビニール袋を被せ、ガムテープで隙間を埋め、荷物を準備した。重さは十五キロといったところか。これを、傘を差しながら、駅まで、そして阿倍野まで運ばなければならない。
前途多難である。それでも僕のそわそわ感は消えなかった。書肆七味のあるフロアは関西スーパーと隣接していて、どんな天気であろうがどのみち地元客は来るだろう。それに、多少お客が少なくても、別にこれで大儲けをするつもりもないのだ。キッザニア感覚で楽しめばいい。
というわけで、店に到着する。

店長の岸さんは僕より先に来ていた。軽く挨拶と、棚を貸してくれたお礼を伝え、三十分ほど業務の説明を受ける。オープン前の清掃。棚の状態のチェック。釣銭の確認。販売カードの管理。買い取り。査定。棚使用のルール。などなど。学生時代のバイト経験を思い出す。
ついでに『14歳からのアンチワーク哲学』の感想を教えてもらった(この前、僕は棚を貸してもらう前にお店に訪問して、岸さんに『14歳からのアンチワーク哲学』を手渡していたのだ)。良かった点だけではなく、よりよく伝えていくための改善点なども含めて伝えてくれた。やはり長く書店に携わられているからこそ、「本がどのように見え、どのように受け止められるか」という点で、僕にはない視点をもたらしてくれる。
そして、サクッと話をしたら「じゃ!」と岸さんは帰っていく。「え、こんなもんでいいのか?」と思わなかったと言えば嘘になる。オペレーションに不安があったわけではない。僕は岸さんに身分証明書を提示したわけでもなく、契約書を書かされたわけでもない。大切なお店と、レジのお金と、大量の商品を、まだ二回しかあったことのない他人に預けることに不安はないのだろうか?
まぁ、ないわけではないだろうが、信頼できるかどうかの見極めには自信があるのだと思う。最初の段階で、棚を借りれるかどうかには審査がある。その時点で、信頼できないと思ったら断られるのだろう。それに、一応緊急連絡先として、岸さんと阿倍野区の警察署の電話番号は教えてもらった。「なんかあったらなんとかなるだろう」という大人の余裕である。
僕はすぐに連絡できるように岸さんの番号をスマホに登録した(さすがに警察沙汰になるようなことはないだろうと僕は思っていたから、警察署の電話番号は登録しなかった)。
ともかく、僕は十三時開店の十分前に一人きりになった。急に「俺の店」感が湧きあがってくる。いや、俺の店ではないのだけれど。
とはいえ、ちんたらはしていられない。オープンまでに自分の棚の準備を終えなければならないのだ。僕はビニール袋を破り、中の本を取り出して並べていく。

なんせ『14歳からのアンチワーク哲学』をPRしたいわけで、大量に並べて置いた。それだけではしょぼいので、昔AmazonのKDPで出した『労働なき世界』と、自分で印刷したニートマガジンvol1、あとは適当に本棚からチョイスした古本を並べた。
事前に箱のサイズは聞いていたので、本の配置はシュミレートしていたわけだが、実際に並べてみると意外とショボい。もっと詰めれそうなものである。それに、装飾ももっとこだわればよかったと少し反省。つぎに搬入するときに、考え直そう。
さて、準備完了し、いよいよオープンである。
とはいっても客足はまばらである。平日で、あれだけ雨が降っていたのだ。ほとんどがご年配の地元住民らしき方々である。とくに年金生活者であろうお年寄りがぽつぽつと店に立ち寄り、立ち読みし、何人かに一人が本を買っていく。たまに学生や若い社会人ぽい人も来るが、体感で十パーセントってところだろうか。
自分の本がバンバン売れるような期待はしていない。だが、それにしても売れないのである。そもそも見てもらってすらいない。なぜか? お客さんの様子を見ていると、僕はあることに気が付いた。
本棚があるのは店内カウンターのある狭い通路の両サイドと、外側の壁面、あとは大量にラックに積まれて店外に展開されているのだが、通路の側にはほとんど人が来ないのだ。多くのお客さんは、外側の棚をぱらぱらと眺めて、カウンターに買いたい本を持ってくるのである。
ご存じ、店員の視線が気になる現象であろう。
狭い店内で本を探していたら、店員の目線や意識がこちらに向くことは避けられない。「だからなんだ?」という話ではあるのだが、それでもなんか気になってしまうのが人情である。その結果、多くのお客さんは無意識に店内を避けて、店員の視線が及ばない店外の本を、誰の視線も気にすることなくリラックスして眺めるのだろう。
僕の棚はカウンターの真ん前の、目線の高さのところにある。はじめは好立地だと思ったわけだが、実際のところはそうではないのかもしれない。カウンターに座る店員に背中を向けながら、リラックスして本を吟味することなど、普通の人間には不可能である。
では、僕がカウンターに座らなければ中に入りやすいのではないか? あるいは、半分客のふりをしながら僕が店内の棚を見ていれば、ほかの人も入りやすいのではないか? 僕はそう仮説を立てた。カウンターにはお金が置いてあるので、あまりにも離れるわけにはいかないが、なんとなく店内をプラプラしてみたのだ。
結果は逆効果。なんだか、やんわり人が店を離れていくのである。きっと僕は知らず知らずのうちに店員オーラを放っていて、居心地の悪い簡易領域を展開しているのかもしれない。
では逆転の発想である。いっそのこと、話しかけてみることにしてみたのだ。「どんな本お探しですが?」「常連さんですか?」「僕はじめて転院してるんです」「僕出版社立ち上げたんです」などなど。お客さんは一応それなりにこたえてくれる。だが、そのなんとも言えない表情を見てすぐに失敗だと気づく。そりゃあそうである。自分が書店にいったときだって、あれこれ話しかけて欲しいなんて思わない。じっくり誰のことも気にすることなく本を探したいと感じるわけだ。たぶん僕はウザい。
あれこれ試行錯誤してたどり着いた結論はこうである。余計なことはするな。僕はただ、カウンターに座ってボーっと前を見つめることにした。
ただただ会計をし、店内を見つめる時間。
こういう時間をブルシットだとかなんとか批判しがちな僕であるが、実は嫌いではないのである。最近、なにもしない時間がなかったので、これはこれでいいリフレッシュになるのだ。座禅を組むように僕はずっと座っていた。
どれくらいたった後だろうか。とある事件が起きた。
カウンターをめがけて、休日のメキシコマフィアのような風貌のエキゾチックな男が「狙いの獲物を見つけた」とでも言わんばかりのにやにや笑いをうかべて近づいてきた。警察署の電話番号をスマホに登録していないことを後悔ていた矢先、カウンターにやってきたメキシコマフィアはこう言った。
「わかりますよね?」
いや、わからない。彼の要求がなんなのか? 金か? レジの金なのか? 頭のなかはパニック状態である。
困惑する僕をみて、彼は一枚のステッカーを差し出した。

そう。無職詩人である。
なんとあの労働撲滅界隈のカリスマが、僕のXをみて会いに来てくれたのだ。まじか。本当に実在していたらしい。
彼は金をくれる人かエロい女としか付き合わないと公言しているわけで、僕はそのどちらでもないのである。しかし、なんだかわからないが来てくれたのだ。嬉しい。
どんな話をしたのかについて紹介すると、公序良俗に反する上に、公安警察に目を付けられる可能性が高いので、ここでは控えさせていただく。だが、ある意味で想像と真逆の人であり、想像通りの人であった。
しばらく話し込んでから「飯食いに行こう」と約束して(いまは家賃滞納しすぎて飯を食いに行ける状況にないらしい)、彼は去っていった。
また、坐禅の時間である。
が、ほんの十分後ほどだろうか。見覚えのある顔が近づいてきた。出版記念パーティに顔を出してくれたお方(無職&生活保護)がやってきたのだ。嬉しい。

どうやら彼女は近所に住んでいて、市民プールに泳ぎにいくついでにきてくれたらしい。この前会ったときに本を渡していたので、その感想を伝えてくれたり、ほかの本の話をしたり、すっかり店長面して店内を紹介したりした。
無職詩人といい、大阪に住んでいる無職は、やっぱり頼りになる。また彼女にはまだまだお世話になりそうだ(そういえばまとも書房をはじめてから、無職の知人が増えたなぁ)。
しばらくあと、サッとまとも書房の棚から『14歳からのアンチワーク哲学』を手に取り、カウンターに置いた人がいた。あきらかに買う本を決めていた人の動きである。「おお、ついに!」と浮き足立っていた僕に彼女は「ホモ・ネーモさんですよね?」と話しかけてくれた。
見覚えのない顔である。どうやらnoteを以前からチェックしてくれている方で、家が近かったので買いに来てくれたらしい。嬉しい。
「『労働なき世界』から読んでました!」「著者の方から直接買えるなんて嬉しいです!」「応援してます!」と早口で語る彼女の様子を見て、なんだか一端の作家になったような気分である。もっとじっくり話をしたかったのだが、本人曰く人と話すことに苦手意識があるらしく、そそくさと帰っていってしまった。また別の機会でお会いしたいものである。

さて、そんなこんなでいろんな人が来てくれたわけだが、これでようやく勤務(?)時間の半分が過ぎたくらいである。まだ書きたいことはあるのだけれど、続きは明日にしよう。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
