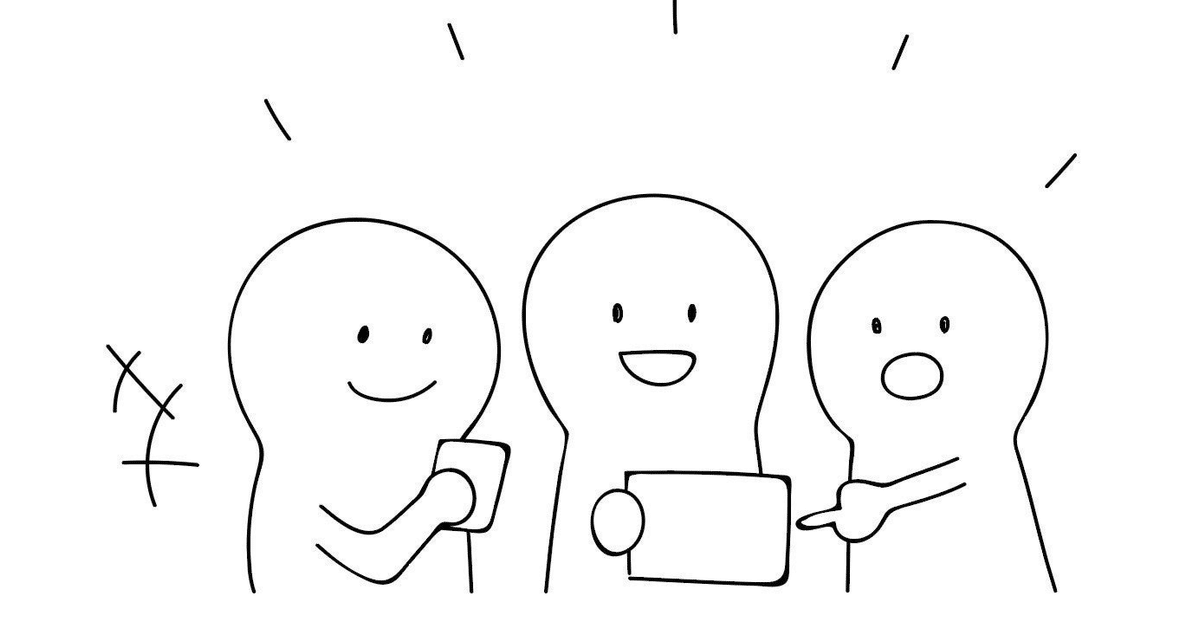
朝生より徹子の部屋【アンチワーク哲学】
先日、ダニエルさんという炎上系ユーチューバーに誘われ対談の動画を撮った。対談の相手はダニエルさんと、ぱくもとさん(陽キャ哲学普及協会)である。とはいえ、時間もさほど長くはなく、途中の中断などもいろいろあって、話したいことはさほど話せていない。視聴者からすれば「で、結局なにがいいたいの?」と感じられたかもしれない。
なので、改めてそこを説明する動画は上げ直すとしたい。だが、その前にぱくもとさんが、先日の動画についてのnoteをあげているので、それに対する回答をしたい。
■ベーシックインカムの実現可能性の話
対談の中でも、対談後記のnoteでもぱくもとさんはBIの実現可能性が低いのではないかという疑問を表明している。
私見を述べると経済政策としてのベーシックインカムは現実的ではないと思っている。弱者は弱者の特権を捨てることができず、強者もまた自らの特権を手放すことができないからである。生活保護や年金制度を廃止して、国民に一律で給付金を配ることは弱者として社会福祉に守られている人間からしたら許せない。経済的な強者も、自らの高額納税を弱者のみならず、中間層にも分配するとなれば反発は強いだろう。素晴らしい社会制度だが、実現可能性は低いという矛盾が現在ベーシックインカムが抱える問題なのである。
まずこの時点で微妙に食い違いがある気がする。僕が想定するシステムは年金や生活保護といった既存社会保障の大半を据え置きで、国債発行を財源としたBIを上乗せ支給するものである。つまり、経済弱者の実入りを減らすことはないし(もちろんインフレで実質的に減る可能性はあるが)、経済強者の税が財源として使われる可能性もない。
つまり、僕が想定するBIに反対するのは、「俺が損するからやめろ」と言う人ではないし「俺が得しないからやる意味ないよね?」と言う人でもないと、僕は考える。
この点はぱくもとさんとの見解の相違点であるようだ。BIの実現不可能性を、ぱくもとさんは次のように言う。
私は対談の中で、社会制度の素晴らしさを喧伝して国民を納得させることは不可能だと述べた。民主主義において、新しいシステムを導入するには『功利主義的システム』を装って、半ば大衆を騙すようなやり方で導入せざるを得ない。
対談の中でも、(あくまでたとえばの話として)「BIが配られればモテるくらいのメリットがないと大衆は納得しない」といった話をしてくれた。
だが、僕は逆だと思っている。BI反対論者の見解をよくよく注視してみよう。「誰も働かなくなる」とか「インフレが起きる」とか「弱者が甘える」とかそんなものではないか。つまり、「俺はいいけど、みんなが甘えるっしょ?」みたいな話であって、自分の身を差し置いて、社会のことを考えてBIに反対する人が大半なのだ。だから彼らにはもっとわがままになってもらわなければならないと、僕は考える。
(インフレも突き詰めれば需要の増加か、供給の減少が原因であり、需要が現在の供給を上回るほどに上昇する可能性はほとんど考えられない。ゆえに、インフレの原因は供給が減ることである。要するにそれは「誰も働かなくなる」を懸念しているということになる。)
BIに反対する人々は、自分の損得で経済を考えることをしない。全体多数の幸福に思いを馳せているのだ。そのため、「ベーシックインカム」と検索窓に入れれば、予測に「メリット」が表示される。これ自体、不思議な現象であると言わざるを得ない。
「お年玉 メリット」とか「給料 メリット」とか調べる人は誰もいない。それなのに、「ベーシックインカム メリット」は検索される。すると次のような記述が見つかる。
まず始めに、ベーシックインカムのメリットを解説していきます。
大きく分けて、以下の4点と言われています。
・貧困解決や対策につながる
・少子化の解消が期待できる
・労働環境が改善される
・多様な生き方が可能になる
これは童貞が自分と付き合うメリットを箇条書きするようなものである。要するに、つまらない。しかしBI推進派は依然として童貞くさいメリットを小難しい数式と共に提示しがちなのである。
この方法は筋が悪い。BI推進派は次のように問い返すべきなのだ。「あなたにとって月7万円か10万円をもらえたときのメリットはなにですか?」と。
クソみたいな仕事を即座に辞めてだらだら過ごす人もいるだろう。やりたかったビジネスを始める人もいるだろう。子育てに専念する人もいるだろう。生活環境を変えて新しい人生を始める人もいるだろう。どんな風にでも人生を変えられる。もはや自分を縛り付ける支配は存在しない。そんな気はしてこないだろうか?
そしてその自由を万人が享受する。それこそがベーシックインカムのメリットである。
ベーシックインカムの議論を始めた途端に、人々は経済学者を気取り始める。そうではなく、ひとりの人間としてベーシックインカムを想像すること。これがまず重要なのである。
そして、その想像を1億人にふくらませていくのだ。僕はその過程で犯罪が減り、健康問題が解決し、ブラック企業が撲滅され、環境問題が解決すると考える。これは順当な推論だと僕は考えるが、ここでも躓きの石はある。一般的な日本人は自分以外の大半の人間をバカだと考える傾向にある。つまり、金を受け取った途端に多くの人は子どものご飯のことをすっかり忘れて舞い上がってしまい、パチンコや新興宗教、ホストクラブにつぎ込んでしまうだろう、というわけだ。もちろんそうなれば、先ほどの僕が挙げたメリットも享受することはできない。
これらの発想のおかしさはすでに以下の著作で指摘している。
とはいえ、ぱくもとさんの懸念も一理ある。特に以下の記述だ。
お金というのは、価値を生み出した対価であると多くの人間が信じている。しかし、これは近代に入ってから生み出された比較的新しい考え方である。中世では貴族階級が存在し、彼ら彼女らは生きているだけで下層階級から税金を徴収することができた。まさに『生きているだけで偉い』状態だったわけである。労働の代替化が進むにつれて、本当に人間が生身で行うべき労働の総量は減っている。しかし、労働の総量が減っても、我々は努力したいし、努力している個人が溢れた社会が好きなのだ。
これはピケティが『資本とイデオロギー』で指摘した内容と共通するが、格差を正当化する社会常識が、「血統」みたいなものから「努力・実力・成果」みたいなものに移り変わったことを指摘している。実際のところお金が成果の対価ではないことは明らかだが、依然としてお金は成果の対価として支払われるべきであると多くの人が考えていることは事実だろう。そして「働かない奴に金を配るなどけしからん」と言い始める人が噴出するであろうことも、おそらく間違いない。
この点はアンチワーク哲学がカバーしようとしている部分である。金は成果を測定しているのではなく、成果を決定しているにすぎないこと。こうした事実を14歳にもわかる言葉で説明しようとしているのだ。
なにはともあれBIを実現するならなんらかの価値観の転換が必要であるという点は、ぱくもとさんも共通見解だと思われる。だからアンチワーク哲学を立ち上げた。
ぱくもとさんは別のアプローチを模索しているわけだが、僕はBIにこだわりたい。そのあたりの理由も『14歳からの〜』に書いたわけで、詳しいところは読んでもらうほかないのだが、長くなるのでとりあえずこの記事はここまでにしておこう。ともかく早速言及してくれたぱくもとさんへの、取り急ぎの返信である。この機会を設けてくれた2人に感謝を込めて。
※タイトルを回収するのを忘れていた。僕は朝生的な議論よりも、じっくり話す徹子の部屋の方が向いていると思った(あんまり上手く話せなかった)という話である。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
