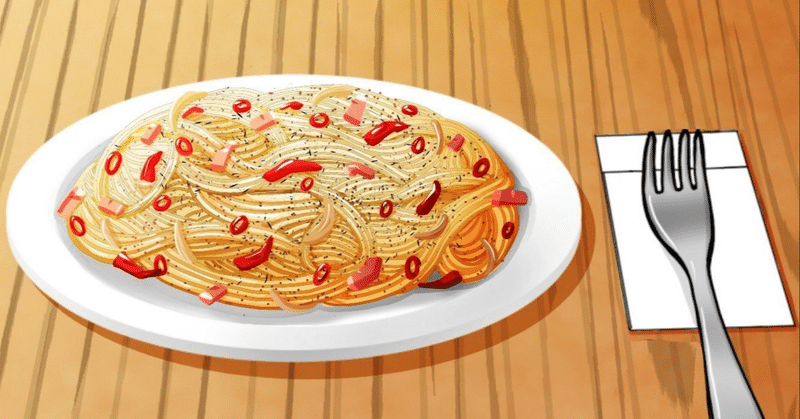
みんな味音痴になろう【雑記】
オリーブオイルが値上がりしているらしいというニュースがあった。まいったな、という気分になる。が、すぐに別にいいか、という気分になる。
純度の高いオリーブオイルじゃなくて、サラダ油と割ってる廉価版オリーブオイルを買おう。そうすればいい。オリーブオイルの純度なんてよくよく考えればたいした問題ではない。なんと言っても僕は味音痴なのだ。
僕はパスタやサラダなんかにオリーブオイルをドバドバかけるのが好きだが、オリーブオイルの味が好きなわけではない。「自分はいま、オリーブオイルをドバドバかけている」という情報を味わっているのだ(僕がサイゼリアが好きな理由はこれである。サイゼリヤの使い放題のオリーブオイルをペペロンチーノにぶっかけて食っている)。
なら、オリーブオイルの純度が高かろうが低かろうが、どちらでも構わないのだ。
この前テレビで「味音痴の人は味の濃い食べ物を食べるから体に悪い」的なことが言われていた。僕のレベルの味音痴になると、味を感じるとか感じないとかそんなことすら気にしなくなる。サラダをドレッシングなしで食うこともあれば、ドレッシングをドバがけすることもある。ドバがけするときは「あ、俺いまドレッシングかけてるわ〜」という感覚を味わうためにやってるし、なにもかけないときは、とりあえずなにかを腹に詰め込みたいときか、「俺いま健康的な食事してるわ〜」という感覚を味わうためにやる。結局のところ、実際の化学成分はさほど重要ではない。
二郎系ラーメンのアブラも同様である。意気揚々とアブラをマシにしたとしても、その大半はスープの上に残ることになる。「俺いまアブラ食ってるわ〜」という感覚のためにやっているのだ。
そもそも僕たちは化学的な成分だけで食べ物を評価していると思っているが、そんなわけがない。食べる環境、見た目、事前情報、食べる相手といった要素の方が明らかに大きい。
産地偽装が問題視されるまでバレないのはそのせいである。「ん? この味は‥国産と書いているが中国産だな??」などと気づく人はいないのだ。国産と言われれば国産の味がする。同じオホーツク海で獲れる鮭でも北海道産と言われればロシア産と言われるより美味しく感じる。伊勢の赤福本店で買った赤福は近鉄難波駅で買う赤福より美味しく感じる。可愛いトルコ陶器に載った料理は紙皿よりも美味しく感じる。キャラ弁は非キャラ弁よりも美味しく感じる。そういうものである。
だから、味音痴である自分を一度受け入れたなら、味覚情報をトリガー程度のものであると解釈できる。そして残りは自分の中で味をつくっていけばいいのだ。
とりあえずなんでも「これは美味しい食べ物だ」と思い込みながら食べればいい。そうすればいくらでも美味しい理由を見つけ出すことができる。コオロギのクッキーは「なんか逆にこのザリザリが癖になるなぁ」と思いながら食えば癖になってくるのである。中国産も「四川産」とか「上海産」と脳内で勝手に変換してみれば、なんだか美味しく思えてくる(中国産と言われればホルモン剤と農薬のイメージが湧き上がるが、四川産と言われれば土着の伝統的な製法で作られた印象が生まれてくる)。これはあくまで思考のトレーニングであり、味覚のトレーニングではない。
味音痴を問題視するテレビでは、味覚をトレーニングする方法が紹介されていた。明らかにこれは、人間は化学的な成分を感知することでしか食を味わうことができないという味覚成分由来説の立場である。
しかし味覚トリガー説に立てば、多少の味音痴は問題ではなくなる。というかむしろ味音痴を自覚しているくらいの方が、なんでも食べられるようになって楽チンである。
実際、楽だ。僕は好き嫌いがまったくないのだし。みんなが不味いと言ってるものも美味しく食べられる。
みんな味音痴になろうよ。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
