
「神戸、辞めてどうなるのか。」私篇③
姫路と聞いて、読者は何を思い浮かべるだろうか? やっぱりアレに違いない。
89年に神戸新聞に入社した私が、姫路支社に配属され、まずは事件・事故担当のサツ回りとして記者生活が始まった話は、前回書いた。
最初の数週間は、加古川市の自宅から半時間ほどかけて電車通勤していたが、サツ回りには定時がない。何かコトが起きれば、すぐに駆け付けなければならないので、姫路警察署に近いアパートに住むことになった。先輩記者が見つけてきた物件である。
1LDKのアパートは姫路城から指呼の距離にあり、家賃は確か月4万7千円だった。大学時代のそれは1万3千円だったので、大躍進である。
アパートの窓から、姫路城の北面がくっきりと見えた。新幹線が通る南側から見ると堂々たる雄姿だが、北側は一転して優美な表情を見せる。異名の ” 白鷺城 ” がぴったりとくるアングルだ。深夜に帰宅し、窓を開けて缶ビールを飲みながら、いつまでもライトアップされた城を堪能したものである。
日本における世界遺産第1号の姫路城は、規模と優雅さにおいて他を寄せ付けない。姫路に住んでいたときは、城を見ない日はなかった。いっぱしの姫路城研究家を自称していた私は、他の城を見ても1㍉も動じない。姫路のシンボルであり、私の宝物でもあった。
「姫路城は、壁にシミがついただけでも大きなニュースになるから、常に注意しとくように」
先輩記者はそう言って城のニュース価値を説いた。その雄姿に惚れ込んでいた私には言わずもがなで、よく城の真下にある事務所に取材に通ったものである。
軍都でもあった姫路は、敗戦直前に空襲されたが、城は大きな被害を受けることはなかった。米軍が意図的に避けたのではなく、偶然だったらしい。

姫路市は、私が赴任した89年は人口約50万人だった。96年には中核都市に指定されている。文化的にも経済的にも播州の中心である。市域は広く、移動には車が不可欠だ。
私は入社が決まってから、山形県の長井自動車教習所で合宿生活を送り、ようやく普通免許を取得した。実家には車がなかったので、入社時は正真正銘のペーパードライバーだった。
サツ回りは事件・事故が発生しると、現場に行かなければならないので、入社後に姫路の自動車教習所で講習を受けた。編集部長のはからいで、費用は会社が持ってくれた。
最初はおそるおそるの運転である。サツ回りが使う社用車は2台あって、1台はパワーステアリング、つまりハンドル操作が軽かったが、もう1台(確かカローラだった)は旧来型で、操作が重くて往生した。
この運転しづらい車で、ひと悶着おこしたことがある。車を駆って、事件現場に急行した。気が急いていたので、キーを指したままドアをロックをし、車外に出た。もう車には戻れない――。
「どうしましょう?」
デスクに電話で相談したが、「なんとかせい」とつれない返事。
「どうしたんですか?」
近所のおじさんが、声をかけてくれた。
「定規をドアの隙間に差し込んだら、開くことがあるよ」
そのおじさんが、家から鉄製の定規を持ってきてくれた。定規を窓ガラスの下に差し込み、上下左右に動かしたら、あらふしぎ、たちまちドアのロックがはずれた。
こんな簡単に開鍵できるなら、車上荒らしなんか簡単やんか――不謹慎なことを考えながら、おじさんに礼を言ったおぼえがある。

私が入社した89年は、アナログからデジタルへ変わろうとする時代だった。両者が混在していた、とも言える。
車には、まだカーナビはない。「〇〇で交通事故発生」という一報が入れば、まずは昭文社の蛇腹式の地図を広げて、場所を確認する。広げては折りたたむことを繰り返すから損傷が激しく、裏面からビニールテープを貼って補強しても、すぐに破れた。数ヶ月使うとボロボロになって地名が読めず、買い替えなければならなかった。これは自腹である。
営業担当者や刑事は歩き回るイメージがあるからか、「靴をすり減らす」と表現されるが、カーナビ登場前の記者は、さしずめ「地図を買い替える」とでも形容すればいいだろうか。
携帯電話はまだないので、いつもポケットベルを腰のベルトにはさんでいた。手のひらにおさまるほどの大きさだったが、「ピーッ、ピーッ」と、けたたましい音が鳴る。それを合図に記者クラブの固定電話か、外であれば公衆電話から会社に架電すると、取材を差配するデスクが出る。
公衆電話用に、テレホンカードか10円玉が必携だった。テレカが使えない旧式の公衆電話で10円玉が切れたときには、50円玉や100円玉を奮発しなければならない。お釣りが出てこないのである。
ポケベルを持たされたときは、いっぱしの仕事人になったようで、最初はうれしかった。ところがそのうち、ところかまわずピーピー鳴り響くそれが鬱陶しくなる。
各社の記者もそれは同じらしく、鳴り続けるそれのスイッチをoffにするのが遅れると、他社の記者から「はよ、切れや!」と怒鳴られた。私のことである。
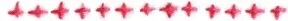
デスクの用命は、いつも突然である。ポケベルが鳴り、電話をかけるのが億劫なときは、「すみません、公衆電話がなかったので」と言い訳をしていた。
いっとき私は、銭湯に凝っていた。勤務時間中は番台に預け、「もしポケベルが鳴ったら教えて」と言い添えて、湯につかった。幸いなことに、入浴中にそれが鳴ることはなかった。記者は拘束時間が長いので息抜きが必要…。そう自分に言い聞かせていたが、単なる自分の趣味だったかもしれない。
デスクは私が真っ当なサツ回りではないことは、うすうす気づいていたように思う。
私は大学時代から、兵庫県内の複数の自立障害者の介護に入っていた。そのひとりが姫路市に住むTさんで、姫路城から北2㌔にある野里の長屋に住んでいた。
Tさんは障害者運動の活動家だったので、昼間は家を空けることが多かった。鍵は郵便ポストに入っていたので、自由に出入りできた。私は勤務時間中、よくTさん宅で昼寝をした。
当時は夕方から、長渕剛が大衆食堂の店員を演じたテレビドラマを再放送していた。一度見だすと、次も見たくなる。もちろんTさんは、私が自由に出入りしていたことを知っていたので、不法侵入ではない。
Tさん宅でくつろいでいると、ポケベルが鳴る。デスクは必ず聞いてくる。
「今どこや?」
その都度、適当な地名を挙げていた。地名が思いつかないときは「あっ、野里にいます」と正直に答えてしまう。何度かそれが続き、「お前、よう野里におるなあ」と隠れ家がバレそうになったことがある。
勘が鋭いデスクは、おそらく私がサボっていることに感づいていたのであろう。

明らかにサボっているのがバレてしまったことがある。姫路市役所の記者クラブに所属し、市政担当記者をしていたころの話である。
記者クラブには、仮眠用のベッドがあった。昼過ぎに眠くなってベッドで寝ていたら、神戸新聞の専用ブースの固定電話が鳴った。デスクからである。ヤバい…。だが、睡魔には勝てない。
しばらくすると、今度は記者クラブの固定電話が鳴った。デスクは、記者クラブに常駐する派遣社員に、私の居所を聞く作戦に出た。電話で派遣社員が話しているのが聞こえてきた。
「…角岡さんは、いま、ベッドで寝てはります…」
おいおい、何を正直に言うとんねん! しかしこうなったら、逃げも隠れもできない。受話器を取ると、鬼デスクの詰問が待っていた。
「角岡、寝とったんか!?」
「はい、熟睡してました!」
正直なジョージ・ワシントン少年は、後に米国大統領になったが、私は正直者にもかかわらず、帰社後はデスクや古株の記者に、こってりしぼられた。
後日、派遣社員には、ふだん私は仕事上、事実を正確に伝えることを信条としているが、時と場合とによっては、それを杓子定規に私に当てはめる必要がないことを伝えた。

新聞紙面は15段で構成されており、通常は下5段が広告である。当時は1段が13字だった(現在は11字)。執筆は今では信じられないことに、手書きである。1字1字、原稿のマス目を埋めていく。書いては消し、書いては消しの繰り返しで、仕上げるのにずいぶん時間がかかった。
入社していちばん最初に取材したのは、聾学校の入学式だった。
「どれくらいの字数でまとめたらいいですか?」
私の問いにデスクは、おもしろいことを言うやないかという表情を見せながら、「好きなだけ書いてみ」とやさしく答えた。記事は字数、行数よりも、内容が重要であることを私はまだ知らない。中身次第で、長くなったり短くなったりするのである。まあ、年中行事は短くていいのであるが…。
取材した内容は、ノートにメモするのだが、これも手書きである。社名入りのノートや鉛筆、サインペンは会社にあって、これらは自由に使えた。サインペンの蓋をするのを忘れて胸ポケットに入れ、シャツをインクでにじませたことが何度もあった。新人記者によくある失敗らしく、「オレもようやったわ」と先輩記者に笑われた。
取材したメモを見ながら、原稿用紙と格闘する。デスクか先輩記者が、私の手書き原稿を読み、やはり手書きで手直しする。市民マラソン大会の原稿で、参加者の発言のあと「‥‥ときっぱり。」と文章を締めたら、それを読んだ先輩記者が「出た!きっぱり」と苦笑いした。月並みな表現と体言止めは、新人記者が通る道ではある。
安易な月並み表現は、今も紙面でよく見かける。「(嬉しさに)目を細めた」「(悔しさに)唇をかみしめた」「拳をにぎりしめた」。これらの常套句を見るたびに、記者1年目の自分を思い出すのである。

新人は仕事の勘所がわからないものである。とりわけ私がそうだった。
姫路市に「豊富町」という地名がある。これを原稿で「豊臣町」と書いたら、デスクが「これで合うとんか?」と聞いてきた。私の辞書の「とよとみ」には、「豊臣秀吉」しかない。すぐに調べればいいのに、私は「はい、合ってます!」と答えてしまった。「強情やな」とデスク。よくこんな新人に付き合ってくれたものである。
記事に誤記があると、翌日の紙面で訂正しなければならない。それが続くと、忍耐強いデスクも、最後はキレる。
「もうお前の原稿は、一切信用せえへん!」
面前でそう言われたことがある。今となっては、デスクの怒りはよくわかる。記者にとって誤報、誤記ほど恥ずかしいものはないからである。
間違いの多い新人を相手にするデスクが、疑い深くなるのは当然だ。だが、稀にこちらが正解のこともある。
姫路市に「橘橘太郎」という市会議員がおられた。原稿で、その名前を書いた。するとデスクが、えらく怒るではないか。
「こらあ、こんな名前があるかあ!」
「いや、ほんまにいてはるんですよ!」
今度はデスクが調べ上げ、実在する人物であることがわかった。デスクが間違うこともあるのだ。

記者会見場をテレビ画面を通して見ることがある。たいがいの記者は、取材メモを最初からノートパソコンに打ち込んでいる。打ち込むのが遅い私には、未来社会にしか見えない。
私が入社した平成の最初期は、ワードプロセッサーが普及しだしたころだった。記者は自腹でワープロを購入し、打ち込んだ文字を印刷した上でデスクに見せていた。
私は1年目の冬のボーナスを財布に入れ、休日を利用して大阪の日本橋の電気屋街に、ワープロを買いに行った。キーボードのタッチがやわらかかったソニー製品を購入したら、店員に「いい買い物をしましたね!」と褒められた。
気をよくして使っていたら、しばらくしてソニーがワープロ生産から撤退したことがわかった。店員は在庫処分ができて喜んでいただけだった。
撤退はしたものの、その後ソニーはワープロ機能を備えたパソコン開発に参入し、それなりに成功した。少なくない私の投資が、ソニーの成長に貢献したのである。〈2024・7・31〉
https://note.com/kadooka/n/n5f260c4aa127
https://note.com/kadooka/n/n6350fe98cd70
いいなと思ったら応援しよう!

