
「神戸、辞めてどうなるのか。」私篇➁
先日、毎日新聞東京本社の藤原章生記者から、大阪に行くので会えないかという連絡があった。当ブログの22年2月の「神戸、辞めてどうなるのか。 私篇①」で触れたが、藤原さんと私は、88年に神戸新聞の入社試験を受けた ” 同期 ” である。
彼は毎日新聞にも合格し、そちらに入社した。私よりふたつ年上で、大学を卒業後、住友金属鉱山でエンジニアとして勤めていたが一念発起し、27歳で記者に転身した。南ア、メキシコ、イタリアなどで海外特派員を長らくつとめ、今は日本に帰ってきているようだ。88年以降は、お会いしていない。いい機会である。
広々とした芝生が広がる大阪市内のカフェで、36年ぶりに再会した。ともに還暦を超えたが、藤原さんの容貌は、あまり変わっていない。定年を過ぎたが、再雇用で契約記者を続けているという。早くリタイアしたい私とは大違いである。
初めて会った頃の話になった。彼の場合、ブロック・地方紙の受験は年齢制限があり、チャンスは限られていた。早々と内定を得た神戸新聞に入社するつもりだったという。
内定者が神戸の本社で顔合わせをする日も出社している。藤原さんによると、会社幹部と会食したあと、内定記者7人と喫茶店に入り、しばらく雑談したという。
そのときだったか、面接のときだったか、言葉を交わしたことはなんとなくおぼえている。私は1浪、1留、既卒で3年ダブっているので、年齢が近かったからかもしれない。住所交換し、互いに年賀状を出していた。
神戸新聞に入社するつもりだった藤原さんだが、毎日新聞だけ最終面接が残っていた。ところが毎日のそれが、神戸新聞の内定者が再度出社する日と重なっていた。藤原さんの腹は決まっていたので、毎日はパスするつもりだったらしい。
すると神戸新聞のT編集局長から電話があり、「君は働いているから、わざわざ来なくていいよ」と言われたという。当時は鹿児島県内に勤務していた。その言葉があったので、藤原さんは毎日の面接を受けた。結果は言うまでもない。
もしT編集局長がそんなことを言わなかったら、藤原さんは間違いなく神戸に来ていたはずである。ただ、毎日に行かなければ、海外特派員の取材経験を活かした『絵はがきにされた少年』(第3回開高健ノンフィクション賞受賞、2005年)やその他の著作は、世に出なかっただろう。神戸新聞は、シンガポールに海外支局があるだけだった。
それを考えると、神戸に来なくてよかったのかもしれない。

それはともかく、久しぶりにお会いできてうれしかった。ノンフィクション作品を数多く書いておられるので、共通の知り合いの編集者やライターもいて、業界の話で盛り上がった。思わぬところで、人生は交差するものである。
ちなみに藤原さんを逃したT編集局長は、酒癖が悪いことで有名だった。私も被害を被ったことがある。90年代初頭の整理部時代、あるスナックで部員と飲んでいたら、へべれけになったTさんが「お前、だれや?」とからんできた。
「俺は記者の名前は全員おぼえている!」
以前にTさんがそう豪語していたことがあったので、「なんで僕の名前をおぼえてないんですか?」と詰問すると、激高しだした。
「お前なんか、辞めさせたる!」
そう放言したので「やれるもんなら、どうぞ!」と返したら、おさまりがつかなくなった。つかみ合い寸前になり、間に入ってくれる人がいて、事なきをえた。
それから間もなく私は中途退社することになるが、「Tさんとの一件が辞める理由になったのか」といぶかる同僚もいた。そんなくだらないことが原因であるはずがない。
有望な人材を他社にとられてはならない。酒癖の悪い人間を幹部に登用してはならない――。私が神戸新聞に在職して得た2大教訓である。フリーになったいま、その教訓は何の役にも立っていないけれど…。

記者経験や部落問題をテーマにした著作があることから、新聞社の新人研修でそれをテーマに話をすることがある。1時間半はたっぷり話すし、質問も受ける。
神戸新聞は、かつては部落問題報道に力を入れていたが、私が受けた新人研修では、その話題は集局次長が数分間しただけだった。
運動団体には、部落解放同盟と共産党系の全国部落解放運動連合会、いわゆる全解連、自民党系の自由同和会がある…といった簡単な内容である。部落問題に限らず、どんなジャンルも自分で深めよということだったのだろうか。それともよく知らなかっただけなのだろうか。
入社して数週間後、私は姫路支社の配属になった。赴任はどの社よりも早かった。” 座学より現場 ” が、当時の社の方針だった。姫路は生まれ故郷の加古川から電車に乗って約30分。同じ播州なので土地鑑もあるだろうという編集局幹部の判断だったと思う。当初は実家から通っていた。
「出社時は、社章はいつも付けておくように」
人事部長が新人研修でそう言ったので、初出勤日はスーツの襟に、神戸の「神」のロゴが入ったそれを付けていった。翌年以降、後輩が毎年春に初出勤してくるわけだが、誰もバッジをつけていないことがわかる。他社にもそんな新人記者はいなかった。人事部長がなぜあんなことを言ったのか、今もってわからない。
その人事部長は、社章は退社時には返還しなければならないとも明言していた。それほど大事なものだから大切にせよと言いたかったのだろう。その後、私が中途退社する際、返還は求められなかった。そもそもバッジを付ける機会は、約5年の在職中まったくなかった。今も実家の机の引き出しの中に、「神」バッジが眠っているはずである。
細長い外国煙草を吸っていた人事部長は経済部記者の出身で、先述した内定者の出社日の会食で同じテーブルを囲んだ。神戸新聞会館の階上の中国料理店で会話した内容が印象に残っている。
「新聞記者にとって最も大切なことは何ですか?」
私の質問に人事部長は、間髪を入れず答えた。
「バランス感覚や。どんな記事もこれがないとあかんな」
その後、外勤・内勤記者、そしてフリーのライターとして文章を書いてきたが、人事部長の言葉は、至言である。新聞は基本的に自分の考えや意見を主張する場ではない。さまざまな事象や見解を取材した上で、記事にまとめる。事実を伝えることが第一なのである。
けれども記者にも個性や見解があるので、それをどのように記事に反映させるかは重要である。これはノンフィクションも同じだ。
私の真剣な表情を見ながら、人事部長は続けた。
「会社のトップ人事の記事があるやろ。次期社長は誰々と特ダネを書いても、喜んでる場合ではないんや。次の社長は誰か、すぐに取材を始めんとあかんのや」
はー、そんなもんですか! その時は驚いたが、あとになって考えると、いずれ社長人事は発表される。ならばもっと別の取材をしたほうがいいのではないか…。そんな怠け者だから、私は新聞記者に向いていないのである。
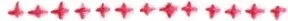
話を初任地に戻したい。初出勤のその日、姫路市内の繁華街・魚町で殺人事件発生の一報が入った。スナックのママが絞殺されたという。
「とりあえず現場に行ってこい」
デスクにそう命じられたものの、現場で何をしていいやら皆目わからない。先輩記者に、「犯人が現場の様子を見に来ているかもしれないので、かたっぱしから写真を撮っといてくれ」と言われたものの、撮影もおぼつかない。
数週間後、スナックの常連の男が逮捕された。痴情のもつれが原因だったと記憶する。男は演劇関係者で、地元では広く顔が知られた存在だった。
「逮捕された男の減刑歎願運動を求める動きがあるそうです」
誰かから聞いた話を先輩記者に報告すると、
「刑も決まってないのに、なんで減刑歎願運動が始まるねん」
そう一蹴された。そりゃそうである。世間知らずの私の社会人1年目は、かくしてスタートしたのだった。
地方紙に限らず記者1年目はどの社も、事件・事故を担当することが多い。いわゆる ” サツ回り ” である。警察を回るからそう呼ばれるのであろう。
入社した89年の初任地・姫路は、事件が頻発した。初出勤日の殺人事件に続き、日を置かずにラブホテルで、男が身ごもった女を殺害する事件が発生した。
コテージ風のホテルは、自然の竹藪に囲まれていた。小雨がそぼ降る中、竹藪にひそんで警察の動きを追っていたら、向こうから丸見えだったようで、しばらく私は ” 竹藪記者 ” と呼ばれた。
「おっ、竹藪記者、きょうは何の取材ですか?」
刑事にそう言われるたびに、穴ならぬ竹藪があったら入りたい気になった。
事件はまだまだ続く。市中心部から車でゆうに1時間はかかる農村の中学校で、いじめによる死亡事件が発生した。
たしか梅雨時だったと思う。小雨が降る中、死亡した生徒の顔写真を求めて家々を訪ね歩いた。ようやく見つけた写真を接写し、締め切りに間に合わせるために支社に帰るべく、小さな川の土手を必死に走ったことを鮮明におぼえている。
帰社したあとは、暗室でのフィルムの現像作業が待っている。デジタル写真やスマホが普及した今では考えられないアナログな世界であった。
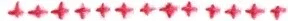
姫路は四代目山口組組長・竹中正久の出身地で、命日には本部の幹部一同が墓参に訪れた。週刊誌で見る最高幹部を現認する機会は、そうあるものではない。
「お、本物や!」
先輩記者たちも興奮を隠せない。神戸市役所勤務を経てその道に入り、最高幹部にのぼりつめた岸本才三総本部長の白い髭が、なぜか印象に残っている。
89年は、四代目組長をめぐる跡目争いから起った山一抗争の余波で、組事務所への銃撃が続いた。そのたびに現場に駆け付けたが、当時は組関係者を取材することはなかった。もっぱら暴力団担当の刑事と話をするぐらいである。
その私が後年フリーになり、四代目・五代目と縁が深かった元組員の小西邦彦氏(部落解放同盟大阪府連の元飛鳥支部長。飛鳥会事件で逮捕)を取材し、『ピストルと荊冠 <被差別>と<暴力>で大阪を背負った男・小西邦彦』(講談社、2012年)を書くことになるとは、この時は思いもしない。

年末には龍野市(現・たつの市)で誘拐事件が発生した。生後3ヶ月の乳児が、白昼にスーパーから連れ去られた。龍野市は姫路に隣接し、姫路支社の守備範囲である。
前線本部となった龍野支局に、姫路支社の記者はもとより、兵庫県警本部詰めや私の同期の記者(別稿で紹介した宮沢之祐氏。現在は琉球新報記者)がかけつけ、取材を続けた。
とはいえ警察との間で結ばれた報道協定で、犯人を刺激しないために、おおっぴらな取材はできない。
「生まれたばかりの子は、大量のおむつが必要なんや。周辺の薬局をまわって、買い込んだ者がいないか、しらみつぶしに調べよう」
子持ちの大先輩のアドバイスで、目立たないように薬局をまわって聞き込みに励んだ。同じような動きを他社もしていた。考えることは同じである。
建前上は取材が許されないかわりに、警察からは捜査で得た情報が、その都度知らされた。
乳児の母親によると、中年女性が言葉巧みにわが子を取り上げ、去っていったという。女は白いコートと白いタイツをはいていた――。その警察情報を聞いたとき、白づくめの女が乳飲み子を抱いて走って逃げる姿を想像し、恐ろしさで鳥肌が立った。
後に兵庫県警は乳児に生命の危険はないと判断し、公開捜査に切り替え、大晦日に女が自首してきたため逮捕した。
警察による記者会見を目指して、週刊誌やテレビ局の記者・スタッフが、播州の片田舎に蝟集した。なにせ全国ニュースである。
会見がおこなわれる龍野警察署前の駐車場に、テレビ朝日の白い中継車が停まっていた。その車両から、電源の音であろう「ブーン」という低いうなりが聞こえてきたのが今も耳朶にこびりついている。テレビ記者は、田舎には不釣り合いな高価なスーツを着ていた。
<あれ、絶対イタリー製やで…>
根拠もなく、私はそう決めつけたのだった。
テレビ局の記者やスタッフは、地元でさほど取材したわけでもないのに、警察の発表を聞いて、自信満々でニュースを伝えている。
<きれいな服を着て現地に乗り込んで、短い間に取材してさっさと帰っていく。ええ気なもんや>
大した取材もできない記者1年生の私は、ひねくれ根性だけは一人前だった。
不肖フリーライターの原点は、竹藪に忍び込んだり、一刻も早くフィルムを届けるべく息を切らしながら土手を走ったりした、あの日々にあったことを、テレビ局の中継車のうなりとともに思いだすのである。<2024・6・30>
あなたのサポートによって愛犬ももじろうのおやつがグレードアップします。よろしくお願いします。
