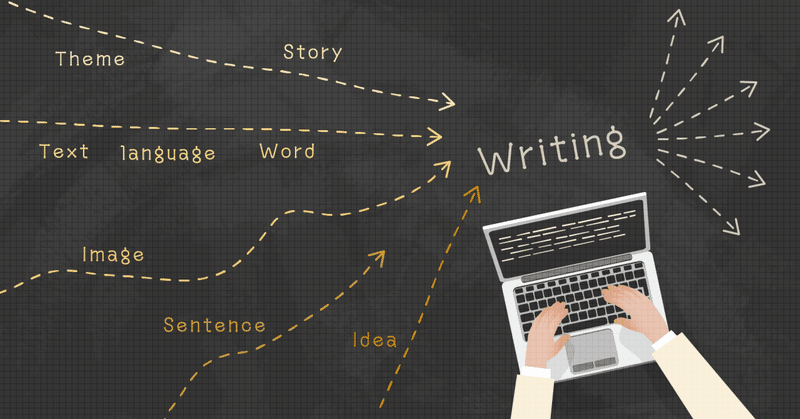
前ジャンルへの卒論
あるいは石愚痴デラックス。
前ジャンルへの気持ちを論文にしないとどうにも今ジャンルの創作にも身が入らないなーと思うのでまとめてます。
前ジャンルとはDr.STONEです。二年?三年? くらい滞在してましたが、長いオタク人生で初めてのはまりかたと離れかたをしたのでわやわやしたものを抱え続けてます、この記事で具現化させて整頓するぞ。
※これはごく個人的な自分の気持ち整理用の大掃除記事です
※とはいえそのまま置いておくと余計な被弾しそうだなとおもったので後半は有料記事にしてます
※Dr.STONEと適切な距離とれててわたしとやりとりある人なら読んでも問題ないと思うんでリプかDMくれれば有料部分お見せします
「石で同人EDが治る」とは、そしてその理由
いきなり界隈用語で見出しを飾ります。
「石」は界隈の作品名、「同人ED」は「二次創作ができない状態」です。
石界隈において、この「同人EDが治った」という報告が気のせいでなく数多くありました。この現象の謎とその要因は落石中からうっすら見当がついてたんですよね。あ、落石っていうのは界隈において「Dr.STONEに沼る」的な意味です。
この「同人EDが治った」系のツイートを何名か追っていると、中高年、しかも長くブランクのある帰還兵の姿が目立ちました。数年ご無沙汰だった、というのでなく、「もう引退した身の上、戦場に出ることはないだろう私はパン屋さんとして生きていく」といったような帰還兵たち。
ボリュームゾーンおよび自分を振り返って思うと、「ああ、これ、「年代」が一致してるんだな……」と思いました。
ここでいきなり、どうして英語圏にはケモナーが多いのかって話になるんですけど。
移民が多く人種のるつぼである英語圏では、幼児向け番組では動物キャラが用いられることが多いんですね。白人黒人黄色人種のバランスやキャラ付けを気にしなくていいし、どの人種のこどもも感情移入できるから。
でもって、どこだかの実験だか論文だかで、「もっとも性的欲求を感じるのは幼児期に慣れ親しんだモチーフ」って結果が出てるそうです。人類という動物の生存バイアスで考えるなら、共同体の中にいたものがつがいの相手として安全という認識、みたいなことでしょうか。
つまり幼児期に動物コンテンツで育つとケモナーになりやすい。ポケモン? その話をするのはやめておきましょう。
まあ性的欲求とまではいかなくても、「魂がぐっとくる」のって、自分の青春期の年代の画風っていうのはあるよなあ、と思ってて。
たとえば私でいうと、最近のアイドル系コンテンツの線の細い美形キャラの絵を「イケメンキャラである記号」としてしか認識できないんですけど、こういうのはすごいぐっとくるんですよ……むしろこういう絵でないと無理くらいある。

逆に若い子には古臭くて性的な魅力を感じられない絵柄であることでしょう。わたしも星矢やサムライトルーパーあたりは難しい。
まあ何が言いたいかというと、「あの古臭さがアラフォーアラフィフにストライクだったんだろうな……」という。
Dr.STONEの絵柄は、古い絵柄です。個人的に二十年、下手すると三十年くらい前のままだと思ってる。でもってセリフ運びも昭和なんですよね。ぎりぎり平成初期かな。
この「青春時代の空気」を纏った作品が、2020年代の週刊少年ジャンプに連載中作品として出現してる。過去の名作でもなくリバイバルでもなく、ライブ感のある存在として。
これがまず「最近のコンテンツにはいまいち乗れないわぁ、もう自分はそういうあれじゃないのかなあ」となっていた帰還兵を呼び寄せたのでしょう。
違う、自分がそうなんじゃなく、自分が燃え上がる時代の空気の作品が今はほとんどないから…… だったんじゃないかな……
別に年をとったから演歌や時代劇が好きになるんじゃないんですよ。ああいうの好きだったシニアは若い頃からそれらが好きだったんですよ。老人向けコンテンツってことじゃないんですよ。もし今、新作大型時代劇がyoutubeで覇権とったらシニアがこぞってyoutube見始めてイキイキし出すんじゃないかなあ。
一線の漫画家ってのは時代に合わせていろんなものをアップデートしています。けれど一般人っていうのはそれができないままで、「60歳の人間は60歳なのではなく40年前の20歳」として考えろ、みたいな論もあります。マーケティング論だったかな。
でもってDr.STONEの原作、作画は両方ともこれなんですよ。アプデがされてない。それが一定の人間を引き寄せた理由であり、また離れる理由でもあるでしょう。
逆にすごい若いかたもちらほらいらっしゃいますが、八十年代カルチャーが好きで絵柄も当時の作風を真似してる二十代とか90年代に若者に60年ごろのヒッピー文化が流行ったりね、そういうのいつでも一定数いますからね。
この、「古い気配」を認識してた人がどのくらいいたんだろう、いるんだろう、と思います。それとも「古かったあの頃」を知らないと、新しいものに見えるんでしょうか。
この古さの認識の有無が「人魚絵師現象(私が今ここで命名しました)引き起こしているように感じます。
Dr.STONEを覆う平成初期のハードボイルド構造
こんな記事書いてしかも有料にしてる理由のコアみたいな話がここなんですけどね、石って昭和後期、せいぜい平成初期のハードボイルドものの構造と空気が強いんすわ。ニコチンがべったりしてるタイプのね。
自分自身の青春時代に憧れたもの、まあつまり20年、30年前からアップデートできてないおじさん、ではなかった、2、30年前の20歳たちが出す「めっちゃ若者向けでイケてる」と思っているもの、です。
千空の実家? と思われる部屋はのび太の部屋に近しく、2016年の小学生の部屋とするには乖離があります。その父親の憧れが赤いスポーツカーであるのも同じなんですよね。時空がずれてる。2、30年ほど。赤いスーパーカーの流行は1970年台中盤です。原作者の子供時代に父親が憧れていたもの、という時期にぴったり一致しますね。
さて、その時代の少年青年の憧れ、昭和末期および平成初期のハードボイルドものについてです。
これはもともと海外の探偵小説の流行を受けて発展したものだそうですが(なお本場の探偵小説かっけえけど日本人がロンドン書いたらなんかあれだよね、よーし江戸時代にしよう、で作られたのが鬼平犯科帳だそうですいつの時代も悪魔合体は起きてる)、昭和のハードボイルドにはだいぶ男尊女卑、トロフィーワイフといった存在が多く出現します。
昭和ハードボイルドというものはいわゆる昭和のなろう系とでもいう存在で、主人公に感情移入して男性的ないろんな気持ちよさを得る娯楽小説です。
これらのテンプレキャラにDr.STONEをあてはめると、いろんなことが腑に落ちるのです。
ここから先は
¥ 1,000
サポートいただいたお金は本代になります! たのしい本いっぱいよむぞ
