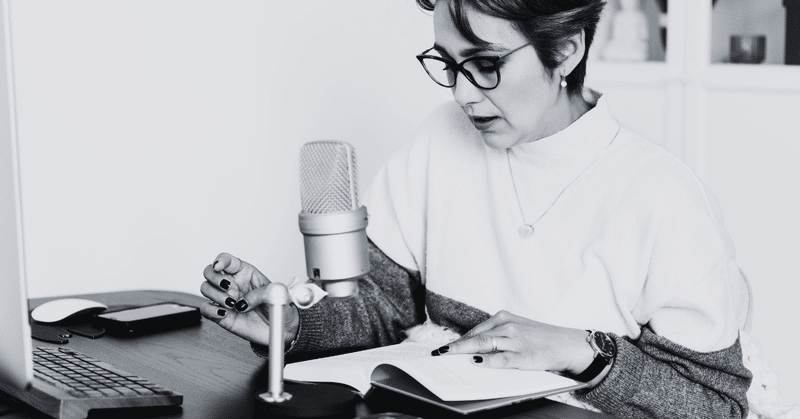
お宮参りに気をつけて~話し言葉はここに注意!~
自分で原稿を書いて、それを自分で声を出して録音する。YouTuberでもUdemy講師でも、そういうシーンはあるはず。映像ディレクターとしての40年近い経験から、話し言葉原稿の書き方と、録音の際の注意事項をまとめました。
👆上記をクリックすれば、定価4800円のところ1000円で購入できます
話し言葉と書き言葉はちがいます
ほとんどの人が書き言葉は学習していても、話し言葉の書き方というものを習得していません。
書き言葉で原稿を書いて、それを読んで録音するから、読みにくいし伝わりにくい。
原稿の段階から話し言葉を意識して書けば、読んで読みやすく、聞いて理解しやすいトークができるのです。
私はかつて「伝わる話し言葉の書き方」という動画講座の中で「ROSEの法則」という原則にまとめたことがあります。
しかし、ROSEの法則だととっさに思い出しにくい。
あらためて語呂のよい覚え方がないものかと思案していました。
そこで思いついたのが「お・み・や・ま・い・り」の6項目。
原稿の書き方と、読む時の注意が混じっていますが、これなら忘れにくいでしょう。
トークを録音しようとする人は(顔出しの有無にかかわらず)「お宮参りに気をつけて」とおぼえてください。
お‥‥音読で下読み
これは、読む時の注意事項です。
録音する前には必ず音読(声を出して読む)で下読みを行ってください。
冗談ではなく、原稿を書いてそれを録音するまで一度も声に出して読まない、という人が多いのです。黙読では下読みの意味がありません。
声に出して読むことにより、読みやすいかどうかはすぐにわかります。
読みにくい原稿は、たいてい声で聞いて伝わりにくいのです。
また原稿段階ではこれでよいと思っていても、声に出して読むと違和感がある、というケースも多いです。
これは、原稿が話し言葉として適切でないということを意味しています。
ですから、録音する前には一度声に出して下読みする。
これを習慣にしておいてください。
み‥‥みじかい文章を使う
これは原稿作成上の注意事項です。
短い文章、だと「短文」という言葉が思い浮かびます。
むしろ単純な構造の文章「単文」と思っていただいたほうがよいと思います。
単文というのは、「ひとつの事柄だけを伝える」文章です。
書き言葉の場合、単文をいくつも接続詞でつなげた、複文を使うケースが多いです。
たとえば
「私は弁護士で企業法務を専門としており株式会社マエカワの顧問弁護士をしている関係で前川氏とは以前より面識がありました」
という文章。これが複文。
これを単文にするとこうなります。
「私は弁護士です。
企業法務を専門としております。
株式会社マエカワの顧問弁護士をつとめています。
その関係で前川氏とは以前より面識がありました」
4つの単文に分解することができます。
話し言葉では原則として、単文を使うことを推奨します。
複文を使うとしても、上記のような多くの文章がつらなった複文ではなく、せいぜい2つの単文が接続詞でつながった文章にしてください。
耳で聞いた時には、そのほうが圧倒的に理解しやすいからです。
や‥‥やさしい言葉を使う
これも原稿作成上の注意事項です。
大人対象の録音だとしても、話し言葉の場合は書き言葉の場合よりずっとやさしい言葉を使ってください。
そのほうが伝わりやすいからです。
日本語には漢字が使われます。難しい言葉はたいてい漢字で書き表されます。この漢字が、意味のガイドになっているのです。
知らなかった単語であったとしても、漢字のひとつひとつに意味がありますから、単語の意味が推定できてしまうのです。
ところが話し言葉では漢字は伝わりません。
音しか伝わるものがないのです。
そうすると知らなかった単語は、まったく理解できないままになります。
さらに話し言葉は「通り過ぎていく言語」です。
わからない言葉があると、それを読み返すようなことができません。
結果的に理解できないままになってしまいます。
どのくらいやさしい言葉にすればよいのか、については私は「中学三年生に分かる言葉にしてください」と言っています。
中学三年生に分かる言葉であれば、大人は確実にわかるからです。
ま‥‥まちがえない言葉
これも原稿作成上の注意事項です。
日本語は同音異義語(同じ音で意味のちがう言葉)が多い言葉です。
そのため、耳から聞いただけではどの意味か、パッと理解できない言葉が多いのです。
書き言葉なら漢字で書き表しますから、区別がつきます。
しかし、声で聞いた場合には、そういうわけにはいきません。
ふだん使っている言葉でも、声だけで伝わるかどうか、今いちど見直してみてください。
一瞬でも「どちらの意味?」と疑問が浮かんでしまう言葉は、別の言葉に置き換えたほうがよいでしょう。
同音異義語だけでなく、たとえば数字の「一(いち)」と「七(しち)」のように混同しやすい言葉は多いです。
「しち」の代わりに「なな」と言い換えるような工夫も必要になることがあります。
い‥‥息継ぎをしっかり
これは読む時の注意事項です
声を出すという行為は、肺の中に吸い込んだ空気を少しずつ外に出しながら、声帯を震わせるということに他なりません。
肺の容量には限りがあります。
ですから一度息を吸い込んだだけで、原稿全部を読めるわけではありません。
適切なタイミングで息継ぎをする必要があるのです。
録音する時の注意として、文章の終わりまでしっかり声を出す、ということがあります。
録音に慣れていない人は、話しはじめはちゃんと声が出ていても、文章の終わりに近づくとだんだん声が弱くなります。
文尾(文章の最後)ではほとんど声が出ていないこともままあります。
意識して文の最後まで一定の声を出すようにしていただきたいのです。
そのためにはしっかりと肺に息を溜めておく必要があります。
息継ぎをするタイミングは、段落の終わりに合わせるとよいでしょう。
段落の終わりは少し間をあけるのがふつうなので、息継ぎに適しています。
り‥‥リズムよく読む
これは原稿作成の時、読む時、両方にかかわる注意事項です。
耳から聞いて伝わりやすい言葉には、一定のリズムがあります。
このリズムをうまく作ることが、原稿作成上も求められます。
また読む時にも、そのリズムに乗って声を出すことが必要です。
「み」の項目で「みじかい文章」としたのは、文章が短いほうが、このリズムをとりやすいからでもあります。
また、文尾(文章の最後)を同じ「‥です」などだけにせず、さまざまな締め方を混用したほうがリズムを作りやすいと思います。
「‥です」「‥です」「‥です」同じ文尾がならぶとリズムが作りにくいです。
「‥です」「‥といわれています」「‥なのです」「‥と思いませんか?」など、さまざまな文尾を混用することによって、よりリズムが作りやすくなります。
原稿を作りながら、下読みをくり返して、よりリズムよく読めるように工夫していくことが必要でしょう。
読んでいてリズミカルに読める文章は、聞いていても伝わりやすい文章です。
お宮参りに気をつけて
口から先に生まれてきたような人は除いて、あまり「話して伝える」経験を積んでいない人がいきなり録音に挑戦すると、失敗することが多いです。
それは「話し言葉」で原稿を書いてみることで修正することができます。
動画教材を作成する時、YouTubeのトーク録画をする時、ポッドキャストやVoicyなどの音声コンテンツを録音する時など、話し言葉で伝えようとする時は「お宮参りに気をつけて」と覚えましょう。
👆オンラインスクール朱雀スタジオでの私の先生ページです
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
