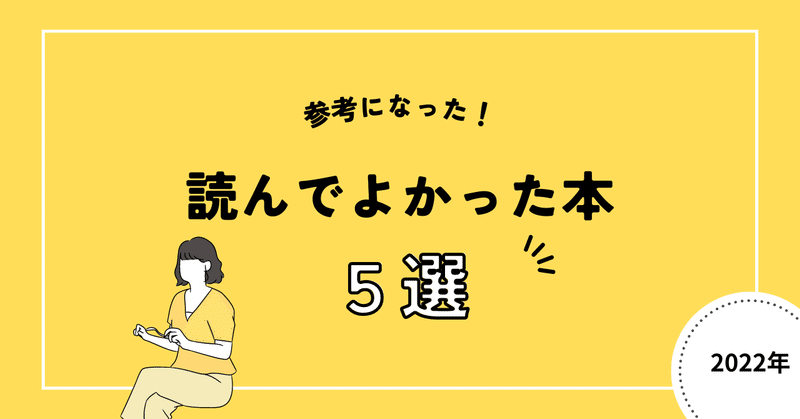
2022年 読んでよかった本 5選
2022年は仕事でのメインの役割がエンジニアからプロダクトマネージャーに変わったこともあり、エンジニアリング領域以外の多くの本も読みました。冊数が全てではありませんが、2022年中は約195冊の本を読んでいました。(仕事はしっかりしていました笑) このnoteでは約1年間で読んだ本のうち、仕事領域を問わないでためになった本5選を紹介したいと思います。
①ゲーマーズブレイン
ゲーム作りのための実用書として書かれている本ですが、現代のゲーミフィケーションが必要なtoCビジネスにおいてはかなり応用できる部分がある本だと感じました。認知心理学と脳の仕組みをベースに、どのようなゲームが売れるのかが書かれていました。企画を考える人やプロダクトマネジメントをする人にとっては特に読んでおいてためになる本だと確信しています。特にChapter 6の動機づけから得られるものは多く、次に紹介する本を読む理由にもなりました。
②動機づけ研究の最前線
子どもの教育、サービスへのオンボーディング、社員のモチベーション向上、自分のモチベーション維持など、全てのアクションに"動機"が必要であり、その動機づけメカニズムがどのように働いているか、そしてどのようにすれば操作できるのかなど、動機づけの研究について1冊でかなり丁寧にまとまっている本でした。2020年ごろに購入していた本で積読をしていたのですが、1つ前に紹介したゲーマーズブレインに触発されてついに完読しました(笑) 今後も見返すことが多くなりそうです。
③問いの立て方 + 問いこそが答えだ
これは2冊セットで読むが良いと思いました。仕事で、最大限の成果を円滑に出すためには「問い」が大事であるということはよく言われていますが、そもそも「問い」が何なのかを論理的に理解できるのが1冊目です。ケースバイケースの具体的な問いの立て方については安宅さんのIssueから始めよや、安斎さんの問いのデザインなども面白かったのですが、個人的には2冊目に紹介した問いこそが答えだが最も面白かったです。論破するための問いも大事ですが、ブレイクスルーした発想を得るためにも問いは大事だなと改めて感じました。
④バカと無知 + 無知の科学
恥ずかしながら、これらの本を読んだのは自分がバカだなと思うことが増えたからです。周囲に優秀な人が多く自分が無知だということを日々痛感しています。これらの本は、「バカは多くのことを知っている理解しているという 知識の錯覚 に陥っている」ということについて書かれています。わかっていないことがわかっていないと言うためには、何を分かっていないのかをしっかりと理解できることが第一歩で、それを恥だと思わないことが大事だと感じました。2冊目の方が読みやすかったのですが、1冊目の橘さんの言い回しが個人的には好きだったので2冊紹介をしています。「知らないことを知らないと言えない」「知れないことをすぐに知ろうと行動できない」と感じる人にとっては面白い内容かと思います。
⑤幻覚剤は役に立つのか
これは完全に娯楽本です。2022年冬ごろに 家業の関係で Bangkok で開催された HEMP EXPOに出展・参加していました。(会場はマリファナの匂いが凄くて頭が痛くなりました笑) この本はLSD(リゼルグ酸ジエチルアミド)などの幻覚剤と脳の関係について事例を踏まえて書かれており、日本にいたら絶対に知ることが出来ないような世界を知ることができる1冊でした。厨二なところがあるので、アシッドトリップというワードに一時期ハマっていました(笑) ここ数年、日本でもCBDビジネスが流行っていますが、より本質的なところに目を向けれる一冊だと思います。面白い文章なので案外サクッと読める内容になっています。Youtubeを見る代わりに是非!
5選には入れなかったものの、同世代の日本人に読んでほしい、(多分)ワクワクするような本を一部共有させてください! (読んで面白いと思ったら弊社に合うと思うの声かけてください…笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
