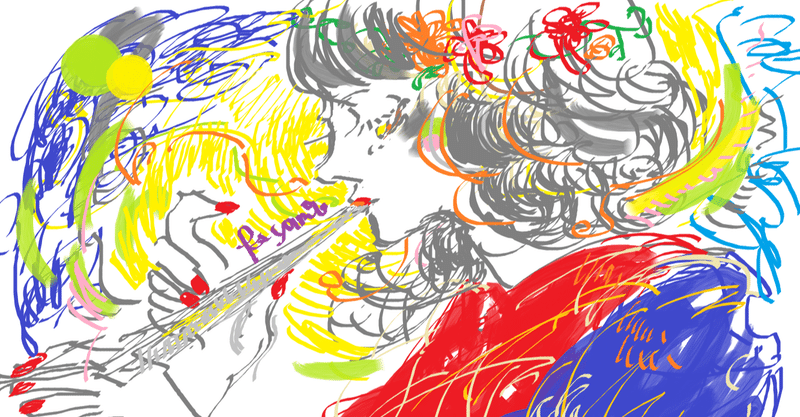
虚船より、フラジオレットを吹く天使へ
聴こえていますか。
私が宇宙に放たれて一体どれほどの月日が経っただろうか。「どれほど」と多くの時が経っているわけではないような気もするけれど、今はなんだかノートに記した正の字を数えてみる気にもならないのだ。私はここ数日由来のわからない倦怠に襲われている。
私の文体の変化に気づいた読み手はいるだろうか。際立った意味はない。ただ、私のこの随筆が「記号」に変化して、それだけの時を旅して故郷の青い惑星に辿り着くのか、そして一体どれほどの人々に読まれるのか。出航して間もない頃は、私のこの文章が、書店に陳列されてベストセラーとなり、故郷に残してきた両親弟妹に莫大な印税が入ることを想像して、柔らかく暖かな語り口を意識してみたりしたけれど、熟考せずともこの異端の罪人の文章がそのまま人々の目に触れることなどありえない。そのような機会に恵まれたとしても、幾度の推敲の末、まったく別の物に成り代わってしまうに違いない。しかし、許されるのであれば、この随筆が出版され、幾分かの利益を生んだとしたら、善良な私の両親、妹、弟にその分け前を与えて欲しい。彼らは、本当に優しく、純粋で模範的な市民なのだから。
どうでもいいが、読み手は私の性別をどのように意識しているだろうか。孤独な遊泳のため、私は随分前から私の肉体的な属性についての関心を失ってしまった。
さて、ようやく今回の本題に入ろう。直近の睡眠の前に私は船の書庫で数冊の美術カタログを見出した。(恥を忍んで告白するが私は、書籍をカテゴリーごとに整然と陳列する能力をほとんど持ち合わせていないのだ。)私は地方都市で古書店の開く以前は、故郷の島国の首都の大都会で働いていて、仕事を早めに終えることができた日は、環状線に飛び乗って美術館、博物館や劇場の建つ恩賜公園へ行って夜間観覧を楽しむことを趣味としていた。日を落とした夜の公園で、低めに設置された浮世絵モチーフの灯篭の淡い光と、それに照られ、逆光で真っ黒になったまばらな人影が揺れる様に、私はベアトリーチェの手に惹かれているような気分になったものだ。
忘れられない絵画というのか数点ある。私は本当に幸せものだ。ホドラーの『オイリュトミー』の点々と続く命の明滅を彷彿とさせる老体のリズムや、ヴァロットンの生物を思わせるあまりにも即物的な灰色の女体だとか。詩的な印象を脳裏に戦慄に刻んだ作品もあれば、ただ、その美しさで私の語彙をことごとく奪っていった作品があったのだ。
私は今の宇宙遊泳の生活にほとんど満足しているが、無念を挙げるとすれば私の心を奪った圧倒的な「青」との再会が叶わなくなってしまったことだ。それはどれほど前ことだったか。記憶が不鮮明なことは、最初に断っておく。もしかしたら私がその天使と出会ったのは、例の恩賜公園ではないかもしれない。それほど、強烈な出会いだったのだ。その他の情報が霞んでしまうほどに。
その青の天使はバーン=ジョーンズに生み出された。『フラジオネットを吹く天使』と名付けされている。絵画にはその背景、描かれたモチーフの物語を知ることで、より濃厚な味わいを与えてくれるものもあるけれども、その天使は何の説明も必要としなかった。窓枠の外、憧れの彼岸の青を吸い込んだ羽、そこに滲む神々しい金色。天使の纏う赤が複雑なの濃淡を引きながら滑る優美。それを目にした私は、その場から動くことができなくなってしまった。混雑した展示会では流れるように作品を右から左へ移行し、十分に吟味する時間を与えられないことも多いが、会期の終盤の夜間観覧では来館者はまばらなため、時間の許す限り気に入った絵画と対面していられるのだ。私は、数歩下がって距離をとってみたり、右に、左へ移動してあらゆる角度からその天使に見入った。どこから見ても、最後に吸い寄せられるのは、観れば観るほど遠のいていくような「青」だった。
そうして私はそれほどまでに「青」に惹かれたのか。
「星流し」の私は、未だ故郷の惑星を臨める距離にあって、かの宇宙飛行士が知らしめたことで世界中の羨望の的となった「青」をいつでも見ることができるのだ。それでも私が願って止まないのはもう観ることの叶わない、『フラジオネットを吹く天使』の「青」なのだ。
私たちの眼の水晶体は青を眼にすると遠いところを見るときのように収縮する。そしてそれは美しいものを見る時の状態とも似ているそうだ。「永遠の憧れ」とも名を打てる青の強烈な引力はそれが、遠く離れていけばいくほど原初の秘密を孕んだ深淵を匂わせて、私たちの眼を引き付ける。手の届かないものに焦がれるのは、古今東西人間の性というものなのか。私は誰もが見たくてたまらない「青」をいつだって眺めることができるというのに。
ここまでで私は一度ペンを置いて食事を摂ることにした。塩むすびの入ったパウチを手に取り、開封すると瞬時に乾いていたおにぎりが炊きたての白米のように膨らみ、温かい湯気立てた。それは塩加減も丁度よく、米粒の間に適度に空気が含まれていて、それは理想的なおにぎりだった。けれども、私が口にしたかったのは母が大量の塩をまぶして固く握った、それでいてその形は何個握ろうともぶれることなく均等に整ったあのおにぎりだった。舷窓から青い惑星を眺めながら米粒ひとつひとつを味わうように噛んでいると自然と涙が出た。
私は、どうやら郷愁に憑かれていたらしい。どんよりとした倦怠の原因もこれだろう。「星流し」というロマンティックな言葉に乗っかり、忘れようとした感情が雪崩れ込むようだった。それでも私は許されて「生きること」と「綴ること」をこの命の限り味わい尽くため、その感情に潰されるわけにはいかないだ。
固く眼を閉じる。目蓋の真ん中の黒点から逃れるようにチカチカを色彩が逃げていく。それでも私はその黒を凝視した。その果ての果てに視野を延々と伸ばしていくように。
眼の筋肉が引き攣るような痛みと共に、その果てに天使の「青」を見た。遠く遠く彼岸を覗き見ようと、薄くなった水晶体が私が焦がれた美しい青を捉えたのだ。
私はすっかり落ち着きを取り戻した。再びペンを取ることができた。そしてこの文章を書いている。二度と眼にすることはできないとかと思われた郷愁の青は、私の深淵、果ての果てに確かに存在していて、少しの集中力があればいつでもそこに辿り着くことができることがわかったから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
