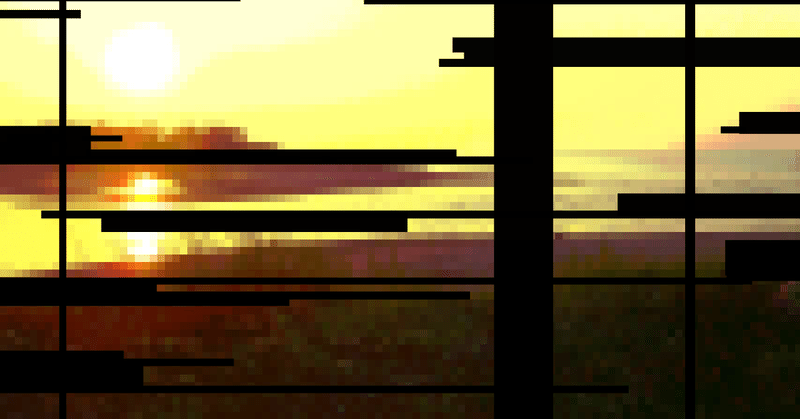
#9 サニー 1
1
桜の花びらが散って地面に染みをつけていた。
土曜日の朝、僕が目覚めて最初に行ったのは、ベランダの窓を大きく開ける事だった。
「うん」
嬉しさに思わず声を上げた。晴天だった。
爽やかな雨上がりの風が僕の髪を巻き上げる。最高の天気だ。家屋と家屋の間に切り取られた小さな青空は、熟練の職人が作り上げた精巧なガラス細工みたいで、きらきら光って今日一日の仕事が上手くいくような気分にさせてくれた。
僕は腕を宙に大きく上げて伸びをする。
気分がいい。
僕の隣には机に乗った小さなサボテンがあった。
「おはよう、サニー」
僕は彼女に朝の挨拶をする。サニーは僕にとって大切な友人だ。彼女(あるいは彼)は、深緑の肌を湿らせ、点々と生えたとげは美しい円錐状を保っていた。彼女はいつも通り、両手に収まる小さな鉢に、ただ存在していた
「今日は大切な日だ。サニー。忙しい一日になりそうだよ。やる事は盛りだくさんある」
サニーに話しかけながらデスクに座る。ワンルームの住居は部屋は布団と机だけでその面積の半分を埋めてしまうほど小さな仮住まいだったが、それでも今は僕の大切な場所だ。
しかしその居場所も明日中には出ていかなきゃいけない。
「まるで小学生に戻った時の気分だよ。確かあの頃の遠足の前日というのは、こんな気分だっただろうね」
サボテンのサニーは相変わらずの寡黙さだったが、僕は気にしなかった。身支度という事なのに、僕の気分はとてもうきうきとしていて晴れやかな気分だったのだ。
僕はデスクの上にあるチェックリストに手を付けた。兎に角今日はやる事が盛りだくさんなのである。
チェックリストに書かれている順に、僕は作業を始めた。
まずはシャワーに入る事である。カラスの水浴び場のような小さいユニットバス、僕はそこに入って身体を清めた。最後に身体を洗ったのはいつぶりだっけ、と思いながら全身を洗い、洗いたての綺麗なバスタオルで身体を拭く。清潔な下着と服を着て、しっかりと髪の毛を乾かす。そうしているうちに僕は、まるで自分が生まれ変わったかのような清々しさを感じる。
一連の作業を終えると腹の虫が鳴き始めた。僕は鼻歌を歌いながらキッチンに入る。冷蔵庫の中は少々のものしか入ってない。卵が二個、半端に残ったウィンナー三本、ケチャップにサラダ・ドレッシングと何年前に買ったか分からないような秋刀魚の缶詰、それからビールが何本か。しかし食材が少ないのは好都合であった。冷蔵庫の中身を空にするのも、僕のするべき作業の一つである。
僕はフライパンを二つ同時にIHに載せて、電源を入れる。フライパンを温めてる間二つの卵を器に開けて菜箸でとき、一方のフライパンにウィンナーを落とす。もう一方のフライパンにはこれでもかと油を垂らし、溶き卵を投入してこちらも炒める。どちらも塩コショウで味付けをする。じゅうじゅう、と物が激しく燃える。その音のさなか、スマートフォンから音楽が流れている。Josh TurnerのアルバムHometown Girl。
トーストが焼きあがった所で、ウィンナーとスクランブルエッグも同時に完成した。皿に盛って、トーストにはいちごジャムを、スクランブルエッグにはケチャップをかける。インスタントコーヒーを淹れて、果たして僕は食事に移る。
ウィンナーもトーストもスクランブルエッグも、全てとても美味い。
ゆっくりと平らげる最中、パソコンモニタに映るyoutubeを時折ちらりと観る。モニタにはアニメーションのような女性キャラクターが黄色い声を上げていた。テレビも点けていたが、そこでは芸能人が二股で浮気をしていたというゴシップを流していた。
僕はゆっくりと食事をする。
スクランブルエッグを食べ終わった頃には、youtubeの動画はシベリアンハスキーが散歩をしているホームムービーへ、テレビでは夫婦のセックスレスの悩み紹介へと移り変わっていた。ごちそうさま、と言うと僕はどちらも閉じてしまう。それらは僕の人生に決して交わる事のない、遠くの国の物語のように見えたのだ。
コーヒーを啜りながらチェックリストに再び目を通す。次にやるべき事は荷造りであった。僕は皿をすべて水桶に突っ込むと、重たい腹を動かしその作業を開始した。
布団を取り出して折りたたみ、服も全て取り出す。用意していた段ボールを箱状に組んで、それらを片っ端から放り込んだ。どちらも時間はそれほどかからない。僕は元々ファッションには興味がない方だったから、服は数種類しか持っていない。季節は春で、衣替えはまだしてなかったから夏用の服は全て片付いている。僕は既に着なくなった一種類だけのコートや、数種類のセーターやカーディガン、何本かのジーンズ、下着を全て片付けた。それだけで、服の身支度は全部終わってしまった。
次は本や書類をまとめたり、廃棄したりする作業だった。これも、時間はそれほどかからなかった。一つだけある本棚は、そのほとんどのスペースを持て余していた。僕は、基本的に本を買う時は、電子書籍として買うようにしていたからだ。手元のタブレットの中には、千冊以上もの書籍があるが、実際の本棚には、昔大学で使った技術書、それから人に貰った本が数冊あるだけだ。そればかりか紙類というもの自体も、僕の部屋にはほとんどなかった。
残っているのは今後も大切にするべき書類だけだったが、僕は迷わずゴミ箱に捨てた。アパートの契約書、余った履歴書、パスポート、印鑑……全てを捨てた。僕にはもう不要なものである。
結局、パソコンとサニー以外は、全てゴミ袋に放り込む形となった。
机の中には大量の薬以外何も無い。
次の住人が使えそうな家電類やプラスチックのケースは、中身を空にしたあと放置する事にした。机やハンガーなどもそのままにする事にした。処分はどうせ大家に頼むのだ。必要ならば次の住居人に渡してくれればいいし、そうでないならばらばらに分解してくれればいい。
シャンプーなどの生活用品は全て廃棄した。
最後にまとめた段ボール類と大量のゴミ袋を押し入れにしまった。
こうして僕の小さな住処は、少々の痕跡があるものの、何もない状態となった。引っ越ししたばかりみたいに部屋が広くなってしまい、それを見ていると僕は自分が持っていたもの全てが失われてしまったみたいに感じた。喪失感、寂寥感……。
――休憩もかねてデスクに座る。片付けたばかりのデスクの上には、チェックリストとサボテンのサニーだけしか残っていない。僕はサニーを慎重に撫でながら、チェックリストの次の項を見た。
・大家と家族に遺書を書く
了解、と僕は過去の自分に言った。自殺する為にはどうしても遺書というものを書かなければならないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
