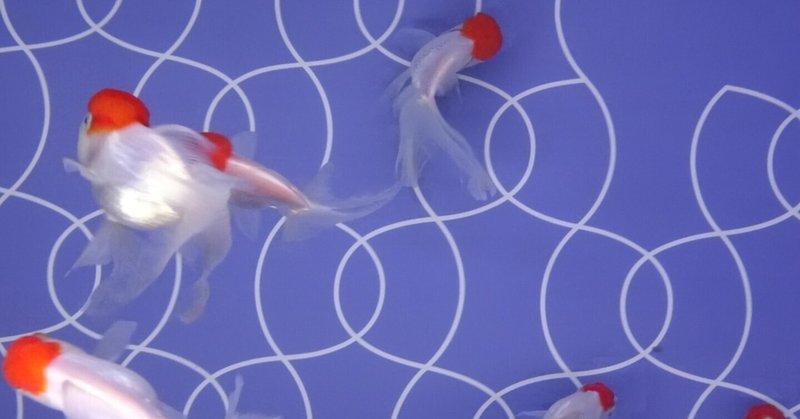
短刀取と懐剣術(上)
短刀取及び懐剣術に関する鶴山先生のメモです。
植芝合気道の五教に短刀取がある。ただし、養神館にはこの五教(第5か条)と称する技がない(懐剣掴み横面打1か条のような技はあるが…)のが不思議である。
さて、短刀とは刀身の長さが1尺(30cm)以下の日本刀の総称であるが、その拵(こしらえ:刀剣の外装・刀装のこと)に鍔(つば)が付いていないものいう。いわゆる合口拵(あいくちこしらえ)のことで、匕首(ひしゅ)・懐剣・鎧通しがあり、九寸五分(約29cm)とも呼ばれる。断ち切るための太刀・刀に対し、刺突(しとつ)用として刺刀(さしがたな)とされるものである。
五教単刀取の原形は、江戸柳生系合気柔術の教外別伝の懐剣術にある。この一部を短刀取と称して組み込んでいるが、五教では短刀を逆手に持つ(懐剣の持ち方)のであるから、刀身の分類からいえば、確かに短刀ではあるが、武術的な用法やそのルーツからすると懐剣取なのである。
短刀は、大正時代にその全盛期を迎えた。ヤクザや右翼が好んで用いた武器であった。斬るより接近(体当たり)して刺すのである。こんなところで本来の使い方が有名になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
