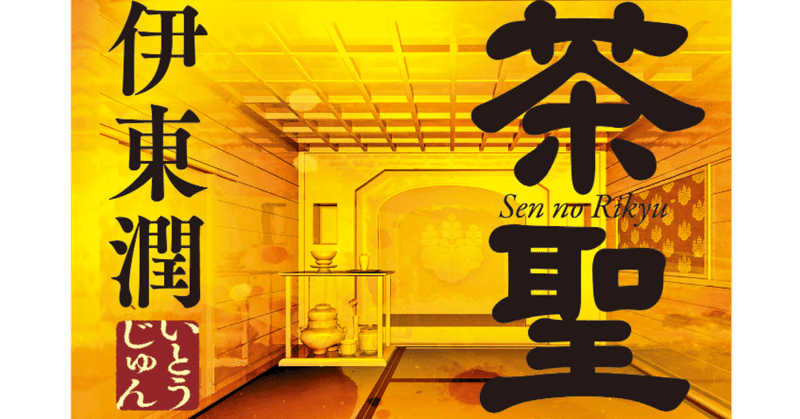
新作歴史小説『茶聖』|第一章(五)
真の芸術家か、
戦国最大のフィクサーか――
安土桃山時代に「茶の湯」という一大文化を完成させ、
天下人・豊臣秀吉の側近くに仕えるも、
非業の最期を遂げた千利休の生涯を、歴史作家・伊東潤が描く!
新作歴史小説『茶聖』。
戦場はたった二畳の茶室――。
そこで繰り広げられる秀吉との緊迫の心理戦。
門弟となった武将たちとの熱き人間ドラマ。
愛妻、二人の息子たちとの胸に迫る家族愛。
発売直後から話題を集め、早くも二度の重版がかかるヒットとなっている本作の試し読みを、noteにて集中連載いたします。
第一章(五)
天正十一年(一五八三)閏正月五日、山崎宝寺城の山麓にある妙喜庵という寺の境内に造られた茶室で、初めての茶会が開かれた。蘇鉄の茂った内露地を経て、簀戸でできた撥木戸をくぐってきた秀吉は、蹲踞の傍らで頭を下げる宗易に一瞥もくれずに言った。
「この座敷(茶室)は、やけに小さい気がするが」
「仰せの通り。中は二畳敷です」
「何と、さように狭いのか。そんなところで茶事などできるか」
秀吉の態度はよそよそしく、これまでのように対等な関係ではないことを主張しているかのようだ。
「まずはこれへ」
宗易が蹲踞を示すと、秀吉は不審そうな顔をしながらも、それに従った。
「手水鉢はないのか」
「はい。数寄屋風の茶室でも、以前は貴人用の手水鉢と供人用の蹲踞の双方がありましたが、新たな趣向として蹲踞一つにしました」
「ということは雪隠も一つにしたのか」
宗易がうなずく。
茶室に付随する雪隠は、貴人用の「飾雪隠」と供人用の「下腹雪隠」の二つがあった。だが空間に無駄が多く無粋でもあるので、宗易は一つにした。また露地も内外に区切らず、同一空間のように設えた。
秀吉は不満そうな顔で手を清め、口をすすいだ。続いて飛び石を踏み渡り、杮葺ぶきで切妻造りの茶室を見渡した。
「随分と侘びているな」
「はい。『新しき趣向を凝らしたものがよい』というご指示のほか何もなかったので、さようにいたしました」
「そうか。まあ、よい。で、この茶室の名は何という」
「待つ庵と書いて、待庵と──」
「何を待つ」
「新しき世でございます」
「そうか。ここで茶を点てながら新しい世を待つというのか。面白い趣向だな」
秀吉はからからと笑うと、面坪の内から右手に見える躙口を見つめた。
「これは何だ」
「客の出入口になります」
「この狭さは、どういうことだ」
その出入口は高さが二尺三寸(約六十九センチメートル)、幅が二尺一寸(約六十三センチメートル)ほどしかなく、秀吉のような小柄な男はまだしも、大男や肥満漢が入るのは容易でない。
「この躙口が、これからの茶事には必須となります」
宗易の言葉に秀吉が目を剥く。
「どういうことだ」
「羽柴様は、『一視同仁』という唐土の古い言葉をご存じですか」
一視同仁とは、「相手が誰であっても平等に見て等しく仁を施すこと」という意味だ。
「知らん」
漢籍や古典籍からの引用を、秀吉は極端に嫌う。元が武士でなかった秀吉は、少年時代にこうした教育を受ける機会を得られなかったからだ。
「わが師、武野紹鴎は『茶の湯は一視同仁』と仰せでした」
「それが、この狭い出入口とどうつながる」
禅問答のようなやり取りに、秀吉は焦れてきていた。
「この口から身を入れれば、身分や立場といったものを忘れ、誰もが平らかに(平等に)なります」
「つまり、身分の差といった俗界の決め事を捨てろと言うのだな」
「ご明察」
秀吉の頭の回転は、武士の中で飛び抜けている。
「それが、そなたの考える数寄というものか」
宗易がうなずくと、秀吉は「よかろう」と答え、素早く躙口に身を滑り込ませた。
亭主は躙口を使わないのが礼法なので、宗易は茶立口から室内に入る。
「ご無礼仕ります」
茶室に入ると、秀吉は五尺床の掛物を眺めていた。
「これは定家か」
「はい。藤原定家の手になる小倉色紙を飾りました」
色紙とは和歌、俳句、書画などが描かれた方形の料紙のことだ。色紙は模様や金銀箔などを散らしているものだが、宗易の用意した小倉色紙は薄茶色で、仮名文字で『拾遺和歌集』所収の恋の歌が記されている。
「いかにも草庵には、定家の色紙がよく似合う」
「これも師匠の教えの一つです」
宗易の師匠の武野紹鴎は、こうした草庵の設えをすでに考案していた。
「それにしても、二畳の茶室とはな」
秀吉が呆れたように笑う。
「これでも広いかと──」
「なんと、これで広いと申すか」
「はい。侘数寄には広すぎます」
「侘数寄か」
こうした間も、宗易は点前を進めていた。釜から上がる白い湯気が清新の気を室内に満たす。
「初めに確かめておくが、そなたらは、わしに賭けたと思ってよいな」
「もちろんです」
「嘘をつけ。別の者が権六にも誼を通じているのだろう」
権六とは柴田勝家のことだ。
──ここは嘘偽りを言わぬ方がよい。
宗易の直感がそれを教える。
「申すまでもなきこと。われら商人は、万が一ということも考えねばなりません」
「万が一、か」
秀吉が呵々大笑ようする。
「権六が天下を取れば、そなたらのような商人はたちまち行き詰まるぞ。そなたらが権六を操ろうとしても無駄だ。そなたらの話が分からんからな」
──その通りだ。
宗易ら堺衆にとって話の分かる相手、すなわち秀吉に天下を取ってほしい。だがそうならなければ、戦乱はいつまでも続く。
「さすが羽柴様、すべてお見通しですな」
「そうでなければ天下など望めぬ」
薄々は気づいていたものの、やはり秀吉は織田家の天下を簒奪しようとしていたのだ。
「そなたは、総見院様から『影になれ』と命じられていたな」
秀吉は、そのことも知っていた。
「よくご存じで」
「当たり前だ。出頭というのは主の意をいかに迎えるかだ。総見院様の側近く仕える者の一人や二人くらい籠絡せずに、出頭など覚束ぬ」
「恐れ入りました」
秀吉は信長の意を先んじて知るために、近習や女房から情報を得ていたのだ。
「総見院様のお考えは独特だ。あれだけ先を見通せるお方はいなかった」
「私もそう思います」
「そうか。それなら話は早い」
宗易が「不調法ではございますが」と言いつつ茶碗を置くと、それを手に取った秀吉は、喉を鳴らしながら飲み干した。
「うまい」と言うと、続いて秀吉は茶碗を眺め回した。
「これは見たこともない形をしておるが、唐土の天目か」
「いいえ」
「では、高麗の井戸茶碗か」
「さにあらず」
「では何か」
秀吉は答えや結論を迅速に求める。
「京の窯元に焼かせた手捏ね茶碗です」
「手捏ね茶碗だと。かように粗末なもので、わしを饗応するのか」
宗易が何も答えないでいると、秀吉が何かに気づいたように言った。
「もはや名物はないとでも言いたいのか。つまり総見院様と同じ手は使えぬと」
「お察しの通りです」
「そなたは『新しき趣向』の謂が分かったのだな」
秀吉が宗易をにらみつける。
「この茶碗がその答えです」
二畳の茶室内に、鉛のような重苦しさが立ち込める。
しばらくした後、秀吉が顔を上げた。
「これが、そなたの答えと──」
「はい。名物がなければ、名物を作るまで。今焼きの茶碗を、唐物や高麗物よりも高い値で取引できるようにいたします」
「そんなことができるのか」
「羽柴様が天下を取り、私の威権を高めていただければできます」
「そなたは何という大それたことを考えておるのだ」
しばしその細い顎に手を当てて考え込んだ後、秀吉が言った。
「やるか」
宗易は畏まると深く平伏した。
(続く)
------
**歴史作家・伊東潤新作小説『茶聖』絶賛発売中!**
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
