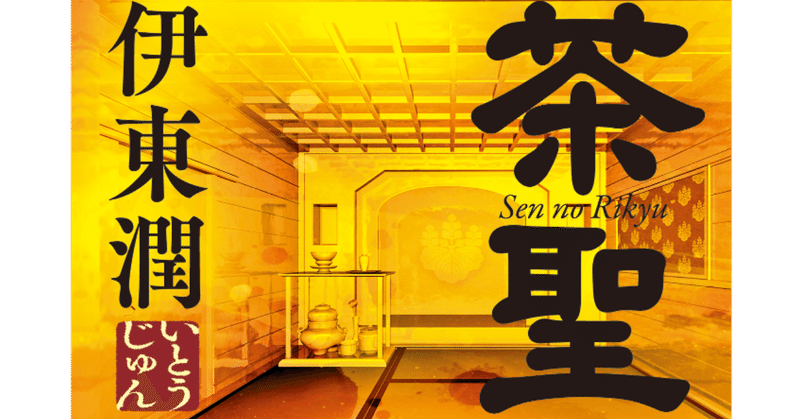
新作歴史小説『茶聖』|第一章(二)
真の芸術家か、
戦国最大のフィクサーか――
安土桃山時代に「茶の湯」という一大文化を完成させ、
天下人・豊臣秀吉の側近くに仕えるも、
非業の最期を遂げた千利休の生涯を、歴史作家・伊東潤が描く!
新作歴史小説『茶聖』。
戦場はたった二畳の茶室――。
そこで繰り広げられる秀吉との緊迫の心理戦。
門弟となった武将たちとの熱き人間ドラマ。
愛妻、二人の息子たちとの胸に迫る家族愛。
発売直後から話題を集め、早くも二度の重版がかかるヒットとなっている本作の試し読みを、noteにて集中連載いたします。
第一章(二)
天正十年(一五八二)六月十三日、備中国の高松城包囲陣から五十里余(約二百キロメートル)の道を五日半ほどで戻ってきた秀吉は、摂津国と山城国の境にあたる山崎の地で、謀反人の明智光秀を討った。世に言う山崎の戦いである。光秀は本拠の坂本城へと落ちていく途次、土民の槍に掛かって落命した。
この戦いで総大将を務めたのは、信長三男の信孝だった。だが誰の目から見ても、この勝利は秀吉あってのものであり、秀吉が天下人としての名乗りを上げたと認識した。
その後、清須会議で、それまでの本拠の長浜城を柴田勝家に明け渡した秀吉は、勝利の地・山崎に、新たな本拠として宝寺城を築いた。
その宝寺城で行われた戦勝祝賀の茶会に、宗易ら「天下三宗匠」と山上宗二が招かれたのは、山崎の戦いからおおよそ五カ月後の十一月七日のことだった。
「おお、皆そろっておるな」
秀吉が足取りも軽く現れると、宗易、宗久、宗及、山上宗二の四人が平伏した。
早速、四人を代表して宗久が祝辞を述べる。
「此度は謀反人・明智光秀を討滅したこと、まことにもって祝着至極。これにより宸襟を安んじ賜ることは必定で──」
なおも祝辞を述べようとする宗久を、秀吉が扇子で制する。
「堅苦しい前口上は要らん」
「ははっ」と言って四人が平伏する。
「どうだ。この茶室は」
宗及がすかさず答える。
「見事なものと存じ上げます」
「世辞は要らん。出来はよいが面白みはないだろう」
秀吉が周囲を見回しながら言う。
確かに武野紹鴎風の四畳半茶室だが、流布されている紹鴎茶室をそのまま写し取っただけで、作意らしきものは見当たらない。
「まだ城の普請(土木工事)が半ばなのでこんなものだが、そのうち風情ある数寄屋風の茶室を設えるつもりだ」
「どのようなものをお望みで」
宗久がおずおずと問う。
「新奇なものだな」
宗久と宗及が顔を見合わせる。
「それは、いかなる趣向でしょう」
「そうさな」と言いつつ、秀吉は顎に手を当て考え込んだ。
──とくに考えがあるわけではないのだ。
宗易はそう見抜いたが、相手は秀吉なのだ。どんな突飛なことを言い出すか分からない。
「総見院様の時代にはなかった新しき趣向を凝らしたい」
総見院様とは信長の法名「総見院殿贈大相国一品泰巌尊儀」を略したもので、その死後、そう呼ばれるようになった。
──そうか。すでに羽柴様は、総見院様の時代を消し去る作業を始めているのだな。
それが茶室にまで及ぶということは、秀吉の並々ならぬ決意が感じられる。
──つまり総見院様の遺児(信雄か信孝)か孫(三法師)を奉じて、新政権を輔弼するのではなく、自らが天下人となるということか。
宗易は秀吉の真意を読み取った。
「で、誰が縄張りする」
縄張りとは設計のことだ。
宗久や宗及と競い合うつもりはないが、新たな天下人である秀吉を思う方向に誘導していくには、自らが頭角を現さねばならない。
「よろしければ、私が──」
「ああ、宗易がやってくれるか」
秀吉が笑みを浮かべると、宗久がすぐに追従した。
「茶室の設えで宗易殿に敵う者はおりません。羽柴様の門出を祝う茶室を造らせるには適任かと」
宗及もすかさず付け加える。
「宗易殿は、われらと違って独自の考えをお持ちですから、面白き茶室ができると思います」
「そうか。楽しみにしておるぞ」と言うや秀吉が話を転じる。
「ときに、こうして『天下三宗匠』をわが茶頭に迎えることになったが──」
──そんなことは聞いていない。
だが誰も否とは言えない。
「これまで、わしの宗匠を務めてもらってきた宗二だが──」
四人の間に緊張が走る。というのも信長から指名されて秀吉の茶頭になった宗二は、秀吉との相性が悪く、これまで一度は職を辞すことを願い出、一度は勝手に堺に戻ってしまったことがある。それでも師匠の宗易のとりなしで、ここまでは事なきを得ていた。
「これを機に、わしの許から去ってもよいぞ」
その言葉を聞いた宗二は、無言で平伏した。
「どうだ。うれしいか、宗二」
「────」
「そなたは、わしを嫌っていた。そうだな、宗二」
それでも宗二は無言を通した。四畳半の茶室の中に氷のような緊張が漂う。
「だがな、わしが宗二を堺に帰すと言ったら、わが弟の小一郎が、『それなら、わが茶頭に迎えたい』と申すのだ。わしは『物好きにもほどがある』と言ったが、小一郎は『それでも構いません』と返してきた」
小一郎とは、秀吉の腹違いの弟の秀長のことだ。
「堺に帰るも、小一郎の茶頭になるも、そなたの勝手だ。好きにせい」
それでも宗二は、唇を真一文字に結んで何も言わない。
宗易は出番が来たことを察した。
「宗二、羽柴様に返事をせい」
「────」
それでも返事をしない宗二を、秀吉が揶揄する。
「師匠の問い掛けにも答えぬとはな。此奴はよほどの頑固者だ。思えばわしとの茶事の時も、問われたこと以外は一切答えず、黙って茶を点てておったわ。つまらぬ茶事だったが、総見院様の指名ゆえ、わしは任を解くこともできず下手な点前を見ておった」
思えば宗易も、この二十二歳も年下の弟子には手を焼いてきた。
天文十三年(一五四四)、山上宗二は、薩摩屋という商家の嫡男として生まれた。子供の頃から暴れ者として名を馳せ、その荒ぶる心を鎮めるために、父親は半俗の沙弥として寺に通わせた。だが宗二は持ち前の頭のよさを発揮し、十六歳の時、宗論で住持をやりこめて寺を放り出された。そこで父親は、理屈だけでは語れない茶の湯に親しませるべく、宗易に預かってもらうよう頼み込んだ。
初めて宗二を見た時、宗易はその猛き心の中にある才を見抜いた。それでも何度か断り、宗二が自ら弟子入りしたいと言うのを待った。一年後、宗二は頭を垂れて弟子入りを願った。
「何も言わぬでは、そなたの気持ちが分からぬ」
秀吉が不機嫌そうに言う。
「宗二、たいがいにしろ」
宗易が怒りをあらわにして言うと、ようやく宗二は膝を秀吉の方にねじった。
「小一郎様のお申し出、謹んでお受けいたします」
「そうか。それでよい。小一郎もさぞや喜ぶであろう。そなたも小一郎となら相性がよさそうだ」
小一郎こと秀長は温厚篤実な人物として知られ、その人柄を慕う者は多い。
それまで黙って事の推移を見極めていた宗久が口を開く。
「では、われら三人は、総見院様の頃と同じく廻り番で、ここに詰めればよろしいですな」
「ああ、そうしろ。だが新しい茶室ができるまでは、宗易が詰めろ。長くても半年だ。宗久と宗及は、茶会の時だけここに来ればよい」
宗久と宗及が平伏する。
「むろん宗易、茶室には新しい趣向を凝らすのだぞ」
「承りました」
「それから宗二よ」
秀吉が凄味のある声音で言う。
「わが弟を虚仮にしたら、わしが許さぬぞ。それだけは心得ておけ」
「はい」
「では、茶の湯を楽しむとするか。誰が点前をする」
宗久が「それでは、私が──」と言おうとした時、それにかぶせるような野太い声がした。
「ぜひ、それがしに」
宗二である。
「そうだな。これが惜別の茶事となるからな」
秀吉が手を叩くと、次の間に控えていた同朋が、台子を運び込んできた。
秀吉に聞かれないよう、宗易が宗二に耳打ちする。
「粗相のないようにな」
「心得ております」
その後、茶事が宗二の点前で行われた。宗二は大過なく点前を披露し、最後には秀吉から称賛の言葉をもらった。
(続く)
------
**歴史作家・伊東潤新作小説『茶聖』絶賛発売中!**
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
