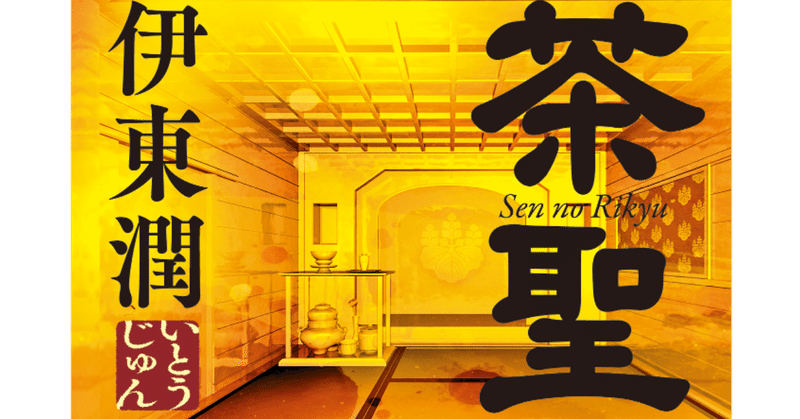
新作歴史小説『茶聖』|第一章(七)
真の芸術家か、
戦国最大のフィクサーか――
安土桃山時代に「茶の湯」という一大文化を完成させ、
天下人・豊臣秀吉の側近くに仕えるも、
非業の最期を遂げた千利休の生涯を、歴史作家・伊東潤が描く!
新作歴史小説『茶聖』。
戦場はたった二畳の茶室――。
そこで繰り広げられる秀吉との緊迫の心理戦。
門弟となった武将たちとの熱き人間ドラマ。
愛妻、二人の息子たちとの胸に迫る家族愛。
発売直後から話題を集め、早くも二度の重版がかかるヒットとなっている本作の試し読みを、noteにて集中連載いたします。
第一章(七)
宗易が風炉の炭を整える間、紹安はりきの用意した焼き魚、膾、汁物などに舌鼓を打った。
「義母上も料理の腕が上がりましたな」
宗易は何も答えない。
「とくにこの麩の焼きは見事だ。父上の焼くものと遜色ない」
紹安は「ごちそうさまでした」と言って一礼すると立ち上がり、いったん蹲踞で手水を使った後、再び茶室に戻り、床に掛かった掛物に見入った。
「この圜悟(宋代の禅僧)の墨蹟は最近買い求めたものですね。私がいた三年前には、お持ちでなかったはず」
「そうだ。そなたの妹が嫁いだ万代屋宗安から買った」
「ああ、あの御仁なら、かなり吹っ掛けてきたでしょうな」
紹安の笑い声を無視して、宗易が紹安の前に茶碗を置いた。
「では──」と言って、一服した紹安が顔をしかめる。
「父上の濃茶は実に苦い」
「そなたには、その方がよいと思うてな」
「さすがです」
紹安が不敵な笑いを漏らす。
「で、どこに行っていた」
紹安は生まれついて気性が激しく、これまでも幾度となく宗易と衝突していた。三年ほど前、些細なことから口論となって出奔したきり、堺には帰っていなかった。
紹安は茶碗を置くと、懐紙を取り出して軽く唇に当てた。
「此度は北陸から関東へと行ってきました」
紹安はこれまで二度ほど長い旅に出ていた。一度目は伊勢から紀州へ、二度目は西国街道を通って赤間関まで行き、九州から四国へと渡った。いずれも二年以上の長旅で、書状も送ってこないので、安否さえ分からない有様だった。
「ということは、柴田殿健在の頃に北陸を回ったのだな」
「仰せの通り。織田家の北陸衆は柴田殿の下、結束力では比類ないものがありました。しかしその結束が、一日にして瓦解するとは夢にも思いませんでした」
「それが武というもの。武に生きる者たちの結束は堅固に見えても、実はもろいものだ。武とは欲得と同義のようなものだからな」
「なるほど。父上らしいお言葉」
「その後は、どこに行った」
宗易は紹安のために茶を点ててやった。
「お心づくし、かたじけない」と言いつつ、紹安が喉を鳴らして飲む。
その顔を見ていると、堺の町を走り回っていた頃の紹安を思い出す。
「北陸から越後に抜け、上野から武蔵へと回ってきました。越後上杉家の兵は精強で、謙信には財力もあります。ただし玉薬の欠乏はいかんともし難く、もはや羽柴殿の敵ではありますまい」
かつて信長は、武田・上杉・北条といった東国の有力大名を討つ前の下ごしらえとして伊勢長島を陥落させ、伊勢湾交易網を掌握した。これにより堺から伊勢長島へと運ばれていた海外産硝石の流通が止まる。だが信長は、武田氏を滅ぼしたものの上杉・北条両氏を討滅する前に、本能寺で横死した。
「それでその後、北条領にも入ったのだな」
「はい。小田原には、父上もよくご存じの板部岡江雪斎殿がおります」
北条家重臣の板部岡江雪斎は、「宏才弁舌人に優れ、その上仁義の道ありて、文武に達せし人」(『北条五代記』)と謳われた傑物だ。とくに茶の湯への傾倒は著しく、北条氏と織田氏が同盟関係の頃は、よく上洛したついでに堺に顔を出し、宗久・宗及・宗易らと親密に交わり、その茶風を東国にもたらす役割を果たした。
「板部岡殿の厄介になりながら小田原で様々な話を聞いたのですが、三河殿は北条家との間に堅固な攻守同盟を結び、織田中将殿を担いで挙兵するつもりのようです」
三河殿とは徳川家康のこと、織田中将とは信長次男の信雄のことだ。
「そうか」と言って宗易が黙ったので、紹安は首をひねった。
「この話は、まだ秘事だと思っていましたが、すでに父上はご存じで」
「いいや、初耳だ」
「では、父上の立身にお役立て下さい」
「何だと」
宗易の胸底から怒りの焔が立ち上る。
「父上は羽柴様に取り入ろうとしていると、風の噂で聞きました」
「風の噂だと──」
「風は時として真を運びます」
「たとえ真だとしても、わしは己一身のために羽柴様に近づいているわけではない」
「では、何のために」
紹安が挑戦的な眼差しを向ける。
「この世に静謐をもたらし、人々が自由に行き来できる世を作るためだ」
「はははは」
紹安が手を叩かんばかりに喜ぶ。
「詭弁にもほどがありますな」
「詭弁だと!」
「そうです。それは建前にすぎません。父上は織田様の時もそうだったではありませんか。今井殿や津田殿と結託し、南蛮からもたらされた銅弾や玉薬をかき集め、織田様に献上していたのはどこの誰か、お忘れではありますまい」
「それがどうした。わしは──」
宗易が言葉に詰まる。
「父上の調達した玉で、一向一揆に加わった農民たちは命を失ったのですぞ。その中には女もいれば童子もいた。私は──」
紹安が言葉に詰まる。
「伊勢長島にいた時、織田様の攻撃に巻き込まれました。それでも命からがら逃げ出しましたが、すぐに捕らえられました。もしもその場に古田殿がいなければ、私も焼き籠めにされていたでしょう」
焼き籠めとは、人々を小屋に閉じ込め、戸口に板を打ち付けて脱出できないようにし、外から火をつけて焼き殺すという凄惨な処刑法のことだ。
「古田とは織部殿のことか」
「そうです。私は織部殿の姿を見つけて懸命に呼び掛けました。織部殿は私に気づき、救ってくれましたが──」
紹安が無念そうに唇を噛む。
「ほかの者たちを救ってはくれませんでした。あれだけ泣いて頼んでも、織部殿は──」
「そなたのほかは救わなかったと申すのだな」
「はい。織部殿は『われらは右府様の命を奉じているだけ』と仰せになり、乳飲み子を抱いた女まで、焼き籠めにしました」
──そうだったのか。
その時、織部の胸中に去来したものが何だったか、宗易には痛いほど分かる。
紹安の嗚咽が糸を引くように茶室に響く。
「紹安よ、それがこの世というものだ。こうした酷い世を終わらせるために、わしは戦っている」
「父上の戦いは、いつか無為なものになりますぞ」
「どうして、それが分かる」
「武人とはそういうものです。いかに羽柴様を操ろうとしても、最後は武人の本性が姿を現し、父上の命を奪います」
「たとえそうであろうと、わし一個の命で世の静謐が購えるなら本望というものだ」
「ご立派なことだ」
紹安の顔に冷笑が浮かぶ。
「私は父上のそうした一面が嫌いだった。父上は悪巧者(偽善者)にすぎません。本音を言えば、羽柴様の御用者(御用商人)として、もうけたいだけではありませんか」
宗易が色を成す。
「それもある。しかし商人が富を得ようとすることの何が悪い。世を静謐に導くことと、堺衆の繁栄は矛盾しない」
紹安が首を左右に振る。
「権勢を持つ者にすり寄れば、いつか大きな対価を払わされますぞ」
そう言うと、紹安は帰り支度を始めた。
「そなたは、これからどうする」
「はて、どうしますかな。白河の関を越え、奥羽の果てにでも行ってみようかと思います」
「さように遠くまで行くのか」
「はい。羽柴様の権勢と父上の威権の及ばぬ地まで赴き、心ゆくまで自らの茶を楽しみます」
「そなたは旅をせねばいられない男だ。わしも止めはせぬ。だが──」
宗易の声が強まる。
「そなたは、わしを超える才を持っている。いつの日か──」
「父上の代わりとなり、権勢を持つ者に取り入り、傀儡子のように操れと仰せなのですね」
傀儡子とは黒装束に身を固め、背後から人形を操る者のことだ。
「そうだ」
「それが嫌だから、私は旅を続けています。その仕事は少庵にやらせたらよいでしょう」
少庵と紹安は同い年になる。だが少庵は、茶の湯を習い始めたのが成人してからということもあり、その振る舞いから目利きまで、宗易の後継者になることは容易でない。
「それが無理なのは、そなたも分かっておるはずだ」
二人の男は対峙したまま、身じろぎもしない。わずかな松籟と茶釜の湯の煮え立つ音だけが、静寂を支配していた。
(続く)
------
**歴史作家・伊東潤新作小説『茶聖』絶賛発売中!**
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
