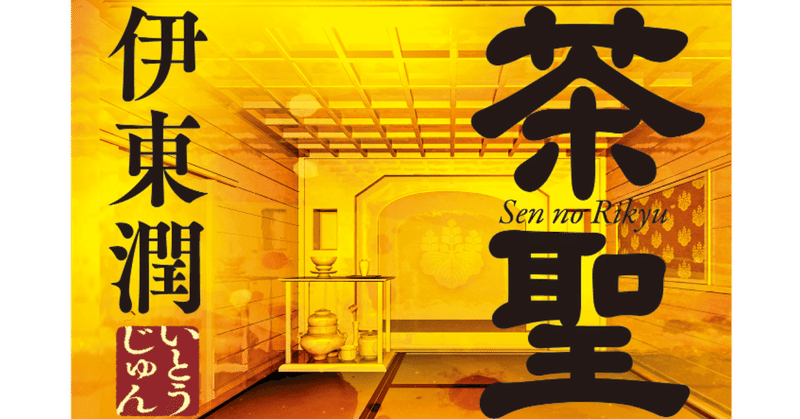
新作歴史小説『茶聖』|第一章(十一)
真の芸術家か、
戦国最大のフィクサーか――
安土桃山時代に「茶の湯」という一大文化を完成させ、
天下人・豊臣秀吉の側近くに仕えるも、
非業の最期を遂げた千利休の生涯を、歴史作家・伊東潤が描く!
新作歴史小説『茶聖』。
戦場はたった二畳の茶室――。
そこで繰り広げられる秀吉との緊迫の心理戦。
門弟となった武将たちとの熱き人間ドラマ。
愛妻、二人の息子たちとの胸に迫る家族愛。
発売直後から話題を集め、早くも二度の重版がかかるヒットとなっている本作の試し読みを、noteにて集中連載いたします。
第一章(十一)
月見櫓台の西側をすり抜けて仮設の門をくぐり、右に折れのある石段を下っていくと、芦田曲輪との分かれ道に出る。左に行けば、さらに石段が続いて芦田曲輪の門に突き当たる。
この曲輪は城内を警護する者たちの長屋と、道具類を入れる土蔵から成る殺風景なものなので、宗易は築地塀によって目隠しし、さらに築地塀の外側に植栽し、できる限り見えないようにした。
一方、芦田曲輪の方に行かずに直進して中木戸をくぐると、いよいよ山里曲輪だ。ここには古風な楼門を設け、ほかとは一線を画した空間に入ることを示すようにした。
山里曲輪はその名の通り、山里を城内に再現した異空間だ。門を入ってすぐのところは鬱蒼と茂る竹林にし、その中に露地を付けて飛び石を設けた。十間(約十八メートル)ほどの小路だが、来訪者はここを通ることで、茶の湯を嗜む心構えを徐々に養っていくという効果がある。
そこを抜けると視界が開け、饗応空間として設えた御広間に出る。ここには月見を楽しむ二階楼と四畳半の茶室が設けられている。
来訪者はここで食事をして振舞(宴)を楽しむ。御広間の前には池泉や四阿が造られ、周囲を回遊できるようになっている。さらに池泉からは小川を引き、川の屈曲や石の置き場所を工夫するなどして、常にせせらぎが聞こえるようにした。
となれば当然、門衛や貴人の供が待機する遠侍、台所、納戸などの建物も必要になる。そうしたものを極力小さくし、さらに瓦葺きにせず、風情のある檜皮葺きや柿葺きにした。
石を運ぶ威勢のいい掛け声が聞こえる中、宗易と少庵は、御広間の脇道を抜けた先の最も奥まった場所に足を向けた。
二人の着いた場所は、整地されているだけで夫丸一人いない。
──まさに市中の山居を造るには、申し分のない場所だ。
そこに建てられる茶室が完成した時の姿が、宗易の脳裏に浮かぶ。
「義父上、ここに茶室を築くのですね」
少庵の声によって目を開けた宗易は、何もない更地が眼前に広がっているのを見た。
「そのつもりだ」
「どのような茶室をお考えですか」
「田舎風の草庵だ」
「どれほどの広さのものに」
「二畳隅炉にしようと思う」
少庵は驚いたようだ。
「羽柴様は派手好み。かような小間に満足なされるでしょうか」
「茶室は小さければ小さいほどよいのだ」
「なぜですか」
「広ければ邪心が入り込む。茶室では、ひたすら茶だけに専心する。それ以外の用途はない」
宗易が、「床は四尺五寸、壁は暦張、炉の脇に洞庫を設ける」という構想を語っていると、背後に人の気配がした。同時に二人が振り向くと、そこに一人の男が立っていた。
「驚かせてしまい、すみませんでした」
その宣教師姿の南蛮人は流暢な日本語でそう言った。
「あなた様とは、幾度かお会いしたことがありましたな」
かつて宗易は、安土城で宣教師のために茶を点てたことがある。
「はい。イエズス会士のルイス・フロイスです」
宗易と少庵は堺に住んでいることもあり、南蛮人は見慣れている。しかもフロイスはポルトガル人なので、黒い髪と黒い目をしている。
「堺の千宗易です」
「同じく少庵と申します」
二人が名乗ると、フロイスは会釈を返してきた。
フロイスはすでに日本に滞在して二十年ほどになり、年齢も五十歳を超えている。
「今日はいかがなされましたか」
「城下に教会ができたので、石田様にお礼を言いに来ました」
「それは重畳」
宗易の脳裏に、三成のしたり顔が浮かぶ。
「十一月二十二日に大坂の教会で初めてのミサを行います。ぜひいらして下さい」
後に三之丸に包含される大坂城下の一角に土地をもらったイエズス会は、教会を建築していた。だが日本の大工たちが西洋建築など知るはずもなく、外見は寺院と何ら変わらなかったので、町の人たちからは南蛮寺と呼ばれることになる。
「こちらの仕事が予定通りに進んでいれば、顔を出すこともできましょう」
宗易はキリシタンになるつもりはないが、商いという点から宣教師たちとは良好な関係を築いてきた。むろん向後も、それを続けるつもりでいる。
少庵が首をかしげつつ問う。
「それにしても、どうしてこんなところへいらしたのですか」
「これだけ大きな城の普請は珍しいので、城内を散策していました。それで静かな方に歩いていくと、この場所に出たのです」
「ははあ、たまたまだったんですね」
少庵が納得したようにうなずく。
「はい。私も閑雅を愛します」
「カ、ン、ガ?」
「ええ、最近教わった言葉です」
宗易が笑みを浮かべる。
「西洋の方々は派手好みかと思っていましたが」
「仰せの通りです。ハライソ(天国)は輝かしい色彩に満ちています」
フロイスの顔にも笑みが浮かぶ。
すかさず少庵が付け加える。
「仏教でも、極楽浄土は極彩色に満ちています」
「そんなものはありません。あるのはハライソだけです」
宗易が鼻白みつつ言う。
「あなた方は素晴らしい宗教をお持ちだ。だが一つの神しか認めないのは、どうしてですか」
「それが真実だからです」
「この世は多様な考えからできています。他を受け容れることができなければ、争いが起こります」
「それがこの国の弱さです」
「いいえ、強さです。美は──」
宗易が軽く瞑目して言う。
「一つではありません。美は万物に宿るのです」
「それは正しい考え方ではありません」
宗易が首を左右に振る。
「あなた方とは最後の一線で理解し合えぬようだ。そうした考え方が、あなた方のしようとしていることの障害になるかもしれませんぞ」
フロイスが困った顔をする。
「つまり、いつか布教を禁じられる日が来ると言いたいのですか」
「それは分かりません。例えば天下人が、あなた方の宗教の敬虔な信者となれば、あなた方の信じるものが、この国の隅々まで広がるでしょう」
「その通りです。この国の民を仏教や神道といった邪教の頸木から解き放つことが、われらの使命なのです」
「そうした考えは改められないのですね」
「もちろんです。真実は一つだけだからです」
宗易がため息を漏らす。
「それでも私は負けません」
「どういうことです。まさか茶の湯が神に勝てるとでもお思いか」
フロイスの口端に冷笑が浮かぶ。
「笑いたければ笑いなさい。いかにも宗教と茶の湯は別物だ。しかしわが行く道を邪魔するなら、それなりの覚悟をしていただく」
「待って下さい」
フロイスの顔に戸惑いの色が浮かぶ。秀吉の覚えめでたい宗易の権威に逆らうことは、布教活動に打撃を与えるとわきまえているのだ。
「千様の茶の湯も、われらが目指すものも同じです。この国から戦乱をなくし、人々が安楽に暮らせるようにすることではありませんか」
「その通りです。お互い道は違っても、目指すところは同じです。しかしこの国の民の大半がキリシタン信者になっても、仏教寺院や茶室を毀つことは許しませんぞ」
フロイスの顔が引きつる。
「あなたは神と戦うというのですか」
「それは、あなた方次第」
「何と大それたことを──」
フロイスは天に向かって手を合わせ、何事か呟いている。
「決してわが領分に立ち入らぬことだ。さすれば共に栄えることができるでしょう」
フロイスは胸の前で十字を切ると、恐ろしげな顔をして去っていった。
いつの日かキリシタンが絶大な勢力を得れば、その排他性をいかんなく発揮し、仏神どころか日本固有の伝統のすべてを破壊していくのは明らかだ。
「義父上、キリシタンとは、げに恐ろしきものですな」
少庵が嫌悪をあらわに言う。
「ああ、耶蘇教は人の心を虜にできる。その目的は崇高だが、他を否定する宗門は、この国にはなじまない」
──空海と最澄以来、多くの俗人が入り込み、財を生み出す構造を築き上げてきた仏教には、もはや衆生を救う力はない。では、他を排そうとする耶蘇教にそれができるのか。われらは手を組めるのか。
気づくと日が陰ってきていた。宗易は自問しながら少庵を促し、その場を後にした。
(続く)
------
**歴史作家・伊東潤新作小説『茶聖』絶賛発売中!**
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
