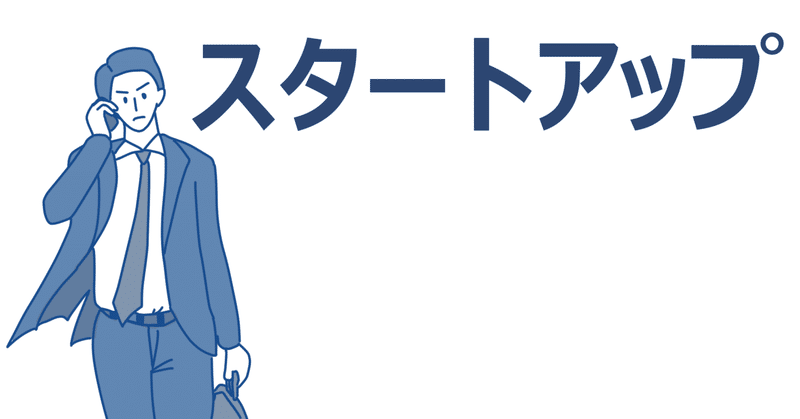
最近読んだ本-2024年4月後半 ー エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」
4月に入り、中小企業診断士試験合格の余韻も落ち着いたころ、大阪府中小企業診断士協会主催の新歓フェスタがあり、参加してきました。
このイベントは中小企業診断士になって1-2年の人達(私のような未登録者含む)へ、協会の取り組みや、協会内にある様々な研究会・イベントの紹介をする場となります。
参加してみると、タキプロメンバーや、実務補習で一緒だった方とも会え、懇親会含め有意義なイベントでした。(結果、5月より入会することとしました)
当日、タキプロの先輩かつ会社のOBの方に参加されている複数の研究会を紹介してもらいましたが、その内の一つで紹介されていたのがこの本でした。
この「エフェクチュエーション」という言葉自体初めて聞いたのですが、簡単に定義すると「起業家の持つ思考方式の一つ」であり、「企業時の不確実な状況に対して何ができ、誰と連携でき、どこまで損失が許容でき、かつコントロールが可能かという観点での意思決定」と理解しました。
ここでは下記の5つの原則が紹介されています。
手中の鳥:今、自分は何を知って何ができるか、誰とつながっているかの観点での検討
許容可能な損失:最悪の事態を想定し、損失可能な範囲で実行する
レモネード:不都合な結果もテコとして活用する
クレージーキルト:競合分析より自発的なパートナーシップを重視する
飛行機のパイロット:予測より「制御可能性」を重視する
この対義語は「コーゼーション」と呼ばれる、行動の前に可能な限り環境分析や最適な計画を立て意思決定を行う方式で、言わば「因果」を重視する考え方になると思います。
中小企業診断士2次試験や、今後取り組んでいく補助金申請の際の事業計画書づくりでも、環境分析や因果が重視されますが、これも「コーゼーション」の考え方に依るものと考えます。
一方、実務補習・従事で小企業経営者の方々とお話できる機会を持ちましたが、いずれも「この事業をやりたい」「お客様に喜んでほしい」という想いでスタートし、それを専門士業含めた周囲がサポートしながら事業を継続・成長させている印象で、これらの企業思考はエフェクチュエーションの考えにも似たものと言えるかもしれません。
一見、「行き当たりばったり」の思考にも見えますが、「許容可能な損失」や「飛行機のパイロット」の原則は、コージェーション方式より慎重な考えと言え、不確実な環境下では現実的な思考法だと思います。
同書は、前半ではエフェクチュエーションに関する研究成果や過去の事例を紹介し、後半ではこの思考方法を現代の日本で実践したケースを紹介しています。こう記載すると学術書のようにも見えますが、内容は平易な説明で記載されています。
2度ほど読みましたが、まだまだ理解しきれていない部分もあり、今後も再読していきたいと思います。(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
