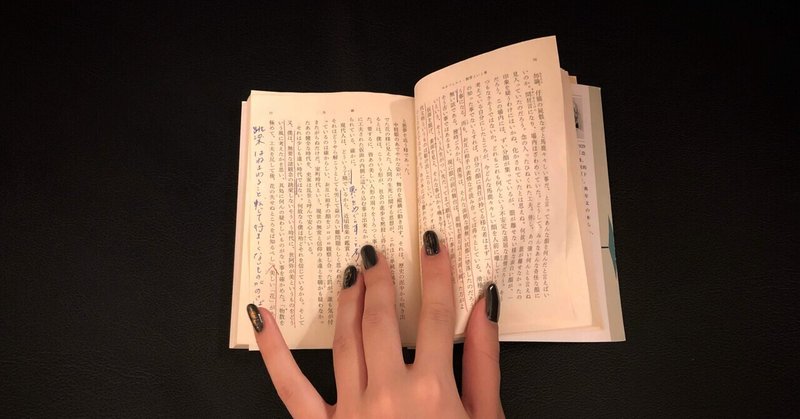
思想の議論
梅若の能楽堂で,万三郎の「当麻」を見た。
僕は,星が輝き,雪が消え残った夜道を歩いていた。何故,あの夢を破る様な笛の音や太鼓の音が,いつまでも耳に残るのであろうか。夢はまさしく破られたのではあるまいか。白い袖が飜り,金色の冠がきらめき,中将姫は,未だ眼の前を舞っている様子であった。それは快感の持続という様なものとは,何か全く違ったものの様に思われた。あれは一体何んだったのだろうか,何んと名付けたらよいのだろう,笛の音と一緒にツッツッと動き出したあの二つの真っ白な足袋は。いや,世阿弥は,はっきり「当麻」と名付けた筈だ。してみると,自分は信じているのかな,世阿弥という人物を,世阿弥という詩魂を。突然浮かんだこの考えは,僕を驚かした。
小林秀雄著『当麻』(たえま)の冒頭部分である。
この『当麻』という作品は,はじめて読んだときから私を掴んで離さなかった。なんとなくずっと,頭に残っていたのである。
好きだなあ,と思ったのは事実であるが,しかしながら何処がどうよいのかと聞かれると,これが解らなくてもどかしい。そもそも,内容自体が難解で,上手く解釈できる自信もなかった。
まさしく,「あれは一体何んだったのだろうか,何んと名付けたらよいのだろう」という小林の言葉が,奇しくも,彼の文章を読んだ後に心に浮かんだものである。
この作品は,曲中に著者を捕捉して止まなかった,ある奇怪な”顔”,つまり能面にたいする感動を反芻する,観劇の帰路を著した随筆である。
……勿論,仔猫の屍骸なぞと馬鹿々々しい事だ,と言ってあんな顔を何んだと言えばいいのか。間狂言になり,場内はざわめいていた。どうして,みんなあんな奇怪な顔に見入っていたのだろう。念の入ったひねくれた工夫。併し,あの強い何んとも言えぬ印象を疑うわけにはいかぬ,化かされていたとは思えぬ。何故,眼が離せなかったのだろう。この場内には,ずい分顔が集まっているが,眼が離せない様な面白い顔が,一つもなさそうではないか。どれもこれも何んという不安定な退屈な表情なのだろう。そう考えている自分にしたところが,今どんな馬鹿々々しい顔を人前に曝しているか,僕の知ったことでないとすれば,自分の顔に責任が持てる様な者はまず一人もいないという事になる。而も,お互いに相手の表情なぞ読みあっては得々としている。滑稽な果敢無い話である。幾時ごろから,僕等は,そんな面倒な情無い状態に堕落したのだろう。そう古い事ではあるまい。現に眼の前の舞台は,着物を着る以上お面も被った方がよいという,そういう人生がつい先だってまで厳存していた事を語っている。
仮面を脱げ,素面を見よ,そんな事ばかり喚き乍ら,何処に行くのかも知らず,近代文明というものは駆け出したらしい。
小林は,室町という時代において,世阿弥の持っていた美の概念に想いを馳せ,又それを以て近代文明,更には自己を批判した。
……美しい「花」がある,「花」の美しさという様なものはない。彼の「花」の観念の曖昧さに就いて頭を悩ます現代の美学者の方が,化かされているに過ぎない。肉体の動きに則って観念の動きを修正するがいい,前者の動きは後者の動きより遥かに微妙で深淵だから,彼はそう言っているのだ。不安定な動きを直ぐ模倣する顔の表情の様なやくざなものは,お面で隠して了うがよい,彼が,もし今日生きていたなら,そう言いたいかも知れぬ。
僕は,星を見たりして夜道を歩いた。ああ,去年の雪何処に在りや,いや,いや,そんなところに落ち込んではいけない。僕は,再び星を眺め,雪を眺めた。
初読からひと月が経ち,私はまた繰り返しこれを読んだ。二度,三度……繰り返し読んでみると,前回までに拾われなかった表現たちが少しずつ網に引っかかっていく感覚はあるのだが,それでもまだ内容を理解できたとは言い難かった。
そして私はどうにかこれを理解しようと,これについて書かれた試論を読むことにした。
尾上(1978)によると,人は自己固有の運命的歴史的現実に徹することで,自己自身であれる,というのが小林の立場だという。
小林は中世を無常観の徹底した時代とし,また自らも徹底した無常観を持ち合わせていた。世阿弥流の美は観念的なものではなく,従って小林は,美というものを現実存在に即して思考した。「当麻」観劇を契機にして内在化した狂気の精神は,彼に現実をダイナミックに生きる道を開示したという(尾上)。
なるほど,これまた難解である。
私は歴史,及び文学批評には明るくないので,小林の作品も,またそれを論じたものすらも,簡単には解らなかった。
しかし一つ,試論を通じたことで,判明したのである。
『当麻』を読んだときの,あの蠢く感情は,”あれは一体何んだったのだろうか,何んと名付けたらよいのだろう”――要するに私は,小林の観劇という行為のなかに,彼の思想を読み取った,いや寧ろ,小林が観劇を通じて彼自身の思想を露にした,といった方が正確か。そこに,強く惹かれたのであった。
私は知りたいのである,人の思想を。
現代は,難解な思想よりも,解りやすいものに流されやすい。所属や経験や出来事ばかりに関心を持つ様にできているのか。
街ですれ違う人の口から聞こえる声,ネットに散らばる写真や簡易な文章は,常にそれらで溢れ返る。
誰と何処で何をした――そんなことはどうでもいい,それよりも,私には知りたいことがある。
それを通じて何を見出した,何を考えた,何故そう思ったのか。何のどの様なところに影響を受けて,それからあなたの思想はどのように広がったのか。
そしてゆくゆくは,より深いところに根差す,自身のイデオロギーを教えて欲しい。
『当麻』は,小林に内在する”無常観”というイデオロギーを露呈するには,十分だったのである。
出典
小林秀雄『当麻』(新潮文庫『モオツァルト・無常という事』収録)
尾上新太郎(1978)小林秀雄「当麻」論試論
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
