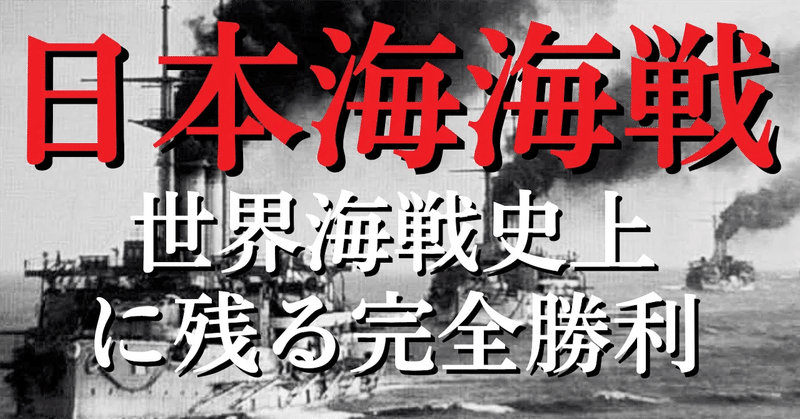
JOG(236) 日本海海戦
世界海戦史上にのこる大勝利は、明治日本の近代化努力の到達点だった。
過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251
無料メール受信: https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776
■1.完全な大勝利■
1905年(明治38)年5月27,28日の日露両艦隊による日海海戦の結果に、欧米諸国は驚嘆した。英国の著名な戦史家H・W・ウィルソンは、次のように語った。
__________
ああ、これ何たる大勝利か、陸戦に於いても、海戦に於いても、歴史上、未だかつて、このような完全な大勝利を見たことがない。実にこの海戦は、トラファルガー海戦と比較しても、その規模、遙かに大である。[1,p368]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
バルチック艦隊38隻の大陣容のうち、撃沈19、捕獲5、逃走中の沈没・自爆・他国抑留10隻で、ロシア艦隊が失った艦船合計34隻の排水量19万5162トン。日本側の沈没、水雷艇3隻、255トンはその0.13%に過ぎなかった。
ちょうど100年前のトラファルガー海戦が∂それまで世界海戦史上もっとも勝敗の際だったものだったが、ネルソン率いるイギリス艦隊が撃沈、または捕獲したのは、フランス・スペイン艦隊33隻中22隻に過ぎず、また名提督ネルソンも戦死している。「このような完全な大勝利を見たことがない」というウィルソンの言葉は決して誇張ではない。
■2.30分の御用のために10年■
もう一つ、欧米を驚かせたのは、その大勝利が極東の開国したばかりの非白人小国によって達成された、ということである。たとえば、アメリ新聞「ニューヨーク・サン」は、5月30日の社説でこう述べた。
__________
日本艦隊がロシア艦隊を潰滅したことは、海軍史のみならず世界史上例のない大偉業である。日本が鎖国をといたのはわずか50年前であり、海軍らしい海軍を持ってから10年にもたたぬのに、早くも世界一流の海軍国になった。[2,p408]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これに照応するのが、連合艦隊参謀として全作戦を指導した秋山真之(さねゆき)の次の言葉である。
__________
三笠以下主力の12艦は、いずれも我が海軍の当局者が多年の惨憺たる経営に依りて製艦されたるものなるが、而(しかも)も之を用ゐるは主として僅々30分の決戦にてありし。吾人が十年一日の如く武術を攻究錬磨しつゝありしも、亦此の30分間の御用に立つ為なり。されば決戦は僅かに30分なるも、之に至らしむには十年の戦備を要せしものにて取りも直さず連綿10年の戦争なり[1,p347]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
日本海海戦は劈頭の30分で勝負が決まってしまったが、その30分のために10年にわたる軍艦建造と作戦・技量の錬磨があったという。さらに近代海軍を持つためには、開国後50年の国をあげての近代化の努力があった。「ニューヨーク・サン」が「海軍史のみならず、世界史上例のない大偉業」というのは、世界海戦史上、最高最大の勝利をもたらした日本民族のこの50年の努力を指している。その努力の内容を見てみたい。
■3.ロシア艦隊優勢■
まず近代海軍には、巨大な軍艦が必要である。蒸気機関、大砲、船体建造と、軍艦こそは近代科学技術の結晶である。我が国が西洋近代文明の威力をまざまざと体験したのは、アメリカからやってきた「黒船」であった。
しかし、我が国の当時の近代技術では、世界最新鋭の軍艦はいまだ国産できず、戦艦はすべてイギリスで建造された。しかも貧弱な国力では購入できる軍艦の数も限られる。日露開戦前の戦力は戦艦6隻であり、ロシアは竣工寸前のものも含めれば、18隻もの戦艦を有していた。
この6隻でも、明治天皇が宮廷費の10分の一を軍艦建造のために下賜され、「文武百官恐懼(きょうく)感激して」こぞってその俸給の10分の一を献納する、という国を挙げての辛苦の末に築き上げたものであった。
日本艦隊は黄海海戦、旅順港攻略などで、戦艦7隻を中心とするロシア太平洋艦隊を撃滅したが、自らも2隻を失い、わずか4隻となっていた。そこに戦艦8隻を擁するバルチック艦隊が、はるばるバルト海から来航してきたのだった。
アメリカの雑誌「サイエンティフィック・アメリカン」は迫りつつある日露両艦隊の激突を前に、戦艦については、ロシア側が日本側に倍する隻数をもち、しかも海戦の運命を決するものが主として戦艦であることからロシア側優勢であると判断している。
__________
大口径の砲の総数では日本軍にまさっている。海戦においては砲の威力が戦局を決するものである。[1,p329]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
と、バルチック艦隊のロジェストヴェンスキー司令長官は言った。30サンチ、20サンチの主力砲は33門と、日本側の17門の約2倍の戦力を頼んでいた。
■4.日本人の自ら工夫せしもの■
__________
日本人は事苟(いやしく)も海軍に関するものは悉(ことごと)く西洋の指導を仰ぐを常とせりと雖(いえど)も、又一方に於ては自ら新機軸を出だせり
日本人は艦隊の編制に於ても一定の方針を樹立したがその方針は大体に於ては日本人の自ら工夫せしものなり[3,p159]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
当時の英国軍事評論家の言うように、戦艦や大砲の数という物量では圧倒的に劣勢な日本は、「自らの工夫」によって、そのハンディを乗り越えようとしていた。その一つに、開戦前の戦艦6隻、巡洋艦6隻が、等しく15、6ノットの高速航行が可能で、一体として連合運動を出来るようにしていた点がある。これが日本海海戦で、敵艦隊の前面で180度旋回して、敵の進路をT字型に押さえ込む戦術を可能にした。
一方、バルチック艦隊は16~18ノットの最新鋭高速戦艦5隻が中心だったが、12~14ノットの旧式戦艦、10ノットの輸送船と一緒に編制されていたため、艦隊としては9ノット程度しか出せなかった。
__________
我が艦が速力で日本の艦に劣ることは事実であるが、戦闘において速力は重大な要素ではない。われわれは遁走することは考慮しないからだ。[1,p329]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
と、ロジェストウェンスキーは言ったが、速度が「遁走」時にしか役立たない、というのは、海戦が装甲堅牢な戦艦どうしで大砲を撃ち合い、先に沈めた方が勝ちという旧来の思想によっている。それに比べれば、高速の艦隊運動こそ攻撃力の源泉である、という日本海軍の独自の「工夫」は、時代を先取りしたものだった。
■5.大砲の威力10倍■
大砲についても、日本側は数よりも質で勝負する工夫を凝らしていた。日本艦隊の射撃速度はロシアの3倍、すなわち、同じ1門でも、単位時間に3倍の砲弾を撃ち込める。さらにバルチック艦隊来航を待つ間の猛訓練によって、その命中率も3倍に達していた。
さらに砲弾の違いもあった。バルチック艦隊の砲弾は装甲部を貫いて一定の深さまで達しなければ炸裂しなかったが、日本の砲弾は、榴弾型で敵艦に当たりさえすれば、弾殻を3000以上の破片にして、飛び散らせる。この弾丸に当たったロシアの軍艦の甲板や舷側は、蜂の巣のようになった。
しかも海軍技師・下瀬雅允によって発明された下瀬火薬を使っており、それによって気化したガスは3千度にも達し、鋼鉄に塗ったペンキはそのガスによって引火して火事を起こすというものだった。この砲弾に襲われた旗艦スワロフの司令塔の模様は次のように記録されている。
__________
砲弾は榴弾で、これが炸裂すると、何千というこまかな破片になって飛び散り、物凄く大きな火焔と、息もつまるような黒色か淡黄色の煙の渦巻がパッとひろがったと思うと、可燃物という可燃物は総なめで、鉄板に塗ったペンキさえ、みるみる燃えてしまった。・・・
司令塔内にいた者は一人のこらず震えあがり、意外の惨状に度を失ってしまった。みんな恐怖におそわれて、垂直の装甲壁のかげに匿れる者や甲板に逃げる者もあった。[1,p348]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
射撃速度3倍に、命中率3倍、さらに砲弾の威力を加えると、日本艦隊の砲一門は、ロシアの砲10門に匹敵する性能を備えていた。主力砲ロシア側33門に対し、日本側は17門であったが、実はその攻撃力は170門にも匹敵するものであった。
■6.誓ってこれを撃滅し■
つぎに戦略・戦術面を見てみよう。日本艦隊を率いる東郷平八郎司令長官は海戦前に明治天皇に拝謁した際に「ロシア本国より新来の敵艦隊に対しては、誓ってこれを撃滅し、陛下のお心を安んじ奉ります」と奏上した。日頃、誇張の嫌いな東郷が、戦力でははるかに優勢な敵艦隊に対して「撃滅」などという言葉を使ったことで、周囲の者を驚かせた。
しかし、日露戦争全体に勝つためにはロシア艦隊を全滅させなければならない、というのが当時の情況であった。一つには日本の国力は限界に達しており、日本が有利なうちに何とか講和に持ち込む必要があった。そのためにも、ロシア側の最後の頼みの綱バルチック艦隊を撃滅して、ロシア側を諦めさせなければならない。単なる「優勢勝ち」程度では意味がなかった。
また、もし、バルチック艦隊を撃滅できずに、一部を撃ちもらしてしまったら、満洲で戦う陸軍への物資輸送船に対し、残存ロシア艦船はゲリラ的な攻撃をしかけることができる。その消耗戦に持ちこまれたら、シベリア鉄道で物資・人員の補給を続けられるロシア陸軍は息を吹き返す。
東郷司令長官は敵艦隊撃滅を唯一の戦略目的として、全艦隊を佐世保軍港内外に集結させ、日本全土の海岸線はがら空きにしてしまった。ウラジオストック軍港には、装甲巡洋艦2隻がおり、それが出撃して日本本土に砲撃を加える恐れもあったが、東郷長官はそれをあえて無視し、あくまでバルチック艦隊撃滅に戦力を集中させたのである。
■7.「肉を斬らせて骨を断つ」T字戦法■
敵艦隊撃滅のための戦術が、上述したT字戦法であった。日本海を北上する敵艦隊と南下する日本艦隊がすれ違いの形で撃ち合っても、撃ちもらした敵艦船はそのままウラジオストックに逃げ込んでしまう。敵前で日本艦隊がターンをして、T字の横棒となり、縦棒をなす敵艦隊の頭を押さえつける形で進路を阻む。そして横棒となった日本艦船から縦棒の先頭部分に一斉射撃を集中し各個撃破を行う。縦棒のロシア艦隊の後半部分は距離が遠く、有効確実な砲撃はできない。
しかし、T字に持ち込むためには、日本艦隊がある一点で順次ターンを行わなければならない。その一点にロシア側が集中砲火を浴びせれば、逆に日本側が次々とやられることになる。まさに「肉を斬らせて骨を断つ」の大胆かつ独創的な戦術であった。
明治38(1905)年5月27日午後2時過ぎ、旗艦三笠の最上艦橋の前面中央にすっくと立った東郷長官が無言のまま、右手を挙げて左側に振り下ろすと、三笠は左舷に回答し始めた。距離8千メートルの射程圏内で旋回を始めた三笠を見て、旗艦スワロフの参謀は「心中、しめたっ、と思った。こんなところで急に変針するとは、おかしな東郷だな、と仲間とささやきあった。」
ロシア艦隊はこの好機を逃さず、先頭の三笠に集中砲撃を加えた。三笠の周辺に巨大な水柱が次々とあがり、そのうちの数弾が命中、そのたびに艦は激しく振動した。しかし、この間も東郷は応戦を許さず、すっくと艦橋に立ったまま身じろぎもしなかった。東郷は黄海海戦でのデータから、ロシア艦隊の砲撃の命中率は8千メートルの距離ではきわめて低いという分析結果を得ていたのである。
■8.日本人の合理主義的精神
日本艦隊先頭の4戦艦が回頭を終え、ロシア艦隊の進路を遮る形となった所で、東郷は「打ち方はじめ」と平静な声で告げた。距離6500メートルの至近距離から、ロシア艦隊の先頭に向けて一斉射撃を開始した。30分後には先頭の戦艦オスラビアに大火災が発生し、ロジェストウェンスキー座乗の旗艦クニージャ・スヴォーロフも航行の自由を失って、戦列を離脱した。後続するロシア艦隊は大混乱に陥り、勝敗の大勢は決した。
ちりぢりになったロシア艦船を、今度は夜陰に乗じて、駆逐艦と水雷艇が魚雷攻撃を行う。あたかも傷ついた熊に、無数の猟犬が襲いかかるように。こうした戦術も世界に例のないことであった。水雷艇のような小型艦船は沿岸防御に使うのが当時の常識であって、外国の専門家は外洋でロシア艦隊を攻撃するには不適当だと忠告していたが、下瀬火薬で攻撃力を失わせた敵艦船にとどめを刺すには、これらの小型艦船による魚雷攻撃はまことに効果的だった。
世界海戦史上最高最大の勝利は、日本海軍の10年におよぶ装備面・戦略戦術面の独創的な研究努力の結晶であった。東郷長官が静かに左手を降ろして、戦史にのこる「東郷ターン」を命じたとき、すでに勝敗は決していたのである。日本艦隊の敢闘精神は凄まじかったが、それは決して勝利の最大要因ではない。闘志の面ではロシア艦隊も決して負けてはいなかった。それは多くの艦船が沈没まで戦い、投降したのは38隻中、わずか5艦に過ぎなかった事にも示されている。
日本人の合理主義的精神は、明治維新以降に近代西洋科学技術を急速に吸収し、さらに独自の工夫を加えて、時代の先端を切り開く独創的な技術・思想を生みだしていった。「海軍史のみならず世界史上例のない大偉業」は、こうした明治日本の全国民をあげての近代化努力の到達点であった。
(文責・伊勢雅臣)
■リンク■
a.JOG(007)国際派日本人に問われるIdentity
b.JOG(048)「公」と「私」と
c.JOG(218)FatherNogi
d.JOG(176)明石元二郎~帝政ロシアからの解放者
■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)
1.真木洋三、「東郷平八郎 下」、★★★、文春文庫、S63
2.吉村昭、「海の史劇」★★★、新潮文庫、S56
3.下村寅太郎、「東郷平八郎」★★★、講談社学術文庫、S56
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■「日本海海戦」について 一読者さんより
日露戦争後の戦勝祝賀園遊会に招かれた米国海軍の士官候補生だったチェスター・ニミッツは、東郷司令長官に会って感激し、いつか東郷の弟子達と太平洋で雌雄を決する事を心に誓います。後に太平洋艦隊司令官となったニミッツは見事に誓いを太平洋戦争で果たします。一方「出て来いニミッツ、マッカーサ。出てくりゃ地獄に逆落とし」と歌い、相手を蔑んだ日本は無残な敗北を喫します。
米国の初代ルーズベルト大統領は東郷大将が戦後に海軍軍人に与えた言葉に感激し、全文を皆に示します。その言葉の末尾は「勝って兜の緒を締めよ」でした。
太平洋戦争中、日本では「ルーズベルトのベルトが切れて、チャーチル散る散る国が散る・・・」と相手を馬鹿にした歌が私達子供にも歌われました。 勝って奢るものは滅び、冷静に観察して学び、努力してそれを実行するものは勝利する。今も昔も変わらぬ教訓です。 山崎さんより
「日本人の合理主義的精神」がいつの間に「精神至上主義」に摩り替り、ソ連との「ノモンハン事件」に繋がったのでしょうか。もちろん、貧乏国の日本ですから、軍備に割くお金は充分でなかったでしょう。しかし、ソ連の戦車に火炎瓶で立ち向かうだけで、日露戦争の203高地のような肉弾攻撃を同じように繰り返していたとは。その後の太平洋戦争の「ガダルカナル戦」も同様でした。陸軍ばかりではありません。合理的と言われた海軍ですら、小史を紐解きますと「精神注入棒」なるものが出で来ます。日露戦争以来、戦勝気分に浮かれて戦訓を忘れたことが、「精神至上主義」を生み出し、果ては「神国」なる日本国像が形成されたのでしょうか。不思議でなりません。
そして現在の政治・経済にしても、依然としてバブルの幻想を引きずっているようで、状況こそ違いますが、いつも同じ愚を繰り返しているような気が致します。これが「島国農耕民族」である日本人の本質でしょうか。
■編集長・伊勢雅臣より
我々は歴史からの学び方をもっと、研究しなければなりませんね。単なる自虐史観でも、真実は学べませんし。
■「日本海海戦」について HNさん(高一)より
この一文を読み、あることを思い出しました。小説家の山岡氏が、鹿児島の神雷部隊のひとりである学鷲に、「この戦争に負けたら悔いは無いのか?そこまでの(特攻をする)心境にどのようにしてなったのか」と、尋ねたといいます。
すると、相手である西田中尉は「我々はインテリであり、そう簡単に戦争に勝てるとは思っていません、しかし、負けたとしても、その後はどうなるのでしょう? お分かりでしょう、我々の命は講和の条件にも、その後の日本人の運命にもつながっていますよ、そう民族の誇りに」と答えられたそうです。
現代の日本人で、これだけの決意を述べる事のできる人間がどれほどにいるでしょうか。日露戦争であろうと、大東亜戦争中であろうと、その中で戦った人々で死が怖くなかった人はどれほどいたでしょうか? 己の命を捨ててでも、愛する国を守る事、其れができる人間であらねば、とそう思う今日この頃です。
■編集長・伊勢雅臣より
現在の自衛隊にも「愛する国を守る」気概に溢れた方はたくさんいらっしゃいますが、それを生かすにも、国民一般の理解と支持が必要です。有事法制の整備などはその一端でしょう。∂
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
