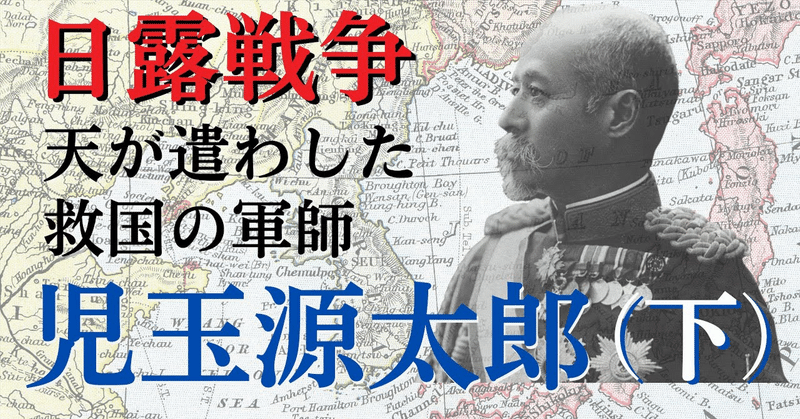
JOG(386) 救国の軍師・児玉源太郎(下)
まさに児玉は国を救うために、天が遣わした軍師であった。
過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251
無料メール受信: https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776
■1.「誓って旅順を落としてごらんに入れます」■
________
乃木と一緒に死ぬ覚悟で行って参ります。誓って旅順を落としてごらんに入れます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
児玉が大山巌・満洲軍総司令官に言った。「乃木の手に余るようじゃ。旅順の面倒をみてやってたもんせ」という大山に答えた言葉だった。「死ぬ覚悟」は本物だった。妻の松子に「きょうまで尽くしてくれた御身に心から感謝す。子供たちのことを頼む」という短い遺書を書いた。
このまま乃木の第3軍が旅順港を落とせなければ、そこに潜む太平洋艦隊は、やがてやってくるバルチック艦隊と合流する。そうすれば日本海軍の勝ち目はほとんどなくなる。日本海の制海権を奪われれば、陸軍も糧食・弾薬が尽きて、大陸で立ち枯れてしまう。それで日本は終わりである。
明治37(1904)年11月27日、第3回の総攻撃も失敗すると、乃木司令官は、今まで言いなりになっていた参謀を初めてて抑え、正面からの攻撃を中止させて二〇三高地に的を絞った。旅順攻撃はようやく合理的な作戦を得た。28センチ砲18門が二〇三高地に巨弾を次々に撃ち込み、突撃隊がおびただしい死傷者を出しながら、山肌を登っていった。[a]
■2.「陛下の赤子をいたずらに死なせてきたのは誰か」■
児玉は旅順に向かう途中の金州駅で、「二〇三高地が落ちた」という報告を聞き、随行の下士官たちとともに祝杯を挙げたが、翌朝大連のホテルで朝食をとっていると、「二〇三高地は今未明、敵に奪還された」という知らせが届いた。憤激した児玉はナイフとフォークを投げ出し、立ち上がった。
乃木軍司令部についた児玉は乃木と二人だけで話し合った。二人は明治初年の頃から、かれこれ30年以上もの親友である。明治10(1877)年の西南戦争で軍旗を奪われた乃木が自決しようとした際には、児玉が「死んで責任が果たせるか、卑怯者」と言って軍刀を奪ったこともあった。
乃木は一時的に児玉に指揮権を預ける事に同意した。児玉は乃木司令部の幕僚たちを集め、「二〇三高地の占領を確実にするために、二八センチ砲を15分ごとに1発発射し、一昼夜連続射撃して、敵の逆襲を阻止すべし」と命じた。
幕僚の一人が、「そうすれば、味方を撃つ公算も大であります。陛下の赤子を、陛下の砲をもって撃つことはできません」と反論した。児玉は怒鳴った。その眼には涙があふれた。
__________
陛下の赤子を、無為無能の作戦によっていたずらに死なせてきたのは誰か。わしは、これ以上、兵の命を無益に失わせぬよう作戦を変更しろと言っているのだ。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
二〇三高地の西南の一角に、百名たらずの兵が昨夜から張りついているという。彼らは歩兵の増援どころか、砲兵の援護もなく、寒風にさらされて死守している。その姿を見てきた者がいるか。陛下の赤子の死が迫っているのに、それを救おうともせず、かれらの占領地域を拡大しようともしないのは、どういうわけだ。参謀が前線を見に行きもせず、それで戦(いくさ)ができるか。
一同は静まりかえった。児玉のひたすらに国家の勝利と兵の命を思う無私の一喝が、乃木司令部の幕僚たちを目覚ませた。
■3.「俺の用は済んだ」■
12月5日、朝から28センチ砲ほか重砲数十門が、二〇三高地と隣接する山々を猛射し続けた。児玉は乃木とその幕僚達とともに、二〇三高地近くの丘に登り、双眼鏡で戦況を見た。西南の一角を守って奮戦する百人たらずの日本軍将兵たちの姿が見えた。「あれを見て、心を動かさぬやつは人間ではない」と児玉は言った。
日本軍の数時間の猛射で、二〇三高地とその周辺からのロシア軍の砲火がめっきり衰えた。そこに第十四師団が、二〇三高地の西南山頂に突撃を開始し、ロシア軍と血みどろの死闘を演じて、10時半頃、ついに制圧した。数日間、山頂を死守していた百人足らずの将兵がようやく救われた。第十四師団はさらに東北山頂にも突撃し、わずか30分で陥落させた。
二〇三高地からは港内のロシア艦隊が望めた。児玉は時を移さずに、西南山頂に派遣していた弾着観測将校に命じて、28センチ砲以下重砲群で巨弾の雨を降らせた。その後の3日間の砲撃で、ロシア艦隊はほとんどが沈められた。
「俺の用は済んだ」と言って、児玉は満洲軍総司令部に帰っていった。乃木軍の幕僚たちには、今回の自分の言動が越権行為として悪い先例と誤解されないよう、堅く口止めをした。
旅順艦隊の全滅によって、日本海軍はバルチック艦隊との決戦に備えて、艦船を日本に戻し補修に掛かることができた。乃木軍は北上して、ロシア陸軍との決戦を控える満洲軍に合流した。
■4.日の出に国運を祈る■
奉天(現在の瀋陽)は、満洲南部の交通の要衝である。ここでロシア軍32万、日本軍の25万の日露戦争中最大の会戦が行われた。時に明治38(1905)年3月、今からちょうど100年前である。
ロシア軍の総司令官はクロパトキン。ロシア皇帝に取り入ったベゾラフゾフ一派に陸軍大臣からは更迭されたが、戦術家としては欧州屈指と名高い。そのクロパトキンと児玉との戦いであった。
先の遼陽会戦ではロシア軍は優勢に攻撃しながら、黒木軍による3万人の大夜襲を受けて撤退した。しかし広大な土地を利用して、後退しながら敵の補給線が伸びきった所で一気に反撃に出るというのが、対ナポレオン戦争でも奏功したロシアの伝統的戦術である。奉天で体制を立て直し、日本軍を引きつけて叩こうというのが、クロパトキンの戦術であった。
逆に、児玉はクロパトキンのこの慎重さが弱点だと読んでいた。完璧な戦術を追求するあまり、奇襲など予想外の事態が起こると弱気となり、撤退して体制を立て直そうとする。児玉はそこに唯一の勝機を窺っていた。
決戦を前に、児玉は毎朝、一人で朝日を拝むようになった。その姿を見た人に、こう洩らした。
__________
わしはいままで宗教心がなかった。ところが倍に近い敵を迎え、決戦にのぞむと、勝敗が気がかりで、夜もおちおち眠れなくなった。日一日、ロシアの兵はふえている。その間、考えるべき事、やるべきことはみなやった。それ以上は、われわれの力にあまることだ。人事を尽くしたのだから、天命を待てばいい。しかしわしは心配で、何かに祈らずにはいられなくなった。遼陽戦のときに、兵が朝日を拝んでいる姿を見たが、あれが胸に沁みこんでいた。それでわしも、毎朝ここにきて、日の出に国運を祈っているのだ。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■5.奉天会戦■
3月1日、大山総司令官が総攻撃を命じた。兵力でも砲数でも劣勢な日本軍が、堅固な陣地に立て籠もるロシア軍を攻め立てるのである。猛攻をかけたが、損害も大きく、苦戦に陥った。
同時に児玉の作戦で、旅順から合流した乃木率いる第三軍が奉天の西側から迂回して、ロシア軍の後背をつこうとした。乃木軍の先鋒3千の支隊は、10万のロシア軍右翼に向かって尺取り虫のように前進していった。
「奉天北方20キロに、約6千の日本軍が進出中」という報告を聞いたクロパトキンは慌てた。あの難攻不落の旅順要塞を攻略した「ノギ軍」というだけで、兵は震え上がる。それが背後に回って、シベリア鉄道を遮断したら、ロシア軍は孤立する。6千が事実かどうか確認する余裕もなく、クロパトキンは全軍に退却を命じた。各地で日本軍の猛攻をはねのけて優勢に戦っていたロシア軍が堅固な陣地から不可解な退却を始めた。猛烈な烈風砂塵の中を、ロシア軍はひたすら退却し、日本軍は勢いに乗って追撃した。
3月10日、日本軍は奉天を占領した。のちに戦勝を記念してこの日が陸軍記念日とされた。日本軍の死傷者約7万。ロシア軍は約9万の死傷者と2万余の捕虜を出した。クロパトキンは降格され、ロシア軍はハルピンに退いて、そこで新たに50個師団を集結する作業にかかった。
しかし、日本軍は、すでに第一線で戦う精強な将兵の多くを失い、弾薬も底をついた。もはや北上して、再度の会戦を行う力は残されていなかった。
■6.「火をつけたら消さなゃならんぞ」■
実情を知らない東京の大本営は、退却するロシア軍をハルビンまで追撃し、さらにウラジオストックまで追いつめて殲滅せよ、と督促してきた。児玉は急いで東京に戻った。新橋駅に出迎えた参謀本部次長の長岡外資少将を児玉はどやしつけた。
__________
長岡あ、バカあ、おまえ、何をぼやぼやしとる。火をつけたら消さにゃならんぞ。消すのが肝心ちゅうに、何もしとらんのは、バカの証拠じゃないか。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
参謀本部も陸軍省も終戦工作を始めていないのに腹を立て、長岡に八つ当たりしたのである。児玉が山県・参謀総長と寺内陸相に実情を詳しく説明すると、二人は児玉に同意した。
元老・伊藤博文を訪問して説くと、伊藤は「これ以上戦えない、などと軍人としては言いにくいことを勇気をもってよく言ってくれた。わしたちも君にならい勇気をふるって発言しよう」と、アメリカで世論工作を行っている金子堅太郎に打電し、ルーズベルト大統領に対する働きかけを積極化するよう指示した。
児玉の根回しで4月8日の閣議では、アメリカに仲介を頼んで講和を急ぐ、という基本方針は固まったが、桂首相と小村外相は、ロシアからの賠償金をとるべきだと主張し、講和条件についてはまとまらなかった。
児玉は「桂の馬鹿が賠償金を取るつもりでいる」と聞こえよがしに言いながら、満洲に戻った。実際、後の講和会議では、ロシア皇帝は「一握りの土地も一ルーブルの金も日本に与えてはならない」と命じている。外交面でも児玉の読みは誰よりも鋭かったと言える。
■7.ロシア皇帝をいかに講和のテーブルにつけるか■
余力を残しているロシアを講和に追い込むためにも、児玉は手を打っていた。まず開戦時に明石元二郎大佐に百万円の工作資金を渡し、ロシアの後方を攪乱せよ、と命令していたのである。今日の貨幣価値で言えば数千億円の資金を投じて、ロシア帝政を倒そうとする革命勢力、独立を目指すフィンランドやポーランドの勢力を支援し、背後からロシア帝国を脅かそうとした。[b]
この年の一月、ペテルブルグの王宮に数万の労働者が待遇改善を要求してデモを行い、コザック騎兵が馬上から剣をふるって数百人の死傷者を出すという事件が起きた。「血の日曜日」事件である。これも明石が裏で糸を引いていた。これを機にロシア全土に暴動やサボタージュが広がっていった。日本との戦争を続けている間に、ロシア帝政そのものが危なくなると、ロシア皇帝は怯えた。
もうひとつの手は、樺太占領である。児玉は「戦争継続は望まないが、今弱気を見せては講和もむつかしくなるので、陸軍としては樺太を占領して余力のあるところを誇示しておくことが必要だ」と山県に吹き込んでおいた。
児玉は、「ロシア皇帝が樺太を日本軍にとられるのではないか、と危惧している」という情報を得て、ロシアを講和のテーブルにつかせるには、これが決め手となる、と思った。これまでの戦いはロシアにとっては、自国領土外の戦いであり、そこで戦闘に負けたと言っても、領土までとられた訳ではない。しかし、樺太を奪われたら、次は沿海州などロシアの領土も次々と奪われるかもしれない。
この作戦は、講和会議の直前、7月に実施された。結局、講和条件として日本が勝ち取ったのは、占領した樺太の南半分だけであった。もし樺太占領をしていなかったら、これすらも不可能であったろう。ここでも児玉の読みは当たっていた。
革命勢力を支援して皇帝の足元を揺るがし、樺太を占領して先行きを脅かす。あの手この手で、勝っているうちに講和会議に持ち込もうと、軍師・児玉の政戦略はシベリアの向こう側のロシア皇帝をゆさぶり続けていた。
■8.一生一度の男泣き■
5月27日、地球を半周して、日本海にやってきたロシアのバルチック艦隊は、東郷平八郎司令長官率いる連合艦隊と遭遇し、日本海海戦が行われた。ロシア皇帝の最後の希望を担っていたバルチック艦隊のほとんどは撃沈または捕獲され、かろうじて数隻がウラジオストックに逃げ込んだのみであった。
ドイツ皇帝ウィルヘルム2世はロシア皇帝に、「いまやロシアが日本に勝つか負けるかを問題にするときは過ぎた。ロシアそのものが亡くなるかどうかの岐路に立つときである」との親書を送った。
ロシアは講和会議のテーブルについた。8月29日、アメリカ・ポーツマスで行われていた講和会議で日本全権の小村外相が苦心惨憺の交渉の結果、なんとか講和の合意をとりつけた[c]。その報を奉天の総司令部で聞いた児玉は男泣きに泣いた。共に泣いた少将・福島安正は「児玉源太郎、一生一度の男泣きであった」と後に語っている。
■9.天が遣わした軍師■
12月7日、大山巌元帥以下、満洲軍総司令部は東京に凱旋した。新橋駅から皇居に向かう沿道には数十万人の市民が出迎えた。「大山元帥、万歳」の声が響く中、児玉は大山の陰に静かに従っていた。
翌明治39(1906)年7月23日朝、児玉がベッドの中で眠ったような顔のまま、こときれているのを、家政婦が見つけた。駆けつけた医者は死因を脳溢血と診断した。
児玉が参謀次長についたのは開戦のわずか4ヶ月前、前任者が肺炎で急死した後だった。そして苦心惨憺の末、大国ロシア相手になんとか辛勝を収めて、1年も経たないうちに忽然と世を去った。まさに児玉は国を救うために、天が遣わした軍師であった。
(文責・伊勢雅臣)
■リンク■
a.JOG(218) Father Nogi アメリカ人青年は"Father Nogi”と父のごとくに慕っていた乃木大将をいかに描いたか?
b. JOG(176) 明石元二郎~帝政ロシアからの解放者 レーニンは「日本の明石大佐には、感謝状を出したいほどだ」と言った。
■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)
1. 生出寿『謀将 児玉源太郎』★★★、徳間文庫、H4
2. 古川薫『天辺の椅子 日露戦争と児玉源太郎』★★、文春文庫、H8
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■「救国の軍師・児玉源太郎(下)」について
「よこちゃん」より
遇然、配信されてきて開き、なんだろうと読ませていただいた。通常、こういう場合、途中で終わるのだが、今回は興味津々。最後まで読みきって、最近にない高揚感を感じている。感謝の一言に尽きる読了感は久々。
現在の日本がこういう人々のお陰であるともっともっとわれら自身が知るべきだと改めて思うこと切。
日露戦争の意味付けは、或いは乃木将軍については、学校時代習っていたが、まさに影の人であった児玉元帥については、本日、目を開かれた面持ちでいる。
「なかの」さんより
日露戦争から100年、第二次世界大戦から60年目の今年。日本の諸外国との関係を思うと将来が大変不安になります。国家100年の計は教育にあり! 今回の児玉源太郎のような国を思う人たちを育てたいですね。このコラムが日本の常識になるよう期待しております。
tanaさんより
昨年から、日露戦争100周年ということで、小説「坂の上の雲」や映画「二百三高地」で理解を深めてきました。
いつも悔しく思う事は、一般的にこのように近代日本を命がけで、また想像を絶するであろう労苦をともないながら作り、我が国のみならず、世界中に影響を与えてきたという事実が、なんだか遠い昔話の、また歴史の単なる1ページということだけで済ましている国民感情が殆どなのだという事です。
また、戦後の自虐史観的な風潮がまだまだ蔓延しているこの日本ですが、日本には世界に誇れるような、外交手腕にたけ、国の存亡に関わる大仕事をやりのけた誇り高き・児玉源太郎のような男達がいたという事実。古今東西変わらぬ日本人のDNAを、今この時代だからこそ改めて見直し、そして誇りをもち、先祖を敬うためにも、日露戦争から学ぶものは多大です。
■ 編集長・伊勢雅臣より
児玉源太郎の無私の心に根ざした愛国心が、当時の人びとのみならず、現代の我々にも訴えかけています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
