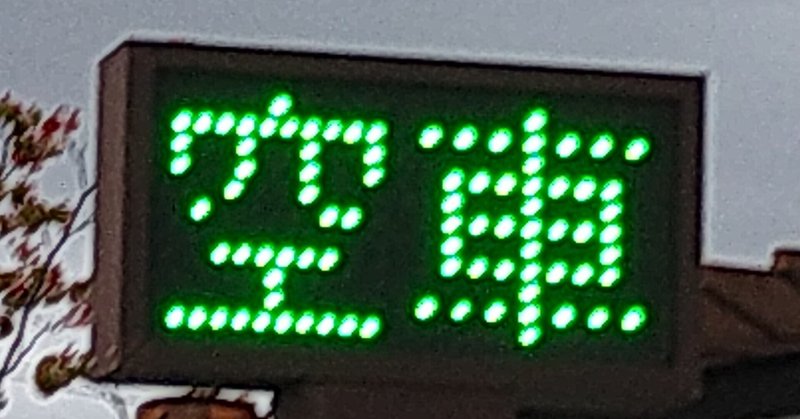
【エッセイ】熱い話の型
由々しき事態だと思った。
お笑い界が、テレビ業界が、良くないフェーズに突入しているのを感じた。
この前、とある解散した漫才師のことを思い出した。東京吉本に所属していたそのコンビは、若手でありながらベテラン芸人の腕と風格を持ち、とにかく実力がある二人というのが、彼らを知る人の共通認識だった。彼らの後輩である「ニューヨーク」のYouTubeチャンネルでも、何度か名前が挙がっている。
私は「その人たちのネタって今でも観られるのかな」と思い、YouTubeで検索した。すると、吉本の劇場のチャンネルが過去にアップした映像や、おそらく違法のライブ映像など、多数の動画がヒットした。解散から数年経つが、残っているものは残っている。
その中に、その漫才師の後輩のコンビが、彼らの凄さについて語る動画があった。現役の同業者が語る彼らの凄さに興味があったので、迷わず再生する。
動画が始まると、彼らがどういったコンビなのかという説明から入り「劇場で毎回ウケていた」「彼らが若手のライブの司会をやれば必ず盛り上げてくれる」といった、近くで見ているからこそ分かるポイントをいくつか語っていた。
最初のうちは興味深くみていた。しかし、途中で少しずつ違和感を覚え始めた。この動画は何か変だ。話している内容とか、編集とかではなく、もっと別の箇所が変だ。でも、何が変なのか?
しばらく観て、ようやく気付いた。「このコンビは『お笑いについて熱く語る』時のテンプレートの話し方をしていて、喋りにオリジナリティがない」と。
「人志松本のすべらない話」という番組が放送されてから、自分でフッて自分でオチをつける「エピソードトーク」の文化が、プロの世界にも一般的にも浸透した。その結果、「上手いしゃべり方」「面白いトークの構成」という型のようなものが誕生する。「こういう喋り方でこういう内容の話をすればある程度ウケる」といった具合に。
漫才の大会であるM-1グランプリも、一時期「M-1で勝てる漫才」といった言葉が使われていた。ボケをたくさん入れると有利という空気が間違いなくあった。
ただ、すべらない話ではその型に縛られないトークが展開されたり、M-1ではそういったネタとは異なるタイプの漫才師が優勝したりするなど、出来上がった型をいかに破るかの勝負に切り替わりつつある。
近年、自らの仕事に対する熱を持ったトークや、番組の裏側を語る場面、同業者の凄さを分析する番組が急増した。テレビをつけると、様々な形で「熱い」トークを展開する芸能人の姿がある。
そういった番組を繰り返し放送した結果、「熱いしゃべり方」「熱いトークの構成」の型が出来上がってしまったのだと感じた。今は「ウケる熱いトーク」が求められるフェーズなのだろう。
彼らの型にはまった「熱い」トークを聴いて、オリジナリティを出すのも才能だと私は思った。どんな話も、自分なりのやり方で喋りたい。目先の伝わりやすさとかは関係なく。
記事を読んで頂き、ありがとうございます。サポートして頂けるとさらに喜びます。
