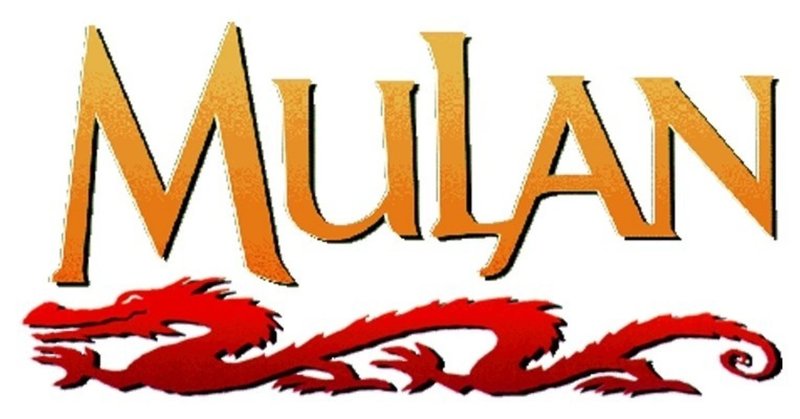
『ムーラン』はステレオタイプ打破の物語だ|アニメ考察
こんにちは遊々自適です。昔Niだけサッと書いてそのまま埋もれていたメモを懸命にTe化してやっとこさ文章に組み立てました。実写映画公開が迫っている(?)ということで今回は『ムーラン』のお話。
1.『ムーラン』とは
『ムーラン』は1998年公開のディズニー映画。冬季長野オリンピックが開催されたり、映画「タイタニック」がブームになったりした頃です。
ディズニー史の中では、『アラジン』『ライオンキング』『ポカホンタス』など、脱欧米化の流れに乗った作品。
フン族の侵略により全土に徴兵令が下った中国。ファ家の一人娘ムーランは足の悪い父親の代わりに男装して入隊する。厳しい訓練を経てある日フン族を撃退する活躍を見せるも、直後に正体がばれてしまい除隊されてしまう…といったあらすじ。
https://twitter.com/Disney_Jiteki/status/1250716331411861504
『ムーラン』はディズニーの「脱欧米」が目立つが、実は「女性のステレオタイプ打破」が主題。余すことなくその伏線が散りばめられていて、登場人物=視聴者の偏見を浮き彫りにしていく。そして最後にムーランが社会的に認められることで、その偏見を覆すラストになっている。
性別の表現に少し敏感になって、この「伏線」というのを時系列に辿っていきます。
2.垣間見える「ステレオタイプ」
①〈Honor To Us All〉「家に名誉を」
ムーランをお見合いに出すためにファ家の人たちが歌う最初の挿入曲で、かなりあからさまに女の役割や義務というものをムーランに説いています。
「男は大人しく、従順で、あくせく働き、育ちが良く、細いウエストの娘を(結婚相手に)求める」
"Men want girls with good taste
Calm
Obedient
Who work fast-paced
With good breeding
And a tiny waist"
「(さすれば)男は喜んであなたのために戦争に行く」
”Boys will gladly go to war for you”
(これはのちの〈A Girl Worth Fighting For〉への伏線にもなっています。)
「男は国を守り女は家を守る」、それが「みんなの誉れ」。という「常識」をムーランに説きます。
②〈I’ll Make A Man Out Of You〉「闘志を燃やせ」
リー隊長が軍隊を奮起させ、弱かった兵士たちが厳しい訓練を耐え抜いて一流の戦士になる流れを歌った曲。
「(お前たちの家は)息子じゃなく娘を寄越したのか?」
”Did they send me daughters when I asked for sons?”
そして幾度も繰り返される”BE A MAN”「男になれ」のコーラス。
ムーランが女性であることを知っている我々にとっては面白い響きですが、リー隊長の偏った男女観がここで浮き彫りになります。
③〈A Girl Worth Fighting For〉「愛しい女よ」
直訳は「(その子のために)戦う価値のある娘」。兵士たちそれぞれの戦うモチベーションになるような「理想の女の子像」を描きます。
「月より白く星みたいに輝く目の娘」
「俺の力に驚嘆し、戦の傷を愛おしく思ってくれる娘」
「俺のことを何の欠点もない掘り出し物だと思う娘」
"I want her paler than the moon
with eyes that shine like stars"
"My girl will marvel at my strength
Adore my battle scars"
"My girl will think I have no faults
That I'm a major find"
「じゃあ頭が良くて思ったことを口にする娘は?」
「あり得ない!」
"Uh, how 'bout a girl who's got a brain
Who always speaks her mind?"
"Nah!"
この曲も〈Honor To Us All〉同様、かなり露骨に女性のステレオタイプを表現しています。
④隊からの追放
敵を一網打尽にする活躍を見せたムーランですが、彼女が女性だと分かったると、リー隊長は彼女を除隊する手のひら返しを見せます。(娘が出ていったことに気づいた両親が心配していたように、本来ならば死刑になるようですが。)
⑤シャン・ユーとの直接対決
本作のヴィランであるシャン・ユーも、例にもれず偏見を浮き彫りにさせます。作戦が失敗し怒りに震える彼は、ムーランには目もくれずリー隊長にとどめを刺そうとします。しかしムーランが軍を撃退した時の兵士だとわかるや否や、一瞬「信じられない」といった表情を浮かばますがターゲットを瞬時に変えました。
これは皮肉にも、彼は皇帝と同じくらい偏見に囚われない人間であることがわかる場面でもあります。リー隊長を筆頭とする兵士たちがムーランの「フン族を倒した」功績(DO)より「女である」(BE)という属性を重んじたのに対し、彼はその真逆の姿勢を示したのです。
3.結末
このようにファ家・リー隊長・隊員・シャンユーを通した、我々の女性への偏見が自然な形で、しかし確実に違和感を残しながら散りばめられています。
そしてきちんとこれらを覆すラストが用意されています。
フン族にとらわれた皇帝を助け出すために、ムーランが提案したのが「女装」して彼らのもとに乗り込むこと。「女がどのように扱われるか」を痛感している彼女だからこそ思いついた作戦でしょう。彼女の思惑通り、フン族の兵士たちは女装した彼らを見つけても”Concubines."(妾たちだ。)と剣を下ろします。
そしてこのシーンで流れるのが〈I’ll Make A Man Out Of You〉のリプライズ。女装×”BE A MAN”というシュールで面白いギャグシーンにもなるが、「ギャグあるところに作品の本音あり」ということを忘れてはいけない。兵士たちはムーランを信じてついていき女装までしたことで、「男」らしさの幻想が払拭された真のMAN(人間)になったとも考えられる。
こうして偏見を見事に利用した戦術でシャンユーを倒したムーランは、皇帝をはじめ国中の人から敬意を表されるまでになるのでした。彼女の属性(BE)ではなく、行動(DO)によって。
4.『ムーラン』の根本的テーマ
この作品における問いかけは、期待に応えられず思い悩むムーランの〈Reflection〉「リフレクション」 で示されています。
「本当の私を映して」
"When will my reflection show, who I am inside?"
超意訳ですが、曲全体を通して彼女は社会への不適合感を訴えています。根強いステレオタイプに周囲や自分自身が翻弄されすぎて、彼女は自身のアイデンティティを見失っていました。
父親の武具に身を包み家を飛び出るシーンで、彼女は何も語りません。足の悪い父を戦いに行かせたくないから、という自己犠牲精神と解釈することもできます。ムーラン自身もその時はそう思ったかもしれません。
しかし後々振り返って見るとこの行為は、生きづらい環境から自分の価値証明の為に飛び出した、単なる「父親を庇った良い娘」ではなく自分の尊厳のための戦いに出た、とも考えられます。
だからこそ家に帰った彼女は真っ先に皇帝から授かった剣とメダルを父親に渡しました。それが彼女の勝ち取った「社会的価値」だからです。しかし父親はその剣を地に落とし、ムーラン自身を抱きしめました。彼女はそこで初めて、特別な役割など果たさなくても自分には価値があることを実感するのです。
5.脱しきれない価値観
ここまで『ムーラン』の主張を辿ってきましたが、最後の最後で気になる展開があります。
再会を喜び合う父娘を見て祖母は「まったく、剣を持って帰るなんて。男でも連れて帰りゃいいのに」。そしてその直後、リー隊長がファ家を訪れて二人は恋愛モードに…。そしてエンディング曲〈True Your Heart〉が流れて物語は幕を閉じます。
こうして結果的には、「良い相手を見つけるという女の務め」を果たした上でのハッピーエンドとなってしまいました。マクロな価値観は変わったかもしれないけど、結局ミクロ的には彼女の待遇は変わっていないのです。
このような「粗」は、『美女と野獣』や『アラジン』では実写化できれいにアップデートされていたので、今度の実写版でどう変わるか(あるいは変わらないのか)が楽しみです。
6.最後に
ムーランは基本的には女性のステレオタイプ打破の物語だが、そこから脱しきれない描写はある。それも次回への布石かもしれないと思ったり…
ちなみに「悪い例」として挙げた〈I’ll Make A Man Out Of You〉ですが、そんな偏見を組み込みながらも恐ろしいまでの魅力を持っているのがこの曲のすごいところ。熱く滾るようなものがあって、ディズニーソングの中でも一、二を争うくらい好きです。
Twitterもやってますのでよろしければ覗いてみてください。
ディズニー考察 https://twitter.com/Disney_Jiteki
類型論考察 https://twitter.com/jiteki_typology
ディズニー考察もたくさん埋もれてるので、まだまだ書いていきたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
