
世界三大焼きそば
誰にだって思い出の買い食いがある。特に学校の近くに必ずある、代々の生徒たちを何十年と見つめてきたような店は思い出の宝庫だ。校門の前にあった店、体育館の脇の知る人ぞ知るケモノ道の先にある店、自転車組は気づかないが徒歩組だけが知ってる裏道の角っこにあるような店。みんなそこに数々の青春を置いてきた。お金があれば買い食いし、お金がなければ友達からひとくちもらい、偶然居合わせた金持ちの先輩がおごってくれようもんなら店が壊れんばかりの大声で歓喜した。私の母校・安房高の場合それは「小倉商店」であり、小倉を愛するあまり「小倉の歌」を作曲する先輩すらいた。
小倉の思い出は多すぎるほどあるが、しかしそこで食べた何かがたまらなく美味しかったという記憶はない。というのも小倉はナショナルブランドのカップ麺やお菓子、アイス、ソフトドリンクを売る店だったので、味自体はスーパーで買ってきたものと変わりはないからだ。グリコのカフェオーレ、日清のカップヌードル、カルビーのポテチが私のお決まりだったが、こういうのは彼氏と小倉でキャッキャっ食べても、家でシクシク泣きながら食べても美味しいに決まってる。なので小倉を愛してはいたが、小倉でなければダメというものはなかったように思う。
ところが中学時代はまったく違っていた。

千倉中学の近くのあの店は何という名前だったか(仮にA店としよう)。「〇〇に行こう」と誘い合った記憶は多々あるので名前はあったはずだが、この長い人生のうちに取捨選択され、脳からこぼれ落ちてしまったんだろう。その代わり何を食べ、何を飲んだかは今でもありありと思い出すことができる。
飲み物はチェリオしかなかった。サビが浮いた大きな冷蔵庫から自分で取って、自分で王冠を開け、店のおばあちゃんに「グレープなくなったよ」などと教えてあげていた。
夏はかき氷があった。いちごとメロンとミルク、たまにブルーハワイ。お小遣いが入ったばかりの時はちょっと高いいちごミルクを頼んだりした。中学生らしくイキった友達が「いちごメロンブルーハワイ」を特注し、赤と緑と青が混ざり合ったとんでもない色に死ぬほどゲラゲラ笑ったこともあった。
そして焼きそばだ。
その店のスペシャリテでありシグネチャーメニューである焼きそばは、店のおばあちゃんが作る「早い・安い・うまい」を体現化したような美味だった。デフォが100円。50円ずつ増量ができ、お腹と懐具合に合わせて自由に注文ができる。といっても200円も出せばかなりの量があり、食べ盛りの中学生といえど満足してしまう。逆にお金がなかったり、小腹しか空いてない人のために50円という小盛り仕様もあった。
肉だか野菜だか天かすだかわからない何かのかけらがほんの少し、あとは麺だけなのに、どうしてあんなに美味しかったのだろう。家ではできない味だからか。こういったものに親は絶対にいい顔をしないだろう、という背徳感が絶妙なスパイスだったのか。ともかく最初っから激しく気に入り、これが焼きそばの頂点だとみんなでうなずきあった。これ以上のものは世界中探したってないと思っていた。1学期の間、部活終わりにはいつもA店の焼きそばのことばかり考えていた。

ところが夏休みになると友達が「もっといい店を見つけた」と言ってきた。それはA店と違い「具がたくさん入ってる」のが売りらしい。キャベツと豚肉、そして人参。地味なA店のビジュアルと比べれば、その華やかさは一目瞭然だ。しかも少量とはいえ肉が入ってる!肉だ! さあ我々は夢中になった。これこそが、このB店の華やか焼きそばこそが頂点だとみんなでうなずきあった。これ以上のものは世界中探したってないと心底思った。こうやって私の中1の夏休みは、B店の焼きそばに彩られたのである。
そして秋になった。
秋はお祭りの季節である。実家のすぐ上には2つ神社があり、特に高家神社という、日本で唯一の「料理の神様」を祀っている神社のお祭りはなかなかに大きく賑わっていて、毎年の楽しみであった。何往復もしながら古本をあさり、ストリートフードに目移りし、知ってる顔に出会えば話し込む。遊び方が今と何も変わっていないことに、改めて苦笑してしまう。ともかくその何往復もしている時、ようやく準備が整ったであろう小さな屋台に気がついた。
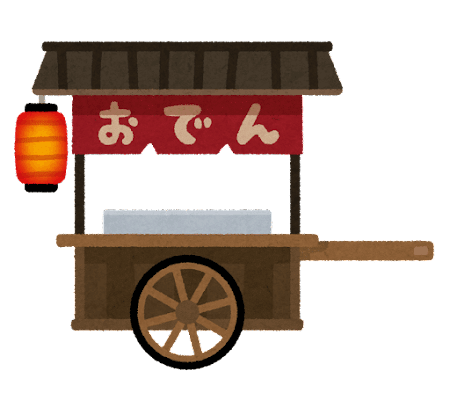
屋台といっても今のテキヤのような立派なものではなく、上の↑いらすとやさんのようにしっかりしたものでもなく、もっとシンプルで、ボロくて、すすけたように真っ黒で、何より小さかった。子供の目から見ても小さいものだった。そしてよく見ると小さなおばあさんが小さな鉄板の上で何やらやっている。
何をやっているんだろう。食べ物かな。
すでにすべての食べ物屋台はチェックしてあるから、あとはこの屋台をチェックすれば今年のお祭り屋台は網羅したことになる。宿題を片付けてしまう気持ちで屋台に近づくと「何やら」は焼きそばだということがわかった。買うつもりではなかったが、私に気づいたおばあさんが「もう出来上がるよ。100円用意して」と押し売りしてくるので、気弱な中学生には「断る」という選択肢はなかった。ほどなくして手渡された焼きそばは、真っ黒だった。
真っ黒な小さな屋台、小さなおばあさん、そして真っ黒な焼きそば。
今なら「さぞかし優秀な会社がやってるんでしょうね。コンセプト、バチバチに決まってるじゃないですか。デザイナー誰ですか」と聞いてしまうところだ。SNSでも動画でもフックはバッチリ、ハッシュタグもすんなり。バエル、バエル、バエまくりだ。フランチャイジー募集してまーす。
そして味。具はA店同様「肉だか野菜だか天かすだかわからない何かのかけらがほんの少し」あるよな無いよな感じだが、謎の真っ黒いソースが異様に美味しい。なんだこれ。どういう味なんだ。わからないけどうまい。うまいけどわからない。ソースの容器にはラベルもなく、いったいどこの何を使っているのかさっぱりわからない。
仲間内で、たちまち黒い屋台焼きそばブームが燃え広がった。次の日もまた祭りに来て、昨日はいなかった同級生を巻き込み、みんなで焼きそばを食べた。しかし美味しさの謎はさっぱりだった。同級生のアホ男子が「あのおばあさんは実は死んでる。だからあれは地獄のソースだ」とか黒い冗談を言ったりしたが、それが正解ならどんなにいいかとにらみつけたりした。

子供の世界はだいたい狭い。小学校よりは少し広がったとはいえ、田舎の中学生の世界なんて実にちんまりしたものだ。あのころの我々は、このちっぽけな自分達が住んでいるちっぽけな範囲だけが世界だと思っていた。その中に3軒しかない焼きそば屋のことを「世界三大焼きそば」と真剣に考えていた。子供の足で行ける範囲に、子供のお金で買い食いできる食べ物は焼きそばの他になかったのに。
だって、ほら。高校になったら選択肢は急に広がる。学校帰りに食べるのはパスタやワッフル、ハンバーガーだ。コーヒー専門店へも行くし、おしゃれなケーキも食べるし、あまつさえ期末テストの打ち上げと称して原宿まで遠征してクレープを食べたりもする。あら生意気ね。
あっという間に卒業し、上京し、そしてハタチもだいぶ過ぎた頃ふと「あの焼きそば屋さん、どうなってるかな」と思い出す。だが久しぶりに帰省しても、世界三大焼きそばのヨスガなど何もない。A店は駐車場になり、B店は居酒屋になり、そしてあの魔法の黒い焼きそばC屋台のことは誰も知らない。もう2度とあの焼きそばは食べられない。あれは中学生の前にしか現れない夢の食べ物だったのかもしれない、なんてセンチメンタルなことを思う。

【魔法の黒い焼きそばかもしれないもの】
大人というより中年をはるかに過ぎたころ、やたらソースに凝っていた時期があった。ソース天国・関西に近かったことも幸いし、手に入る限りのソースを集め、自分の店で串カツを頼んだお客さんに「どれにしますか」とずらりとソースを並べたものだ。1本199円の串カツだけでもソースを15本並べる。お客さんはワクワクするし、大抵の場合もっと味見したいからと追加注文が入るしで、双方にとてもいいシステムだったと思う。
今は市販のめんつゆバンザイの私だが、そのころは「お金をとるんだから」と、かえしなどはやたら自作していた。小さな店だから少量ずつ作っていて、少なくなると空き瓶に移し替える。そんなある日、ソースの瓶に入れたかえしとソースをうっかり混ぜてしまう失敗をしてしまったのだ。
ところがそれを味見してみると、なんか、こう、悪くない気配がする。何かに使えそう。串カツもそんなに悪くない。あと何が合うかな。あれは?これは?といろいろ試すうちに、焼きそばを思いついた。出来上がった焼きそばはなんと、あの魔法の黒い焼きそばに思い切り近いものだったのである。
そのかえしは東海地方ではよく売られている溜まり醤油を使っていた。個人的な好みで、砂糖は控えめだった。おそらく偶然、ソースとの割合もちょうどよかったのだろう。
今でもたまに思い出して、具なし真っ黒焼きそばを錬成することがある。焼きそばの麺、ウスターソース、たまり醤油(中国の老抽でも良い)を適当に炒め合わせるとかなり近いものが出来上がる。足りないとしたらそれは真っ黒い屋台と小さなおばあさんの演出だろう。あとは…令和では入手できないようなケミカルな調味料かな。そんなのがあったかどうか知らないけど。
いいなと思ったら応援しよう!

