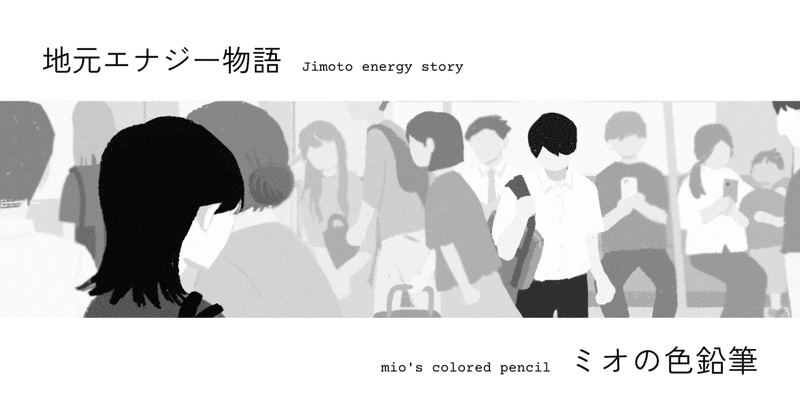
地元エナジー物語 1 ミオの色鉛筆
都会で働きながら子育てをするミオ、35歳。子育てに協力してくれない夫とは2年前に別れ、小さなアパートで2人の子どもたちと暮らしている。実家の父母とはなんとなく疎遠なまま、何年も地元には戻っていない。仕事と子育てに追われ、余裕のない日々を送っていた。
ある日の仕事終わり、電車に揺られていると、ふと中学生くらいの少年が他の乗客に逆らうような動きをしているのが目に入った。皆それぞれにスマホをいじったりイヤフォンで何かを聞いたりしてじっとしている中で、一人床に目を落とし、キョロキョロとしている。焦った表情で人の波をかき分けながらあちこち移動している必死な表情を見ていると、急に懐かしさがこみ上げてきて、不思議に思った。

記憶の糸をたどると、遠い昔、中学生の頃のことがよみがえってきた。有明海に面した東与賀海岸の小さな公園。ミオが海岸で落としてしまった色鉛筆を、同級生だったカツヒコがどういうわけか必死で探してくれた。どうしてあんなに必死で探してくれたのか、よく覚えていないし、その時色鉛筆が見つかったのかどうかすら、もう覚えていない。ただ、あのときのカツヒコの必死な表情だけは、脳裏に強烈に残っていた。
「あの、大丈夫ですか」
必死な表情で何かを探す少年が、あまりにあのときのカツヒコの表情によく似ていたので、ミオは思わず声をかけた。少年ははっとして顔を上げた。
「なにか、探しているのかと…」
ミオが言い訳をするように言葉を紡ぐ。
「生徒証、なくしてしまって。」
状況を飲み込んだミオは、黙って少年の生徒証を一緒に探しにかかると、ほどなくして座席の下の方にブルーのカードケースが見つかった。
「あれじゃない?」
「あ。あれです。ありがとうございます。僕、目、悪くて。」
「良かった。」
気のせいか、ミオの心が少し潤ったような気がした。次の瞬間、少年は思い出したように通学かばんから何かを取り出し、ミオに押し付けた。
「あのこれ。父も母も忙しい人で、あんまり家に帰らなくて。この前これが家に届いたんですけど、僕に好きなの選んで食べろって渡されて。でも僕、おばあちゃんちでいつもご飯食べてるから。」
「ん?」
「それじゃ!ありがとうございました!」
「え、ちょっと…!」
問いただす間もなく、停車した駅で少年は降りてしまう。困ったな、と思いながらも、とりあえずソレをバックに押し込み、子どもたちの迎えに向かった。
家に着くなり慌ただしくご飯を作り、風呂を済ませて、子どもたちが寝たのは夜10時過ぎ。ご飯を作っている間に3歳の娘はジュースをカーペットにこぼし、片付けている間にパスタを茹ですぎて、7歳の息子は「まずい」と手を付けなかった。
駄々をこねる子どもを持て余していた帰宅途中、通りすがりのおばさんに「今だけよ、こんなにいい時代はなかったって後から思うわ」といかにもな視線で声をかけられたことを思い出して、小さなため息を一つつく。麦茶をグラスに注いでダイニングチェアに座りこんだ。
ふと少年から受け取ってバックにしまい込んだままにしていたアレのことを思い出し、取り出してみる。どうやら九州の地域産品を集めたカタログギフトのようだ。たかだか捜し物を一緒にしただけでもらっていいものかどうか迷ったが、開いてみると、一つ一つのカードに掲載されている食品のつくり手の笑顔が印象的で、つい見入ってしまった。
つくり手のやわらかい笑顔を一つ一つ眺めていくと、いつの間にかミオの脳裏には、幼い頃からずっと見てきた有明海の景色が広がっていた。なんの見返りもなく「ミオちゃんはいい子だよ」となでてくれた祖母の手のぬくもりも。
そうしてふと、少年と一緒に生徒証をみつけたときに感じた潤いを思い出した。あれは一体、なんだったんだろう?ずっと忘れていた、いつかのおばあちゃんの手のぬくもりに、少し似ているような気もする。
カードをめくっていたミオの手が、ふいに止まった。1枚のカードに掲載されていたつくり手の笑顔に、強烈な懐かしさを覚えたのだ。一瞬あの少年の顔を思い浮かべたが、それとは比べ物にならないくらいの懐かしさに、思わずぶんと頭を振る。
「これ…もしかして…、かっちゃん!?」

カツヒコだった。20年前、必死でミオの色鉛筆を探してくれたカツヒコが、当時と変わらない日に焼けた腕を組み、当時と変わらないエクボを見せて、カツヒコの父親と並んで笑っていた。
驚きと嬉しさで気持ちがはやり、もどかしさを覚えながら急いでカードを裏返す。
"一度出ていったからこそわかる地元の技術と魅力。継承するのはオレだ!"
そんなキャッチコピーと共に書かれていたのは、一度は美容師を目指して大阪に出たものの、体を壊したお父さんを思って家業の海苔養殖を継ぎ、その技術と魅力を全力で継承しようとしていた、紛れもない、カツヒコの生き様だった。
体の中に、有明海の潮風が吹いたような気がした。そうして唐突に思い出したのだ。
あの日、カツヒコが必死に探してくれた色鉛筆は、絵を描くのが大好きだったミオに、大好きだったおばあちゃんが最期に買ってくれた水彩色鉛筆の水色だったことを。そして水色の色鉛筆は、結局見つからなかったことを。そして、それから何日も、カツヒコがあの海辺に通いながら、探し続けてくれていたことを。
ああ、私がみてきた有明海の景色を、子どもたちに見せてあげたいな。ふとそんな気持ちが湧き上がった。
絵を描くことを諦めてからもう何年も経っているけれど、あの日描きあげることができなかった有明海の風景を、次は描きあげることができるだろうか。
ミオは迷わずカツヒコの海苔を注文すると、明日、自分のために水色の色鉛筆を買いに行こう、と思いながら布団に入った。
(完)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
