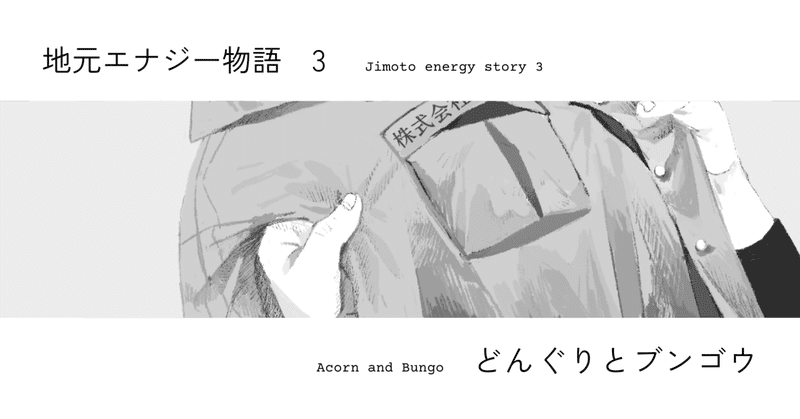
地元エナジー物語3 どんぐりとブンゴウ
朝七時半。
丁寧にアイロンがけされた作業着を着た初老の男性が、古びた自転車にまたがって、京急本線の踏切が開くのを待っている。自転車は随分年季が入っているのだけれど、よく磨かれ丁寧に手入れされているのがわかる。見ると、作業着の肘の部分にも、繕ったあとが見えた。
毎朝きっかり七時半に、その男性は踏切を待っている。
男性のことを、カオルは密かに「ブンゴウ」と呼んでいた。森鴎外とか島崎藤村とか夏目漱石といった文豪たちの、穏やかで知的な雰囲気に通ずるものがあるような気がしたからだ。
カオルは地藻都商店街のクリーニング店で働いている。毎朝同じ時間にブンゴウを眺めてから踏切を渡り、歩いて出勤するのが日課だ。
この街で初めてブンゴウを見かけたとき、砂漠で清楚な花に出会ったような気持ちになった。以来、ブンゴウに毎朝会えるのをどこか楽しみにしている。
クリーニング店の仕事は、シュコーッ、シュコーッというプレス機の音も心地よいし、様々な持ち主の衣服を預かるのも楽しくて気に入っている。持ち主たちの人生や暮らしに思いを馳せてアイロンをあてる時間は、カオルに心の平穏をもたらす。
夕食はいつも2畳ほどの小さなキッチンでお味噌汁とごはんを炊事して、あとは魚を焼くか、スーパーで割引されているお惣菜を買ってくる。朝は毎日、バタートーストとジャムをのせたヨーグルト。週に一回は商店街の銭湯にいき、月末には千円を児童養護施設に寄付することにしている。そうすることで、この一ヶ月生きたことを認めてもらえるような気がするのだ。そうやって淡々と繰り返されるカオルの日常に、ブンゴウの存在は違和感なく入りこんでいた。
ある朝、いつもの時間に、いつもの場所にブンゴウがいなかった。風邪をひいたのかもしれない、と思ったが、翌日も、その翌日も、ブンゴウは姿を見せなかった。
ブンゴウに会えなくなったまま十日ほど過ぎようとしていたある日、白髪交じりの女性が、痩せた肩にトートバックを下げてクリーニング店にやってきた。
「クリーニングをお願いできますか。」
女性の声は、少しかすれているような気がした。泣いているような、笑っているような表情だ。
「一週間後のお仕上がりになりますが、よろしいですか?」
「はい、一週間後でも、一ヶ月後でも。」
女性は今度は力なく笑った。
「そうですか…ではお品物を拝見いたします。」
カオルがそう言うと、女性は肩から下げていたトートバックを広げ、一枚の作業着を取り出した。
(あっ)
女性が広げてみせた作業着を見て、カオルは思わず出そうになった声を飲み込んだ。これは、ブンゴウが着ていた作業着ではないか。会社名が印字された作業着に見覚えがあったし、肘の繕いは、たしかにブンゴウが着ていたものだ。

「あの」
少しだけためらって、カオルは女性に話しかけた。
「失礼ですが、こちら、ご家族のものですか。」
「ええ、そう。主人のものなの。でも、先日亡くなってしまってね。」
カオルは息を飲む。
「とても几帳面な人だったの。だから最後にこの作業着もキレイにしてあげたくて。」
「そうだったんですか…なんだかごめんなさい。」
「いいのよ。几帳面で、真面目な人でね。山が好きで、この時期は朝早く山にでかけていって、きのこを採るのが毎年の楽しみだったのよ。」
女性はそう言うと、肘の繕いを愛おしそうになで、寂しい表情でカオルに作業着を手渡した。
女性が帰った後、作業着のポケットを確認すると、小さなどんぐりが一つでてきた。本来ならお客様がお帰りになる前に確認するべきだったが、驚きで頭がまわらず、うっかり確認を忘れてしまったのだ。
どんぐりをにぎりしめると、ザラザラした傘の部分やおしりの先にあるヒゲのチクチクが手のひらに伝わってきて、「ああ、私は今、どんぐりをにぎりしめている」と当たり前のことを思い知る。そして、山が好きだったというブンゴウのことを思った。ブンゴウはどんな思いでこのどんぐりを拾い、ポケットにしまったのだろう。
少し迷って、カオルはそのどんぐりを持ち帰ることにした。
帰宅し、いつものように月末の寄付を準備しようとパソコンを広げたが、ふと思い立って手を止めた。どんぐりを再びにぎりしめ、その感触を感じると、パソコンを閉じ、カオルは久しぶりに実家に電話をかけた。
*
翌週、女性が作業着の受け取りにやってきたのは、先週と同じ水曜日、先週と同じ開店直後の時間だった。この女性はたしかにブンゴウの家族なのだ。
「こちらでよろしいでしょうか。」
そう言ってクリーニングが終わった作業着を手渡すと、女性は両手を胸の前で合わせて言った。
「キレイにしていただいて、ありがとうね。」
満足そうな女性を見てほっとしたカオルは、レジ下に置いていたダンボールをカウンターの上に出し、切り出した。
「あの、もしよかったら、これ…」
女性は少し驚いた様子でダンボールを受け取り、ゆっくりと開いて中身を確認すると、きゅうっと瞳孔が開いた。
「まあ…きのこ!」
「ええ。実家の父が、きのこを採る人なんですよ。ご迷惑かな、とも思ったんですが、よかったらいかがですか。」
ダンボールの中には、実家で購読している地元紙が敷かれ、ハナビラタケやアミタケ、コウタケがぎっしりと詰まっている。
「いただくわ。ありがとう。」
女性は静かに目に涙を浮かべ、ダンボールと作業着を両手に抱えて店を後にした。
ブンゴウがどんな人物で、どんな仕事をして、どんな家庭生活を送り、どんな亡くなり方をしたのか、カオルは知らない。でも確かにブンゴウはカオルの日常を構成していたし、もしかしたらブンゴウの存在に救われていたのかもしれない。
実家の父に頼んで送ってもらったきのこが、ブンゴウの妻であるあの女性の秋を、来年も再来年もよい季節にしてくれるといいな、と願う。
女性の後ろ姿を見送りながら、カオルはエプロンのポケットに手をいれ、どんぐりをにぎりしめた。どんぐりのゴツゴツした手触り感は、きのこがたくさん入ったダンボールをブンゴウの奥さんに渡したときの感覚とよく似ている気がした。
それは、自分が生きてきたことを誰かに認めてもらえるように試してきたどんなことよりも、強烈に自分の存在を感じることができる手触り感だった。
これまで寄付してきた児童養護施設に、今度足を運んでみようか。
父のきのこを、手土産にして。
(完)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
